マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

筋膜解剖コース開催実現に向けて
私が最初に解剖クラスに参加したのは、今から14年ほど前のことでした。コロラド州ボルダーに当時作られたばかりであった、トッド・ガルシアのラボで開催された5日間の解剖コースは、ロルファーであるリズ・ガジーニと解剖学者のトッドがリードする、ロルファーや徒手療法に関わる人たちを対象としたクラスでした。トッドのラボは、エントランスエリアの日当たりも良く、サンキャッチャーが壁に虹色を反射する明るい場所で、生まれて初めての解剖にドキドキしていた私をホッとさせてくれるものでした。 素晴らしく清潔で換気の良い整った環境での解剖でしたが、ホルマリンで保存された献体での解剖は、やはりホルマリン独特の強い匂いが、クラス終了後にどれ程長くシャワーを浴びても拭いきれない気がしました。匂いに圧倒されはしたものの、トッドの正確な解剖にリードされて進むクラスでの学びは、奥深いもので、解剖学的な部位を実際に立体的に確認するのみではなく、生命や死に対しての想いを改めて認識することができる意義深いものでした。 友人であるトム・マイヤースが、アリゾナ州テンピにあるトッド・ガルシアのラボで、筋膜の繋がりを重視したホルマリン保存されていない献体での解剖コースを数年前にスタートしたことは彼自身から聞いてはいたものの、“解剖クラスには一度参加しているし、わざわざそのためだけにアメリカに行くのはどうかなぁ?5日間の解剖コースにまた参加する気合があるかなぁ?”などと考えて、参加するタイミングを逃し続けていました。 一昨年の1月、トムは、2つの5日間解剖コースとともに、2日間のみの解剖と運動を組み合わせたミショール・ダルコートとの共同クラスを提供し始め、トラビスと私は“2日間なら調整できそうだ”とクラスに参加することに。短い日程のコースではありましたが、全てホルマリン保存されていない冷凍された献体での解剖を生まれて初めて経験したことで、筋膜をはじめとする結合組織が変性していない状態での身体の可動域の大きさ、組織の質感、身体という空間の在り方、すべてが全く異なる新しい経験を得ることができました。 私とトラビスの配属されたチームが担当させていただいた献体は、特に肥満でもない中肉中背の年配の女性でしたが、解剖の最初の段階からペースメーカーの存在が明らかになり、何らかの心臓血管系の疾患を患っていらした方であろうということが伺えました。解剖を進めていくうちに、大腰筋を確認したいという参加者の要望に応えて、トッドが内臓を摘出。ここで私たちがあっと驚いたのは、この献体の腹部の大動脈に拳骨ひとつ分ほどもある大きさの動脈瘤が存在していたことでした。 ちょうど私の父が、腹部の動脈瘤の手術をした直後ということもあって、私はこの動脈瘤に釘付けになってしまいました。この動脈瘤の上部、下部、鼠径部の辺りまで、動脈硬化はかなり激しく、筋肉を含み弾力性に富んだ動脈血管とは全く異なった、まるで石灰の詰まったプラスチックのストローのような質感。 この方は特に肥満であったわけでもなく、この動脈硬化の状態、この血管の石灰化の度合いは外側から見るだけでは、きっと知る由もなかったであろう、と考えた途端、身が引き締まる思いがしました。 ボディワーカーとして鼠蹊部付近の組織にアプローチをする際、大腰筋にアクセスをしようとしてASIS の内側辺りから指先を組織に沈めていくというような状況を考えたのです。弾力性のある血管であれば、外部からかかる圧に対してするりと身をかわすことができるでしょう。しかし、このような石灰化した血管の周辺組織に圧が加わるとしたら。。。 人の身体に手を触れることを仕事の一部とする立場の人間として、いかに注意深く接さなければならないかを、改めて考えさせられました。身体の中でどのような変化が起きているのか、私たちはそれを全て知った上で人の身体に手を触れているのでしょうか?知らないで対応しているとすれば、どれほどの侵害を起こす危険性を抱えているのでしょうか? ホルマリン保存された献体では比較的簡単に行える、それぞれの筋肉を分離させて解剖することが、薬品処理をされていない、つまり組織が固定されていない献体では、一つ一つの筋肉を周辺組織から分離させるためには、かなり繊細で精確なテクニックが要求されることも、このクラスでは学びました。 “腹直筋や、腹斜筋を動員せず、腹横筋のみを働かせる”とか、“内側広筋のみを働かせて”とか、“中臀筋の後部線維のみを起動して”といったような、還元主義的表現に現実味は全くないな。と、それまでも強く感じていた身体構造の全体性と、その連動の重要さを改めて再確認できたことは、その後の指導における確信にもつながりました。 短い期間のクラスではありましたが、このクラスに参加したことで人の身体に手を触れるときの私自身の心構えは大きく変化しました。そして、この経験を日本の皆さんにも是非シェアしたいと強く考えるようになったのです。 日本国内において、このような環境を設定することは不可能です。アリゾナで開催されているトムがリードする解剖コースに日本から参加する皆さんを募って一部通訳に入ったとしても、他のコース参加者の学習を妨害することにもなりかねません。だとすれば、日本から参加される皆さんのみを対象としたクラスを企画するしかない。 アメリカで開催される5日間のコースに参加するには少なくとも1週間の時間の余裕が必要です。コースの参加費のみではなく滞在費や渡航費といった経費がかかります。どれほどの人数の皆さんが参加してくださるのか? この解剖のクラスは、解剖学者のトッドの指導料、施設使用料、大学のプログラムからの献体の購入代金、トムの指導料をはじめとして、かなりの固定経費が存在します。この固定経費をカバーできるだけの参加者の皆さんが集まるのであろうか?などと考え続けた1年後のことです。 昨年のトムの解剖コースに参加された理学療法士の山本篤さんが、トムに“是非日本人を対象にしたクラスを通訳付きで開催してほしい”というリクエストを強く訴えかけてくださいました。 それまでも“そうだねぇ、日本人だけのクラスもできたらいいねぇ”程度の意欲しか見せていなかったトムが、山本さんの熱意についに動かされたらしく、“多少赤字になってもいいから実現してみよう!”と言ってくれたのです。こうなったら実現するしかありません。このチャンスを掴まなくてどうする? 赤字になろうがどうなろうがわからないけれど、とにかく実現してみよう! こうして、今回の筋膜解剖コースの企画が生まれたのです。 この素晴らしい学びの経験を,できるだけ多くの仲間と共有したいというトムの情熱が、山本さんの情熱が、そして私の情熱が周りを巻き込んで、結果として50名近くの参加者の皆さんが集まる一大企画となりました。 幅広く奥深い知識と経験を惜しみなくシェアしてコースのリードをするトム。ありえないほどに繊細で精確な解剖の匠の技を惜しみなくシェアしてくれる解剖学者のトッド。アシスタントとして解剖のサポートをしてくれたローリーとホリーという2名の大学教授達。講師陣と参加者の意思の疎通のために通訳としてサポートしてくれた理学療法士の諸谷万衣子さん、KMIプラクティショナーのモール加奈さん、そして私の夫であり、今回のコース開催のためのテクニカル面をしっかりと支えてくれたトラビス。参加者の皆さんとの連絡や事務作業を一気に担ってくれた大室泰三さん。そして、仲間を誘って再度コースに参加してくださった山本篤さん。 素晴らしいメンバーで構成されたチームが、はるばる日本からこのコースに参加するために準備を重ねて参加してくださったコース参加者の皆さんを迎えることがついに現実のこととなったのです。 そして、この解剖コースでの時間と経験は、期待と予想を大幅に上回る貴重で素晴らしいものとなったのでした。

筋膜解剖コース2016
今回の解剖コースの参加者の皆さんの中には、今回の旅行が初海外旅行となる方も何名もいらっしゃいました。会社の社員全員11名が揃って参加されたグループもあれば、誰も知り合いはなく、一人で参加された方も。トレーナーやストレングスコーチ、ピラティスインストラクター、アレクサンダーテクニック指導者、ロルファー、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、歯科医、ボイストレーナー、インソール専門家、鉄道技師等、様々に幅広い分野の皆さんが、身体の構造を奥深く学ぶために、それぞれの目的を胸に抱えて日本全国から参加してくださいました。 コースをリードするトムは、私たちのコースがスタートする前に、すでに2つの5日間筋膜解剖コースを、そして2日間の解剖と運動のコースを指導していました。すでに2週間以上をラボの中で過ごしていたのは、トムだけではなく、ラボのオーナーであり、解剖学者であるトッドも、そしてトムのアシスタントとしてサポートをしてくれた、ローリーとホリーという2名の大学教授たちも同様に、なんと3週間連続の解剖コースに突入してくれたのです。 毎朝8:30~10:00の90分の時間は、ホテルのミーティングルームで、トムのスライドによるプレゼンテーションや質疑応答、そしてジョシュ・ヘンキンを迎えての体験ワークショップに費やされます。 まず初日の朝、参加者の皆さんと出会ったトムが私たちに伝えてくれたメッセージは下記のようなものでした。 “これからの5日間の実習から皆さんは多くのことを学び、気づくことになると思います。 単に古典的な解剖として、筋肉や骨をバラバラにして構造的に身体を学ぶことはもちろんできるでしょう。 ただ単に言葉で表現し伝えることができる知識や経験を学ぶだけではなく、うまく言葉にできない、言葉にするとうまくその本質を伝えられない何かに気づくことになると思います。 このうまく言葉にできない魂からの学びは、すぐに何かの形として現れるものではないかもしれません。これからの皆さんの人生の中で、生きていく上で何かの選択に迫られた時に、皆さんの背中を後ろから応援するように押してくれる。そんな形で現れてくるかもしれません。 私自身、もうすでに20回以上トッドとともに解剖を経験していますが、その度に私の魂は何かを学んでいます。私の母は、つい最近98歳の誕生日を迎えたばかりですが、彼女の驚くほどに軽く繊細になった手を握りながら、今回の旅から戻った時に、また彼女に会うことができるのか?と考え、人の死とは何か?人が生きるということは何か?ということを深く感じさせられています。 現代の社会に生きる私たちは、生命の誕生や死に立ち会うことが、ほとんどない。 ただ人は、誰しもいつかは死を迎える。 こうした経験をすることで、死を理解し、死に対しての準備をすることができてくるように感じます。 私も67歳になりました。残された時間の中で、果たして自分に何ができるのか? 私の師であるアイダ・ロルフと、ある日教室で二人きりになった時、彼女が私に言った言葉と同じようなことを、私も今感じています。やっと何かを始めたばかりなのに、あとどれだけ伝えていくことができるのだろうか?後を引き継ぐ人たちに自分は何を残していくことができるのか? 貴重な献体を提供してくださった皆さんの身体を通して、深い学びを得ることができる素晴らしい5日間になるでしょう。“ 毎朝のミーティングルームのレクチャーでは、ラボでは見ることのできない、細胞レベルやDNAレベルでの身体の構造や生理学の素晴らしさを学び、発生学の見地からの身体の構造と機能を学び、筋膜やその他の結合組織の塑性、粘性、弾性といった性質を理解することができる充実したサポートが提供されました。 内臓や脊柱を扱う日の朝には、昨年後半に腰椎椎間板の固定手術を受けた経験を持つジョシュ・ヘンキンが妻であり理学療法士であるジェシカと共に、手術からのリハビリの過程をシェアしてくれました。 実際に内臓のスペースを確認し、それぞれの構造の密接な関係性を理解した上で、この手術のプロセスを経験者から聞くことは、かなり強いインパクトがあったように感じます。 5日間の解剖は、表在の組織から始まって、各参加者のチームごとのプロジェクトに沿いながら進められていきます。 トムは、それぞれのチームのテーブルごとに、その時、その時のプロセスに応じて彼の奥深い知識と経験を惜しむことなくシェアしてくれます。 トッドは、もう“匠の技”としか表現できない、ありえないほどに繊細で精確でありつつ、素早い解剖の技術で、全て一つにつながっているように見える組織を、綺麗に分離させ、それぞれの構造をはっきりと見せてくれます。 大学教授であるローリーは、解剖のプロセスの途中で、心臓と腎臓を取り出し、それぞれの臓器を洗剤等を混合したバケツに浸けて、臓器の筋肉や細胞を洗い流し、枠組みとなっている筋膜の組織のみを残す。という、現代の医療科学の分野で進んでいる自己免疫の反応を刺激せずにより安全に行うことができる臓器移植への夢を実現するような、素晴らしい実験のプロセスをシェアしてくれました。 他者の臓器を移植して、免疫系がその組織の身体への同化を拒絶する可能性を最小限に抑えるために、内臓器の細胞を全て溶かし去って、結合組織の枠組みのみを残し、その枠組みに患者本人の幹細胞を移植して成長させ、その自分自身の細胞でできた臓器を移植する。という、まるでSFのようなことが現実のものになる日も、あまり遠くないのかもしれません。 トッドの技術を持ってして、はじめて分離させることができるほどに、密接につながっている身体組織。皮膚を取り去ることによって劇的に変化する関節可動域。手術の後の瘢痕組織の癒着の強力さ。各献体間に見られる個体差。頭蓋の厚さ、硬さ、強さ、ホルマリンで固定されていない脳のまるでクリームのように形を持たず柔らかい質感。脳下垂体の驚くほどの小ささ。 今回の解剖コースでは、通訳として各テーブルを移動していた私自身も、数々の発見と驚き、そして感情の奥深くを揺るがされるような経験を得ることができました。 解剖の本を読むだけでは、決して得ることのできない気づき、思い込みとか受け売りではない、本物の理解。生きるということに対しての自分自身の在り方、そして死をどう受け止めていくことができるかの準備。このコースでは、ただ知識を得るよりも、何十倍も奥深い学びを得ることができたように感じます。 トムが作った造語に“Spatial Medicine =空間の医療”という言葉があります。 私たちの健康に関わる医療には、身体の化学的なバランスを整えるための現代医学による化学的医療があり、整形外科的なアプローチや外科手術をすることでの機械的医療があります。これらの医療は、どんどん進化をし、人々は、そのクオリティーは別としても、昔よりはるかに長く生きられるようになりました。 でも、私たちの身体という空間を取り扱う、空間の医療とでも呼ぶべき分野は、まだまだこれから発達すべきもの。身体という空間を、より健康に維持をするためには、そこに動きが存在することが不可欠です。動かないもの、停滞するものは腐敗していきます。命を動かし続けるために、私たち運動指導やリハビリに関わる職業にある人たちは、これからの世紀にとって、とてつもなく重要な役割を担っているのです。 こうした、空間医療に関わる人たち全てが、一人一人バラバラに、あるいは、それぞれの専門職同士が孤立した状態では、この重要な役割を果たすことは望めません。 空間医療に関わる全ての専門職の人たちが、共に共通の言語を使って、お互いに理解しあい、お互いに助け合いながら成長していけることの重要性をトムは語ってくれました。 そして、今回の解剖コースを終了した後で訪問させていただいた、メジャーリーグのダイアモンドバックスでアスレチックトレーナーとして活躍する阿部正道さんも、EXOSで教育担当をするトリスタンも、フィッシャースポーツで活躍する理学療法士の管野恵介さんも、それぞれに違う言葉で同じメッセージを私たちに伝えてくれました。 私たちが、それぞれの専門性を尊重し合いつつも、お互いに理解を共有して繋がっていくことができること。ケアのコンティニュアム=連続体を実現することの重要性。 これは、キネティコスを立ち上げるにあたって、私が何よりも実現したかったこと、そのものなのです。 コース終了後の打ち上げパーティーで、ピザとビールを前にして、仲良く会話に興じるコースの参加者の皆さんの様子を眺めながら、“これこそが実現したかったことなのだ。”という想いを強く感じて、思わず涙が溢れました。 様々なジャンルの専門職の皆さんが、ひとつの想いでつながること。そしてこの繋がりが日本全国の運動/健康に関わる専門家の皆さんにどんどん広がっていくこと。そして、より多くの人々の健康と命をサポートすること。これは決して、誰かが一人で実現できることではありません。どれほど優れた治療家でも、どれほど優れたコーチでも、ひとりがアクセスできる人の数には限りがあるのです。 ピザとビールで楽しそうに歓談している皆さんを眺めながら、私は自分自身のミッションを再確認して、一人深い想いに浸っておりました。 今回のコース開催は、“まずは1回実行してみよう。次回はいつになるかわからない。”と、特に先の計画なしでスタートしたものではありましたが、今回のコースにご参加いただいた皆さんから、来年も是非!という言葉を沢山いただき、私たちは来年も開催することに決定いたしました!! コース参加者募集のご案内は、かなり早い時期にスタートをする予定です。皆さん、是非、この貴重な学びのチャンスを掴んでみてください。 来年も、今回のスタッフが再集合して、ベストチーム体制で準備をします。お楽しみに!

Kaori’s Update #9 - 変動性
障害予防、リハビリ、パフォーマンス向上のために重要な役割を果たす、運動の多様性、変動性とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?

Kaori’s Update #10 - 裸足でのトレーニング
シューズを履いた状態では同様に得ることのできない、固有受容器への情報供給や足部の内在筋の活動の促進を、段階的に進めていく方法に関するアイデアをご紹介します。

Kaori’s Update #11 - ベアクロル
ベアーポジションとベアクロール。それぞれの目的とポジションのポイントをご紹介します。しっかりと体幹を安定させて行うのは予想外に難しいですよ。^_^

Kaori’s Update #12 - ストレッチマトリックス
ファンクショナルの父とも呼ばれる、理学療法博士のギャリー・グレイが、動きの三面全てにおいて動くことを提唱した”動きのマトリックス”のコンセプトの一部を、わかりやすい言葉でご紹介します、

Kaori’s Update #13 - バイラテラル/ユニラテラル/アシメトリックとは?
トレーニング用語としてよく登場する、バイラテラル(両側性)、ユニラテラル(片側性)、アシメトリック(左右非対称)といった言葉は、どのような動作を意味するのでしょうか?

Kaori’s Update #14 - 狭い場所でも実行可能なパワートレーニング
SAQやパワーの向上のためのトレーニングは、屋外の広いスペースや人工芝を敷いたジムのオープンのスペースがなければ実践できない。と思い込んでしまいがちですが、簡単なツールを利用して狭い場所でも実践することが可能なトレーニングのアイデアをご紹介します。

Kaori’s Update #15 - 基礎的な有酸素能力の重要性
グレイ・クックのパフォーマンスピラミッドでは、ムーブメントの基礎の上にパフォーマンス、そしてスキルが築き上げられています。人体生理にとって重要な心臓血管系の能力を高めるためにも、まず、しっかりとした基礎を築くことが大切なのではないでしょうか?
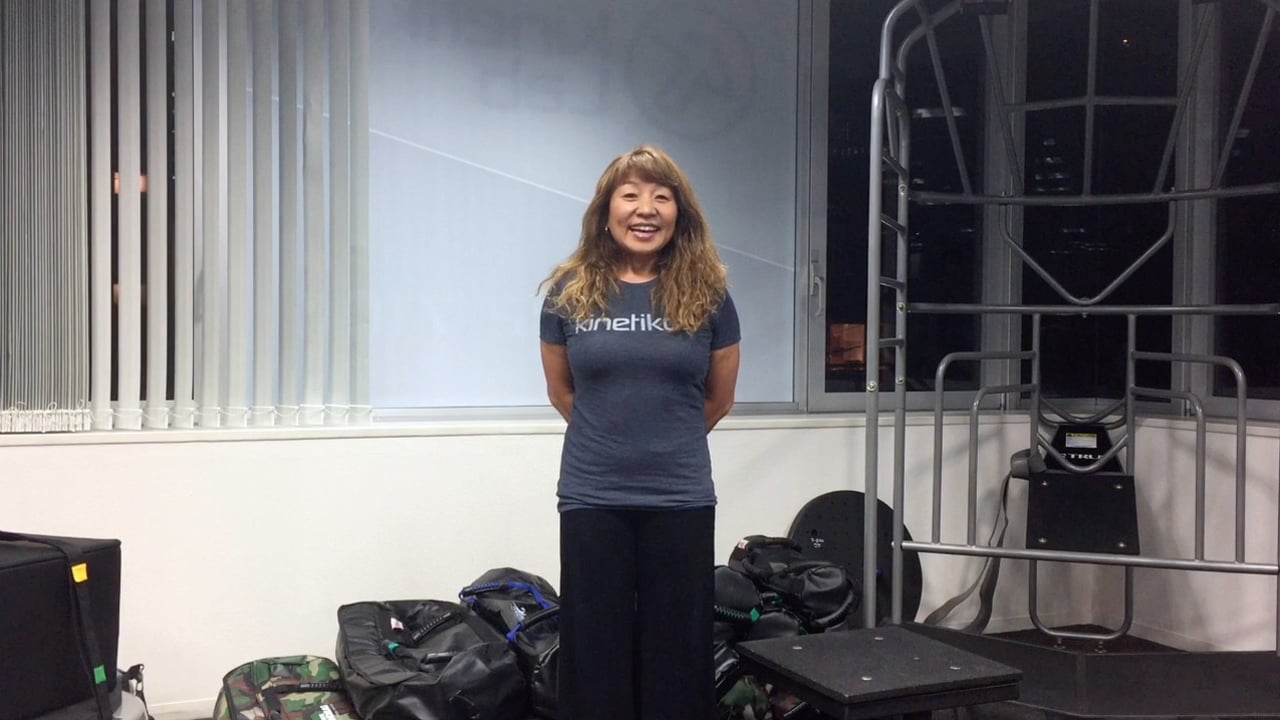
Kaori’s Update #16 - プラシーボ効果とは何か?
プラシーボ効果の本当の意味合いとは何でしょうか?私達が、クライアントや患者さんに接する時、どのようなコミュニケーションをとることができるのか、どのような信頼関係を築くことができるのか、ということは、何をするのかよりも更に意味深いことなのかもしれません。

Kaori’s Update #17 - スクワットの効果的な指導方法
スクワットの動作を指導するときに同様なキューイングを使えば、より効果的にコーチング出来るのだろうか?と頭を抱えたことはありませんか?外部負荷を効果的に利用することで、反射的に身体ポジションを修正することができる方法とは?

Kaori’s Update #18 - スクワット時の膝のポジションは?
スクワットを行うときに、つま先が膝を超えてはいけない、というキューイングを聞いたことはありませんか?それは何のためなのでしょう?そして、そうすることの影響は?目的に合わせて動きを選択すること、動きの多様性を考慮することの重要性を考えます。