マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。
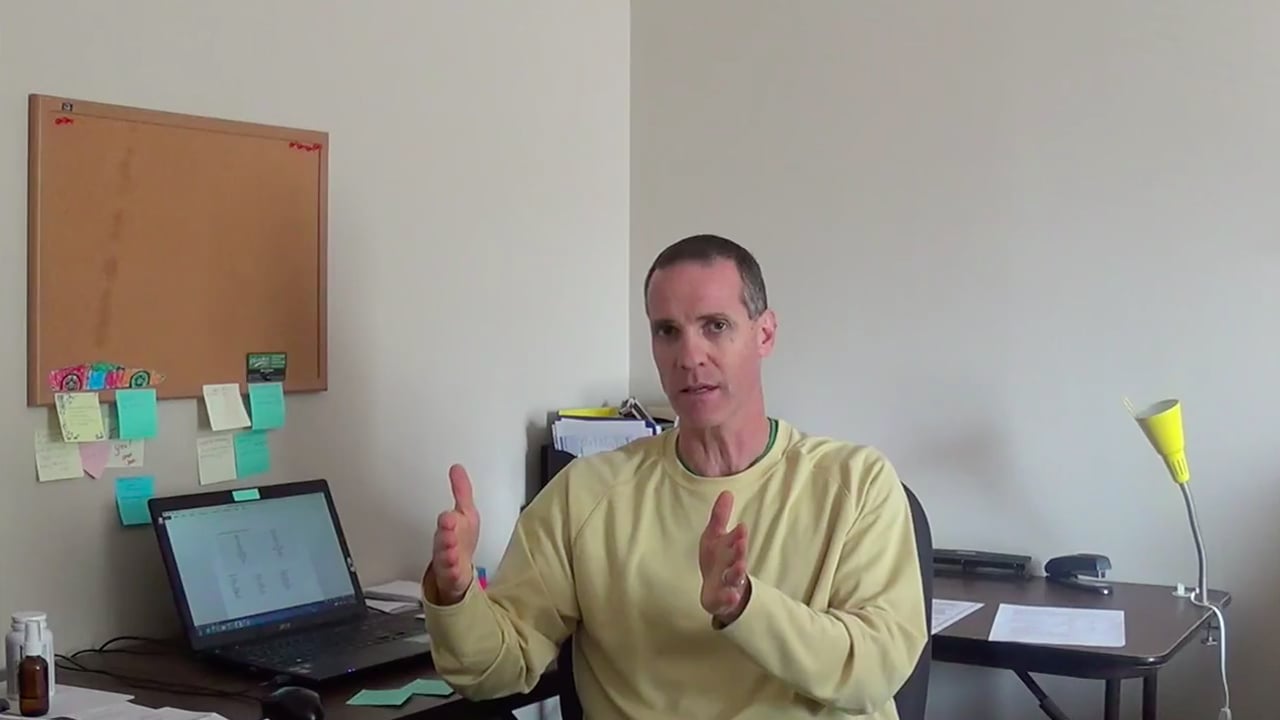
減速のメカニクスを改善する
減速のメカニズムがうまく実践できないアスリートの動きを改善するために、どのような対応策があるのでしょうか?SAQのエキスパートであるリー・タフトが、幾つかの提案をシェアしてくれます。

スプリンターステップアップ
ボックスにステップアップしてステップダウンするシンプルなエクササイズのプログレッションとして、スプリンターステップアップを行う方法を、マイク・ロバートソンがわかりやすく解説します。

姿勢は重要か?その1:動作との関わり
(パート2はこちらへ) 現在チェコのプラハはモトル病院にて発育発達過程を応用した運動療法を学んでいます。 ここでは”発育発達過程において赤ちゃんが獲得してきた姿勢”を再学習することを重要視しています。 この理論は日本でもDynamic Neuromuscular Stabilization (DNS)で有名になってきていますよね。 モトル病院にて、再び姿勢について色々と考えさせられましたので、これから数回にかけて考察したいと思います。 ※姿勢は”アライメント”と呼ばれることも多いかと思いますが、ここでは同意義とします。 姿勢は大切か?? 現在も姿勢については議論が行われており ”姿勢は大切だ” または ”姿勢は重要ではない” と両極端の主張が見られます。 それぞれの主張をサポートする文献もあり、単純にOか×で判断することは難しいのですが、私は現時点で”姿勢は重要である”と主張します。 おそらく、運動指導に関わる多くの方も、姿勢の重要性については肌で感じてらっしゃるのではないでしょうか? ※ちなみに話題のPostural Restoration Instute(PRI)のPは”Postural"=姿勢ですよね。 Ron Hruska信者である私なんかコレだけで”姿勢は重要です”って思えちゃいます。 では姿勢の重要性を説くため以下に”姿勢と動作がいかに関わっているか?”を考察いたします。 1. 姿勢は動作の開始位置である 全ての動作は姿勢から始まります。姿勢は重要ではない、との意見の背景には“静的な姿勢と動的な動作”を分ける考えがあるかと思いますが、そもそもこの二つを分けることは出来ません。 例えば、ジャンプ動作に股関節・膝関節・足首の伸展(底屈)=トリプル・エクステンションが必要だ、とは良く聞きますが、そもそも姿勢(動作の開始位置)が伸展位から始まったらどうでしょうか? 腰が反り、骨盤が前傾し、膝が過伸展し、足首が底屈位で止まった身体から、適切なトリプル・エクステンションは産まれるでしょうか? もし上記の位置でスタックしていたとすれば、ローディングが出来ないために最高のエネルギーは産み出せません。 また仮に、上記の位置から動くことができる(ローディングできる)としても、この位置からのローディングはジャンプ動作において最適な時間を提供することができない(ローディングにかかる時間が長すぎる)ため、最速のスピードでエネルギーを産み出すことができません。 最適な動作を行うためには、正しい姿勢から動作を始める必要があります。 2. 姿勢は動作の終了位置である 次に、姿勢は“動作の終了位置”でもあります。 すべての動作には終わりが来ますが、その動作の質を反映したものが姿勢であると考えられます。 例えば、競技選手はその競技独特の姿勢を持つことが多いです(投球系、ラケットスポーツの選手の大半は利き腕側の方が下がって見えます) 動作の開始位置を正しい位置から行ったとしても、動作に大きな偏り(例えば明らかな右重心)があった場合、動作終了時での姿勢(=次の動作の開始位置)は右に偏っていることが多いです。 すなわち、姿勢は動作の質を教えてくれる重要な情報となります。 また、反復動作の多いスポーツにおいて選手は“次の動作を始めるのに最も有利な姿勢”を作る傾向にあります。 短距離ランナーの寛骨前傾位などはこれの代表格で、踵着地(寛骨後傾位)の必要性がない競技特異性を考えると、短距離ランナーが競技後に寛骨後傾位の姿勢をとるとは考えづらいです。 ※短距離ランナーに寛骨後傾位を学習させることによりパフォーマンスは上がるのか??は非常に興味深いトピックですね。疼痛、傷害予防に関しては、動作に多様性を持つことが有益なのは間違いないですが、短距離走のタイム向上に焦点を絞ると判断が難しいとこです。 もしこれがサッカー選手となれば話は別です。よっぽど独特なスタイルの持ち主でなければ、パフォーマンスアップのために多様性は必須ですよね。 今回は姿勢と動作の関わりについて考察しました。 1. 姿勢は動作の開始位置である 2. 姿勢は動作の終了位置である 以上について何かご意見があればぜひお聞かせください! 次回からは、姿勢と呼吸機能、心理状態の関わりを考察いたします。 長文にお付き合い頂き、ありがとうございました!

シングルレッグトレーニングセミナー パート4
(パート3はこちらへ) (パート5はこちらへ) マイク・ボイルが、なぜバックスクワットを行わなくなったのか?その理由をインハウストレーニングでマイクが語るセミナーのパート4をお楽しみください。

モビリティーとコアの強さを向上させるための4つの方法(ビデオ付き)
抱えている問題の多くが、股関節の働きの悪さに起因していると気づいている人も多いでしょう。信じられないかもしれませんが、硬い股関節、不安定な股関節、弱い股関節は私たちが行うことのほぼ全てに影響するのです!強化したいとか、体脂肪を落としたいとか、あるいは痛みを解消したいというようなことの全てに。 ここでの鍵となるのは、股関節とコアはお互いにかなり関連し合っているということ。実生活に必要な強いコアの働きを持っていながら、股関節に問題を抱えている人を見ることはほとんどありません。考えてみれば納得がいくでしょう。脊柱は骨盤の真上に位置しているのですから、コアと股関節がしっかりと機能していなければ、大きな問題を引き起こしてしまうことになるのです。 これに関してはすでにご存知かもしれませんが、それではどうすれば良いのでしょうか?最近目にしていることでとても素晴らしいと思っているのは、モビリティートレーニングにフォーカスを置くということです。これに関しての唯一の問題は、モビリティートレーンングの多くは、すでにモビリティーが十分にある人のために行われているということでしょう。 少し偏見があるのかもしれませんが、10年以上理学療法士として仕事をする経験の中で、運動と安定性に関してかなりの制限を持っている人たちを見てきました。皆さんは”私は、そんなに悪くないから”と考えているかもしれませんが、正直なところ、フィットネスのプロの皆さんの中にも、股関節やコアをの状態がかなり良くない人たちがいるのです。多くの場合において、彼らは股関節に問題があることは認めるものの、コアに大きな要因があるということにはあまり気づいていません。 これら両方を同時に取り扱うのが”秘訣”です。コアを安定させるとともに股関節の動かし方を改善すること。この素晴らしい例の一つはコアのアクティベーションを伴うシンボックスのポジションを使うことでしょう。シンボックスは、私たちにとって最も必要となりがちな股関節のポジションである、股関節内旋へのチャレンジとなるからです。多くの人たちにとって、股関節を適切に内旋させる能力の欠如は最も大きな問題です。座位での生活や良くないトレーニングによって、かなり失われがちなものなのです。 このポジションで座るだけで何かプラスになるのでしょうか?それだけでも助けにはなりますが、理想的には、より目的意識を持ちたいですよね。座っていることは股関節にとって大きな問題であると人々は言いますが、それだけでなく座っていることでコアもスイッチオフになってしまいます。ですから、これらどちらかのみに単独でアプローチをしても、あまり意味はありません。これら両方を同時に改善するためには、これらが協働するということを利用したいのです。 このDVRTの記事は、そこに目的があります。どこからのスタートにでも対応できるようにここではコアサイズのアルティメイトサンドバッグとバンドを使用して、コア強化とモビリティー向上のためのシンプルでパワフルな方法をご紹介します。

クランチとシットアップは効力がない!(ビデオ付き)
こう言えば、誰かが何か言い始めるのは分かっています。シットアップとクランチには効力がないのです。 それが必要であると議論を試みる“そんな人”がいるであろうということは分かっていますが、これが私に教えてくれる2つのこととは…彼らは研究論文を読んでいないということと、実際にトレーニング指導をしていないということです。 では、なぜクランチとシットアップに関してこのような発言をするのでしょうか?思うに、すでにこういったエクササイズは乗り越えてしまったにもかかわらず、これらはまだ多くの人たちにとって“後ろめたい歓び”だからでしょう。でしょう。それらのエクササイズをしていないという人も確実にいるでしょうが、それでも彼らはVシットやバイシクル、その他数多くのクランチやシットアップを変化させたエクササイズを行っています。 しかしなぜでしょう?なぜこれは人々が行なうべきことではないのでしょうか?高名な理学療法士である、シャーリー・サーマンは、“日々のほとんどの活動の中で、腹筋の主たる役割は等尺性の支持を提供することと体幹の回旋を制限することである。腰痛の多くは、腹筋群がL5-S1レベルで骨盤と脊柱間の回旋に対してしっかりとした制御を維持できないために起こる。“と言及しています。 軍隊ではシットアップを除外する方向に動いていますが、あなたもそうするべきではありませんか? そうですね。私は今まで生きてきた中で腰部の傷害を長年経験してきました。医者は私に“コアを強化するように”と伝えましたが、実際には具体的なものではありませんでした。私には動きを制限する能力を強化することが必要だったのです。この考えこそが、我々にコアの安定性を与え、四肢がよりスムーズに動くことを可能にしてくれるのです。コアを強化する方法を教えてもらえなかったことで、私は繰り返し背中をねじり続けるエクササイズを行い続けていました。(ロシアンツイストもやりましたねー)。 シャーマン女史がシェアしていくれているのは、プランクがコアのトレーニングと強化の標準になった一つの理由です。プランクは正しい方向性を持つ動きですが、ここには1つ大きな問題があることが分かっています…動けないということ! プランクが、脊柱を安定させるために使用したいブレーシングを産み出す能力を構築することに優れているということを研究者たちは認めていますが、それが“機能的”であるかということに関しては、認められていません。動きがないからです。私たちが望むものは、動きのあるプランク、3面すべての力に対し抵抗することができるプランクであり、私たちに可能な限り効率的な動きを教えてくれるものです。世界的に著名な脊柱の専門家であるDr. スチュアート・マックギルは腰部をサポートする最良の方法を伝えています:”動きと動きのパターンの欠陥はより重要であると記録されていることから、これらを治療的エクササイズのターゲットとすべきである。” 本当に我々が行な痛いのは、動作中に体幹の動きを制限することをコアに教え込むこと。我々は、自分自身にうまく動くことを教えたいのです。あなたが考えていることは分かりますよ。“じゃあ、どうやってシックスパックを手に入れることができるのか”。では、まず、悪名高いシックスパックに関してお話しましょう。これは特別な腹筋のエクササイズで発達するのではありません。Dr. マクギルが指摘するように“繰り返し脊柱を屈曲することが屈筋群(腹直筋と腹壁)を鍛える良い方法であるということを信じている人もいる。興味深いこととして、これらの筋肉は、動きを止めるときにコアのブレーシングに使われることが多いため、この方法ではほとんど使われない。従って、これらの筋肉は、屈筋というよりは安定筋としてより活動する。” シットアップやクランチでコアをトレーニングすることは、私たちの自然な動きに反しています。シックスパックは、筋力よりも体脂肪率により関係しているということは言うまでもありません。であれば、代謝も刺激できる、よりよいコアエクササイズを作り出すことは理にかなっていると言えませんか? 今回のDVRTアルティメイトサンドバックトレーニングの記事やビデオは、これに関するものです。

ハムストリングスの柔軟性に影響する神経の張力
ハムストリングスの筋繊維自体が短いのであれば、数分間ストレッチを行っただけでその長さが変化する、ということはないはずです。神経系の影響を考慮した神経張力のテクニックとストレッチの組み合わせ方法をマイク・ライノルドがご紹介します。

シングルレッグトレーニングセミナー パート5
(パート4はこちらへ) 両側性欠損とは?片側での力の出力の合計が両側での力の出力をうわまること。両側性のトレーニングと片側性のトレーニングに関してマイク・ボイルが語ります。
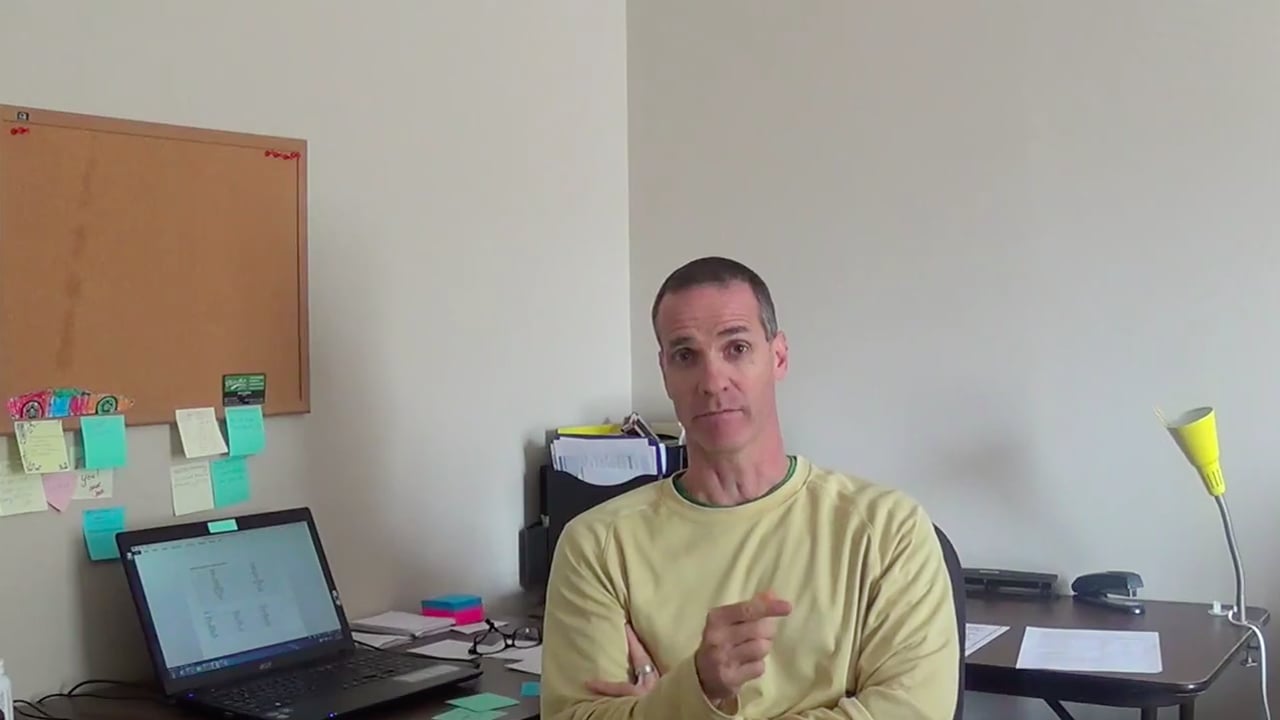
強化トレーニングとスピードトレーニングの組み合わせ方法
選手の指導をする際に、強化が目的のトレーニングと多方向的なスピードトレーニングをどのように組み合わせるのか?という広範囲な質問に対してリー・タフトが答えます。

胸郭回旋
様々な運動に不可欠となる胸椎、胸郭の回旋を促すエクササイズに使用するキューイングのアイデアをストレングスコーチのマイク・ロバートソンがシェアします。

ヒップヒンジの習得に役立つエクササイズ
みなさん、RDLやってますか? ヒップヒンジ動作はクリーンやスナッチなどのオリンピックリフティングの基礎として欠かせない動作です。股関節の伸展を伴う下肢の爆発的な伸展動作は、スポーツパフォーマンスにおける主要な原動力の一つになっています。 しかし、トレーニング初心者にとっては脊柱のアライメントを維持しながら、股関節の屈曲伸展動作を行うヒップヒンジは非常につかみにくい動きです。また、指導者がコーチングに苦労する動きの一つではないでしょうか。 当たり前ですが、屈曲できなければ伸展による力発揮も十分には期待できないでしょう。また、腰椎による代償的な伸展を引き起こすかもしれません。 以前、Dan Johnのヒップヒンジの指導法のアイデアがコンテンツで紹介されました。ヒップヒンジの習得方法は様々あるかと思いますが、利用可能な習得方法の一つとしてアクティブローディングを使った方法があります。 アクティブローディングは以前にスクワットの習得でも取り上げた方法ですが、ヒップヒンジにも同じように使うことができます。 ローディング局面(実際の負荷をかけたRDLではエキセントリック局面)の動作に負荷をかけることで、起きてほしい動作が自然に(反射的に)出るようにしていきます。言語的なキューイングによって、何とか動きを作っていくというのではなく、結果的にその動きができていたという方向にもっていきます。 ●ヒップヒンジ(アクティブローディング) ケーブルマシンを利用した方法で説明します。 準備:ロングバーをケーブルに取り付け、上方から下方に向かって抵抗がかかるようにセットする。 ① 両腕を伸ばした状態でバーを引き下げ股関節の前あたりに保持し、スタート姿勢をとる。 ② 両腕を伸ばしたまま、バーを足に向かって押し下げる(股関節を屈曲させる)。 ③ 十分にヒップヒンジの動きが出たら、ゆっくりと開始姿勢に戻り繰り返す。 必要に応じて動作を修正します。 例)動作中に脊柱が屈曲してしまう。 →頭頂部に手をあてて押し返すような意識を持ってもらい脊柱を軸方向に伸展させる。 →同時にお尻で壁を押すようなイメージを持って行う。または実際に手などを当てて押し返すようにして股関節の屈曲動作を出していく。 スクワットのときと同様にチューブ(またはバンド)を使って十分に代用することができます。チューブの場合は逆V字型になるようにチューブを吊り下げ、チューブの両端を握ります。このようにチューブを握ると前かがみになったときに、逆V字に分かれたチューブの間に上体が入るような形で実施できます。一ヶ所からしかケーブルを引いてこれない場合には、ケーブルが頭に当たってしまいます。この様な環境下ではチューブやバンドを利用したほうがやりやすくなります。 RDLの導入段階に使えば、RDL習得の手助けになると思います。ぜひお試しください。
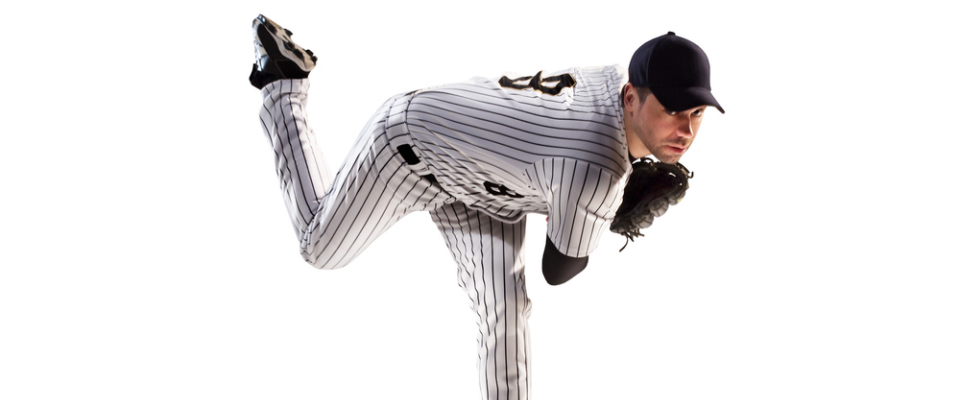
“安全”なエクササイズレパートリーの拡大
脊柱の専門家であるDr.スチュアート・マックギルは、彼の素晴らしい新刊本である、背中のメカニクスの中で、時間の経過とともに“痛みなくできることを拡大させる”ために、彼がどのように患者に対応しているかについて頻繁に述べています。このことは、一日の活動の中で良好な“脊柱のケア”を実践することと、症状を出現させるあらゆるポジションや動きを避けるということから始まります。 患者が無症状の時間をしばらく獲得できるようになれば、新しい動きとエクササイズが徐々に紹介されます。時間と共に、その人の痛みのない動きのレパートリーは、包括的なエクササイズプログラムに統合されていきます。いきなり難しいことをすることなく、様子を見ながら慎重に行う効果的な方法です。このことは慢性的な腰痛を患っている患者にとって特に重要なプロセスであり、そのサイクルを遮断し、実際に心地良いと感じることがどのようであるかを再獲得する必要があります。Dr.マックギルは次のように記しています、 “長年、私たちに最良の結果をもたらしてくれているアプローチ方法とは、患者に痛みのない動きを教えることです。このことは痛みの”ゲート理論“に基づいています。痛みを引き起こさない単純な動きを見つけることで、固有受容器システムが関節や筋肉のセンサーの信号で満たされ、痛みの信号が神経の”ゲート“をくぐるためのスペースをほとんど残さなくなります。これら痛みのない動きを繰り返すことで、脳にそのパターンがコード化されます。より良く、そしてより長い期間動けるようになるまで、ゆっくりと患者の痛みのない動きのレパートリーは増えていきます。彼らは脳に刻まれた痛みを引き起こすパターンを、痛みのないパターンに置き換えることに成功したのです。” 私はDr.マックギルの本を読みながら、リハビリやフィットネス業界における他の領域にどのように応用できるだろうかと考えずにはいられませんでした。例えば、野球選手のトレーニングという、私の一番の興味ある領域に関して言えば、野球のリハビリテーションの現場において、このことをどのように投球復帰プログラムに応用するのかについて考えなければなりません。真実を言えば、野球選手はもっとも独特な種類の機械的疼痛を持っているため、オーバーヘッド投球のアスリートにおけるリハビリテーションシナリオのほとんどの場面では、このアプローチは従来から上手に適用されてきませんでした。言い換えると、肘、または、肩は唯一そのポジションでしか問題にならず、また、大抵はかなり早い速度の時にしか起こらないのです: 現場で見かける顕著な上肢の投球傷害のほとんどでは、休息時の痛みはあまりありません。むしろ、腕は投球の動作時にのみ痛むのです。残念なことに(あるいは、見方によっては幸運なことですが)、日々の生活のなかで、実際に投球のストレスを再現するものはありません。投手にとって痛みのない能力を広げることは、単にそれ自体では従来次のことを意味しているのです: 1つの段階が次の段階に“繋がる”という漸進がまったくないことが多いということに気付き、実際に驚くでしょう。“投球しない”段階において、私たちは一般的な腕のケアエクササイズを多く見ますが、動きの速度,下肢とコアの統合、アスリートの投球方法(アームスロット)に特有の腕のポジションでのレーニングを組み入れることにはほとんど注意していません。残念なことに、テーブルに横になって、5パウンドのダンベルを使ってエクササイズをすることのみでは、120フィートの距離でボールを投げるために必要な準備ではないでしょう。 この理由のため、アスリートを“全体的”にケアし、様々な投球フェーズで徐々に増加していくストレスを理解できる理学療法士をいつも探しているのです。最も重要なことは、これら3つのそれぞれのカテゴリーの間でいくつかの“状態を判断し慎重に行う”ステップを組み入れていくことなのです。選手がオフシーズンの投球プログラムの強度を上げていくことと、全く同じように行います。過去に理学療法士であるチャーリー・ウェイングロフが鋭く言及したように、“トレーニング=リハビリテーション、リハビリテーション=トレーニング”なのです。 投球をしないということと、平らな地面での投球の間にあるギャップをできる限り埋めるにはどのようにすればいいのでしょうか?先発投手にとっては、腱板のエクササイズは、投球時に起こる肩甲骨の上方回旋と肩の挙上を反映するために、90度外転位に近い姿位で行う必要があります。さらに、投球のレイバックフェーズに“問題”となる強さをテストするには、外旋の実際に最終可動域に近いところでトレーニングすることも重要です。そして、外旋から内旋にどのように移行しているのかをテストする必要もあります。 この点に関して、私の経験のなかで、内転位(腕は身体の横)のポジションで腱板の強さを計るテストには合格するのに、問題となる“アームスロット(投球方法)”ポジションでは無惨にも不合格となる多くの投手を見てきました。正しい漸進を選択することが本当に重要なのです。 さらに、よりアグレッシブな回旋系メディスンボールエクササイズを行うことは、投球動作という独特な動作における力の産生、移行、そして受け取りを教えることに役立ちます。