マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

非特異性の腰痛は存在します。あなたはそれを認めたくないだけなのです。
非特異性の腰痛とは、多くの場合で臨床医が恥ずかしいと感じるかもしれない診断です。まるで彼らが失敗したかのように。まるで、確信の無いことが悪く、不十分な治療につながることを認めているかのように。そうではないのです。それは多くの場合で唯一の適切な診断であり、最も正確な診断なのです。他の容認できる診断として非特異性の肩の痛みがあります。または非特異性の膝の痛みもあります。なぜなら、非特異性の腰痛と言及する時は、侵害受容・痛みの特定の解剖学的な根源を誰もが知らないということを認めることだからです。これは実際に議論できる問題ではないのです。 あなたがパニックになる前に、患者のために特定の診断を見つけようとすることは価値があるということを私は間違いなく認めます。なぜなら、時にはそのような診断が存在し、それは多くの場合で厄難であるからです。しかし、覚えていてください、診断とは常に(身体の)構造に対してです。痛みを引き起こしている構造なのです。そしてもし、あなたが文献に対してとても実直であれば、侵害受容を取り除くために構造を特定してターゲットにすることができず、また、構造が痛みを引き起こしていることを確かに示すことができないということを理解しているでしょう。痛みは間違いなく、それよりもずっと多因子性のものです。そして、非特異性で構造的な痛みの診断は、私たちを驚くべき複雑性への可能性を開き、私たちの治療を向上させることもできるのです。 もし考えてみるなら、私たちの「特定的な」診断さえも実はそれほど特定的ではないのです。例を挙げると、膝蓋大腿痛症候群とは実際には一体何を意味するのでしょう?患者が訪れ、スクワットや走るときに膝蓋の周りが痛むとあなたに伝えます。あなたは彼らにスクワットをさせ、それが痛むことを発見し、もしかしたら膝に負荷をかけることで膝の痛みを再現し、あるいはその痛みは別の部位が引き金になっていないことを確認して、ジャーン!真剣な臨床医の顔をまとい、解剖学の教科書を取り出して「膝蓋大腿痛症候群」、おおざっぱに訳すと「脚の骨の上の膝のお皿の痛み症候群」であるという悲報を伝えるのです。ええと、患者は30分前に膝のお皿が痛いと伝えたばかりですよね。あなたは本当に組織に対して特定的な診断にたどり着いたわけではなく、患者が言ったことを言い換えただけです。侵害受容の源がいまだにわからず、そして間違いなく痛みの根源はわかっていないでしょう。 同じことが大多数の腰痛のケースにおいて言えるのです。私たちは痛みの組織的な根源を実際には理解していません。しかし、これは私たちの治療が非特異的であるということではありません。では、腕の良い臨床医がこの解剖学的に不確かなことについて行うのはどのようなことでしょう? バイオメカニクスの分野のみの作業では、臨床医はその人を力学的に悪化させるものを見つけ出します。曲げたり、ひねったり、ジャンプしたりといった特殊なテストを用います。患者がどの動作が痛いかを伝えてきた時、その単純な説明を「あなたは動的伸展パターンを持っています」と言い換えるかもしれません。これはCFTの研究グループにおいてみられた以前の分類方法です(しかし、もうすでに使われていません−進化とはすばらしいものです)。しかし、それが本当に意味するのは、どの動作が患者の痛みを悪化させるのかということだけです。どの構造が感作されているかを確実に推論することはできませんし、関係もないのです。多くの人達が長年かけて、これを機能的な診断であると主張してきましたが、それは診断ではないのです。脊柱を屈曲したときに痛みがある人にも同じことが言えます。これは屈曲障害または屈曲不耐性と呼ばれるかもしれません。もう一度言いますが、これは診断ではありません。これから、どの構造が感作しているのか推測することができません。私たちは椎間板を考慮しなさいと学校で教わりましたが、椎間板から「痛み」を評価しようとする唯一の研究は、それは脚から脊柱への症状が集中化していることが椎間板の炎症の根源であることを示しているだけということを示唆しています(原文はこちら)。 脊柱の屈曲不耐性と呼ぶことは、腹痛と診断するものの、それがブリトーによって引き起こされた腹部のストレスであると言うようなものです。その「診断」は正確で有益ですが(ブリトーを食べる量を減らしましょう)、正確な診断ではありません−単に炎症を引き起こすものを分類する炎症性の腰痛の診断のようなものです。 しかし、もう一度言いますが、どちらにせよ、構造的な診断は必要なく、何故ならそれでは何も変わらないからです。もし、あなたが炎症や痛みの力学的な要素に注目しているセラピストであるならば何をしますか?ほとんどのセラピストは治療をしてからその動作の過敏性に合わせて取り組んでいくでしょう。一部の人はその動きを避け、一部は干渉し、一部はただその人の脱感作のために他の何かをするでしょう。 しかし、なぜこのような過敏な動作を基準にしている機能的な診断が本当の診断ではない、または全体像すら見ようとしないのかを指摘するために、ここで少し視点を変えてみましょう。もし、腰痛を「伸展によって引きおこる腰痛」と呼ぶことを診断と考えるのであれば、より幅広い規制の中で治療するときあなたは何をしますか?つまり、あなたが生物心理社会的なモデルの範疇で治療するなかで、痛みに影響する動作や、力学的な負荷以外の他の分野に注目するということです。 あなたは、痛みの感情や認知的な原動力に注目するセラピストであるかもしれません。私たちは、不安や鬱が痛みと関連していることを理解しています。確立された手段を用いることで、あなたの患者の心配事や鬱の程度が上昇していることが、一時的に痛みの発現と悪化の両方に関連していることに気づくかもしれません。そこで、あなたはこの患者を不安不耐性による腰痛であると診断しますか?これらの変数に対して取り組む治療プログラムを出し、そして患者は回復します。ははあ、あなたは正しい診断をしました。それとも違うのでしょうか? そして、もしあなたが本当の生物心理社会学者になろうとするのであれば何が起きるのでしょうか。痛みのすべての原動力、媒介、モジュレーター、誘因、交絡要因、素因や(もうおわかりですね)を探すのです。同じ患者を評価し、痛みに関連した多くの要因を見つけます。 患者は: 脊柱の伸展に過敏になっています 痛みの発現は繰り返しの伸展に関係しています 不安が大きく、鬱になったことが何度もあります 特に痛みに関連した不安があり、損傷することを心配しています 有意義な活動に参加することをやめてしまいました 彼らの痛みがレントゲンで見つかった退行性の椎間関節の変化によるものであると信じています(通常の加齢に伴う変化と一致しているにも関わらず) 直立した姿勢が健康的だという考えを広げ続けるような持久的な対処行動に積極的に参加しています 通常の家庭での役割を負担して「助け」ようとする配偶者がいます。彼らの腰部に関するボディマップは歪んでいます。 痛みの多面性を認識することは、あなたがより特定的になることを可能にするでしょうか? 上の要因の全ては、確実に患者の痛みの一因になっているでしょう。そこで私たちはこれらの誘因要素すべてを統合した文字の混ぜ合わせ診断でも作るのでしょうか?例:伸展・不安・恐れ・反芻・意識的・抑制・ノーマル人体構造の不耐性腰痛を持っています。というように。 いいえ、そんなことをしなくてもいいのです。私たちは痛みが複雑なものであることを認識しています。私達は、いまだにこれを非特異性な腰痛と呼んでいますが、徹底的な評価を行い、いくつもの誘因要素があることが理解できました。患者の話を聞き、徹底的な検査を行うことで、彼らの器の中に何が入っているかを本質的に理解したのです。 あなたの器の中に入っているのは何か? 痛みとはあなたに害をなす全ての物(あなたの器の中のもの)とあなたにとって良い全ての物(器を大きくするもの)のバランスなのです。 ストレス 組織の損傷 睡眠不足 気苦労 恐れ 不安 癖 (それらが)器からあふれたときに痛みが起こるのです。 患者の敏感性という器の中の物に対して取り組むか、その器を大きくするためのトレーニングをするかのどちらかを行います。 痛みとは多くの場合で構造的に非特異的であることを認識した時、その痛みに関与している全ての要素を治療することができるのです。あなたのその治療法は、推測された構造的または機能的特殊性から予測された治療プログラムよりもより個別に適応したものであるでしょう。

痛みの治療のために特定の身体的介入が必要になるのはいつか?
挑戦 腰痛に関する文献では、特異的な介入(たとえば、運動制御エクササイズ、対象部位の強化など)は、一般的な活動の段階的介入と効果に差がないことを示しています。つまり、痛みの治療は、実際、執拗な問題を起すような何らかの機能障害を治すということではないと示唆しています。私が以前述べたように、最も成功するエクササイズプログラムは、先ずは症状を落ち着かせるために特定のエクササイズ/ポジション/動きを避け、それから再構築に役に立つあらゆる活動やエクササイズプログラムを実施することです。これは症状によって加減するという簡単なことです。痛みを出すような動きがあれば、行うのを短期間だけ止めてみて、それからゆっくり許容範囲を広げていけばいいのです。しかし、症例によっては、その人はある特定のエクササイズを必要とするのではないか、また痛みを解決するために身体的な何かをやっておくべきではないかという考えにいつも悩まされます。 痛みを伴う状態の多くは、取り組むべき身体機能障害がないことがあり、痛みを取り除き、障害を低減し、有意義な活動を復活させたりするために、取り組身を必要とする身体機能障害がないことがあります。実際、有意義な活動自体がリハビリテーションエクササイズになっていくのです。つまり、その人がもしデッドリフトやラン、演奏、ガーデニングをしたいのならば、それがリハビリとなります。ゆっくりこれらの活動に慣らしていけば、適応しそれらに耐えられるようになります。これらすべては、痛みの科学を上手に教育することによって育てられます。私たちには、症状に対する彼らの思い込みを変える役割があり、最終的に彼らは大切なことを再開する“許可”を彼ら自身に与えることになります。ホッジスとスミート(2015)の記述によると: "動きや活動を回避しようとする認識に挑戦しながら、身体的活動に段階的に慣らすことを教えてくれるのが痛みの科学です。" リハビリは治すことというより、むしろ促進ということ その人を診る時、治療が必要な人としてではなく、強く適応力がある人と捉えることで、私たちのエクササイズの選択が変わってきます。もはや、何か重要な活動をスタートするための前提条件というものはありません。多くの症例では、低下した筋力、張り、筋の発火パターンの“乱れ”などが原因で痛みがあるのではありません。したがって、その人たちの痛みを取り除いたり、運動を再開させたりするために、これらに対して特化して取り組む必要がないかもしれないということです。適応を可能にしてくれるのは日常の活動への露出であり、このことはマックス・ズスマンが10年以上も前に雄弁に記しています。 "慢性疼痛患者の脳で起こっているエラーを納得させるために、彼らをエクササイズや日常の活動へ安全に露出しなさい。" 特定のエクササイズが必要になるのはいつか? これは難しい質問です。身体的介入という点で、まさに最適である介入を見つける必要のある症状がなくてはなりません。言葉を変えて言うならば、ある障害が存在し、しかもその障害を治し痛みから救ってあげるのに唯一の解決策しか存在しないという状況です。おもしろい思考の実験ですが、痛みのパズルを解く方法がほとんどないような状況を考えつきますか? 治療の選択肢が制限されるような状況を思いつきますか? 下記は、私たちが使える3つの異なる身体的介入の要点をまとめた簡単な図です。図の下にある線は介入の選択肢を考えるのに役立つかもしれません。特異性がより高い介入は左、介入の特異性が低くなればなるほど右となります。 では、どのような時に特異性が必要になるでしょうか? 上の図で、症状/活動の調節における役割が分かります。この構成要素の一つはシンプルで:痛みを見つける:痛みを変える。もし、何かしたことで痛いのであればそれを短期間だけ回避するか、または痛みを受け入れその動きに対して脱感作させるのもよいでしょう。もし、曲げて痛みが出るならば、短期間だけ脊柱を中立位のまま持ち上げ動作を行ったり、新しい動きを強化できるようなエクササイズを選択してもよいでしょう。しかし、このことは、あなたの股関節屈筋群が硬く弱化していて、臀筋の発火がなく、脹ら脛が張っているから、ランニング/デッドリフト/ガーデニングを始める前に治療する必要があると主張しているわけではありません。 しかし・・・もしかしたらこれらの機能不全は時には重要なのかも? そこで、私たちは問う必要があります。“この身体的機能不全/症状は、患者の訴える痛みに関連しているのか?”または、“もしそれに対処しなかったら、痛みは残ってしまうのか?” 脱感作を起すために何かを“治す”必要があるのかもしれない症例 例1:背屈の制限は、脊椎のポジショニングの選択肢を減らす。 システムに感作をし続けてしまう動き方を変えようとしても、足首の背屈の欠如がそれを抑制してしまうという場合があるかもしれません。感作が落ち着かない限り再構築もできません。たとえば、深くスクワットしたくても、脊椎がある角度を越えて屈曲すると腰部の状態が増悪するとします。足首の背屈(または、胸椎の伸展かもしれませんが)が増えない限り、増悪させてしまうこの姿勢を回避できる脊柱の屈曲角度に変更することはできないでしょう。ここでは、機能不全は関連のあることになります。しかし、もしほとんど足首の背屈を必要としない平地をゆっくり走るランナーに対応するのではれば、背屈の制限は関係ないでしょう。 ひとつ注意しておく点:上記の例でさえも、背屈に対しての特別な介入は必要ないかもしれません。多くのセラピストは、脊柱の脱感作をすることができ、患者を痛みのない状態で同じ運動に復活させるという症例を作ることができます。要するに選択肢は多くあるということです。 例2:高負荷の活動にもかかわらず特異的な弱化があるときも運動の選択肢の幅を狭める。 他の例は、股関節の伸展筋群の弱化に関するかもしれないものです。しゃがんだり負荷下で膝を屈曲させたりすることに対して両膝が敏感である患者がいるとします。膝が脱感作するまでの短い間、股関節に負荷をかけるようにシフトすることは合理的です― 股関節のヒンジが代わりをするだけです。これは、股関節の強度に関わらずたいていの人はできます。なぜなら、どちらにしても最大能力に達するほどのことではないからです。テクニックを学部必要があるだけです。しかし、ジャンプやスクワットを激しく行う人に取り組む場合、股関節の伸展筋群の弱化があると負荷を膝や脊柱から股関節へとシフトするというわけにはいかなくなります。このような激しい負荷がかかる症例では、この機能不全は関連のあるものとなります。 しかし、一般的な腰痛を患っている人は、筋が弱化しているとか臀筋が抑制されているからという理由で痛いわけではありません。関節可動域の減少や筋力の減退、発火パターンの乱れは見られるかもしれませんが、これらは関係ありません。なぜなら、その人の生活において、それぞれの関節が持つ全能力を使うようなことは決して要求されないので、その欠如が他の部位に機能的な影響を及ぼすはずがないからです。 このような症例では、特定の身体的機能不全に取り組む必要がありません。これらは、治すというよりも促通に関する症例です。 その他の特異性の例 経験則として(本質的に議論の余地がある:))、痛みの発信源が末梢神経である侵害受容性のものと考えれば考えるほど、局所的で特異的な治療を施すことで得られる意義は大きくなるでしょう。ちょうどよい例として腱障害があります。もちろん私たちは中枢神経系の要素も重要だと認識していますが、侵害受容性の痛みを鎮め、傷を癒し、適応のために特異的な負荷をかけることもその腱に必要と考えます。しかし、必要としているのは特異的なエクササイズではないかもしれません― 単に、管理された負荷を徐々に増やしていけばいいのです。 少し長い投稿になってしまいました ずいぶん記述しすぎましたが、要点は、実際どのぐらいの頻度で“特異的な”改善や治療が必要なのかを考えることです。私個人は、特異的な“治療”はかなり限られていると考えています。たとえ“治療”が必要である場合でも、それは一時的なものに過ぎません。このアプローチは、私たちがいかに適合力を持つのかを認識したものです。私たちの仕事は、症状を鎮めそして再構築することです。症状が一旦鎮まったならば、徐々に負荷をかけるようにし、患者が希望する意義のある活動に戻していくことです。身体とエコシステムは適応するでしょう。 しかも、機能障害があっても筋力強化を加えると良いと私は信じていますが、それはまた別の機会にお話ししましょう。

論文批評:脊柱屈曲の計算と意味合いが間違っている パート2/2
脊柱屈曲の数値の計算が間違っていますよ、と指摘を受けた研究者グループが行なった2つ目のリサーチでも、問題は解決されておらず、計算とその解釈に誤りがあった点に関して、グレッグ・リーマンが解説を提供します。すべてのリサーチが優れたリサーチではないということを気づかせてくれます。

論文批評:脊柱屈曲の計算と意味合いが間違っている パート1/2
脊柱屈曲は、腰椎の健康のために避けるべきである、特に荷重時の腰椎屈曲は避けるべきだ。という主張は様々な場面で耳にする論議の一つですが、果たしてリサーチのエビデンスは何を伝えてくれているのでしょうか?実際に発表された論文の脊柱屈曲の値を導き出す計算が間違っているというポイントをグレッグが指摘します。

運動と変形性膝関節症に関する専門家の偏見との奮闘
私たちは、膝の変形性関節症(OA)の管理のための新しい臨床ケア基準を持っています(リンクはこちら)。これは、私が実践する方法と私が教えることと完全に一致しています。 これ以上の偏見を確認することはできず、私は幸せであるべきです。しかし、私は心地悪いのです。 それは私が愛するものを支持します: 良い教育 適切な画像化 人間を中心としたケア その人全体に対応する 関節のレジリアンシーに関する楽観主義 「磨耗や損傷」に関する信条の再構築 栄養 減量 痛みと機能のための運動 すべて良いことのように見えるでしょう?そう、しかし、私は同様の臨床結果を持つ他の保存的アプローチを提唱することなく、痛みと機能のための運動を提唱することに気まずさを感じているのです。私たちは一貫して、他のあらゆる介入と同様なエビデンスに基づく実践の厳格な基準を、エクササイズに対しては保持していません。そして、この一貫性の欠如が私を心地悪くさせるのです。私にとって、ここで強い意見を持つことは学術的に真実性に欠けるのです。運動に関する研究基盤を簡単に批評し、私たちの偏見が患者のケアにどのように悪影響を与える可能性があるかを説明させてください。 運動は他の介入と比較して非常に低い基準に保たれています。 研究者と臨床医は、研究が行われる前に、運動と身体活動が膝の変形性関節症の主要な治療法であるべきであるという決定を下したことを私は主張します。 私達が介入を評価する時のゴールドスタンダードは、ランダム化比較試験(RCT)の宝庫であることを願っています。これらのRCTでは、対照群が必要とされます。介入の非特異的な影響を制御する必要があるのです。これは、運動と変形性膝関節症の世界では決して起こらないか、まれにしか起こらず、それを誰も気にしていないようです。 この例は、GLADのエクササイズと教育の試験(リンクはこちら)でしょう。これらは、エクササイズと教育が効果的かどうかをテストするために設計されたものではない、実用的な研究です。対照群がないため、その結論を出すことができません。 要約を読むだけで、著者がGLAD介入が痛みの軽減と薬物使用の減少につながったと述べているのがわかります。しかし、それを言うことはできないのです。対照群がなければ、その結論を出すことはできません。私たちは、鍼治療や電気療法などの他の介入に対して、このような種類の試験を受け入れはしないでしょう。実際、多くの臨床診療ガイドラインでは、対照群が存在しないため、受動的治療法に関する文献を明示的に除外しています。 運動と他の介入との間で直接比較を行うと、運動はそれほどうまくいかないことがわかります。たとえば、Messier 2021の論文(リンクはこちら)では、高重量の抵抗トレーニングは非常に低負荷の運動プログラムを上回らず、注意対照群を上回りませんでした。GLADプログラムを生理食塩水注射と比較したときにも同じことが見られ、グループ間で違いは見られませんでした(リンクはこちら) なぜ私はおどおどしているのでしょうか? 私は、運動と変形性膝関節症の最大の応援団員になりたいのです。この基準があらゆる種類の運動を提唱し、身体活動のための多くの選択肢を提供するという点で、非常に患者中心であることを嬉しく思います。 これは、「適切なアライメント」と「神経筋コントロール」の運動を提唱していた元のGLADプログラムからの大きな改善です。(当時の人々は、そのタイプの運動の必要性の証拠として、すべての非対照GLAD試験を引用しました…彼らは決してそうすべきではありませんでしたが、やってしまったのです。)幸いなことに、私たちはそこから前に進みました。 しかし…もし私が文献をよく知っているのだとすれば、いかにして学術的に厳密で正直であることができるのでしょうか? どれだけ不十分にテストされているかを知っているのに、いかにして運動を支持することができるのでしょうか? 私たちは他の一般的な介入をはるかに高い基準に保っているがゆえに、それらの介入を省略する基準を、いかにして支持できるのでしょうか? または、運動に関する研究が多く行われているので、臨床診療ガイドライン(CPG)に含めるべきであると言いますが、そのような推論は循環的で自己充足的です。私たちはこの説得力のない運動研究を続けており、それがCPGで繰り返され続けています。そして、CPGでこれらの介入を最小限に抑え続ければ、当然それらを研究する試験が少なくなるために、その他の介入(手技療法、受動的療法、鍼治療など)に関する研究は限られていると言われることになるでしょう。単に自己充足的になるのです。運動は厳密さなしに受け入れられ、他の形態のケアは研究がないために却下されます。 私たちは本当に人間を中心に考えているのでしょうか? 人間を中心としたケアの基盤は、選択肢の提供です。そして、人々が持っているオプションと、それらのオプションを支える研究について、私たちは正直でなければなりません。このような臨床ケア基準とCPGは、文献の非常に偏った解釈に基づいてオプションを単に選別しているのです。これは基準からの引用です: 「治療用超音波や電気療法などの受動的な手技療法は、変形性膝関節症の治療において重要な役割を果たしていない」。 これもまた、これらの受動的な様式に関する研究の解釈に基づいています。 実際に痛みと機能を調査する論文を見ると、受動的様式グループが痛みと機能に同等の減少を有することがわかります。しかし、これらの論文の多くには対照群が存在しません。そこで、CPG委員会はそれらの論文を無視してしまうのです。 他の論文では、偽の比較グループがあります。そして、何が見つかるでしょうか?両方のグループが痛みの軽減と機能の改善を示します。しかし、違いがないため、私たちは結果が現実的ではないと言います。 しかし、繰り返しますが、私たちは何をしたのでしょうか?私たちはこれらの介入を、運動とは異なる基準に保っているのです。 徒手療法や鍼治療でも同じことが見られます。エクササイズを徒手療法に対して直接比較してみると、痛みの軽減や機能の違いは見られません。しかし、運動に関する研究が非常に多いため(弱いものですが)、ガイドラインはより支持されているものとして運動を提唱します。それがより良いということを意味しているわけではないのです。ただ、研究がより多いというだけです。これは私が先に述べたように、CPGによる自己充足的な予言です。 もし私たちが患者に対して本当に正直であるならば、彼らには痛みと機能を助けるための多くの選択肢があると言うのは公平だと思います。私たちは、少なくとも私は、正直に言って、エクササイズが優れていることが「証明されている」とは言えません。そして、私たちがそれを言うことができないのであれば、これらのガイドラインはどのようにそれを言っているのでしょうか?なぜ彼らは人々から選択肢を奪うのでしょうか?この人間中心のケアはどうですか?私には門番をしているように見えます。 運動やその他の選択肢についての、より正直な見方は何なのでしょうか? 臨床医と患者の会話は、次のようになるとイメージします: 「運動は膝の痛みを和らげるのに役立つかもしれない選択肢の一つだよ。運動を続けて活動的でありたいのであれば、絶対にできますよ。運動は完全に安全で、あなたにとって有害ではありません。変形性関節症を悪化させることはありません。エクササイズプログラムを開始したいのなら、いくつかのオプションとガイダンスを提供できます。エクササイズには、転倒防止、健康的な老化、すべての原因による死亡率の低下など、健康上のメリットもたくさんあります。」 「しかし、運動をしたくない、何か他のことを試したい場合には、痛みや機能の改善を報告している人々がいるという研究や多くの事例がいくつもあります。鍼治療、理学療法、手技療法、装具、さらには歩行の再トレーニングなどが役立つかもしれません。しかし、これらの問題は、誰かがあなたに対して行う介入であるということです。非常に受動的です。クリニックに来なければならず、費用がかかる傾向があり、運動のような健康効果は得られません。」

痛みやケガ、さらにパフォーマンスのマネジメントにおいて、生体力学が問題になるとき パート2/2
WBM #4:鈍感にするための一時的な動きの修正 (続き) 一時的な動きの修正は、一般的に多くのセラピストの間で使われる、症状によって加減するアプローチです。こうすると痛いので、しばらくの間、他のやり方でしましょう。患者によっては、そうすることによって、自分で痛みを制御でき、できなかったことを始めるのに有効かもしれません。治療の一環として必要かどうか分かりませんが、役には立ちそうです。 ここでは、 “正しい”動き方がひとつしかないと言っているのではありません。むしろ、現時点で痛みが少ない動き方があるということです。シンプルです。 また、痛みを軽減させるのは生体力学だけであると考えるべきではありません。生体力学的な変化は心理社会的要素に大きく影響するかもしれません。私たちは、ただ常に生体力学の枠組みで治療を説明してきました。もしかすると動きを修正することは、認知的な挑戦なのかもしれません。−自分自身のストレングスに直面させられ、自分が感じている痛みの見方を反証させられることに繋がるのです。 リスク:痛みを制御するために動き方を変えるように指導する場合、安全ではあるが有益とは言えない行動をさせてしまうリスクがあります。私達が介入しすぎることもあります。症状によって修正する方法は、リングシフトや仙腸関節の矯正のような非常に極端な介入をしてしまうことがあります。筋膜網とやらに歪みが起こるかもしれないという理由で、耳たぶが一直線に並んだ姿勢でなければならないなどと、患者に思って欲しくはありません。また、動き方のチェックリストを作り、念入りに修正しながらでないと、特定な動きが行えないと思い込んで欲しくはありません。一時的な変更であることを説明するべきだというのが私の意見です。 最後になりますが、症状によって動きを修正する方法による運動学的な変化は、恐怖による運動逃避や動きの制限をする人に対して、良いアイデアではないかもしれません。これらの人たちは、すでにさまざまな動きを避けてきているので、むしろ痛い動きや不安な動きにさらすことが治療になります。ここでも難しい決断を下さなくてはなりません。余計なことをしてかえって悪化させてしまうかもしれませんが、焦って急ぐべきではありません。 WBM #5:習慣になってしまった動きの中断 関係変数:運動制御、ストレングス、ROM #4にとても似ています。これは、痛みがある時に繰り返し同じことを行って、悪化させてしまうという考えです。たぶん気づかなかったのか、または、生体力学的要素に障害が起きて、回避できなかったのか。ここでも余計なことをして悪化させるかもしれませんが、慌てるべきではありません。 さらに、私たちはたいてい自己修正が備わっているものだという考えが根本にあります。もし、あなたが座っていてお尻が痛くなり始めたら、動きます。侵害受容覚が働いて、痛みや損傷が起きる前にアクションを起こします。もし自分で修正できず、動けなかったら、損傷が起こるでしょう(床ずれを思い出してください)。 彼らが苦境について間違ったことを信じ込み、痛みに敏感になるような動きをし続けている患者がいるかもしれません。座っている時も背骨をニュートラルに真っすぐに保ち、背骨は屈曲するべきではなく、常にコアを20%ブレーシングしているべきであると、彼らは信じているのかもしれません。このような場合、彼らは健康的である前かがみの姿勢や様々な動きを避けていたために、習慣となってしまった彼らの動きが、感作を起こしているのかもしれません。 他の例が、ストレングスや柔軟性などが重要であるときの説明をするかもしれません。これから紹介するビデオで、私の娘がバック転とブリッジをしているのをご覧になれます。彼女の股関節はほとんど伸展していませんが、腰が大きく伸展しています。彼女の習慣で、いつも伸展は腰で行っています。もし、彼女に腰痛があって伸展により増悪するとしたら、腰にとっては数日間の“お休み”が与えられるかもしれないテクニックを使ってそのスポーツに取り組むのは難しいでしょう。彼女は、引き続き感作を起こしてしまうかもしれません。前足部で着地をすることでアキレス腱痛や前足部痛、脹ら脛痛を繰り返し起こすランナーは、フラットフット着地に変更して走ることで効果が見られることがあります。しかし、このような簡単な変更を行う能力がなければ、症状/負荷を調節しながら走り続けるのはもっと難しいことでしょう。 これについては、ボート選手に行われた症例研究/ランダム化比較試験がここでご覧になれます。この試験のすばらしいのは、脊椎の運動学は症状によって変化させましたが、その変化をずっと保つ必要はなかったということです。 生体力学的要素に左右される動きの習慣についての例として、股関節外転のストレングスがあります。私たちの多くは骨盤の下制や股関節の内転が増えても走ることができます。ランニングに関連した痛みがあるということは、傷害の宣告ではありません。しかし、いつもと違う痛みが出てきたならば、骨盤の下制に取り組んでみることは、実行可能な選択肢で効果的かもしれません。ランナーにとってストレングスは、反対側の骨盤の下制に貢献する要素かもしれません(ここ&ここ)。つまり、不足部分を強化してみることで、痛みを軽減したり回復したりできる動きに変えられるように促してくれるかもしれないのです。 まとめ ここでは、多くの “かもしれない、たぶん、だろう”という言葉を使いました。痛みを持っている人を助けるにあたり、生体力学はひとつの選択肢であって、唯一の解決策ではないという考えです。生体力学を変えることや“生体力学的”アプローチは有効でしょう。しかし、必ずしも必要ではないかもしれません。私はこう提案します。負荷が大きくなり、組織の損傷が大きな弊害になったら、生体力学はかなり重要になり、選択肢というよりも“必須要素”の一つになるでしょう。また、損傷につながるような外的負荷に反応できるようにするためには、生体力学的テクニックを変えるより、動きに対する準備やトレーニングの最適化、負荷への反応などがより重要になるということも提案します。

痛みやケガ、さらにパフォーマンスのマネジメントにおいて、生体力学が問題になるとき パート1/2
私は、生物心理社会学の専門家です。 痛みがある人にとって、たいてい生体力学は重要になると思います。 これら二つの事は相反してはいません。 生体力学が痛みやケガの要因になる状況について、ひとつの見解を下記に示したいと思います。つまり、「生体力学が問題になるとき」(When Biomechanics Matters:WBM)についてです。これに関するビデオ講義がウェブにあったと思いますが、アップされている自分の講義をすべて把握しているわけではありません。下記に挙げた状況のほとんどは、重複したり、互いに影響を打ち消し合ったりします。みなさんには自分なりの分類方法があるかもしれませんが、ここでは私のものを紹介します。 WBM#1: 高負荷がかかる活動 関係する要素:テクニック/運動の質、ストレングス、ROM、準備度。 要点:外的負荷が、組織の負荷耐性能力を超えると、損傷が起こる。 この例は、ハムストリングの挫傷でよく見られます。高負荷がかかればハムストリングは断裂を起こす一方、ハムストリングのストレングスはケガのリスクを軽減するのに一役買います。他のほとんどの筋断裂にも同様なことが言えるでしょう。ストレングスの基礎は、重要であるように思われますが、それが唯一の要素ということではないと考えます。しかし、生体力学的な影響(ストレングス)が大きいことを示す好例です。 これに関連した例として、非接触のACL(前十字靭帯)断裂があります。リスクを軽減するための要素は、ストレングスだけではなく、テクニックや動きの質もあります。たいていの膝は、動的な外反方向への低負荷に耐えられ、さらに膝が25度以上屈曲していれば動的な外反方向への高負荷にさえも耐えられるとされています。しかし、状況によっては、膝の外反方向への動的負荷が、ACLにとって“過負荷”となってしまい、損傷を起こすことがあるのです。これは、ひとつの生体力学的要素(ストレングス)が保護的に働き、その他の生体力学的要素(テクニックや準備、筋収縮のタイミング)を無視してしまうことを“可能”にする良い例です。その原理を証明するものとして、ACLに関するFIFA-11予防ブログラムがあります。これらは、ケガのリスクを軽減するとされていますが、そのリスクの減少を調節する要素を研究者が測定してみると、関節運動学/技術に何の変化も見ることができません。そのため、選手たちは未だにクオリティーに問題がある動きをしながらも何とか対処しています。 WBM#2:パフォーマンス そうです、あなたがどのように動くかは、パフォーマンスに影響します。これは、生体力学が最も重要となる分野かもしれません。ジャンプやリフティング、スローイングなどすべては、動きの質に影響を受けます。しかし、痛みやケガは別の話です。 WBM#3:準備は質に勝る - 長期に対する短期の仕事量の比の重要性 関係する要素:適応性と適応能力の限界 自分の身体がこれからどのようなことにさらされるのかに対して、準備しておく必要があります。私たちは身体にかかるストレスに適応することができるとみなし、また、そのストレス自体は本質的に悪いものではありません。このことは、生物心理社会的なストレス要因範囲のあらゆる側面でみられるでしょう。 長期に対する短期の仕事量の比は、仕事量やストレスが一定でゆっくりと増していく過程を経験していれば、急激にかかる負荷でも大きな変化に耐えられることを示唆しています。これは、人間であることの根本です。身体は、ストレスにポジティブに反応します。もし身体が準備していた以上の生体力学的な負荷がかかれば、ケガのリスクは増えるでしょう。 しかし、私達の適応能力は限られており、適応速度にも限界があります。これは、職場環境によく見られ、累積性負荷の合算が腰痛のリスクを高めます(興味深いことに、負荷の持ち上げ方が原因ではなかった)。また、筋断裂のようなケガにもよく見られ、個人レベルで損傷を予知する能力がなかったとはいえ、全力疾走による負荷がケガのリスクを高めるかもしれません。 この適応性モデルの興味深いのは、それが力学的および物理的な仕事量に限ったことではないということです。私たちの適応性、物理的な仕事量への反応、そして“準備度”は、その他の心理社会的ストレス要因の影響を受けるのです。これは、ソリガード氏の最近の論文で詳しく説明されています。 WBM#4:鈍感にするための一時的な動きの修正 関係する要素:運動制御、ストレングス、ROM、動きによる鎮痛 ここでも、これは他の要素と相互関係にあります。痛みを感じるときは身体/自分を休ませてあげればいい時もあります。ストレスは適応を起こしてくれる良いものであると考えますが、しばしば負荷を手控えたい時もあるかもしれません。 セラピストとしての私たちの挑戦は、“さらす”のか、または、“守る”のかという問に答えなくてはならないことです。“さらす”ということは、プラスの適応を起こすために新たな刺激が必要とされることです。そして、“守る”ということは、刺激となっているものを取り除くことをより重要視するということです。または、さらされることに対して、まだ“準備”ができていないこともあるかもしれません。 この例は、痛みに対処するために症状によって修正していくアプローチにしばしば見られます。急性期の組織の挫傷であれば、サポートで負担を減らし刺激を調節するのが適切かもしれません。また、継続的な痛みであれば、動きを変えることで、自分自身で痛みが制御でき、行えなかった活動や日常生活を取り戻せるかもしれません。 症例: 6ヶ月間の膝痛を患っているランナーがいます。ランから休みを取ってエクササイズをし、徐々に体調を回復しようとしています。膝はまだ痛みます。歩幅をあれこれ変えてみて、歩行速度を7.5%上げました。これによって、膝にかかる負担が約10−15%変わります。そして、なぜか痛みを感じずに2Km多くは走ることができました。すばらしい。この調子。 腰痛患者がいます。動けないほどではないようです。運動恐怖症はほとんどありません。痛みを怖がってはいません。ただうんざりしてしています。しゃがもうとして前屈するたびに、いつも痛くなるようです。脊柱をニュートラルにしていれば比較的痛くないので、脊柱があまり屈曲しない方法で、スクワットやジャンプ、他の有効な運動を指導することができました。痛みも少なかったようです。これは、痛みの感覚を減らすための一時的に行う対処であると説明します。脊柱の屈曲はそもそも悪いことではありません。しかし、なぜか前屈を繰り返し痛みに敏感になってしまったのです。 頭上に腕を挙げると肩に痛みが出る患者がいます。授業中に質問のために挙手したり、壁にペンキを塗ったりするので、この動作を繰り返し行っています。肩をすくめてから腕を挙げると痛みが緩和します。包括的な肩の能力のプログラムの一部として、腕を挙上する際、このような単純で一時的な修正を行います。
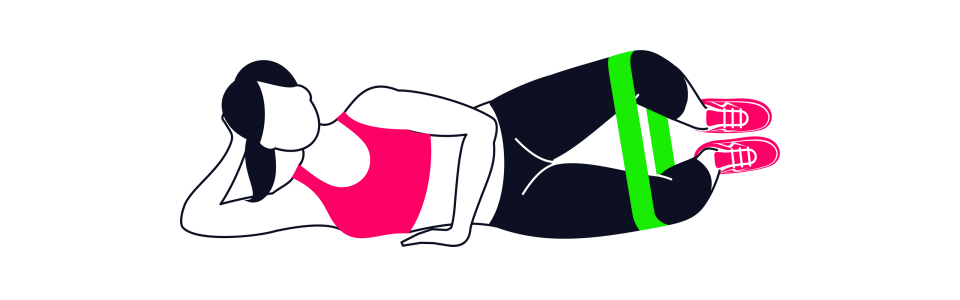
ファンクショナルエクササイズとは十分でない用語である。包括的能力というのはどうだろうか。パート2/2
バンドウォークは無駄なのでしょうか? そうではありません。バンドウォークはランナーにとって有益なものになり得ます。私は滅多に使いませんが、ランナーがバンドウォークを使ってトレーニングをすることは意味があると思っています。バンドウォークは、「機能」という最も単純なカテゴリーを満たしています。ランナーが必要な筋肉グループを鍛えることができます。こういったエクササイズは、それらの筋肉の能力を高め、おそらく力学的効率性の向上につながり、障害予防にさえ役立つかもしれません。しかし、もしバンドウォークが、ランナーのフォームを実際に変えることに対し機能的に十分であると考えると、残念な結果に終わってしまうかもしれません。 ストレングスコーチやリハビリの専門家にとって、この最後の正当化に関する問題は、それが単純すぎることです。 私たちは治療家として特定のエクササイズに対して特別な知識を持っていると思いたいのです。しかしそんなことはありません。特別なエクササイズはありません。一生懸命に鍛え、賢く鍛え、強くなり、パワーを構築し、忍耐を構築し、能力を高め、耐久性を高め、衝撃を吸収する能力を築き、振動を抑え、あらゆる範囲で筋力を発揮するのです。一般化した、全面的に良質なプログラムを使えば、いい結果が得られるでしょう。アスリートに何が欠けているかを確かめるために何か評価を使用して、その結果をもとに必死にトレーニングをすれば、より良くなるでしょう。しかし、ランニングエクササイズというようなものはないのです。そしてそれは、研究や専門家が勧めていることとは真逆のことです。ストレングス&コンディショニングの専門家(パワーリフティング、オリンピックリフト、矯正エクササイズ、ピラティス、ヨガ、コアの安定性など)を捕まえて聞いても、皆、ランナーを成功に導けると誓うでしょう。彼らは皆おそらく正しく、つまり、特定のランニングエクササイズなどないのです。 では、クラムシェルがより優れているのでしょうか? まさか!クラムシェルは大抵の場合、最悪です。私はかつて思っていた程効果がないために、クラムシェルを嫌っていました。ランナーは決してやるべきではないものだと思っていました。クラムシェルは治療のためのエクササイズで「機能的ではない」と思っていました。 クラムシェルでは、より少数の筋肉しか働かず、寝た状態で行い、運動学的にランニングとは異なり、先述した機能的な原則の多くを満たしていません。しかし、クラムシェルは、バンドウォークとは大きく異なる筋肉を鍛えることができます。これこそクラムシェルが有益なエクササイズに成り得るポイントです。 クラムシェルは、股関節を90度に屈曲した状態で、股関節を外旋させます。90度では、多くの臀筋(大臀筋、中臀筋、梨状筋)の引く方向が変わるため、股関節の外旋を行う筋肉は深部の外旋筋だけになります。この外旋筋の能力を鍛えることは、ランニングに活きる可能性があります。 私はかつてクラムシェルを見下していました。そしてその後、クラムシェルを多くのランナーに試し始めました。多くのポジションにおいて強さを示した何人ものランナーが、クラムシェルを行う際に震えていました。おかしいですが、素晴らしい片脚スクワットができて、股関節の外転も強いのに、10回か15回のクラムシェルを行うことが困難なのです。これは何を意味しているでしょうか?機能の重大な欠陥です。ここでクラムシェルを行うことを勧めますか、それともその特定の動きに対処する何かを勧めますか?この場合は、クラムシェルを勧めるのが良さそうです。ランナーができないのなら、その欠陥に取り組みたいと思います。クラムシェルができないことが問題だとは言い切れませんが、パフォーマンスに関係のある筋群において、こんなに単純なことができないのなら、それは対処すべきでしょう。 しかし、全てのランナーに「機能的な」プログラムの一部としてクラムシェルを行ってほしいのでしょうか。もちろんそんなことはありません。クラムシェルはそれには適していません。クラムシェルを行うのは、特定のランナーの特定の制限に対応するため、エクササイズの処方が「機能的」である場合です。 では、私は何を勧めるでしょうか? 「機能的」の全ての要素に対処することのできるエクササイズはありませんが、それこそがランナーが包括的なプログラムを行うべき理由なのです。 もし私にバイアスがあるなら、「包括的能力」をトレーニングする傾向があるでしょう。これは、ランナーをアスリートのようにトレーニングするという意味です。筋力、高負荷のパワー(例:クリーン)、低負荷のパワー(プライオメトリックス)、様々な範囲(中間の範囲だけでなく、最終範囲や変ったことも)のエクササイズや、片側性のエクササイズを鍛えることのできる大きな多関節複合のエクササイズです。「機能的」という言葉の問題は、言葉の範囲が広すぎてエクササイズを正当化するには意味がないことです。改善したいと望む神経筋システムの特定の許容能力を基準にエクササイズを選んでください。 それはさておき、もし「包括的能力」を鍛え、バランスのとれたトレーニングプログラムを構成するとして、本当に詳細な評価をする必要があるのでしょうか?エクササイズは評価にはならないのでしょうか?エクササイズのシステムがとても良く構成されていて、評価を通じてわかるかもしれない全てのことに対処できるということはないでしょうか。 重要な問い:なぜあなたはそのトレーニングを行なっているのですか? ランナーには、筋肉、関節、腱、ランニングがもたらすストレスに対する神経系の耐久能力を鍛えることのみを考えます。これらを鍛えることにより、ランナーはより力強く、力学的に効率的になり、怪我をしにくくなります。 エクササイズはランニングフォームの変化に役立つのでしょうか? これはランニングのように見えるエクササイズの背景にある考えです(例 クラムシェル)。そのようなやり方でトレーニングを行うことはランニングフォームの改善につながります。しかし、そうではないことを示している証拠もあります (Willy 2011)。私たちは恐らく、フォームをトレーニングしているわけではないでしょう。特定のエクササイズを選択することによってランニングの生体力学を矯正しているわけでもありません。ランニングへのキャリーオーバーのある運動プログラムを刷り込もうとしているわけでもありません。こういったことをしたいのであれば、ランニングをしている間に行わなければなりませんし、その際になんらかのフィードバッグを得られるようにする必要があります。私たちの身体は、異なる姿勢やフォームを獲得するために収縮または弛緩される筋肉をもった操り人形ではありません。それは運動制御能力であり、他のエクササイズをすることによって変わるものではありません。 ではあなたはなぜ、あなたの指導するランナーにそれらのエクササイズを処方しているのですか?
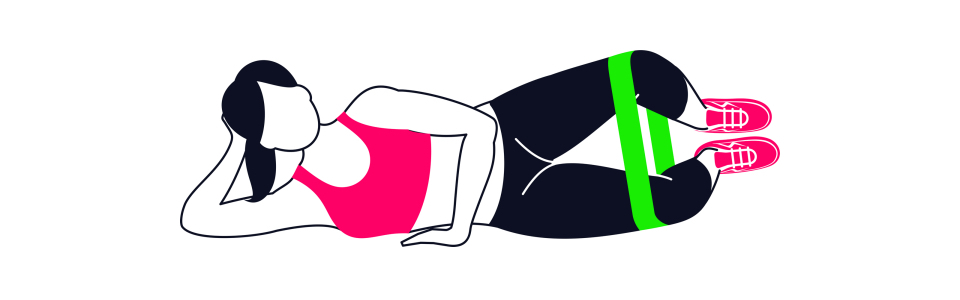
ファンクショナルエクササイズとは十分でない用語である。包括的能力というのはどうだろうか。パート1/2
数年前、私はランナーのために、評価の低いクラムシェルエクササイズを擁護している自分を発見しました。私は、他の理学療法士たちとクラムシェルエクササイズがバンドウォークエクササイズ(弾力性のあるバンドを膝/足首の周りに巻き、前方向、横方向、後ろ方向へ歩くエクササイズ)より「機能的」ではないかどうかという点について議論していました。私は、どちらのエクササイズも機能的ではない(または同じ程度に機能的)が、どちらのエクササイズにも意味があると提案しました。そのときは誰も説得できませんでしたが :) 私に反対する共通の意見は、クラムシェルは最悪で、バンドウォークエクササイズの方がランナーにとって、より「機能的」だから優れているというものでした。私は、バンドウォークは確かにより優れたエクササイズかもしれませんが、それはバンドウォークがより「機能的」だからではないと議論しようとしました。 問題は「機能的」という言葉です。 「機能的」とは一体何を意味するのでしょうか。 バンドウォークエクササイズがクラムシェルに比べてより「機能的」だと誰かが言うのを聞いた瞬間、ナンセンスだと思いました。「機能的」という言葉を聞いた私の反射反応は、脳の中で「機能的」という言葉を「動きの特性」あるいは「運動学特性」に訳すことでした。つまり、行っているエクササイズが特定のスポーツ動作(この場合はランニング)の運動学(特に変位や関節角度)に適合するということです。 運動学/動きの特性を使って、バンドウォークやクラムシェルを評価することは、難しいことではありません。機能(運動学特性の定義を使う)という意味ではどちらも最悪です。ランナーは横向きに寝た状態で脚を上げる(例 クラムシェル)ことはないですし、膝に伸縮性のあるバンドを巻いて横向きに走ることもありません。 ですから「機能的」を定義しましょう 「機能的」を「運動学的に特定の」何かであるとする私の反射的翻訳は、もう少し狭義です。 私にとって、機能とは、そのエクササイズが、アスリートが達成したいと思っているタスクに対して何らかの関連性があることを意味します。この見方をすると、エクササイズは複数の意味から機能的、あるいは関連性のあるものになります。 1. 動きの特性:これは、エクササイズのタスクが、鍛えようとしている運動のタスクに、いくらか似ていることを意味します。つまり、そのエクササイズが、目標のタスクに似た形態(運動制御のため)であるということです。さらに、神経筋の動員パターンが似ているということも示唆しています(例:筋肉のオンセット、オフセット、割合など)。例えば、スクワットは椅子から立ち上がるというタスクに対してとても機能的なエクササイズです。 2. 筋肉または関節の特性:これは、目標のタスクで使われる筋肉と同様の筋肉を鍛えていることを意味します。 3. 速度特性:これは、目標のタスクが速く動くことを求めるなら、トレーニングでも速い動きをするべきであろうということです。目標のタスクであるスピードの要求につながる何らかの成果があるのであれば、エクササイズは「機能的」ということになります。この成果を得るために、実際に速く動く必要はなく、時には速く動こうとする意図だけで改善することもあります。 4. 動きの方向性:目標のタスクにおいて減速が多く求められるのなら、エクササイズの中で伸長性負荷の能力を鍛えるべきでしょう。ランナーは、0.01秒以下で起こるランニングの衝撃段階において股関節内転が増加していると考えることができます。そのため、エクササイズを機能的にするためには、この減速能力をその特定の時間枠で鍛えるべきでしょう。 5. 環境:エクササイズは、目標のタスクの環境と似たものであるべきです。環境とは、重力とエクササイズの関係かもしれませんし、社会的、あるいはパフォーマンスの背景かもしれません(例:人が叫んでいる中でフリースローを打つ) では評価の低いクラムシェルとバンドウォークはどちらがより機能的なのでしょうか。 ひっかけ問題です!答えることはできません。機能のスコアシートはありません。より良い質問は、何がランナーやアスリートにとってより有効か、です。まずはじめに、なぜそのエクササイズを指導しているのかを答えられなければなりません。各エクササイズに対するあなたの意図は何ですか?何を達成しようとしていますか?もしあなたが、そのエクササイズが「機能的」だから指示しているとしたら、それは質問をはぐらかしているだけです。機能的という表現は十分ではなく、何らかの特定の成果につながっている必要があります。もしそれが機能的だと考えるなら、なぜそれが有効なのでしょうか? 機能的正当化の限界の事例:バンドウォーク 多くの人は、ランナーにとって、バンドウォークがより「機能的」だということに賛成でしょう。バンドウォークは、ランニングで使われる筋肉を運動学的により近い方法で鍛えることができ、ランナーが走る際に使う多くの筋肉を鍛えることができるようにみえるからです。 しかしそれは本当でしょうか?バンドウォークは、先述の「機能的」要素のどのくらいを満たしているでしょうか? 動きの特性:膝にバンドを巻いた状態で走るランナーはいませんし、横向きや後ろ向きに走ることもありません。表面的に、関節角度や変位という意味ではあまり似ていません。動きの特性が大切だと考える、あるいは練習をすることこそが完璧につながると考えるのなら、ランニングとは全く異なる動きをトレーニングするバンドウォークは、動きの特性という観点において正当化することができません。 動きの方向性:側方向へのバンドウォークは、ランニングで使われるのと同じ要領で股関節の外転筋群を鍛えることはできません。ランニング時、伸長性制御は高い衝撃負荷の下、非常に短い時間で起こります。バンドウォークはそれとは全く異なります。バンドウォークはとてもゆっくりです。ランニングの際に、関節のトルクを作り出す力のベクトルとはかなり異なる外部負荷がかかります。動きの特性、あるいは速度特性議論においても満足には至りません。このことを考慮しても、バンドウォークは機能的と言えるでしょうか? 環境?バンドウォークはクラムシェルよりは確かに良さそうです。アスリートは立っていて、体重を移動しています。しかし、ランナーが体重移動をするように、立って体重移動をしているでしょうか?していません。ただ立って体重移動をしていることが、エクササイズを機能的にするために十分なのでしょうか?立って、体重移動をしながら、ダンベルカールをするのはどうでしょうか? 運動制御:まさか。バンドウォークはランニングの運動パターンとは似て非なるものです。タイミングは全く違いますし、衝撃もなく、振動を抑える筋肉のフィードフォワード活性もなく、弾性エネルギーの貯蓄もほとんどありません。バンドウォークの際に「伸展筋パラドックス」が起こると思いますか?無理です。これらの二つのタスクは完全に異なるものです。バンドウォークの際に何らかの運動パターンを刷り込んでランニングを向上するという議論をする余地はありません。

すべてのムーブメントスクリーニングが抱える限界 パート2/2
現行の身体機能のスクリーニングに伴う限界(続き) 限界#3:負荷やスピードの汎用性に乏しい FMSでいつも教えられている優れたことのひとつに、動作のテストはその部位ごとのテストの総和よりも得ることが多いということがあります。筋の徒手テストや関節角度計から簡単に予測できないこと、その人がどのように動きを選ぶか(運動制御)の手がかりを提供してくれるのです。最近私たちが直面しているのは、検査台の上で行うテストと動作のテストとの間で一貫性に欠けているということ。両者のテストは諸刃の剣かもしれません。つまり、クリニックで実施されるテスト(たとえば、スクワット、片脚スクワットなど)は、日常生活や、スポーツ、異なる負荷やスピードを要する状況下でその人がどのように動くかを、反映していないかもしれません。デビッド・フロストとシュワート・マックギルは、この論文でそのことを強調しています。 私にとって、テストのポイントは、欠陥を表面化することです。もし片脚スクワットテストやFMSの他のテストが、別の機能的タスクにおける欠陥を見落としてしまうとすれば、もはやそのテストはスクリーニングではありません。欠陥を見落としたのです。スクリーニングは当然、過剰な感度を持つものであるべきです。偽陰性よりもはるかに多くの偽陽性を出すべきです。クスリーニングテストは、その与えられたテストをその人がどのように行ったかについて示すだけで、別の場面での動きや異なる内容の動きについては何も知らせてくれないかもしれません。それでも、選手がそのテストで不合格となれば、価値のある情報を提供してくれたことになるでしょうが、それではスクリーニングではないのです。 限界#4:スクリーニングは、必ずしも関節機能のすべての側面を評価するとは限らない もし私の記憶が正確であれば、運動評価テストが使用されるようになったきっかけは、筋力や持久力といった単純なテストを避けるためでした。しかし、スクリーンニングテストの使用者の人たちが、スクリーニングテストで不合格になるのは、股関節や脊柱が弱化しているからだとか、“安定性”がないからだと示唆するのをよく耳にします。私自身もそのように考えたことがあります。不十分な片脚スクワットは、股関節が弱いんですよね? 違います。そして、骨盤が傾くのは、股関節の外転筋群が弱いからかもしれないと推測してしまいます。驚くことに、これらは関連していないのです。股関節の外転筋の麻痺に関する最近の論文(ここに同様の論文があります)で、股関節の運動学には何の変化もないことから、トレンデンベルグは適切なスクリーニングではないとしています。二番目の論文では、片脚スクワットを評価し、股関節の内転は股関節の筋力と何の関連性もないことを発見しています。動きの技術に関わらず、股関節の筋力自体ケガの予防になるかもしれないと考えるのであれば、私たちが行うスクリーニングテストでは見落としてしまうので、さらなるテストが必要になります。この研究の中での股関節の内転運動は、大臀筋の動員と関係付けられ、つまりその動きのパターンは運動制御の問題であると示唆しています(FMSで絶えず教えていること)。従って、テストはそれ自体には価値があるのですが、代用にはならないということです。 私たちは、動作のスクリーニングはパフォーマンステストや関節の強度、関節可動域のテストの代用にはならないことは分かりましたが、このような情報も重要ではありませんか? コアの持久力は、あなたの関わっている選手にとって大切ではないですか? ホッケー選手にとって、股関節の外転筋と内転筋の筋力のバランスは重要ではないですか? ランニングでの股関節の外転筋群には高度な筋力が欲しいと思いませんか? おそらく、イエスでしょう。動作のスクリーニングは、これらのことを把握する手がかりを提供してくれません。みなさんが行っているテストをスクリーニングというレベルで終わらせてしまえば、この情報を見落としてしまいます。 片脚スクワットテスト(またはランジ、オーバーヘッドスクワットなど)で不合格ということだけでも、価値のある情報になり得ます。私はこれらのテストを完全に廃止するつもりはありません。しかし、今となれば、これらはテストであってスクリーニングではないのです。動作の“スクリーニング”が、それ自体が単なるテストであると私は思いません。これらの動作評価は、独立したものです。これらのテストを特定して行うことには価値があるかもしれませんが、私には、そのテストがその他の機能や状況を調べるための代りにはなるとは言えません。よって、これは、スクリーニングとしては限界があり、単なる一つのテストにすぎないのです。 あまり批判的にならないように:スクリーニングはそれでも役に立つ ここで、限界についてばかり指摘しているのでは不公平です。私は、これらの動作のスクリーニングテストのすべてを部分的に利用しています。動作のスクリーニング(表面化された欠陥)の背景にある考えは、自分独自のスクリーニング(たとえば、すべてのエクササイズが評価の対象になる)を開発するのに役立ちます。動作のスクリーニングは、動きの欠陥を見落とすかもしれないということ、筋力/持久力についての基本的な情報を提供するということ、関節の可動性を調べるテストとしては必ずしも正確でないということを述べてきました。しかし、テストをすること自体が、何かを知らせてくれるのです。もし、負荷のない状態のテストで“不十分な動き”をしていたならば、負荷下やスピードを付けた動きでは、間違いなくうまく行うことができないであろうと多くの場合疑うでしょう。これらのテストは、もちろんその人がどのように動きを選択するかについての情報を提供してくれます。そのこと自体、エクササイズを処方する際に役に立つことがあるかもしれません。 身体機能スクリーニングの代替 テストはテストをすることを目的にするよりも、欠陥を見つけること目的にしてみます。総合的な能力を調べるテスト。私たちが把握する必要のあることは、もっと様々なスポーツやアクティビティ、異なる人口においてケガを予測できるような身体制限は何か、または、フォームの変化は何かということです。たとえば、脊柱が側方に傾いていると特定のスポーツではケガのリスク因子になると考えられているとしたら、私達の使命はそのリスク因子を表面化するようにすることです。そういった意味で、FMSはぴったりのスタートになるかもしれません。しかし、テストに“合格”したらそこで終わりにしないようにしてください。スクリーニングが何かを見落とす可能性があるということに同意しているならば、すべてのテストをしなくてはなりません。もし、スクリーニングテストが身体に負荷やスピードがかかる状況下で、身体機能にどのような変化が起こるかに反映しないということに同意しているならば、これらの状況下で彼らの持つ欠陥を表面化するようなテストに修正しなくてはなりません。もし、その選手がランナーであればランニングでスクリーニングをすべきです。自分が使いたいスクリーニングを作るkとができるのです。私たちの仕事は、欠陥を表面化することですから。 動作のテストすべてにある限界:どのような時に“欠陥”が“欠陥”となるのか。 私は、まるで当然のことのように “欠陥”という言葉を使っています。私たちは、特定の動きが、よりケガに関連すると推測します。残念ながら、研究はそれほど絶対的なものではありません。研究上と臨床上で、私たちが抱える最大の困難と挑戦は、いつ“欠陥”が本当にケガのリスクを増加させるような“欠陥”になるのかを見分けることです。欠陥としての動きの“欠如”のもう一つの考え方としては、それらを異なった動きの選択肢として捉えることです。そのような人を見たことがありますね。 “ひどいフォーム”で動いているにもかかわらず、パフォーマンスは良く、ケガをしない人たちを。彼らはどうやっているのでしょうか? そのような姿勢でも耐えられるように十分トレーニングされているのかもしれません。 重要ポイント 動作のスクリーニングは、感度に欠けることから恐らく最適なスクリーニングではないでしょう。動作のスクリーニングは、特定のテストを実施している時にその人がどのように動きを選択しているかを表面化するのに適しているものです。残念ながら、私たちは、これらの動きのパターンを他の場面でも通用するように一般化できません。ですから事実上、動作のスクリーニングに合格することは、私たちが表面化したいと思っている欠陥がテスト中には起こらなかったということを知らせるだけです。しかし、それが、日常の動きの中で起こる可能性はまだ残っています。 動作のスクリーニングは、身体機能の他の部位にまで役割を果たすことはありません。スクリーニングは、脊柱の“安定性”測定や体幹の持久力/筋力、身体パフォーマンス、関節運動学の基本的測とそれほど関連しているわけではありません。このような測定基準のすべてに、ケガ防止にとっての価値がありそうです。 恐らく、動作のスクリーニングは、本来、単なる動きの評価として見られるべきでしょう。もし、他の動作への汎用性に欠けていて、他の部位の機能の代替えとして役割を果たさないのであれば、独自のものとして見るべきです。それでも、これらのテスト中に、その人がどのように動くかを見るには価値があるでしょう(そうなると、これらはテストであってスクリーニングではなくなります)。 みなさんは、自分で動きの評価を創ることもできます:動きのスクリーニングの背景にある考え(“欠陥”を表面化すること)が、役に立ちます。もし、みなさんが欠陥/動きの機能異常がケガのリスクやケガの再発に関連すると考えるのならば、すべてのテスト、動き、エクササイズ、パフォーマンスが評価の対象になりえます。FMSを教えている専門家たちから学ぶことは、自分自身の評価を構築するのに役立つかもしれません。グレイ・クック著の『ムーブメント(Movement)』という本を購入してみてください。彼らの教育、描写、理論的根拠の説明においてとてもよくできた本です。彼らに反論することもできますが、それでも彼らの成したことに敬意を払うことは大切だと思います。

すべてのムーブメントスクリーニングが抱える限界 パート1/2
私は、これまでも動作のスクリーンを行ってきましたし、今でもどのような動きをするか調べるにために動作テストを使っています。もし、みなさんがファンクショナル・ムーブメント・スクリーン(FMS)を使っているならば、きっと患者の動きを評価するのに多少の限界を感じているでしょう。このような見落としが、ある人にとっては将来的に起こりうるケガに結びつくことがあります。これら“スクリーニング”の見落としは、すなわち“スクリーニング”にすらかけられていないのです。スクリーニングは、取りこぼしなくすべてをキャッチするべきですが(たとえば、もっと偽陽性があったり、偽陰性がほとんどなかったりするなど)、動作のスクリーニングテストは、実際、テストしている動き以上のものはスクリーニングできていないのではないかと私は懸念しています。 私は、動作の評価テストとスクリーニングに、重要な2つの懸念を感じています: とても簡単なテストをするだけの“スクリーニング”は、実際、私たちが調べたいと思っている動きの“欠陥”や“機能障害”を見落としているということはないでしょうか? “欠陥”を見つけ出そうとするスクリーニングで、単なる正常範囲の動きのバリエーションや選択肢のあら探しをしているだけではないでしょうか、そして、私たちはそれらを機能障害と早まって分類してはいないでしょうか? 圧倒的に最も広く使われ成果をあげているスクリーニングは、ファンクショナル・ムーブメント・スクリーン (FMS)です。私はFMSと、その臨床的な親類のようなSFMAの開発と研究に注ぎ込まれた考え方と成果を尊敬しています。今回の投稿は、FMSや他の動作スクリーニング(たとえば、ニュージーランドにおけるMCSなど)を攻撃する目的ではありません。むしろ、私たちが使っているすべてのテストは、運動の機能障害を評価したり、ケガのリスクを予測したり、痛みを治療したりするには、限界があるということについてです。これらのスクリーニングの成果は多くの尊敬に値するもので、私もそのように思っています。 身体機能のスクリーニングの背景 “医学におけるスクリーニングは、ターゲットとなる集団に対して、兆候や症状がない個人におけるまだ気がついていない病気を特定するために行う手法です。前駆症状性疾患や無症候性疾患を持つ対象者も含まれます。スクリーニングは、とりわけ健康に見える人に行われるユニークなテストです。”(ウィキペディア) 身体機能スクリーニングの目的: 動き方を基にケガのリスクが高い人たちを特定する。 身体の部分的な動きの総和のみを示すのではなく、その人がどのように動くかの知見を提供する。 身体の特定部位の可動性と安定性の知見を提供する。 特定された部位の機能の“疑いを晴らす”。スクリーニングは“優先順位付け”として働き、次にどの部位の評価をするか優先度を判断するのに役立つ。 FMSの大きな長所は、そのシンプルさです。このことは同時に、その感度の低下につながります ケガの予測の限界 ケガを予測するための動作のスクリーニングの性能は、スクリーニングの考案者たちによる多くの研究と伴に何度も詳細にわたり分析されてきました。FMSに関する研究のレビューは、ここをクリックすると見られます。ケガの予測はあまりにも複雑で困難です。私たちがFMSや他のスクリーニング方法にそれを求めるのは不公平でしょう。それよりも、考案者たちが提案するように、補填的なテストのひとつであるべきでしょう。身体機能の簡単なスクリーニングを使用する代わりに、スクリーニングの範囲を広げ、すべての動きを構成するすべての部位まで掘り下げる必要があり、さらに人間全体(たとえば、認知、心理社会的側面など)に取り組む一連のテストが必要であるとさえ示唆したいと思います。そこで、もし動作のスクリーニングが一連のテストのひとつになったとしたら、それは本当にスクリーニングなのでしょうか? 私にとって、それは今や多少の情報を与えてくれる一連の良いテストのひとつになってしまいます。もし、スクリーニングの範囲を広げさらに詳細を調べるテストを含めたとしても、まだそのスクリーニングを必要としますか? 私にとって、スクリーニングで行うそれぞれのテストは、確かにそれ自体は価値のあるものになるでしょうが、機能という範囲で捉えるとその代用にはならないのです。 現行の身体機能のスクリーニングに伴う限界 スクリーニングの感度は高くあるべき もしかすると、スクリーニングテスト自体はそれほど重要ではないかもしれません。スクリーニングテストで何かが表面化される何かが重要なのです。私たちが調べていることは、フォームの修正や動きの異常です。私たちは、もっとよい動き方があり、特定の欠陥がケガのリスクを高めると仮定するのです。そこで、良いスクリーニングをすることで、ケガに結びつくと推測される“欠陥”をテストで表面化できるはずと考えるわけです。ここに、ほとんどのスクリーニングテストが見落としをしてしまうポイントがあります。それは、機能に限界があることを見落としています。たとえば: 限界#1:スクリーニングは、修正された機能のちょっとした側面を見落とすことがある 仮に、足関節の背屈制限は、ランナーにとってケガのリスク要因になるとしましょう。スクリーニングのプロトコルでその欠陥は明らかになるはずですね。この機能を見るために、たいていの一連のスクリーニングテストでは、何らかのスクワットテストを行います。FMSでは、オーバーヘッドスクワットを採用しています。もし選手がこのテストで、腕が前方へ傾いたり背中が顕著に丸くならずに深くスクワットできなければ、何かが悪いと推測します。なぜスクワットができないのかはFMSでは分かりません。それから、ブレイクダウンを行い、股関節屈曲に制限があるか、胸椎の伸展が不足しているか、運動制御の問題や背屈制限があるかどうか見ていかなくてはなりません。それから、追加的テストに進み、どれに相当するのか調べます。ここでの問題は、もし腰椎や胸椎の伸展が十分にあり、もし下半身に対する身体前面の体重の比率が大きければ(幼児を考えてみてください、彼らの大きな頭部がおしりとのバランスをとっています)、深くスクワットするのにそれほど大きな足首の背屈は必要ないのです。これが、私たちが見つけようとしている欠陥を見落としてしまうケースです。FMSのその他のテストでも同様です。足首の背屈についてもっと把握するには、Yバランススケールを追加しなくてはならないでしょう。それでも、動きの中で何かが正しくないことを教えてくれるという意味でこのテストは素晴らしいですが、スクリーニングの役目はもっと包括的であるべきです。 限界#2:類似したタスクにおいても動きの欠陥を見落とすことがある 私は、片脚スクワットテストが好きです。これは、股関節がどのように膝を制御しているかを把握する手がかりになると思います。さらに、股関節の強度、ランニング時の膝の制御、ジャンプ時の膝の制御の手がかりになればよいとも考えています。ただ問題なのは、たぶんそうにはならないということです。オーバーヘッドスクワットでもランジ、またはステップオーバーテストでも同じことが言えます。私のお気に入りのスクリーニングテストは、それほどスクリーニングには向いていません。なぜなら、私が見つけようとしている欠陥(スポーツ中の膝の動的外反など)について教えてくれないからです。私は、ランナーを三次元運動学的に分析できる道具を持っていますが、ランニング中に股関節内転が増加してしまうランナーの内、半分以上の場合、片脚スクワットでは正常な股関節の内転を示すと推測します。

運動楽観主義 VS 運動病理学モデル パート2/2
適応性:分割する楔 さあ、あなたが考える番です。私は要点を伝えました。合理的な人は、同じ研究、同じ患者層を見ていても、異なる決断をします。これは、人がどのくらい適応できるかに対する潜在的な考え方に集約されると思います。 運動楽観主義者は、膝の外反のある人を見たときに、「素晴らしい、彼はきっとロッククライミングが得意で、ホッケーではキーパーをやるのだろう」と考え、この人は問題なく、安全であり、いずれ膝の外反による代償を払うことにはならないという仮説を立てます。あなたは、股関節の内旋は膝蓋骨の外側面に与える負荷を30-70%増加し得ると論議するいくつかの研究に詳しいかもしれません。しかし、あなたはこうも考えます。「たいしたことだ。負荷は適応をもたらす。負荷は良い。負荷は、力学的シグナル伝達の触媒であり、私をデカくしてくれるものだ!」 また、KPMの支持者としては、脊柱が丸まった人を見て、「わあ、あれでは脊柱の衛生状態が良くない。椎間板は時間をかけてゆっくりと層剥離し、核は後ろに追いやられ、今は痛みがなくとも将来は痛みが出るだろう。もしこの姿勢に、重い負荷が組み合わさって、分厚い脊柱と特定の椎間板形状が形成されれば、椎間板損傷につながりやすくなるだろう。椎間板に損傷があっても痛みがない状態にある人はたくさんいるが、このような姿勢は椎間板の該当部位に増長したストレスをかけるという死体研究やモデル研究の証拠がある。怪我や痛みにつながる可能性があるため、この人にはそのような姿勢を避けることを教えると価値があるかもしれない。」と考えるかもしれません。 運動楽観主義者は、これと同じ研究を知っているかもしれませんが、これをどう考えるかや、これに対する行動については二つの潜在的な方法に分かれます。 姿勢や負荷は、椎間板が良い方向に適応するのを実際に刺激しているかもしれない そのような姿勢や負荷が椎間板に悪い影響を与えるとしても、その椎間板の変化と痛みとの関係性は薄いかもしれない。より詳しい内容はこちら。 再度になりますが、要点は適応性に対するあなたの考え方次第なのです。あなたが、人がどのように適応するかに対して大きな余裕を持つ見方をする方であれば、あなたは運動楽観主義が支配するスペクトラムの端に当てはまるでしょう。あなたが、人は適応に対して限られた、少ない潜在能力しか持っていないという見方をするなら、あなたはより極端なKPMや動きの質アプローチの側のどこかに当てはまるでしょう。 私たちは知識の限界にきているため、このような意見の違いがあるのだと考えています。私たちは、実際には、各個人がどのくらい上手に適応できるかを知りません。適応能力は様々な要因(生物社会学が非常に関連するところです)によって影響されるため、誰かがどのくらい上手く適応できるかも知りません。反応が良い神経系を伴う生きた椎間板が、曲がった姿勢や負荷にどのくらい本当に適応しているかにより詳しくなることができれば、人がどのように動くべきかに対する考えの不一致は少なくなるでしょう。 最後に、もう一つ考え方があります。 KPMをその内側から非難する:生体力学が生体力学にチャレンジする時 私はよくKPM主義に挑むのは「痛みの科学」ではなく、生体力学それ自体だと言っています。多くの生体力学研究は矛盾していて、提唱している損傷や痛みの生体力学的リスク要因は必ずしも証明されていないことがこの考え方の一例です。しかし、これには他の考え方もあります。「ハードコア」生体医学男/女で、負荷や姿勢は痛み/損傷にとって非常に大切だと考えていても、KPMモデルの中で支持される一般的な考え方に異議を唱えることはできます。 脊柱の屈曲は、この完璧な例です。どうしたものか、どこかの時点で、脊柱はニュートラルゾーンにある時に負荷が与えられているのが、最も安全であるというのが主流な考えになりました。30-40年前は激しい「前かがみ姿勢 vs スクワット」討論がありましたが、生体力学の世界ではその討論は消えてしまったようです。しかし、消えるべきではなかったかもしれません。20年前には、脊柱が負荷に耐えるには最大屈曲の50-80%にあるのが最も安全だと唱えたパトリシア・ドーランのような偉大な生体力学研究者がいました。彼らは、この功績により賞さえ獲得しているのです。屈曲した脊柱に関する、しっかりとした生体力学的議論を扱う生体力学者がいるのです。 また、屈曲が少なく、剪断が高い重量挙げ選手のスクワットと比較して、身体を屈曲したリフティング姿勢は、脊柱に対する前方剪断負荷の減少につながるという、Kingmaの論文がここで読めます。 アキレス腱障害のリハビリに関する議論でも、こういった考えを見ることができます。どうしたものか、背屈によって起こる圧縮負荷は、一般に認められた生体力学的ブギーマン(恐怖が実体化したお化け)になりましたが、リハビリに重い負荷だけではなく腱の静的ストレッチ(高いレベルの圧縮を生み出す組み合わせ)を提唱するジェフリー・ベラルのような生体力学的考えを持つ臨床研究者もいます。 これは膝の痛み/損傷予防及び治療においても見ることができます。治療家は、動きの質は、誤った生体力学的パラメーターを重視して注意を散漫させるものだと言うかもしれません。これは、股関節の内転の最小化に対して脚の伸展筋力を最大化する議論にも見ることができます。 大雑把に言うと、運動楽観主義アプローチでは、「残念な動きの質」と考えられる姿勢において、特定の組織への負荷が高くなると認めているかもしれませんが(いつもではありませんが)、私たちは適応性を尊重しているので、このことについてはあまり関心がありません。しかし、この代替的な見方は適応性を認識すらしていません。適応性は、人によっては、「残念な貧しい動きの質」は、実際には良い動きの質であるかもしれず、その人にとって、より低い、より良い負荷につながるかもしれないことを示唆しています。そしてこれこそが、現在の生体力学者の討論なのです。 結論とまとめ 運動楽観主義者であれば、生体力学が無関係だと考えるわけではありません。それは、生体力学、及び、損傷や痛みを持つ人に生体力学が持つ意味に対して異なる見方をしているということです。伝統的な運動病理学モデルを非難することは、すべての力学的介入を非難するわけではありません。力学がいつどのように関連するかに対する解釈が異なるというだけです。