マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

ニーリングオーバーヘッドから立位へ(ビデオ)
床の上に両膝立ちになった状態でのオーバーヘッドホールドのポジションから、立ち上がる動きへの移行は、可動性に問題のない人にとっては素晴らしいエクササイズのひとつです。このエクササイズを行うにあたって、避けるべき制限とは、どのようなものがあげられるのでしょうか?

DVRT 統合されたコアの安定
2014年7月3日に開催されたDVRTレベル1認定コースから、全てのポジションの基礎となる、重要な姿勢であるプランクに、アルティメイトサンドバッグを用いて負荷を加えることで、より統合されたコアの安定を実現する方法をご紹介します。

TRX TV 5月3週目のシークエンス(ビデオ)
胸椎のローテーション、股関節のローテーションは、腰部や膝を保護しつつダイナミックな動きを実現する際にとても重要な動きの要素です。サスペンショントレーナーを使った、胸椎と股関節の回旋の向上を目指したエクササイズのシークエンスをご紹介します。
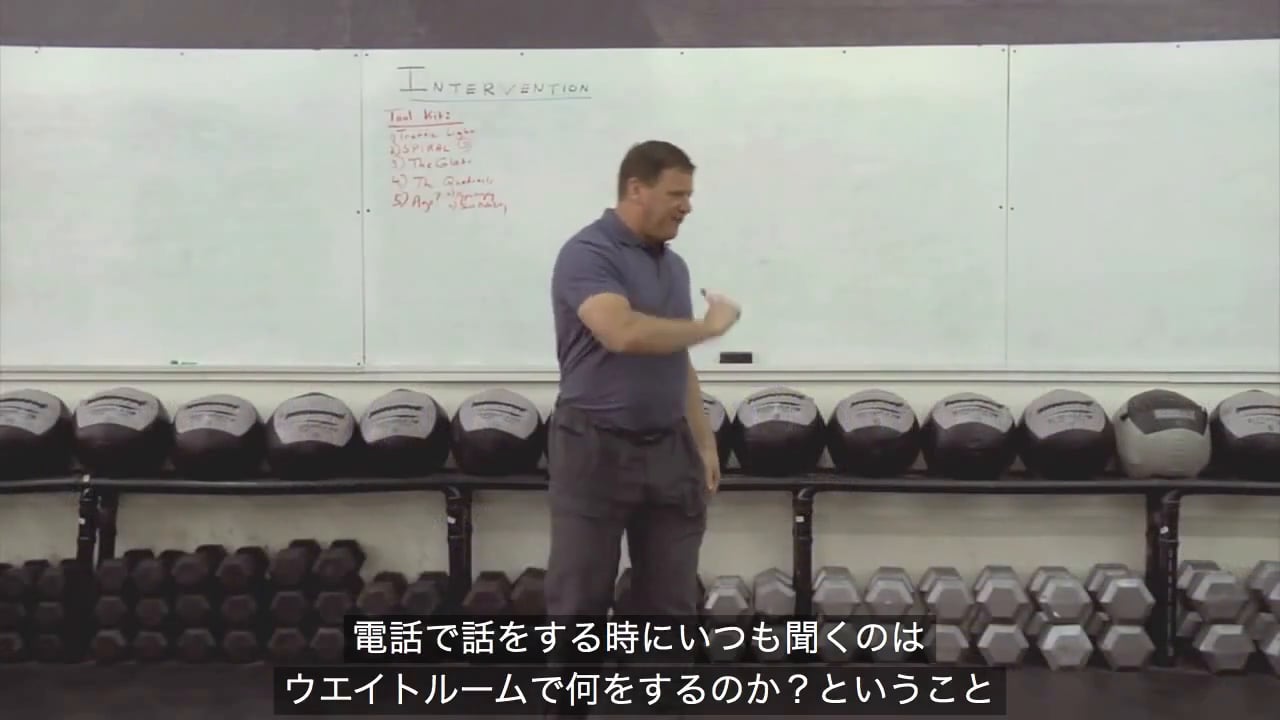
人間の基本の動き(ビデオ)
人間の基本の動きを何とするか?様々な見解があると思いますが、ダン・ジョンがトレーニングに関しての基本の動きとその重要性に関して指導するセミナーからの抜粋をお届けします。

股関節の可動域アセスメント
2014年6月22日にSYNERGYにて開催させていただいたITTピラティスのジーン・サリヴァンのセミナー”足部から股関節へのコネクション”から、テーブル上での受動的な股関節の可動域アセスメントをご紹介します。丁寧に注意深く、股関節の多面的な動きのアセスメントを行うジーンのディテールに注目。

阿部勝彦さんインタビュー バックグラウンド(ビデオ)
旧アスリーツパフォーマンス、現EXOSで活躍中のストレングス&パフォーマンスコーチである阿部勝彦さんとのインタビュー第一弾。アメリカで学ぶことを決めたきっかけや、在学中の経験、そしてアスリーツパフォーマンスでのポジションを得るまでの経験談をシェアしてくださっています。

スポーツパフォーマンスのトレーニングに関する4つの考察
1.私たちは、通常のバーベルベンチプレスを野球選手たちに対して行いません。 ダンベルベンチプレスをプログラムに組み込むことは、更に稀です。というのは、ひとつには、肩甲骨をベンチに押しつけ固定してしまうのではなく、肩甲骨の自由な動きを利用したいからです。ベンチプレスを除外したことを踏まえ、代わりに何をするのかと、しばしば問いかけられます。 多くの方がすでにお分かりでしょうが、答えは、ランドマインプレス、プッシュアップやケーブルプレスのバリエーションなどです。多くの人が忘れられがちな優れた選択肢として、ターキッシュゲットアップやケトルベルボトムアップキャリー等、シンプルにプレス(押す動作)を頭上でホールドするような動作へ代えるというものがあります。 ほかに私が好きなバリエーションは、膝立ちでのオーバーヘッドホールドから立ち上がる、というもの。これは、ターキッシュゲットアップをするためのちょっとした準備段階として、特に初心者を対象によく行います。素晴らしい回旋腱板の反射的収縮に加え、肩甲骨の上方回旋を促す必要がある人にも効果的です。これでもまだ、全ての人がこのバリエーションに適しているわけではありません。動画で学んでみましょう。 2.リフティングによって肘内側部を痛めるのは、まったく珍しいことではありません。 これは通常、とてつもない量のグリップトレーニングと多大な負荷下の肘屈曲の組み合わせで生じます。この問題が起きたら、通常、リフティング量を減らし、エクササイズの選択を修正するのが原則です。 しかし、多くの人に十分認識されていないのは、補助的なコンディショニングトレーニングがオーバーユーズパターンに与える影響です。ローイングマシーンに飛び乗り、数千メートルに達するまで20分間漕ぎ、またバーベルやケトルベルをさらに組み込んだ時、どれだけ共通屈筋腱を酷使しているかを想像してみてください。これらはすべて、かなりグリップに集中したアプローチですから、プログラムに組み込む際には注意が必要ですし、常に行うものでもありません。プログラムに組み込んだり、ときには外したりします。 たとえば、私の肘の内側のあちこちに刺激を感じているとします。漕ぐ動作を増やすと、たいていそれを感じるとします。このような場合、もし私が通常と同じ量の上半身のトレーニングをしていたならば、ローイングは1週間に1セッションが限界だということに気づきました。 3.十分な股関節のヒップヒンジ(屈曲伸展)があるということは、競技での成功に大きく貢献します。 そのためにも、トータッチプログレッションを多くの選手に実施しています。疑いもなく最大の間違いは、選手がトータッチを行う際、股関節屈曲の代わりに膝を過伸展していることです。このように見えます: 重心の後方への移動が一切なく、足首は底屈位のまま(ふくらはぎがストレッチされていない)なのがおわかりでしょう。関節に過可動性がある選手に多くみられます。以前にも紹介した動画があります; こちらの関節が緩い選手は実際、壁にブロックされているにもかかわらず、ヒップヒンジをまったくしなくても、トータッチを成し遂げていることがわかります。関節の過可動性がある選手は、よくこのようなトリックを使うのです!

肋骨のコントロール
開き過ぎてしまったり、閉じようとして屈曲してしまったり、肋骨のアライメントを正しく整えるのは、思いのほか難しいことではないでしょうか?シンプルな動きを通して、分かり易く繊細に、肋骨のアライメントを整えるヒントをジーン・サリヴァンがシェアしてくれます。

東 vs 西
ずっと前に皆さんに、私に何を書いてほしいかを聞いたことを覚えていますか?そのときのリストは、今でも持っていて、ゆっくりでも全て書くつもりです。そのリストの中のアダム・ウォルフさんによる質問が下記です。 動作をどのように徒手療法や東洋医学と融合し、それをどのようにして、絡まりあい融合を強めていく「東洋」のホリスティック(全体論的な)医学と西洋(哲学)、およびそのパラダイムに調和させているのでしょうか? あぁ…それは全て東 vs 西ということに集約できます。私の高校がケンモアウエスト(マスコットはブルーデビル)であった頃のように。私の高校のライバル校は、ケンモアイースト(マスコットはブルドッグ)でした。絶妙な詠唱をよく覚えています:「西は最高…東は最低!」 徒手療法は、身体構造を改善することが全てです。ちょっと、言い直させてください。おわかりだと思いますが、上腕骨を形成したり、大腿骨頭を造り直したりするわけではありません。わかりますよね。変えることのできる軟部組織の構造を変えようとしているのです。伸ばしたり、安定させたり、生理学的治癒や変化に影響を与えたり、軟部組織の形成に影響を与え、順応させようとしているのです。 構造は、そのエリアの機能を決定づけます。手首や手には、なぜたくさんの骨があるのでしょうか?そこに必要な器用さを考えてみてください。なぜ関節窩上腕の臼状型は、大腿骨寛骨の臼状型と異なっているのでしょうか?肩関節は、上肢の可動性の必要性に即して設計されているのに対し、股関節は、体を支えるために、よりしっかりとした、構造的な安定性が必要です。構造が機能を決定づけるのです。徒手療法を行うことによって、構造を向上させられるのであれば、行うべきです。機能は、やがて構造に影響していきます。悪い姿勢で座り続ければ、脊柱は可動性を失い、やがては堅くて曲げられなくなり、まっすぐ立つことさえできなくなります。構造と機能は、密接につながっており、分離することはできないのです。それゆえの、私の会社の名称なのです。(訳注:スー・ファルソネの会社の名前「Structure & Function (構造と機能)」) 私にとって、東洋医学と西洋医学は密接につながっています。東洋医学が西洋医学より全体論的であるとか、あるいはその逆か、というような考えはしません。誤解しないでください、私は何も私が東洋医学哲学の専門家であると言っているわけではなくて、東洋医学についての本や論文を読んだり、概念を学ぶことが好きなのです。東洋医学の要素の多くは、何千年もの歴史を経て受け継がれています。なぜなら、それがうまくいっているからです!過去に東洋医学に従事していた人々は、その時代に得ることができる資源を使わなければなりませんでした…山にある植物やハーブを使って、病気の治療をし、診断テストを使わずに、私たちが自分自身の内部に感じるエネルギー、そして他人から感じるエネルギーの描写を使っていました。それはまさに私たちが、今ある資源を使っているのと同じです…薬、診断、動きの分析など。 ホリスティックの定義: 部分の分析や治療や解剖ではなく、全体、または完全なシステムに関係すること、関わっていること。 人間の動きに関して、多くの人々がホリスティック医学を実践していると思っています。私達は、全体のつながり、または部分全体を見て、システムの中でどのように動くかを見ます。ここに栄養学の知識を加えると、「よりホリスティック」になります。さらにスポーツ心理学カウンセリングを加えると、「もっとホリスティック」になります。それゆえ、西洋医学はホリスティックなのです…少なくともそうなれる可能性があるのです。あなたは、どのくらいホリスティックにしたいですか? これこそが、馬博士のドライニードリングの哲学が、私にとってとても共感できる理由です。彼は、身体をとてもホリスティックに見ています。筋肉のトリガーポイントの定義について考えてみてください: 身体の敏感なエリア、刺激や炎症が与えられると、別の部分に特定の影響を及ぼす。特に、刺激されすぎると、全体的な筋骨格系の痛みを生み出す筋肉の敏感なエリア。 刺激。過度に刺激される。身体の中で、刺激はどこから来るのでしょうか?末梢神経です。だから、末梢神経を治療する必要があります。神経はどこから来ているのでしょうか?脊髄です。ですから、中枢神経系も同様に治療する必要があります。さあ、これでさらにホリスティックになってきました! 覚えておいてください、道具をあなたの理念と混同させてはいけません。道具は、理念を表現するために、その時々で、それぞれのアスリートのために、選んでいる手段に過ぎません。カップ、ドライニードル、フォームロール、呼吸パターン、動作、ケトルベルなど、何を使うかが大切でしょうか?いいえ、全くそんなことはありません。これらの道具が、古典的に東洋医学または西洋医学のどちらに分類されようが、道具は、私がアスリートをどのように評価したかの理念を表現しています:そしてその理念は、純粋にホリスティックなものなのです。

阿部勝彦さんインタビュー EXOS(ビデオ)
旧アスリーツパフォーマンス、現EXOSで活躍中のストレングス&パフォーマンスコーチである阿部勝彦さんとのインタビュー第二弾。EXOSのアスリートトレーニングの4本の柱を中心に、トレーニングの基本原則の関わるお話を伺いました。

DVRT メンズヘルス掲載エクササイズ
全米で発行部数の多いメジャーな雑誌であるメンズヘルスに掲載されたアルティメイトサンドバッグのエクササイズ。多面的でチャレンジ度の高いエクササイズを各自のレベルに合わせた確実なリグレッションにしてご紹介します。確実に積み上げていくことが成長への鍵ですね。
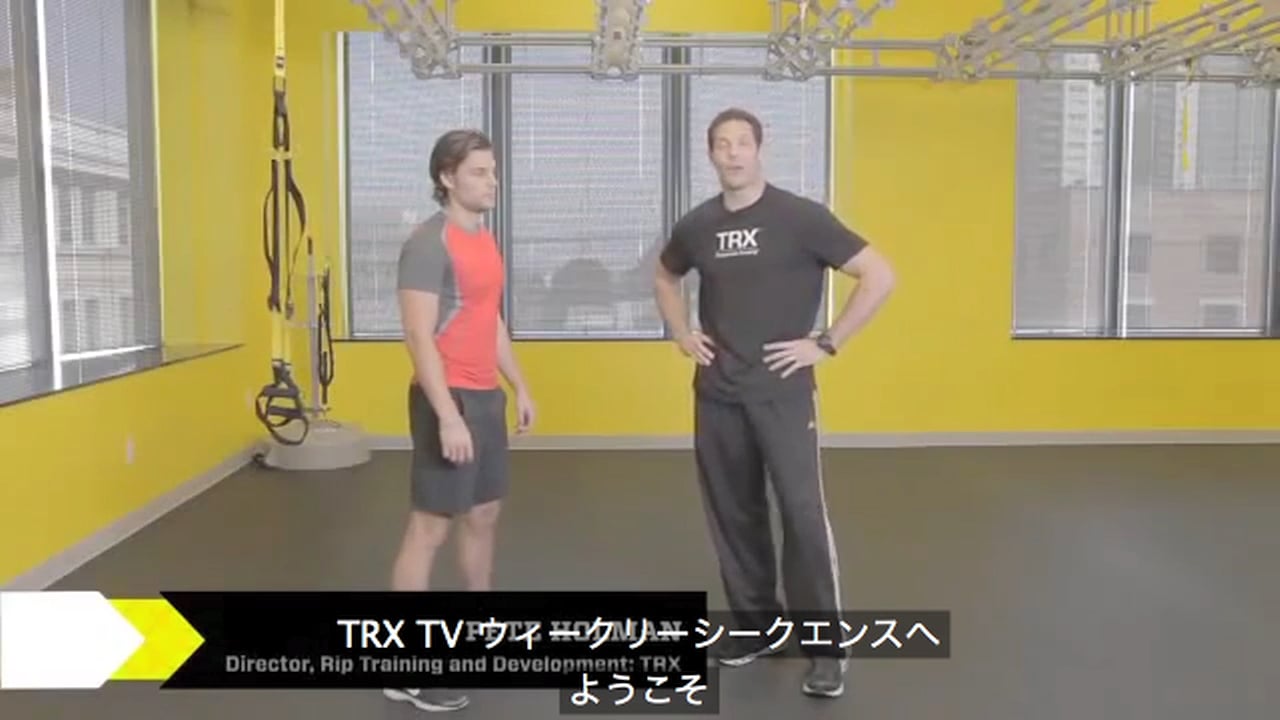
TRXTV ポステリア キネティックチェーン(ビデオ)
TRXサスペンショントレーニングとリップトレーニングのそれぞれの特徴を活かして、更にその効果を高めるエクササイズを組み合せたフュージョン=融合のエクササイズを、リップトレーナーの開発者であるピート・ホルマンが熱くご紹介します。