マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

スプリントのためのバリスティックトレーニング
目的 この記事は、趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングを行う成人アスリートのいずれかにおいて、バリスティックトレーニングは、スプリントスピードを向上するためにどの程度効果的であるかということを提示している。 背景 序論 バリスティックトレーニングは減速段階が存在しないレジスタンストレーニングの一種である。実践的にこれは、外部負荷を空中へ放出するということを意味する。減速段階の欠如は、この種類のトレーニングを行う際、アスリートは加速に費やす時間を増加することが可能であるということを意味する。この加速に費やすより長い時間は、トレーニングへの適応を増進すると考えられている。スプリントトレーニングプログラムの際、最もよく使われる下半身のバリスティックトレーニングエクササイズはジャンプスクワットであるが、多くのオリンピックウェイトリフティングエクササイズおよび(パワークリーンのような)そのバリエーションもまた一般的に使用されている。バリスティックトレーニングという用語を、爆発的ではあるが、減速段階と共に行われる、低負荷レジスタンストレーニングエクササイズを示すために使う研究者やストレングス&コンディショニングコーチもいる。しかし生体力学的な観点からは、これは用語の正しい使用方法ではない。減速段階と共に爆発的に行われる低負荷レジスタンストレーニングエクササイズは、アスリートが本来のバリスティックエクササイズのように長時間加速を持続することができないため、この混同は非常に重要である可能性がある。 メタ分析 趣味としてトレーニングを行うアスリート 少数のメタ分析もしくは系統的レビューが、スプリントパフォーマンスに対するバリスティックトレーニングの有益性を分析している。ルンプおよびその他(2014年)は、趣味としてのアスリートにおける、スプリントパフォーマンス向上のための異なるトレーニング方法の影響に関し、メタ分析を行った。最初に彼らは、トレーニング方法を特異(スプリントもしくはレジステッドスプリント)、および非特異(プライオメトリック、レジスタンストレーニング、及びバリスティックトレーニング)へと分類した。彼らは、趣味としてのアスリートにおいて、スプリント速度を向上するために、特異および(レジスタンストレーニングのような)非特異両方のトレーニング方法は同様に効果的であったと記述している。これは、趣味としてトレーニングを行うアスリートにおいては、バリスティックトレーニングは、スプリントパフォーマンスを向上するために効果的なようであるということを示している。しかしながらこのメタ分析は、全ての確認された研究が、全体の効果規模にまとめるために適した形式でデータを提示していたわけではなかったという点で制限があった。これらの研究がこの情報を開示していたら、異なる結果が観察されていたかもしれない。とはいえこれらの研究結果は、プライオメトリックトレーニングのスプリントパフォーマンスに対する効果を評価するメタ分析を行った、サエス・ヴィラリアルおよびその他(2012年b)により支持されている。この調査で彼らは、本来バリスティックレジスタンストレーニングの定義である、追加の負荷有り、および無しでのプライオメトリックエクササイズを分析している。彼らはエクササイズに対する追加の負荷は(例:負荷付きカウンタームーブメントジャンプ)、負荷無しの同等のもの(例:標準のカウンタームーブメントジャンプ)と同様に、スプリントパフォーマンスを向上することに効果的であったということを報告している。このメタ分析は、トレーニングされた被験者、およびトレーニングされていない被験者の両方にわたり行われたという点で制限はあるが、趣味としてトレーニングを行うアスリートに対し、スプリント能力を発達させるためのバリスティックトレーニングの使用を支持している。 高度にトレーニングされたアスリート 上記のようにバリスティックトレーニングは、趣味としてトレーニングを行うアスリートにおいて、スプリント能力を向上することが可能なようである。高度にトレーニングされたアスリートにおいても同様であるが、このグループは同程度まで恩恵を受けない可能性がある。ルンプおよびその他(2014年)は、高度にトレーニングされたアスリートにおける、スプリントパフォーマンスに対する様々なトレーニングタイプの影響に関し、メタ分析を行った。最初に彼らはトレーニング方法を、特異(スプリントもしくはレジステッドスプリント)および非特異(プライオメトリックス、レジスタンストレーニング、そしてバリスティックトレーニング)に分類した。彼らは、特異および非特異な両方のトレーニング方法は効果的ではあるが、非特異な方法は効果が低いようであるということを発見している。彼らは、高度にトレーニングされたアスリートにおいては、既に筋力、パワー共に発達した基盤を持ち、これは、バリスティックトレーニングのような追加の非特異なトレーニングの方法によって更に向上しなかった可能性があると示唆している。 アスリートにおけるスプリント速度に対するバリスティックトレーニングの影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – オリンピックリフトもしくはそのバリエーションを含むバリスティックトレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:ウィルソン(1993年)、マッケヴォイ(1998年)、マックブライド(2002年)、ホフマン(2005年)、ホフマン(2005年)、ムーア(2005年)、ハリス(2008年)、バルサロブレーヘルナンデス(2013年)。少数の研究は向上を観察することができなかったが、これらの研究のほとんどは、バリスティックトレーニングはスプリント速度を向上するために効果的であるということを報告している。ゆえに、バリスティックトレーニングはアスリートにおけるスプリント能力を向上することが可能であるようである。 アスリートにおけるバリスティックトレーニングの際のスプリント速度に対する負荷の影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – オリンピックウェイトリフティングもしくはそのバリエーションを含む、異なる負荷を使用した2つ以上のバリスティックレジスタンストレーニングプログラム 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール、および異なる負荷を使用したバリスティックレジスタンストレーニングプログラム 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:マックブライド(2002年)、ハリス(2008年)。これらの研究により報告されたほとんどの測定は、使用された負荷に関し、スプリント能力の変化に差違は無いということを示している。より軽い負荷は高負荷に比べ、より優れた向上につながるという一つの研究結果が存在しており、バリスティックトレーニングの際の、より低負荷およびより速い動作速度は、スプリント速度を向上するために有益であるということを示唆している可能性があるが、明確ではない。 スプリントに関しての結論 バリスティックトレーニングは、アスリートにおけるスプリント能力を向上するために効果的である。現在のところ、バリスティックトレーニングの際の正確なエクササイズや使用する負荷は明確ではないが、より軽い負荷は高負荷と比較し、より有益であるかもしれない。.

アイシングについて
RICEの処置に関しては、近年様々な意見が聞かれます。急性の炎症や外傷時のアイシングの使い方に関して、最新のリサーチの結果を基にしたレニーの見解をシェアします。

クローリングと脳の再教育
機能不全や身体構造、脳の機能は変えることができないと思い込んでいませんか?キネティコスの新しいコンテンツ提供者である、美しく強く賢明なドクター キャシー・ドゥーリーのビデオをご覧ください。

股関節包の硬さ
股関節の硬さの要因が筋肉ではなく関節包そのものにある場合、私達は関節包の前側が硬い、あるいは後ろ側が硬いと部位に特定してしまいがちです。ひとつにつながった軟部組織である関節包に対して治療的アプローチをする際に理解するべきこととは?

イマキュレートダイセクション:大腿筋膜張筋
皮膚の上に描かれた解剖図を活用して解剖学を学ぶイマキュレートダイセクション(きれいな解剖)。セミナー準備中のドクタードゥリーが、大腿筋膜張筋の働きに関して解説するビデオご覧ください。こんなクラスが受けられるといいですね。

下半身の力の発揮を高めることによって投球速度を上げる3つの方法
投球動作には、速度と正確さを伴う途方もない量の技術が必要です。投球速度の向上は、多くのピッチャー、特に少年野球のピッチャーにとって、一番の関心事になっています。速度を向上する方法を学ぶためには、事例的情報や古典的な野球の考え方に頼るよりも、科学的根拠を学習することがより重要です。 Journal of Sports Science and Medicine(スポーツ科学と医学ジャーナル)で最近発表された日本の研究者たちによる研究では、投球メカニクスにおける体幹と脚の使い方を、少年野球と大学野球のピッチャーの間で比較しました。 この研究では、少年のピッチャーも、大学生のピッチャーも同様の生体力学の運動、すなわち、同様のメカニクスで投球を行っていることがわかりました。 しかし、同時にその研究は、推進力や力の生成においては、大学生ピッチャーの方が優れていることを示しました。大学生のピッチャーは: ストライド時に軸足で地面を蹴る力がより大きい 一連の投球動作を通じて、骨盤および体幹の回旋がより大きい 加速時のストライドレッグ(踏み込む側の脚)のコントロール力がより高い 球のリリース前のストライドレッグの伸展がより大きく、爆発的な力を発揮できる ここで注意しておきたいことは、このデータは、若年期のピッチャーの体重の軽さや身体のサイズを考慮するために、身体質量に合わせて標準化されたものであるということです。こうすることにより、比較が平等になります。 この結果は、同じ研究者らによって過去に発表されたレポートの内容と一致しています。その研究では、投球速度の速い大学生ピッチャーは、投球速度の低いピッチャーに比べ、脚と胴部から力を生成する能力が高いことが示されています。 加えて、その結果は、グレン・フレイシグ、ジェームス・アンドリューズ医師、およびアメリカスポーツ医学研究所(ASMI)が、若年期のピッチャーと、若年期以降のピッチャーを比べた際に、上半身と胴部に関して発見したこととも類似していました。 速度を最大限に上げるためには、脚および胴部でより大きな力を発揮する 先に述べたように、若年期でも投球のメカニクスは似通っているのですが、力を発揮する能力は異なります。脚および胴部でより大きな力を生み出すことが速度の向上につながるのです。 しかし、強くなるだけでは、おそらく不十分でしょう。 先にあげた2つの研究によると、強くなることだけが投球速度を高めるために必要な要素ではないことは明らかです。投球速度を高めるには、より高いスピードと力の発揮が必要になります。 スピードも力の発揮も、単純に歳を重ねて、身体が大きくなることによってある程度は上昇します。より強い身体、より長い腕は、より大きな力を生み出します。これは単純な物理学です。しかし、他にも力の発揮を高めることができるコツがいくつかあります。下記は、最新の科学的根拠に基づいた、少年野球のピッチャーが、投球速度を高めるために鍛えることのできる3つの要素です。 筋力を高める 筋力は、それだけでは十分ではないでしょうが、若年期のピッチャーが投球スピードを高めるために最初に着目するべき要素です。パワーの発揮を高めるためには、強くなる必要があります。力の発揮が高まれば、より力強く投げることができます。 こういった研究に基づけば、下半身の強化は大きく注目をするべきエリアです。脚は投球動作の初期段階において使われるため、ここで生み出される力の量が、残りの投球フェーズにおける、より大きな力の発達と伝達につながります。 プロのピッチャーを見てみてください。楽に投げているように見えるピッチャーの大半はしっかりとした脚、股関節、お尻を持っています。ジョン・レスターは現役投手として優れた例ですし、少し前では、ロジャー・クレメンスがとても良い例になるでしょう。 背が低く、小さいピッチャーは、より労力を使って投げる傾向にあります。 脚がより太く、より強ければ、より大きな力を発揮することができ、それが速度と相関のあることが、多くの研究で示されています。 スピードをこうじょうさせる 私は、若年期の多くのピッチャーが筋力の強化のみに留まっていると感じていて、これは実際有害であると考えています。ストレングス&コンディショニングの研究では、筋力やスピードなどの特定の要素のトレーニングは、身体の適合につながることを示しています。 ゆっくりトレーニングをすれば、投球もゆっくりになるとはよく言ったものです。 筋力の基礎が確立できたら、「意図」にフォーカスするようにしています。どういう意味かというと、ここではアスリートの爆発的能力を高めたいのです。若年期のアスリートの多くはこれを理解していません。どうやって爆発的に発揮するかを知らないのです。 若いアスリートが重いウエイトをゆっくり動かす方法を理解できたら、負荷を少し軽くして、より速く動かすようにし、最終的にはもっと軽いウエイトをさらに速く動かすようにします。 プライオメトリックジャンプやメディシンボール投げ、ケトルベルスイング、トラップバーをつかった速いデッドリフトのようなエクササイズは、このトレーニングの領域としてとても効果的です。 野球のトレーニングに関して考慮すれば、ピッチャーには、長い距離の投球や、重い/軽いボールが重要になります(取り入れ方に関しては正しい方法と間違った方法あり)。こういったトレーニングが「腕の振りのスピード」を高めるのと同じくらい「腕力」を高めるかどうかは定かではありません。 大きな違いがありますから。 安定性を最大限に高める 最後に、おそらく最も理解されておらず、取り入れられていないトレーニングが、安定性に関するものです。投球スピードを高めるためには、適切なモーターコントロールと、腕とストライドレッグを安定させる動的安定性が必要です。ここ最近は、腕に注目が集まりがちですが、ストライドレッグを無視してはいけません。 軸脚から発揮した力を適切に伝達するためには、強く、安定したストライドレッグが必要です。 力の伝達には、ストライドレッグの安定性が必要ですが、身体は怪我を避ける内部制御機能を持っていることを思い出してください。ストライドレッグが力を安定させることができなければ、理論的には身体が、力を発揮することを制御してしまうでしょう。 このことは腕にも当てはまり、負荷付きのボールを間違った方法で使うと、若いピッチャーには特に、害を及ぼす可能性があると信じています。力を発揮するためには、腕が力に耐えることができる必要があります。そうでなければ、脳は賢明に力の発揮を制御します。 速度を最大化するためには、力を発揮できるようにすると同時に、力に耐えられるように身体を鍛えなければいけません。力を発達させることのみに集中する人達が多すぎます。これは、トレーニングプログラムの効果をなくし、生理学的限界を超えることにより、怪我につながりやすくなります。 野球の投球における最大速度は様々な要素の組み合わせにより実現できるということを理解してください。これらの要素に働きかけていくことが、怪我の可能性を減らしながら、速度を最大限高めることにつながります。

足首傷害の予防法
足首の怪我は様々なスポーツで一般的であり、アスリート達は休場し活動できなくなってしまうことも良くあります。 足首の傷害から自分を守る最初のステップの1つは、足関節複合体全ての弾力性を強化向上させることです。これはシンプルに縄跳びを利用することで可能となります。 縄跳びによる足関節の傷害予防 裸足でウォームアップを開始します。低レベルでの裸足のホッピングは足首の強化に大きな効果をもたらし、これはまた総合格闘技の選手が滅多に足首の怪我をしない理由のひとつでもあります;彼らは常に裸足でトレーニングするのです。 テクニックに関してのアドバイス: 足の母指球を使ってジャンプするべきです。 素早くジャンプする;ジャンプ間の時間を長く取らないようにします。 ジャンプ間のスムーズなリバウンドに注目します。 基礎的なテクニックを習得したら、応用にはいっていきます… 60秒、又はそれ以下のインターバルで片脚ジャンプをすることができます。ジャンプに前後の動きを加えても良いですし、サイドホップやドットドリルを取り入れることもできます。 沢山のバリエーションがあり、怪我を予防する為にそれぞれ異なる方法で足首の強化に役立ちます。基本的には、ウォームアップ中に何かしらの縄跳びのバリエーションを3分~5分間取り入れることをお薦めします。関節への衝撃を最小限に抑える何かしらのゴム素材、または芝のフィールドで行うようにして下さい。 次に、バンドに注目してみましょう... 傷害予防のバンドの使用法 バンドエクササイズはウォームアップやクールダウン中に足首を強化できるもうひとつの優れた方法であり、バンド自体は、たった数ドルで手に入ります。 十分な張力を与えてくれるバンドを使用することが大切です。そうでなければ、あまり足首の強化には繋がりません。足の甲にしっかりとバンドを巻き付けて下さい。 バンドを十分な張力がかかるまで引っ張り、底屈をおこないます。バンドに均等に張力をかけて、全可動域を使うことを意識して下さい。 このエクササイズは疲労を感じるはずです;決して楽なエクササイズではありません。私達は通常、他のバンドエクササイズをする前に15~20回の底屈エクササイズを行います。 次に、バンドの外側の張力を緩め、内側を強く引っ張ります;足を自分から遠ざけるように回すことにフォーカスしてください。このエクササイズでは、ふくらはぎの外側を使う感覚があるはずです。 今度はバンドの外側を引っ張り、内側の張力を緩めて自分に向かって足を回していきます。足首/足部の複合体全体を通して、できるだけ多くの筋や可動域を使うようにしましょう。 次のエクササイズは両側のバンドを引っ張り、膝を90度に曲げ、全可動域で足を上下に動かします。15回~20回の範囲をねらって行って下さい。 最初のうちは基本的にこれらのバンドエクササイズをウォームアップ、又はクールダウンの際に各1セットのみ行います。足首が強くなってきたら、各エクササイズを2~3セットに増やすことができます。より強い張力をかけるためにバンドのサイズを大きくしても良いでしょう。 最後のエクササイズはケトルベルフットリフトです… ケトルベルを使った足首の傷害予防 これはロシア人がケトルベルを使った最初のエクササイズのひとつで、ロシアに昔からあるエクササイズです。 ここでのアイデアは、足首を2段階のレベルで動かすということです: 実際にケトルベルを持ち上げている方の足首が働く。 直立姿勢を維持する接地した足の足首の安定性を向上させる。 このエクササイズは、片足を使ってケトルベルをベンチの上に持ち上げて、そこから床に下ろす用にして行います。 より難易度を上げるには、ベンチの高さを上げるかケトルベルの重量を上げる、またはベンチとの距離を広げることができます。これは各脚、10~20回で2~3セットをウォームアップに取り入れられるエクササイズです。 もしこれら全てのエクササイズを同時に行えば、傷害の予防と力の発揮に大いに役立つでしょう。沢山の時間をかける必要はありません;これはウォームアップ、クールダウン、または補助的エクササイズの一部になりえます。これはより強い足首、傷害予防、より良い可動性と筋力/パワーを得るために、ほぼ毎日組み込むことができるものなのです。
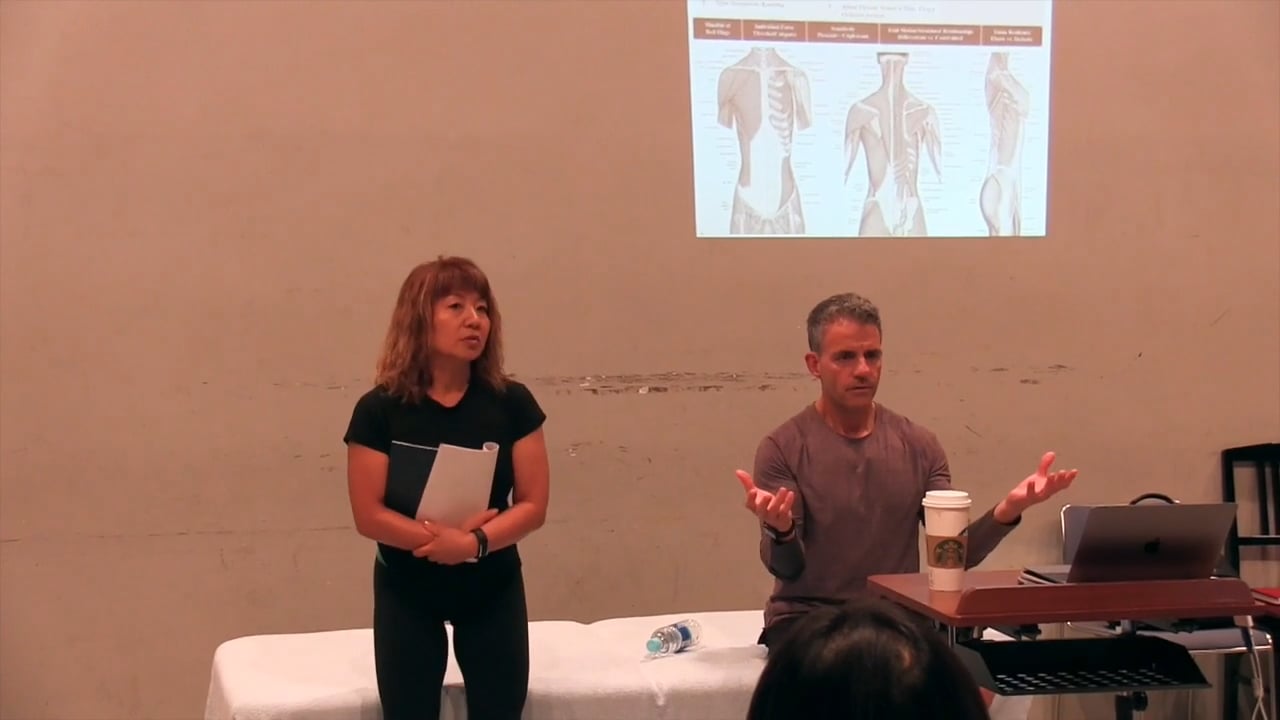
組織へのローディングの理論
組織の統合性が崩壊した時に起こる怪我から回復する為には、組織に徐々に力が加えられる必要があります。組織に力を紹介し始める為には、まずはアイソメトリックに、そしてアイソトニックに、そして最終的に弾性リコイルを取り戻すという理論的であり漸進的なアプローチが必須です。

RFEスプリットスクワットの方法
ブルガリアンスプリットスクワット、またはリアフットエレベーテッド( RFE )スプリットスクワットを呼ばれるエクササイズは、片側性の下半身強化のエクササイズとして人気があります。このエクササイズを安全に効果的に指導する為のポイントをマイク・ロバートソンがシェアします。

RDLのしてはいけない方法
RDL、ルーマニアンデッドリフトは、オリンピックリフターやアスリートどちらとっても定番のエクササイズです。 普遍的に人気があるのは、より難易度の高いリフト(フルデッドリフト、クリーンなど)を指導するためのツールとして使えるというだけではなく、ハムストリングを強化し、股関節を適切に屈曲、伸展させることを教えることができるからです。 しかし、RDLは初心者に教えるのに、最も難しいエクササイズの1つであると死ぬまで言い続けなければならないでしょう。 単に股関節を後ろに押しだしながら、脊柱をロックするという考えが、ほとんどの人にとって信じられないほど難しいものであり、その為に今日は、このブログ全てを、このエクササイズに費やすことにしたのです。 まずは、正しいRDLの方法という基本から見ていきましょう。 RDLの行い方 まず、身体の前で腕を伸ばして、バーベル、ダンベル、またはケトルベルを掴みます。体幹は上にまっすぐに伸ばし、足は大体股関節幅から肩幅に開き、膝を弛めます(若干屈曲する)。 このスタートポジションから、脊柱をしっかりと安定させたまま股関節を後ろに向って押すようにします。背骨を一旦セットしたら、動かしてはいけません。 ハムストリングに微かな伸張感を感じるまで股関節を後ろに押し、今度は股関節と骨盤を前に押し出して、スタートの位置に戻します。 RDLの正しい方法を確認したところで、今度はリフトを教えているときに最も良く見かける6つの問題を見ていきましょう。 RDLのしてはいけない方法 #1 – 膝の位置 RDLにおける膝の位置は、かなり微妙です;多くのアスリートは、体幹やバーを動かしながら、膝は緩めた状態で保持するという概念に苦労するようです。 よく見る最初の問題は、膝をロックしてしまう、さらに悪い場合には、過伸展させてしまうことです。 背骨をロックすることを理解すると、同じように、膝もそこでロックしてしまうのです。 それとは対照的に、かなり膝を曲げているアスリートを見るのもそれほど稀ではありません。 多くの理由で膝の過度な屈曲が起こり得ます: ハムストリング・ポステリアチェーンの硬さ ハムストリング・ポステリアチェーンの弱化 身体への気づきが乏しい など 準備の時に、若干膝を“揺らして”、あるいは、“緩めて”とアスリートに助言することが多く、そこから、膝を動かさないようにして、体幹と股関節を膝に対して動かします。 #2 – 背中の位置 膝は簡単に(ある程度)修正できることが多いのに対して、背骨・背中は、複雑で解決困難です。 呼吸の仕方がかなり良くない人が多く、そのせいで背骨があらゆる異常な姿勢や位置に押しやられてしまっています。 我々ストレングスコーチやパーソナルトレーナーにとって残念なことは、誰かにRDLを教える時、そのすべてが我々に跳ね返ってくることなのです。 誰かにRDLを教えるとき最初に気づく問題は、腰部に過剰なアーチができてしまうことです。 だいぶ昔に、最小限の股関節の動きで、バーが膝を超えてしまう女子高生バスケットボール選手がいました。ただ単に、彼女は腰部を激しく反り返させることで、それだけの可動域を得ていたのです。 一方で、“ニュートラル”がどのように見えるのか、感じるのか全く分からず、動き始めるとすぐに腰椎が屈曲したり背骨が丸まってしまう選手もいます。 これを矯正するために、私はまず塩化ビニール(PVC)パイプを頼りにしています。 同じことを繰り返す老人の様に聞こえるでしょうが、PVCパイプを使わず、選手に空間における身体の正常な位置の運動感覚的理解をさせようとしても、うまくいかないでしょう。 PVCパイプを背中に置き、3つの接点を見てみましょう(実際には4点): 頭の後ろにPVCが当たっている、 上背部にPVCが当たっている、 仙骨・おしりにPVCが当たっている、そして 腰椎とPVC管の間に指の幅程の小さい隙間がある。 3点の接触があることで、頂点から下までがニュートラル・まっすぐであることを確かめることができ、腰椎とPVCパイプの間に小さな“隙間”があることで、過度に屈曲、伸展していないか確かめることができます。 (このビデオをご覧ください。) #3 – 首の位置 首の位置について話をすることなく、腰の位置の話をすることはできません。これら2つは密接に繋がっているのです。 腰が過度に屈曲する、あるいは伸展するように、首もそうなってしまいます。 ここで気づく大きな間違いは、首の過伸展でしょう。腰の位置を矯正し始めると、このことが良く起こります;1つの場所の伸展を取り去ろうとすると、どこか違う場所を伸展することで、代償をしてしまうのです! このように考えてみてください―もしも、安定性を産み出す唯一の方法がアーチを作ることだとすれば、とにかくアーチをしたくなるでしょう。これはパターンであって、身体はそう動こうとするのです。 つまり、これを頸部で矯正することなく腰部で矯正しても意味がないのです。そこで、PVCパイプが役に立ち、参照ポイントを与え、それに従うことで“あごを下げる”、あるいは、“あごを引く”ことに繋がります。 一方で、頚部の位置が悪いと(深部屈曲筋の弱化や呼吸補助筋群が強いため)、首を屈曲しようとするか、首を前に突き出してしまう傾向があります。 ここでもまた、頭と首を管パイのほうへ“引く”ことを指導できるので、PVCパイプは驚くほど効果があります。かなり違和感を感じるでしょうが、以前よりもしっかりと動きを感じることが多いでしょう。 それともう一つ―この動作を改善すると、“頭を後ろに”という指示が頚部の過伸展に繋がるかもしれないことに気づくでしょう。これを修正するには、まず“頭を後ろに”から始めて、“それからあごを引く”というふうに続けなければならないかもしれません。 #4 – 膝の位置(再び) 最初の3つのポイントは矢状面に焦点をあて、90度横から選手を指導します。では、前後から見て、何を矯正できるか、または、するべきか見ていきましょう。 膝の位置というのは、もう1つの大きな問題ですが、今回は前額面(左右)と水平面(回旋)の観点から見てみます。このことについて以前言及したことはないのですが、ここで言うと:矢状面と横から見えることをまず矯正します。矢状面の動きを改善せずに、前額面、水平面を思い通りにすることはできません。 前や後ろから選手を指導するとき、膝が内に入っていたり(外反)内側に回旋している(内旋)をみることは稀ではありません。 これは、間違ったスタートポジションのためかもしれません。選手に足を大きく開いて立たせれば、これが起こるでしょう。まず足を直します。 もし足幅が適切であれば、通常、股関節、または、外側ハムストリングの弱化が原因であることが多いでしょう。もし膝が内に入っているようなら、膝を外へ“押し出す”よう選手に指示します。もし膝が内側に回旋しているのであれば、膝を外へ“回す”よう指示します。 このコンセプトがよく分からないようであれば、ウエイトを下ろし、ボトムポジションで保持することをさせるでしょう。私は、彼らの前に片膝をつき、実際に膝がどの位置にあるのか示し、あって欲しいと思う場所へ動かします。 これは、ぱっとひらめく瞬間であることが多く、正しい位置へ導くことで、正しく使えていなかった筋肉が活動し始めることが多くあります。 #5 – 股関節のシフト アスリートRDLを教える時、股関節のシフトはよく見る間違いの一つです。 股関節のシフトが起きてしまう理由はたくさんあります: 片側の股関節・大腿の弱化 片方の股関節後方関節包の硬さなど 当然ですが、最初にこれを修正するように指導を試みます。反対の股関節へ押し出すといった、単純な指示をする、あるいは手を使って適切な位置へと指示します。 しかし、精魂尽き果てるまで徹底的に指導し、指示しなければならないのであれば、おそらくそれは筋骨格系の問題以上のものであり、RDLを行う前に、修正エクササイズや特別な強化・ストレッチをする必要があるでしょう。 #6 – バーの位置 最後になりますが、大切なこととしてバーの位置があります。他のすべてのことを正しく行えていても、バーが身体に近い位置になければ、扱える重さには限界があり、背中に過度のストレスと負荷がかかってしまうでしょう。 スタートポジションから、バーは大腿の前をスライドして下がるべきです。ボトムポジションであっても、バーは前方に離れてはいけません(右側の写真のように)。こうなってしまうとかなり不利なポジションになってしまいます。 これを直すためには、広背筋を働かせ、動きの全体を通して、バーを身体に向って“引く”ようイメージします。このイメージは、リフトの下げる段階のみでなく、スタートポジションに戻ってくる時更に、役立つかもしれません。 結語 まぁそんなわけで:RDLの方法のみではなく、RDLのしてはいけない方法。 多くの人にとって神経学的に複雑な動きではあるますが、効果的だと感じなければ教えはしないでしょう。 時間をかけて、このエクササイズを正しく指導する方法を学んでください。そうすれば、選手はより多くのことを、この素晴らしい動きから得ることを保証します。

胸椎モビリゼーションと代償パターン
単純なエクササイズの様に見えるベンチを使った胸椎のモビリゼーションドリル。起こりえる様々な代償動作を考慮した上でのコーチングの重要ポイントをエリックがシェアするビデオです。

感覚のミスマッチ
感覚器や皮質からの情報を調整する役割を持つ小脳が、調整機能を適切に行えなかったり、感覚器からの情報に不一致があったりすることで、システムにエラーが起きます。エラーの原因となっているのはどの部分なのか?