マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

クライアントが嫌う6つのこと パート1/2
経験を通してしかできないことに対して、何年もかけて考えを蓄積していくというのは面白いことです。古くからある言い草で「今ならわかることをあの時わかっていたら」というのは、まさにその通りでしょう。私はよく、自分が昔やっていたことをおかしく思い、クライアントに、当時の私が経験不足だったことを伝えます。先日、チャンピオン(著者が運営するトレーニング施設)で学んでいる学生とこのような会話をしていて、これはキャリアの発展における通常の過程であると思いました。 自分の個人的な経験を振り返り、治療やトレーニングに反映するのに加えて、クライアントが伝えてくれる、彼らの過去に関わった他の専門家達との経験から学べることもたくさんあります。 私は、過去に他のヘルスケアやフィットネスの専門家を試してみて、何らかの理由で、望んだ結果を達成できなかったクライアントによく出会います。これまでの経験から、その原因には、以下のようなことがあげられると思います。 クライアントの言葉を聞かなかった クライアントとのコミュニケーションが欠けていた クライアントに十分な時間をかけなかった これらの理由は、本質的に「臨床的」ではないことに注目してください。私のクライアントのうち、きちんと診断されず、適切な扱いを受けなかった人も少なくはありませんが、現実として、私自身も完壁ではありません。でも私は、クライアントの言葉をしっかり聞いて、コミュニケーションを取り、時間をかけます。そのため、間違った方向に向かっているかもしれないと感じたら、クライアントに聞いて話し合うことができます。クライアントは私を信じています。クライアントが私を信じていなければ、彼らは次の臨床家を探しに行くでしょう。 最近、私がクライアントから聞いた、過去の他の専門家との経験についての下記の2つのコメントについて考えてみてください。 「セラピストが私に言うことは全て、私が何を間違って行っているかでした。間違って行っているのはわかっています、だから治療に行っているのです。」 「最後にかかっていたセラピストのところを出るときは、いつも自分自身に対して落ち込んでいました。セラピスト達によって私は自分自身を悪く感じるようになりました。」 若い治療家に(経験のある治療家にも!)、私が長年をかけてわかったクライアントが嫌っていることをいくつかシェアしたいと思います。忘れないでください、クライアントに最善を尽くすためには、コミュニケーションを大切にしなければなりません。私の失敗やエラーから学んで、あなたがやってしまっている、でも実はクライアントは嫌っている下記の6つのことをしないようにしてください。 デバイスを凝視する 質問を聞きながら、コンピューターを凝視してタイピングをすることは、クライアントが、ヘルスケアの専門家と初めて接するときに直面する態度として最悪だと思います。これは、クライアントとのコミュニケーションとしてもそうですし、クライアントにあなたが親身になって考えていると感じてもらうためにも良くないことです。クライアントは、あなたがただ評価という「タスク」を終わらせようとしていると感じるでしょう。私は今でも紙と鉛筆で簡単なノートを取り、あとでパソコンに記録します。たしかに、こうすることでより多くの時間がかかりますが、これは正しい方法だと思っています。 セッションの間、携帯電話を眺めることも同様です。急を要するメールや、仕事関係のメールに返信しているのかもしれませんが、クライアントは、あなたがフェイスブックに子猫の写真を投稿していると思っているかもしれません。急を要するメールに返事をしなければいけない場合は、クライアントにしっかり断ってから行い、その場合にもクライアントの目の前では行わないようにしてください。こういった行為は、あなたにとってクライアントが大切ではないように見えます。急用でなければ、携帯電話はポケットにしまっておきましょう。 アップルウォッチは、私たちにとって助けとなるのか、それとも悪影響と働くかはわかりませんが、それはこれからわかるでしょう! セッション中は、クライアントが、あなたにとって世界で一番大切な人だと感じられるようにするべきです。 クライアントの言葉を聞かない クライアントと最初にするやり取りは、複数の理由からとても大切です。もちろん、何から始めるかを決める必要もありますが、最初のやり取りは、クライアントとの関係を築くのに非常に大切です。 まず、クライアントに話してもらうことから始めます。彼らの話を聞きましょう。すぐに核心に入りたい人もいれば、時間をかけたい人もいます。流れに従いましょう。できるだけ邪魔をせず、クライアントに会話をリードさせます。 経験を重ねるうちに、私の行う初期評価の主観的な部分は、たった30秒くらいしかかからなくなりました。でも同時に、クライアントとの関係を築くのに重要なことは、クライアントの主張を聞くことだと学びました。クライアントがあなたに期待していることを話せる、適切な環境を提供しなければなりません。 できていないことのみをすべて伝え、できていることを伝えない アセスメント、評価をしていく中で、「欠陥」を見つけることに夢中になってしまいがちです。良くあることではありますが、気をつけなければいけないのは、それをクライアントにどのように伝えるかです。 小さなことを気にしすぎる人もいれば、ただ純粋に落ち込んでしまう人もいます。 全てのクライアントが、あなたの施設を出るときに、気分がよくなり、楽観的になり、いい気分でいられるようにするべきです。あなたとの時間が、クライアントの一日の中で、最もいい経験の一つになれるようにしましょう。

フォームローリングと自己筋膜リリース パート1/2
ローリングするべきか、せざるべきか? それが問題だ。 自己筋膜リリース(SMR)に用いるフォームローラーやボール類、他の用具を使用してローリングすると、体内でどのようなことが起るのでしょうか。 まずは、筋膜だけを単独にフォームローリングすることはできないということです。他のすべての細胞(神経、筋、上皮など)も“ローリング”されます。 上皮と筋組織では、圧力が組織を通過する時または通過後に、水分は組織から絞り出されたり組織に再吸収されたりします。流し台でスポンジを絞った後で、鍋釜を洗う時に再びスポンジに水を満たしたりするのと同じイメージです。昔のベドウィンの箴言に “溜まった水は毒!流れている水は生命!”とあります。 16世紀の著名な医師であったパラケルスス曰く、“病気はひとつしかない。その病名は鬱滞である”。鬱滞してしまった組織に対してローラーを転がせば、その分、鬱滞に流れをつくり分散してくれるでしょう。 筋を強化することはできませんが、動脈の弾性を向上することができるかもしれないという初期エビデンスがあります。 神経の反応に注目してみると、ローリングは確かに‘感覚に満ちている’かもしれません。痛すぎれば筋の収縮や細胞の退縮を引き起こすのでマイナスに働きますから、私は痛いローリングは好きではありません。心地良い範囲、または‘快楽レベル’(快感と痛みの中間)の範囲でクライアントに行ってもらいます。 しかし、痛みを辛抱してローリングすることは、過去に外傷を負った部位に役立つこともあります。たとえば、昔骨折した跡にローリングするなど。しかし、ローリングが終わったら痛みもなくなっていて欲しいですし、アザを残したり、更にトラウマ化させたくありません。私見ですが、基本的にアザは治癒過程ではなく、ほぼ常に組織へのダメージを示唆しています。痛い部位には、用具をゆっくり動かすことが重要です。 もちろん、ローリングによって‘感覚運動性健忘症’の部位を目覚めさせることもできます。日常生活では動かさない部位に感覚を呼び起こすのです。これについての2つのポイントは: 1)腸脛靭帯(ITB)は、感覚運動性健忘症の部位ではありません;外界と接しており日々刺激を受けています。‘健忘’に最もなりやすい部位は、見つけにくくローリングしにくいのです――大腿内側部の内転筋全体や、分かりにくく小さい(しかし重要な)股関節後面の深部外旋筋群、後頭部のすぐ下の上部頸椎エリアなど。 2)自分自身の身体の健忘部位を見落としがちです。これは、単にこれらの部位を感知しないのでどこにあるのか分からないという理由からです。クライアントが、ITBや浅層の背部筋群のように分かりやすく表層に出ている部位ばかりを繰り返しローリングするのではなく、ローリングが必要な部位にローリングできるように私たちが手助けしましょう。 これを実践するには、臀部やITBの分かりやすい部位ばかりをローリングするのではなく、ローラーやその他の用具を腸骨稜縁の下部(縁の遠位部または下部で、ちょうど臀筋の上端)に敷き、試してみてください。骨の縁の下側に用具を敷いてロールし、骨から離れるように2~3cm下方へロールします。このように骨の縁に沿って、前の骨の出っぱりから後ろの骨の出っぱりまで(上前腸骨棘から上後腸骨棘まで)全体をローリングします。ボディーワークでも自己筋膜リリースでも見落としがちな部分ですが、新たな結果、新たな感覚、新たな水和作用が期待できます。 また、ITBのもう一端で、膝の外側、ちょうどITBが停止する脛骨顆と腓骨頭の間にローラーを当て、ゆっくりローリングし、ローラーの上で下肢を少しずつ動かして回旋しましょう。そうすることにより腓骨頭が開放され、スポーツ中、特にテニスやフットボールのように足が地面に接地中に捻る動作のあるスポーツでの回旋運動に対応できるようになります。

痛みの科学について知るべき7つのこと パート2/2
4. 脳はたびたび、そうでない時も身体が危険だと “思い込む” これの最も極端な例が、被害者が失った身体の一部に痛みを感じるという幻肢痛です。痛みのある四肢は何年も前に失っていて、もう脳にシグナルを送れないにも関わらず、四肢を感知する脳の一部は残存し、近隣の神経活動との混同によって誤った形で痛みが誘発されてしまうのです。これが生じた場合、被害者は失った四肢から信じられない程鮮明な痛みの感覚を経験することがあります。驚くことに、幻肢痛での腕の痛みは残った手をミラーボックスに置き、失った腕は問題なく存在していると脳を騙して思い込ませることにより、時折治癒することがあるのです!!これは痛みの緩和の本当のターゲットは大抵脳であり、身体ではないという事実の驚くべき例です。 この他にも、脳が身体の中で何が起きているのか理解できず、明らかに安全なのに痛みの原因となってしまっている箇所など、他にも沢山の例があります。あらゆる種類の関連痛、痛みが感じられる場所と実際の問題箇所とは離れているというのがこの例であり、異痛症はもう1つの例です。 5. 痛みは痛みを繁殖させる 痛みの生理学の残念な一面は、痛みが長引くにつれて痛みを感じやすくなるということです。これは長期増強と呼ばれる、とても基本的な神経処理の結果であり、基本的には脳が特定の神経経路を何度も使う度に、その経路をより簡単に活性化するようになるという意味です。スキーで山を下りながら、雪の中に溝を掘っていくような感じです – 何度も同じ溝を通る回数が多い程、同じ溝にはまりやすくなるのです。これは私達が習慣を学び、技術を磨くのと全く同じ過程です。痛みに関しては、特定の痛みを頻繁に感じる程、少ない刺激で痛みを誘発できるのです。 6. 痛みは物理的傷害に関わらず誘発される もしかすると“共に繋がっている神経は、同時に活性する”というフレーズを耳にしたことがあるかもしれません。この原則の最も有名な例はパブロの実験で、彼は愛犬がエサを食べるたびにベルを鳴らしていたら、後に、わずかなベルの音で犬のよだれがでる原因になったことを発見しました。神経レベルで何が起こったのかというと、ベルを聞く為の神経がよだれを出す為の神経と繋がるようになったのです。なぜならこれらの神経はしばらくの間、常に同時に活性していたからです。痛みにおいても同じことが起こりえます。例えば、あなたが仕事に行く度に、コンピューターと向かい合ったり、腰痛を起こすような方法で箱を持ち上げたりというようなストレスのある活動に従事するとします。しばらくすると、あなたの脳は、ただ仕事に行くだけで、もしくは仕事の事を考えるだけで痛みを感じるくらいに、仕事の環境と痛みを結びつけるようになります。仕事の不満は、腰痛の大きな予測因子であるというのも驚きではありません。 さらに、怒りや鬱状態、そして不安などの感情の状態も痛みの耐性を低下させることが証明されています。信じ難いことですが、研究は、大部分の慢性腰痛は実際の組織への肉体的ダメージよりも、感情や社会的要因が原因となっているという強力な証拠をもたらしています。長年戻っていなかった場所に帰った時、永遠に忘れ去ったと思っていた昔の話し方や姿勢、振る舞いにあっという間に戻ることに気づいたことがあるかもしれません。痛みも同様で、痛みに関連のある特定の社会的状況や感覚、または思考によって引き起こされたり、呼び戻されるのです。休暇中は無くなっていた痛みが、帰って来たら戻ってきたことに気づいたことはありませんか? 7. 痛みの感度を変えられるCNS CNSが、身体からの刺激に対して感度を増減できるメカニズムは多岐にわたります。脱感作の最も極端な例は、前述のように、身体からの痛みのシグナルが脳に届くのを完全に遮断させる緊急事態のなかで起こります。 大抵の場合怪我は、恐らく脳がダメージを受けたと感知した部位をより簡単に守れるように、感度のレベルを上げるでしょう。その部位が敏感になった時、痛みはより速く強く感じられることが予測され、通常は害のない機械的圧力でさえ痛みの原因となるのです。感度レベルの増減など、この記事で取り上げる範囲を大きく超える複雑なメカニズムが山程あります。私達の目的として、重要なポイントは、CNSが様々な要因による痛みのシグナルに対してコンスタントにボリュームレベルを調整しているということです。何らかの理由で、慢性痛のある人々の多くは、その音量があまりにも大きく上げられて、あまりに長く放置されているようです。これは中枢性感作と呼ばれ、恐らく多くの慢性痛の状態に少なくとも何らかの役割を果たしているでしょう。これは慢性的な痛みが、必ずしも身体への継続的、あるいは慢性的な傷害できるとは限らないもう1つの例です。 まとめ 身体がうまく機能している時、傷ついた組織は数週間もしくは数ヶ月以内に可能な限りの範囲で回復し、痛みは無くなるべきです。もし身体が回復の為にベストを尽くしたのであれば、なぜ痛みが続くのでしょう?傷害やダメージが長引く実際の原因も無く痛みが長期間続いた場合、ひょっとしたら身体そのものではなく、痛みを処理するシステムが問題なのかもしれません。言い換えれば、もしあなたに慢性痛があったとして、実際は痛めていない可能性が、少なくともあるということなのです。リサーチは、ある人達にとってこれは励みとなる考え方であり、痛みを悪化させる不安とストレス、そして脅威を軽減する働きをすると証明しています。

痛みの科学について知るべき7つのこと パート1/2
痛みの科学は過去50年間で多くの事を学んできましたが、これらの情報のほとんどは、一般的な痛みの対処においてわずかな影響しか与えていないようです。もし痛みがあるのであれば、これはあなたが知るべき内容です。この記事を読み終える頃には、あなたは痛みのメカニズムについて他の医療従事者達よりも多くの事を学ぶでしょうし、もしかすると結果として少し楽に感じるかもしれません。なぜなら痛みに関しての教育は、結果を改善することを研究が証明しているからです。痛みの科学の基本的な考えは以下の通りです。 1. 痛みとは身体の保護を目的とした生き残る為のメカニズムである 痛みとは、通常、脳がダメージを受けたと考える(正しいか否かに関わらず)身体部位を守る為に、あなたに何かをするよう働きかけることを目的とした不快で主観的な経験として定義づけられます。もし痛みを感じるならば、それはあなたの中枢神経系システム(CNS)が、あなたの身体は危険にさらされていて、それに対して何か行動を起こさなくてはならないと考えているということです。こういった意味でも、痛みは根本的に重要な生き残るメカニズムなのです。痛みを感じる能力を持たずに生まれて来た人達は(そう、実際に存在します)長くは生きられません。あなたのCNSがその痛みを作り出す作業をしっかりと引き受け、それによりいつ身体が傷つけられるのかを予測し、それが何か行動を起こすのにこれ以上ない程はっきりとした刺激を与えるのです。 2. 痛みは脳の出力であり、身体からの入力ではない これは痛みの科学において近年起こった根本的なパラダイムシフトです。痛みは身体から届くあらかじめ形成された感覚として、脳に受動的に受け取られるわけではなく、脳で作られるのです。身体部位が傷つけられた時、神経終末が脳にダメージの性質を含む情報をシグナルとして送ります。しかし、脳がこの情報を読み取り、痛みがダメージを保護して治癒に役立つ行動を起こす良い方法だと判断するまで、痛みは感じられません。脳はこの判断を下す為に膨大な量の要因を考慮し、同じ判断は2度と下しません。感情の支配や過去の記憶、そして未来への意図等を含む脳の様々な部分が痛みの反応を処理する手助けとなるのです。それゆえ、痛みは組織のダメージの度合いを測る正確な尺度にはなりません。行動を促すシグナルなのです。プロのミュージシャンが手を怪我した場合、彼の脳は同じ怪我をしたサッカー選手とは全く異なる行動を考えるかもしれません。それをふまえると、その個人が全く違った疼痛反応を起こすかもしれないということが理解できるでしょう。 3. 肉体的危害と痛みは異なる。逆もまた同様である。 もしあなたが痛みを抱えていても、必ずしも怪我をしているとは限りません。そしてもしあなたが怪我をしていても、必ずしも痛みを感じるとは限りません。痛みのない組織の損傷の極端な例として、戦闘中の戦士の負傷やサーファーがサメに腕を噛みつかれるといったことが挙げられます。こういった状況において、被害者は緊急事態が過ぎるまで痛みを全く感じない可能性が十分にあるのです。痛みとは生き残る為のメカニズムであり、痛みが生存をより困難する場合において痛みがないのは、驚くべきことではありません。私達のほとんどが腕をサメに噛み付かれた経験などないでしょうが、試合が終わるまで気づかなかった試合中の衝突や転倒、ちょっとした事故ならば経験があるでしょう。さらに、腰や肩、膝に腰椎ヘルニアや回旋筋腱板の断裂等のMRIで確認されるような、深刻な組織のダメージを抱えている人々の大半が無痛であるという沢山の研究報告があります。 どうやって痛みなしでダメージを受けるのでしょう?どういうわけか、脳はダメージが行動を起こすとは考えないのです。可能な説明の1つとして、ダメージは脳が危険として捉えないないように長い時間をかけてゆっくり起こる、もしくは、脳はダメージの回復が非常に順調であり、痛みはこれ以上効果的な機能ではないと結論づけたのかもしれません。もしどのような行動も効果なく必要なければ、もしくは行動がすでに起こされていれば痛みの理由はなくなります。診察室に入ったとたんに消えてしまうような痛みで医者に行ったことはありませんか?おそらくこれは、行動を起こすシグナルが集積され、修正措置が実行されたと結論づけた後に脳がリラックスした結果なのです。 その一方で、組織の損傷が全くないのに痛みに苦しんでいる人々も沢山います。異痛症と呼ばれる恐ろしい状態で、例えば軽く皮膚を触る程度の通常の刺激でさえも激しい痛みの原因になります。これはより一般的な範囲でも頻繁に起こり得ることの極端な例です –脳が無害な感覚情報を組織のダメージの原因として誤解し、不必要な痛みの原因となってしまうのです。

運動の変動性と痛みやリハビリテーションへの関連 パート2/2
リハビリテーションに必要不可欠なもの では、いったいなぜこれがリハビリテーションにとって重要なのでしょうか? 簡単に言えば、痛みは運動を変化させるのです。 私達が重要な関係性を発見した、運動の変動性に対する痛みの影響に着目することから始めましょう。いかなるリハビリテーションプログラムも、個人のその後の機能における痛みの影響に着目すべきです。研究によって浮き彫りにされた機能性の欠如を対象にすることは、リハビリテーションにおいて、‘最良の実践’と考えられるべきです。 痛みのある状態での運動への適合は、しばしば有益です。足を引きずることは、運動パターンの変化を通して、傷害組織への負荷を軽減させる絶好の例です。これらの変化は、回避の特異的パターンにおける場合だけではなく、運動のスピード、範囲、変動性においてもみられるかもしれません。身体のシステムは、傷害部位とそれに関連する部位に起こる、機械的剛性の増大、運動の変動性の減少を通して、‘防御’を作り出します。 これらの変化における概要をより詳しく述べたHodgesの新しい研究論文は、*ここをクリックしてください*。 下記は、私のお気に入りの引用文の一つです: “痛みへの適合は多くの短期的な効果をもたらすが、長期的な影響をもたらす可能性がある” ~P Hodges - Moving differently in pain ( 2011年)より 短期的な効果がもはや有益でなくなる際に、問題は発生します。これは、不適合と称されるかもしれません。防御の目的は必要なくなりましたが、誰もシステムに対して、もう充分だと知らせていないのです!特に、もしこの戦略が不変になるのであれば、組織レベルにおける運動の不適合による長期的な影響は、特定の組織への負荷の増大と、あまり使われなくなった組織における失調となり、従って、過負荷のリスクは増大します。 認知レベルにおいて、私達は、恐怖回避行動のような要因が人の運動の変動性を縮小するのを理解し始めるかもしれません。トップダウン(認識)に基づいたアプローチもまた、再度、より変動的になる手助けをするのに有益かもしれません。トップダウンとボトムアップ(身体運動に基づいたもの)が一体化したアプローチは、良好なリハビリテーションに関係する2つの要因に取り組むための、成功を期待できる方法です。 Zusmanは、この研究*ここをクリックしてください*で、優れたプロセスの概要を説明しています。使用される新しい、異なる、今までにない記憶を作り出すことは、この一体化したプロセスを使用しているリハビリテーションの目的なのです。Nijsおよびその他もまた、この研究*ここをクリックしてください*において、同様の概要を説明しています。 不変の戦略はまた、疼痛経験とその痛みの維持を強調する神経系レベル(神経タグ)において、痛みと特定の運動が一体となっている反復的な固有感覚情報を引き起こすかもしれません。私は、‘痛みの記憶’の概念について、この記事*ここをクリックしてください*で考察しています。 Moseley と Hodgesは、運動の変動性は認知的要因と関連があるということを発見しました。そして彼らは、実験的な痛みを経験した後の姿勢の変動性の低下を経験した人たちにとって、元の姿勢の戦略における正常な解決が起こらず、腰痛に関する認知的効果にも関連していたことを発見しました。 これは、腰痛の存続と再発の両方に影響を与える可能性があり、慢性腰痛の発生における潜在的な危険因子に関する研究論文において議論されています*ここをクリックしてください*。また、Jacobsおよびその他による研究論文*ここをクリックしてください*においてもみることができます。 一貫して文献で述べられているように、運動の変動性の低下は慢性痛と関連しています。よって、私はこのことに関して、下記でより詳しく検証してみたいと思います。急性痛は運動の変動性の増加と関連しています。これは、痛くない運動の変化を見つけようとしている運動系によるものであると、理論化することができます。もしある人のシステムが、その運動を変化させる能力を持っていなければ、代わりの戦略を見つけることには、問題があるかもしれませんし、これが慢性化の原因になるかもしれません。 傷害の慢性化における潜在的な素因として、私達は、慢性傷害において鍵となるリハビリテーションの構成要素として、そして、慢性化への移行を阻止する手助けをするための予防対策としても、その素因を見なければなりません。確実にその素因は、既往症が今後の類似した傷害に影響を与える理由に関するいくらかの洞察を私達に与えてくれるでしょう。 Debra Fallaのグループ*ここをクリックしてください*は、19名の慢性腰痛患者を集め、彼らを同年代同性からなる対照群と、箱の持ち上げ作業の繰り返しで比較しました。慢性腰痛群は、脊椎部硬直の増大に起因しているものと仮定される、脊椎からの運動減少を含む運動の変化を示しました。彼らが用いたもう一つの評価基準は、腰部脊柱起立筋の異なる部分の筋電図の活動です。彼らは、慢性腰痛群は、筋肉の同じ部分を使って作業を行っていたことを発見しました。その一方で、対照群は作業の間、筋肉の異なる部位を異なるタイミングで活性化させていました。慢性腰痛群の不変の戦略は、腰部における圧痛感受性の増大と関連していました。彼らは、下記のように仮説を立てました: “筋活動の変動性の低下は、腰痛の誘発と再発に関して重要な意味を持つであろう” この研究論文*ここをクリックしてください*において、著者は12名の慢性アキレス腱障害群と12名の健康なランナーの対照群における、ランニングの運動学に着目しました。彼らは、アキレス腱障害群の全員が、“荷重の独特で一致したパターン”を示した一方、対照群はレベルが増加するにつれて、著しく異なる変動パターン、本質的により高い変動性を示すことを発見しました。 この研究*ここをクリックしてください*において、著者は、以前に脛骨疲労骨折を経験したことのある女性ランナーに着目し、走行距離が同じで脛骨疲労骨折を経験していない女性ランナーからなる対照群と比較しました。彼らは、女性ランナーの両脚間の変動性(協調的変動性)に着目しました。既往症のあるランナーは、健側と比較した際に、患側において股関節−膝関節、膝関節−足関節(最大の影響)の変動性低下を示しました。対照群は両脚間の差異を示しませんでした。 変動性の低下は、潜在的に痛みの原因と結果の両方でありえます。Stergiouは、彼の研究論文“Human movement variability, nonlinear dynamics, and pathology: Is there a connection?(人間の運動の変動性、非線形力学、病理学:関連性はあるのか?)”において、この疑問を検証しました。既往傷害が無い場合の原因要素としての変動性の低下は、今後の前向き研究を通しての調査を確実に必要としています。この研究論文*ここをクリックしてください*は、画一的な職業活動における運動の変動性と、変動の低下がもたらすかもしれないリスクに着目しました。 多様性を持つために、恐らく私達は、固有受容感覚系や大脳皮質の運動野のような正しく機能していて、かなり正確な基本運動ハードウェアを必要とするでしょう。研究論文には、これら両方が痛みに影響されているということがよく解説されています。そして、私達はこれを運動経験の記憶の貯蓄と、私達が変動的で異なる状況と変動する刺激に適合する手助けを可能にする、私が基本的な‘運動の語彙’と称しているものを形成する機能と一体化する必要があります。特に慢性傷害や痛みを持つ人達においては受傷後、これらの基本的な運動の技能もまた、しばしば欠落しているのです。

運動の変動性と痛みやリハビリテーションへの関連 パート1/2
この1年間、運動の変動性は、より注目を集めており、ますます運動に関する議論に加わってきています。このブログに注目してきた方達は、過去数年にわたり、このテーマが定期的に言及されてきたことにお気づきでしょう。もし私達がこの分野に対する研究を探索すれば、トレーニングやリハビリテーションプログラムには、氷河のようにゆっくりと浸透しているものの、学界においては、かなり長い間、注目されているということを理解されるでしょう。 私達の人体に関する理解は、力学的な観点から離れ、より生物学的な観点に移行し始めてることを望んでいます。これは、身体の一般的な姿勢の変化や‘バランスの悪さ’は、実際には、純粋に力学系で問題になるほどには重要でないということを理解する手助けをしてくれるかもしれません。人間の生体系の耐性は、恐らく、私達が評価しているよりも優れているのです。 機構に対する怒り 今日教えられている主たる考え方である力学系の枠組みの中では、身体の操作は、精密機械と見なされています。もし機構の一部が破損、あるいは操作のために設定された正確で制限されたパラメーターから外れて操作されれば、それが機構全体に災いを及ぼします。私達はしばしば、そこに明らかな相関関係が無いときにも、はっきりと定義されていない理想と、様々な傷害や疾病に関わる体内での理想的な関係性からの逸脱に責を求めます。 痛みと痛みと姿勢の関連は、‘過回内’や筋発火パターンとタイミングのような概念のように、申し分のない例です。運動は全く同じで、客観的に定義されている‘正しい’運動の方法が多くないために、非難され、その代わりに、私達は広範なパラメーターの‘標準’を持っているのです。 人間は、単に機械の様なものではなく、異なる耐性、適合、適合率のように、身体を操作する多種多様な方法を持っています。生物有機体としての人体は適合し、その耐性を増大させる一方、金属には破損する限界点があります。ウォルフの法則は、ジムに通うことのように好例です。必要以上に私達の適応機構に頼っていると、時折、私達はこれらの耐性を超えることもあります。 運動の中の変動は、従来、‘エラー’と見なされていました。これらの‘エラー’は、余剰で、もはや必要とされていないものとして見られ、実践を通した従来の運動制御モデルにおいて、このエラーは排除されれば良いと考えられていました。現在、運動‘過剰’の概念という、全く異なる見解が提案されています。余剰な要素が、むしろ利用されるべき身体能力のプラス面として理解され、実際、運動に極めて重要なのです。このLatash氏の論文、“The bliss (not the problem) of motor abundance (not redundancy)((余剰ではなく)運動過剰の(問題ではなく)至福)”*ここをクリックしてください*が、この新しい見解の概要を見事に説明しています。 私達がエクササイズを教えられる際に、静的な解剖学に基づいた筋収縮で、定着した‘的確な’方法に基づいた筋肉を対象にすることを目的とした‘正しい’テクニックを見せられます。そのエクササイズは、繰り返されることを目的とし、柔軟性に欠け、特異的な結果に対して恒常的です。特異的で不変な過負荷は、より大きく、より強いものを作るときの狙いです。もし運動が可変的ならば、そうなるために筋肉は機能しなければなりません!私達が解剖学と運動に関して教えられる際に、この基本的現実は省略されています。恐らく、力学モデルには複雑すぎるのかもしれません。 1930年代のBernsteinによる、金槌でのみを打つ鍛冶屋を対象にした研究において、経験豊富な、作業に基づいた職工は、“反復の無い反復”を示し、金槌による打撃の軌道は、安定した反復可能なパフォーマンスに必要な低い変動性を示したことを発見しました。技能の終点は同じでしたが、関節の角度や部分的な変動性は高かったのです。 この部分的な変動性は、協調変動性*ここをクリックしてください*と呼ばれています。これは、反復される技能のパフォーマンスと、その特異的過負荷に対してパフォーマンスを維持し、その崩壊を防ぐ能力にとって必要不可欠です。例として、これはランニングと変動性の減少に非常に関連していて、膝蓋大腿関節痛に関して議論されています*ここをクリックしてください*。健康なグループにおいて、疎結合が基準でしたが、 膝蓋大腿関節痛を患っているグループのランナー達は、部分間で密結合(低変動性)を示しました。 Seayおよびその他*ここをクリックしてください*は、現在腰痛を患っている被験者のグループと、腰痛を一度経験している被験者、腰痛を過去一度も患ったことの無い被験者のグループ間で、変動性における差異を発見しました。受傷者、あるいは傷害から回復した被験者と、過去一度も患ったことの無い被験者のグループの間の変動性における差異は、リハビリテーションにおいて、私達が注目する必要があるかもしれない要因において、価値ある洞察を私達に与えてくれるかもしれません。 このことに関する更なる詳細は、後ほど述べます。 彼らの結論は、下記のとおりです: “これらを基に、データは、一度の腰痛発作にさえ関連するパフォーマンスの欠如と傷害リスクの増大への洞察に役立ち、臨床医は腰痛のためのリハビリテーションを処方する際に、痛みの解決のその先を見る必要がある” 運動の変動性は、生体系の中に本来備わっています。本来備わっているだけでなく、過負荷によるリスクの減少にとって有益で、その能力が、私達を取り巻き、絶え間なく変わる環境の中で発生する事象への適応を可能にしています。一流のアスリートが、何時間も熱心な練習を行っても、精密で不変の運動を繰り返し再生することはできません。最良の運動をする人達は、パフォーマンスの制約と前後関係による数多くの多様性を用いて、同様の安定した終点技能を遂行することができます。弾力的で強固であることの一部は、変動性の中にあるのかもしれません。負荷への耐性能力は、私達の協調変動性を介して、幾分、内部で必要な処理が行われる方法に関わっているかもしれません。 運動が研究され、その研究されたグループの手段を反映するために、しばしばデータは均質化されます。この飲み込まれてしまった重要なデータではなく、*ここをクリックしてください*存在する広範囲の運動変動と、これが私達に示しているかもしれないことをより理解するために、私達はまた、人同士の相互関係(人と人の間)と情報の内部(タスク間変動)に着目すべきです ここに私が集めた、運動センサーを着用した同一人物による、5回のシングルレッグ・スクワットの例があります。それぞれのスクワットは、計測によって微妙に異なります。 自分で行う小さな実験として、あなたの名前を同じ場所に10回繰り返し書いてみてください。そのうち何回、寸分違わずに書けましたか?どれも大体同じような輪郭を描いていますが、ピッタリと重なることは絶対になく、あなたが何千回も練習している運動でも同じことでしょう。
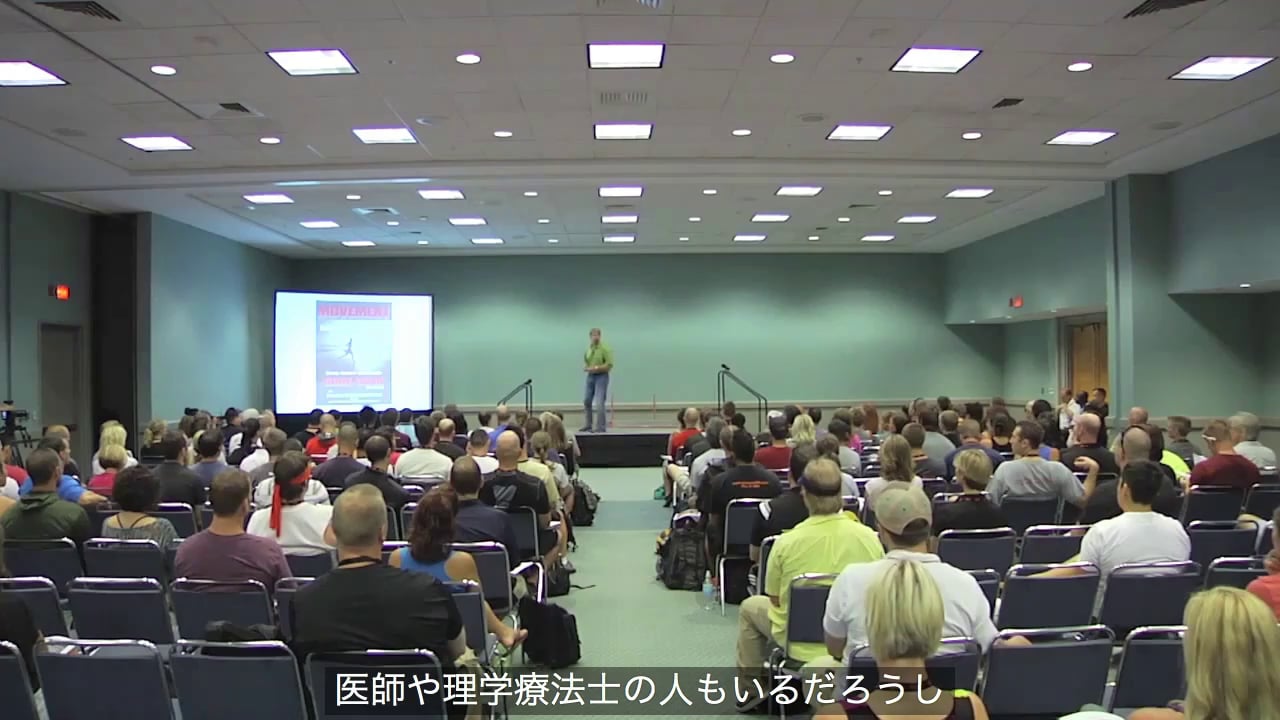
FMSモデルの実際例への応用 パート1/2
アメリカで開催されるパフォームベターのサミット前日に開催された、FMSのセミナーを収録したビデオ ”FMSモデルの実際例への応用” から、の抜粋。グレイ・クックが、スクリーンとアセスメントの違い、動作を学ぶプロセスの重要性を熱く語るビデオのパート1。
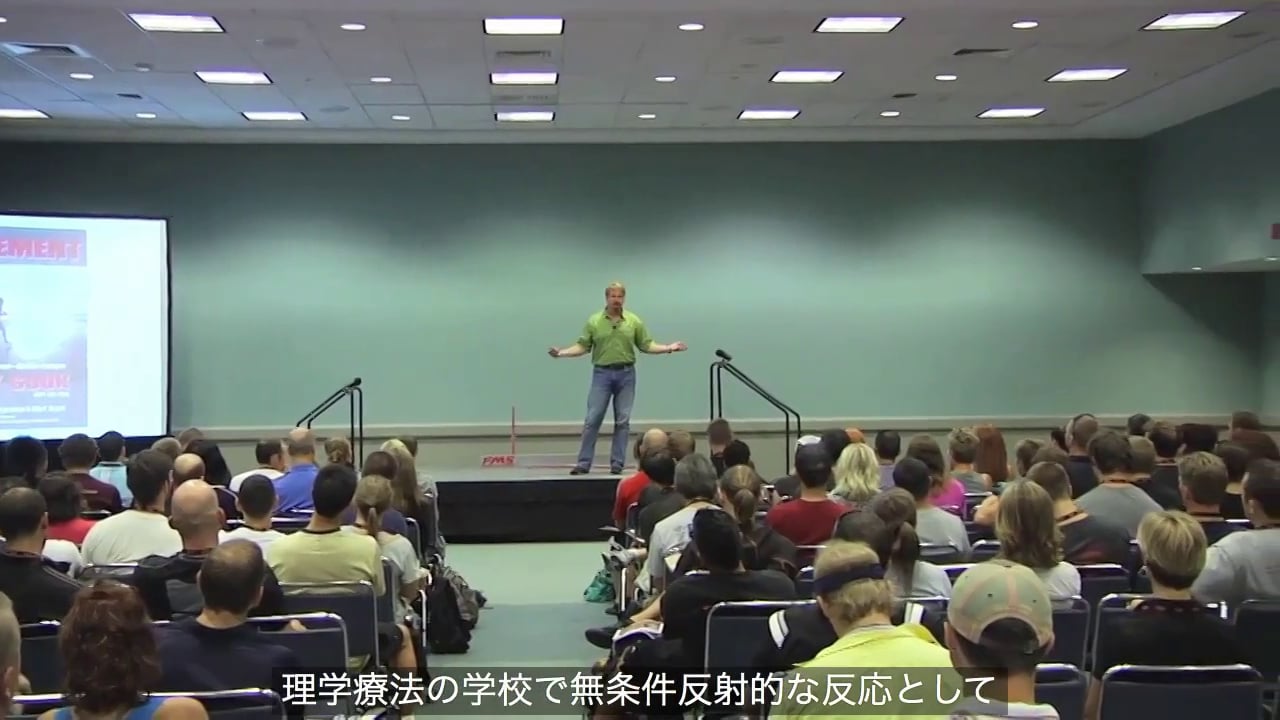
FMSモデルの実際例への応用 パート2/2
アメリカで開催されるパフォームベターのサミット前日に開催された、FMSのセミナーを収録したビデオ ”FMSモデルの実際例への応用” から、の抜粋。グレイ・クックが、スクリーンとアセスメントの違い、動作を学ぶプロセスの重要性を熱く語るビデオのパート2。

トータッチプログレッションでつま先に触れてみよう パート2/3
トータッチプログレッション 段階2:トーダウン 段階2も同様に行いますが、ここでは踵を持ち上げます。これによって、平衡を移動させ正しい体重移動を指導します。 両足を揃えて立ち、踵同士とつま先同士を付けます。板のようなものを利用して両側の踵を1~2インチ(2.5~5cm)上げます。 足の位置を変えないようにし、両膝を軽く曲げます。左右の膝の間にフォームローラーまたは巻いたタオルを挟みます。 腕を天井に向かって伸ばし、手の平は前方に向けます。 呼吸を変えないようにして腹部をできる限り引っ込めます。 そして、ゆっくり緩やかにつま先に手を伸ばしていきます。スティッキングポイントではフォームローラーまたはタオルをしっかりと挟みます。 つま先に触れられない場合は、膝を弛めてチーティングします。 再テストを行います。 この2つの段階を完了したら、板やフォームローラー、タオルを外し、トータッチ動作を行ってみます。 腕を天井に向かって伸ばし、腹部を引っ込め、つま先に手を伸ばします。 腰やハムストリングに多少強めの緊張を感じるかもしれません。また、段階1よりふくらはぎの緊張はやや軽めになるかもしれません。 トータッチプログレッションに沿って行えば、手がつま先にずいぶん近づくはずです。 これで効果がなかったらどうしますか? このプロセスを試みたにも関わらず、成功しない人もこれまでにいたことでしょう。なぜでしょうか?それは、はじめにアクティブストレートレッグレイズをチェックしなかったためです。 アクティブストレートレッグレイズができなかったら、それをまずできるようにすることが先決です。簡単なアクティブまたはパッシブレッグロワーリングドリルが、下半身を整えてくれるでしょう。 しかし、私たちのアウトラインに忠実に従って行えば、トータッチの大きな改善が見られます。 向上を“定着”させる方法 つま先に触れないというのは悪い習慣ではありませんが、痛みなしでつま先に触れることは、明らかに良い習慣です。 どうしたら悪い習慣を崩せるでしょうか。何かもっと良いものに置き換える必要があります。 これは、特定の筋のストレッチやストレングスということではなく、パターンを変えるということなので、誤ったパターンを打破した直後に、新たな情報をシステムにしっかりとアップロードしなくてはなりません。 そのパターンを打破しさえすれば、誤ったパターンに立ち戻る前の短期間のチャンスを得ることができます。 背中に棒のようなものを当てがえば、脊椎を真っすぐに起立した状態が保てるでしょう。 デッドリフトのメカニクスを練習してみましょう。簡単な方法は、壁から約30cm離れ、壁にお尻がつくように後方へ出来る限り近づけます。しかし、壁に寄りかかってはいけません。 ちょうどこれからトータッチをしようとしている人への良い教え方があります。「つま先に触れられるまでに5分も必要ありません。朝、外出する前や就寝する前に5分間ぐらいする時間はありますね。それだけです。」 デッドリフトやケトルベルスウィング、あるいは何らかのタイプの股関節のヒンジを伴う動き、ジャンプやハングクリーン、パワークリーンなど、もっとバリクティックな動きがあるようなエクササイズをするならば、これらを行う前につま先が触れるかどうか確かめてください。 最後に、3人の別々の患者がトータッチで改善した3つの症例を記したいと思います。これによって、トータッチのような簡単な動きがどれだけ強力で実践的かがおわかりになるでしょう。 トータッチ症例1:腰痛を訴える高齢の女性 グレイ・クックが、腰痛を患う高齢の女性を彼と同僚が担当したときの話をしてくれました。彼女の評価を始めたとき、信じられないほどバランスが損なわれていることが分かりました。彼女の腰痛は、伸展することで出ますが、トータッチに制限がありました。 前屈では痛くなく、後屈で痛みがありました。さらに、彼女のバランスは、極端にやっかいなものでした。グレイはこう言いました。「彼女がクリニックまで歩いて来られたこと自体が驚きです」。 彼女に片脚でバランスをとらせると、ふらふらとバランスを崩しどこかにつかまらなくてはならなかったり、3秒も経たないうちに挙げていた脚を下ろさなくてはなりませんでした。片脚立位は左右両方とも損なわれていました。前屈は痛くはないが、曲げることができませんでした。そして、後屈は痛みがありました。 臨床医として彼女の腰痛に対処する責任はありましたが、彼女の症状を悪化させないで初日から行えそうなエクササイズは2つしかありませんでした。痛みが出る方向に動かすのではなかったので、腰痛を悪化させるものではありませんでした。むしろ、前屈や片脚立位の機能的障害がある方向に動くものでした。 片脚立位は複雑です。多くの運動制御を必要としますが、動きはほとんど伴いません。グレイは常に、安定性や運動制御を改善しようとする前に可動性を増加させようとします。 彼らは、この高齢の女性がアクティブストレートレッグレイズを行うのをチェックしてみましたが、それほど悪いように見受けられませんでした。彼女が仰臥位になり、一方の下肢が上がらないようにしながらもう一方の下肢の膝は真っすぐにして、股関節がどれくらい屈曲できるかを見せてくれたとすれば、それを見た私たちは全員「この女性が、つま先に触れられないはずは絶対にない」と言ったことでしょう。 しかし、立位ではそれができなかったのです。 そこで、彼女を、両脚を前に伸ばした長座位で座らせました。彼女は、この肢位ではつま先に触れることができたのです。更に、つま先を触れるだけの可動性があることを示してくれたわけですが、立位になるとどうしてもつま先に触れることができないのでした。 彼女のバランスにチャレンジするために、彼らは、もうひとつのトータッチプログレッションを実施しました。彼女のサポートができる位置で、解説をしながら、彼女が呼吸を止めていないか、呼吸をしているかどうか確認しながら行いました。つま先を挙げた状態で10回トータッチを行い、休憩を入れました。 次に、つま先を下げた状態で10回トータッチを行い、休憩を入れました。グレイは言いました。「では立ってつま先を触ってみてください」。 彼女は完全につま先を触れたのです。 「片脚立ちでのバランスも見せてもらえませんか?」 彼らは、彼女の片脚でのバランス能力を、ほぼ4倍にしたと彼は言いました。 更に彼らが「後屈をしてもらえますか?」と加えて、彼女がした伸展は、以前よりも2倍の可動域がありました。可動域最終域で少しだけ違和感があっただけでした。 片脚立ちのバランス能力がトータッチを改善することで向上するというのは、どういうことでしょうか? 彼らは、彼女の矢状面上の動きを変えることにより、彼女の動作を改善しました。動きが改善されれば必ず入ってくる感覚入力も改善します。 可動性が高ければ高いほど、多くの情報がインプットされます。情報がバリアに達した瞬間に支障を来たし渋滞を起こし情報が止まってしまいます。可動性の制限があるところはどこでも、インプットされる情報は減少します。減少した情報がインプットされるということは、結果的に洗練性が減少することになります。 安定性または運動制御は単に、脳にインプットされる情報の処理および筋緊張の適切な振り分けによるものです。 安定性と運動制御は、決して筋の最大収縮によってもたらされるものではありません。ブレーキを急に強く踏むのではなく、軽く踏んで調整するのです。もしブレーキを強く踏みすぎれば、横滑りしてしまいます。逆に、踏みが十分でなければ、カーブを曲がり切ることはできません。これらの微調整には、インプットが必要なのです。 どうすれば、繰り返し説明しなくても質の良いインプットが作れるでしょうか? それには、可動性をもっと増やすことです。そしてなにか変化を起こせたかを確認してみます。 この症例で、彼らは幸運にもトータッチを正常化し、片脚立ちが可能な時間も質も4倍にすることができました。

トータッチプログレッションでつま先に触れてみよう パート3/3
トータッチ症例2:膝の術後の患者 この患者は1ヶ月間、膝を20−25°以上には充分に伸展したことがありませんでした。彼は手術を受け、当初取り組むべきリハビリテーションに十分に参加していなかったのかもしれません。または、家でのエクササイズをしていなかったのかもしれないし、もしくは、担当者が、彼が行うエクササイズの重要性を説明せず、彼の疑問に十分応えていなかったのかもしれません。 この症例は、グレイと彼のパートナーが担当した、膝が伸展できない患者についてです。彼らは、ポステリアチェーンに鍼を施し、それからモビリゼーションを行いました。 彼の膝にテーピングをすることで、膝はほぼ完全に伸展できましたが、問題がありそうな行動パターンがあり、グレイは治療家としてこの効果は続かないと直感しました。この患者は膝が屈曲位のまま4週間も歩き回っていたのです。膝が15分間だけ伸展したからといって彼の行動を変え、いま治療したばかりの膝を使うには十分なはずはありません。 彼は、屈曲位の膝に長い間慣れてしまっていて、膝を伸ばすことに抵抗や恐怖感があったでしょう。そこで、彼らは、この患者が考えることなく膝の伸展を行える環境を作る必要がありました。 トータッチプログレッションはどうでしょうか? トータッチプログレッションで、彼は膝に力を入れるでしょう。 予想通り、彼らは、この患者にトータッチプログレッションを行ってもらいました。そして、毎回終わるたびに膝の伸展の動きは増えました。 トータッチ症例3:頚部痛 首に問題があると訴える患者ですが、彼の首には問題が見つかりませんでした。首を動かすと痛いのですが、動きの制限や筋力低下は見つかりませんでした。 彼の肩は調子が良さそうに見えますが、これまで診てきた患者の中で最もこわばった姿勢をしているひとりでした。 彼らは、彼の歩行を観察し、コアと骨盤、腰部が共同で機能していないことに気づきました。そして、彼らが、この患者に片脚立ちをしてくださいと伝えると、バランスをとる為に、いつも同じ側の肩をすくめなくてはなりませんでした。彼は、首や肩をまるでコアであるがごとく使わなくてはならなかったのです。コアが動員されるべき時、彼は代わりに上半身を使っていました。 これは、とても良く動く痛い頚部とまったく動かない痛みのない腰部の症例でした。 そこで、彼らはどのような方法を使ったのでしょうか? トータッチです。 彼らは、トータッチプログレッションに腰が耐えられるかを、臨床的に確認しました。そして、トータッチブログレッションを実施し、悪いパターンを壊し、つま先に触れることができるようにしたのです。 再び、片脚立ちを確認すると、今度は僧帽筋を使わずにバランスをとることができました。 僧帽筋がどれだけ強力か考えてみてください。スクワットで持てる重さより、シュラッグで持ち上げられる重さの方が大きいかもしれません。デッドリフトの達人ではない限り、シュラッグで持ち上げられる重さは、デッドリフトで持ち上げられる重さと同じぐらいでしょう。 安定させる手段が他にない為に、地面に足が着くたびに僧帽筋を動員しなければならないとしたら、首にどれだけのストレスを与えるか考えてみてください。 この患者の頸椎には何も悪いところはなかったのですが、コアが身体全体と共に矢状面の動きにおいて機能していなかったため、首が酷使されてしまっていたのです。 トータッチプログレッションを使うタイミング グレイ・クックによれば: 若い臨床医がかつて私にこう言いました。「クックさん、あなたはひとつしか芸当がない馬のようですね。どんな人にもトータッチプログレッションをさせています。」 私は、彼に言いました。「そうお考えになっても結構ですよ。あるいは、ここにあと2ヶ月いてそれを使うのを二度と見ることがないか、それとも30倍使っているのを見るかしても良いですよ。」 トータッチを使宇野は、それが私の好みだからではなく、必要な状況で使うのです。 3人目の患者は、サイドプランクを使った方がコアをより発火できたかもしれません。しかし、そうすることで、すでに過活動になっている頚部や僧帽筋はどうなるでしょうか。トータッチであれば、問題のある部位に負担をかけずにコアの発火を助けられる方法でした。 膝を伸ばせない患者に、家に帰ったら大腿四頭筋のエクササイズを何セットか行うように言うのは簡単だったでしょう。しかし、その機能性はどうだったでしょうか? 彼が立ち上がる時、すでに膝の伸展は行っていたのではないでしょうか? トータッチプログレッションでは、彼はすでに立位であり、膝は負荷下で伸展になることをすでに学習していたわけです。 高齢の女性は、腰痛の他にバランスにも問題がありました。トータッチプログレッションによって、バランスとることに一生懸命になるように言わなくても、どちらにも改善がありました。 バランスに問題がある人の多くは、バランスをとろうと一生懸命になると、かえって悪化してしまいます。なぜなら、もしバランスのとりかたを知っているのであれば、すでにそうしていたでしょうから。更にがんばるということは、そもそも間違った方向に更に努力することです。このような理由で、トータッチプログレッションは大変役に立つのです。 これらすべての症例で、トータッチを私が使いたかったから使ったのではなく、これが全てを救済すると信じているから使ったわけでもありません。必要とされる状況であったから使ったのです。

プラシーボの科学 パート2/2
学習 ある刺激を受けた直後に、痛みの緩和を感じる経験を重ねると、脳の中で、刺激と痛みの緩和が関連づけられます。たとえば、頭痛を緩和するために、定期的にアスピリンを取っていると、脳は、薬の存在を気持ちが良くなることと関連付け始めます。この状況で、もし本物そっくりの偽物のアスピリンを取るとすると、この関連付けがされていなかった場合と比べ、かなり高いプラシーボ効果が得られるでしょう。その期待が完全に無意識で、過去の関連付けに基づくものだとしても、過去の経験は、特定の刺激からの効果を「期待」させます。 同様に、この関連付けは「忘れる」こともできます。パブロフの犬は、ベルを鳴らすとよだれを出しますが、もしもベルを鳴らし続けつつも、食事を一切与えなければ、どこかの時点で、犬は学習し、よだれを垂らすのをやめます。また、先ほどの例で、有効成分を含まない偽物のアスピリンを取り続ければ、やがて学習したプラシーボ効果はなくなるでしょう。 関連付け学習が、どのようにプラシーボ効果を生み出すかを実証した面白い実験があります。好きな液体と免疫抑制薬を関連づけられたネズミは、その液体を飲むと、薬がなくても免疫抑制を経験するようになります。同様の結果が、人間でも起こることがわかっています。おいしい飲み物を抗ヒスタミン剤と関連付けると、その飲み物により、アレルギーによる鼻水が改善するようになります。無意識の学習はまた、内分泌系システムにもプラシーボ効果をもたらします。本物のインスリンを使って関連付けをすると、偽物のインスリン注射が血糖値を下げることがわかっています。 これらの事象は全てとても興味深いものですが、なぜ、徒手療法や運動療法の専門家がこういったことを気にする必要があるのでしょうか?私たちは(願わくば)、トリートメントの際に、患者に治療と痛みの軽減を関連付ける薬を与えるビジネスを行っているわけではありません。 私たちがなぜこういったことを気にするべきなのかというと、この研究が、運動療法に関連した痛みの軽減において、おそらく主要な働きをしているであろうものに関する洞察を与えてくれるからです。それは、動きと痛みの負の関連性を「忘れる」ことです。この関連付けは、怪我から起こることもあり、怪我が治ったあとでさえ、やっかいなノシーボ効果として残ることがあります。 あなたが腰を痛めて、腰椎の完全屈曲にむかって前方に屈曲するときには常に痛みを経験するとします。意識的にせよ、無意識にせよ、あなたはこの動きを痛みと関連付け始め、やがてこの動きをするときに、痛みを予測するようになります。 しばらくして腰の怪我が治っても、この関連付けは残ります。前方屈曲がノシーボとなり、痛覚の「有効成分」がなくても痛みが起こるようになります。どうしたらこのノシーボ効果を止めることができるでしょう?学習された前方屈曲と痛みの関連付けを取り除かなければなりません。 ゆっくり、それまでとは違う痛みの恐れのない方法で、十分な回数の前方屈曲を繰り返せば、脳はやがて痛覚の「有効成分」がもう存在しないことを学習します。こうして、動きと痛みの関連性を忘れていき、やがて痛みのない完全屈曲が取り戻せます。 でも、もしこの忘却プロセスをたどらなかったとしたら、どうなるでしょう?恐らく、怪我が治り、痛みがなくなっても、痛みを経験するのが怖くて、その動作を完全に避けることになるでしょう。学習された痛みと動きの関連性を取り除いていないために、ノシーボ効果が残るのです。これは、動きに対する恐れ(運動恐怖)が、急性損傷が慢性的痛みへと発展する有効な指標であることを示す理由の一つです。 運動療法により慢性痛を取り除く主な方法の一つは、意識しているにせよ、無意識にせよ、痛むことを予測している動きを、ゆっくりと慎重に発展させていくことです。 結論 プラシーボの科学はとても興味深く、有益です。動きを基盤とした治療における成功の大部分が、プラシーボのような効果、あるいはノシーボを取り除くことによって起こると考えるのは、間違いではありません。しかし、プラシーボという言葉は混乱を招き得るものだと思います。プラシーボは、異なるメカニズムを通して起こる、異なる効果をもたらす様々な現象を表しています。 不安の軽減を通して働くプラシーボ効果もあれば、報酬システムの起動を通して効果をもたらすプラシーボ効果もあり、さらには、痛覚の下行性抑制によって効果がもたらされるものもあります。共通するのは、それらは全て認知の入力、つまり、患者が自身の健康に対して期待しているもの、信じているものによって起こるということです。 これは、プラシーボという言葉の別の問題とも関連しています。プラシーボという言葉は、患者の期待の変化を通じて効果が出る治療が、惰性であり、効果的でなく、はたまた意味のない、倫理に反したもの、さらに、詐欺であるとさえ示唆します。もちろん、その治療がシュガーピルのようなものである場合や、疑似科学やインチキ療法に基づいたものである場合は、その通りかもしれません。こういった場合は、患者は騙されて、期待や信念を変えさせられます。これは多くの場合、倫理に反しています。 しかし、もし治療が主に信念や期待の変化を通して効いているとすれば、そして変化はその信念をより正確にするものであるとしたら、どうでしょう?次のシナリオを考えてみてください。どれも騙してはいませんが、プラシーボ効果が関わっているように描写されています。 腰の痛みとMRIの所見に関連性がほとんどないという正確な情報を与えられたクライアント。これは不安や痛みを軽減します。 違う方法で行えば、痛みなく前方屈曲ができることを、受動的、および能動的動作を通して教えられたクライアント。これは不安を軽減し、治療の効果を期待させ、痛みを減らします。 思いやりのあるセラピストから慈悲深く、共感できる治療を受けたクライアント。これは、不安を軽減し、効果を期待させ、痛みを減らします。 マッサージによる痛みの軽減を過去に多く経験しているクライアント。この学習された関連性は、マッサージによる更なる痛みの軽減に関与しています。 これらは全てプラシーボ効果でしょうか。これらの例は全て、患者の信念を変えることが大きな役割を果たしています。しかし、そもそもそれこそが治療の目的だったのです!だから、治療が惰性であり、効果的でなく、見せかけであるという提言はされるべきではありません。こういったケースで、プラシーボという言葉を使うことは、批難や混乱を招くことにつながります。 私はこう考えたいと思います。痛みは恐れを認識することによりもたらされ、クライアントに、その恐れを疑問視させる最大限の良い知らせを与えることによって治療することができます。 これによって倫理的な問題は起こりえますか?あるとすれば、それはその良い知らせが真実ではなく嘘に基づいている場合でしょう。幸運なことに、クライアントには、セラピストのタッチ、動き、会話から学ぶことのできる多くの楽観的真実があると思います。

トータッチプログレッションでつま先に触れてみよう パート1/3
簡単なテストで、その人が持つ潜在的な問題の多くを明らかにすることができます。 トータッチは、そのようなテストのひとつです。 深いスクワットのようにトータッチも、かなり細かいところまで観察すると、たくさんのことが分かる基本的なムーブメントパターンです。 それでは、どうしてつま先に触れることができない人がいるのか、そしてそれは何を意味するのかを見ていきましょう。 つま先に触れることができない理由 つま先になかなか届かない場合、ハムストリングの硬さのせいにされることがよくあります。なぜなら、この動作をするとそのように感じるからです。 しかし、ハムストリングの硬さが本当の原因なのでしょうか。それともこれは、なにか他の問題の症状にすぎないのでしょうか? 多くの場合は、後者です。過去のケガが完治していなかったり、トレーニングにおける悪い癖があったり、ポステリアチェーン(身体後面の連鎖)に対してアンテリアチェーン(身体前面の連鎖)のトレーニングの方が過多になってしまうなど不均等なトレーニングであったり、可動域が十分でなかったり、他の多くの原因の可能性があるかもしれません。これらどれがあっても、つま先に触れることができる生まれ持った能力を低下させる可能性があります。 なぜ皆さんやクライアントが、つま先に触れることができないのか、その主な理由は下記の通りです。 不十分な後方への体重移動—上半身が下方と前方に傾いた時、後方へ体重を移動できなければバランスを崩し、前方に倒れないようにするために、ハムストリングが収縮します。この場合、ハムストリングは、単にケガを食い止めるサイドブレーキにすぎません。 こわばった腰部—つま先に触れる際、腰を丸めたがらない人がいますが、おかしなことに、このような人ほど、デッドリフトなどの負荷下で危ない腰の曲げ方をしたがるのです。 頸椎や胸椎のこわばり—頸椎と胸椎のこわばりもまた、床に向かって手が届く距離を制限することがあります。 底屈筋群の緊張の増加—緊張の増加は、膝関節と足関節をまたがる腓腹筋に主に見られます。底屈筋群の緊張は、関連する痛みがない限り、ほぼ必ずといってよいほどハムストリングに感じられます。 では、どのように原因を絞り込んでいきますか? FMSのアクティブストレートレッグを行ってみてください。 片側の脚を動かさずに床にぴったり置いた状態で、もう一方の脚が約80°あるいはそれ以上挙上するにも関わらず、つま先に触れることができない場合、問題は骨盤よりも上部に潜んでいる可能性があります。 脚が70°前後にも挙上できない場合、問題は骨盤より下部にありますが、骨盤より上部に潜む問題を除外できるわけではありません。 注: ファンクショナルムーブメントスクリーンでは、トータッチはプログレッションではありますが、スクリーンではありません。 SFMA(メディカルムーブメントスクリーン)では、最初にトータッチを行います。もし、症状が引き起こされたら、その原因を見つけるためにリグレッション(後退)を行います。 デッドリフトをする前にトータッチができている必要がある理由とは つま先にしっかり触れることができない人は、矢状面での低速でテンションの高い動きをする時や、高速でテンションの高い動きをする時の、生体力学的な動きと体重移動が不完全です。 その動作に必須であるコアの安定化と脊椎の安定化を放棄してしまい、屈曲動作の初期に、安定し硬くなっているべき部位を使って屈曲しようとしているのです。 これは、適切なヒップヒンジが行えないということを意味します。この場合、軽いウェイトであってもデッドリフトをしようとする姿勢をとったとき、動作の初期には腰部を丸くしてしまいます。股関節を働かせるのではなく、最終的に、脊椎に負荷をかけてしまうのです。 注:非荷重の動きであるトータッチで脊椎を丸めることは、オーケーです。トータッチで脊椎を丸くしないことは、機能不全を示しています。なぜなら、それは正常な体重移動や身体力学、アライメントが乱れているということだからです。 トータッチは、腰部の緊張を緩め、踵からつま先へ滑らかに、一貫した体重移動ができるようにします。これらは共に深いスクワットとヒップヒンジに極めて重要です。 つまり、クライアントにトータッチを指導することにより、デッドリフトや深いスクワットを指導する為のより良い環境を提供します。 体力があって健康的に見える人を指導する時、確証がない限りその人がトータッチのような基礎動作パターンを遂行できると推測しないでください。デッドリフトやケトルベルスウィングのような負荷下の動作を行う前に、必ずスクリーニングを実施し、つま先に触れることができるかどうか確認しましょう。 つま先に触れるようになるためにどう指導するか つま先に触れることができない人のほとんどは、アクティブストレートレッグレイズの際、ある程度の困難が生じます。もしそれが問題であれば、常にまずアクティブストレートレッグレイズを先に正常化します。 もし、アクティブストレートレッグレイズが完璧であるにもかかわらずトータッチが行えないならば、立位でこの動作を行う際、完全な可動域を妨げる何かがあるのかもしれません。 この場合、簡単に行えるトータッチプログレッションに従います。ここではストレッチや軟部組織のモビリゼーションは一切必要ありません。 トータッチプログレッション 段階1:トーアップ 両足を揃えて立ち、踵同士とつま先同士を付けます。板等を利用して両側の前足部を1~2インチ(2.5~5cm)挙げます。 つま先に触れることができない人は、矢状面の動きにおいてのバランスのとりかたが異なります。体重の移動を正しく行うことができず、平衡を保つために、底屈と背屈に偏っているのです。 つま先を上に向けておくことで、バランスを保つために脚に頼ることが少なくなり、より体幹と体重移動の能力に頼るようになります。 足の位置を変えず、膝を軽く曲げます。フォームロールまたは筒状に巻いたタオルを膝と膝の間に挟みます。 前屈を妨げるのは、アンテリアチェーンやポステリアチェーンだけではありません。外側線である腸脛靭帯と大腿筋膜張筋も、前屈を妨げることがあります。両膝が触れていなければ、外側ハムストリングと腸脛靭帯に偏ってしまい、膝のロックが解除されます。これは、関節の後面を保護するためのハムストリングの発火をストップさせます。 両膝の間に何かを挟むことは、持越し効果もあります。内転筋群が発火すると、腹筋へも影響してそれらも発火します。そうすれば、相反抑制と背部の筋群の弛緩を得ることができます。 このポジションは不自然に感じるかもしれません。もしクライアントがこの足のポジションを保持できないようであれば、フォームローラーやタオルから他の小さめの道具に代えてください。 まず、両腕を天井に向かって伸ばし、手のひらは前方を向けるようにします。 呼吸を変えることなく腹部をできる限り深く引っ込めます。 ここで、ゆっくり緩やかにつま先に向かって手を下げて伸ばします。スティッキングポイントに達成したらフォームローラーやタオルをしっかりと挟みます。 スティッキングポイントに達したら、フォームロールまたはタオルをしっかりと挟むことにより、腹筋群を活性化させ、大腿の外側と背部を弛緩させ、さらにつま先に近づくことができます。 腹部を引っ込めた状態を保つことを忘れないようにしましょう。 つま先に手が届くまで繰り返し行います。 つま先に触れることができない、少しチーティングします。 これでもまだつま先に届かない時、足の位置を変えなくても膝を曲げることによりチーティングします。 息を吐いて、つま先に手を伸ばします。 たとえ膝を軽く曲げてしまうことでチーティングしたとしても、毎回きっちりと成功することが重要です。 「毎回、できる限りチーティングを少なくするようにし、チーティングする必要がなくなるまで改善させていきましょう」とクライアントに伝えます。