マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

仰臥位でのパッシブな股関節屈筋アセスメント
2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGYで開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、仰臥位でのパッシブな股関節屈筋の長さのアセスメントの様子をお届けします。大腿直筋の柔軟性や大腰筋の柔軟性、それぞれに注目したアセスメント方法は、実践的に使えますね。

動作のテストを行うべきでしょうか?
動作をテストする それは私達が思っている事を本当にテストしているのでしょうか? 私はこの20年間で、数えられない程のアスリート達をテストしてきました。それにより私はより賢くなったり、私のアスリート達についてより学んだりしたでしょうか? それははっきりとはわかりません… アスリートの動作能力 アスリートは動くようにデザインされています。彼らにも当然弱点や、可動域の問題、そしてスキル修得に関する問題などがありますが、全般的に我々は動くようにデザインされているのです。この事実を知ったうえで “私は彼らをテストする必要が本当にあるのでしょうか?それとも、ただ彼らがアクティブに競技をしていたり、スポーツに参加している所を見ている方が良いのでしょうか?” 皆さんに問いかけをした理由は、彼らが私の行うテストによって審判を下されるという心配がない中で、最も純粋な動きの形をみられるようにしたいからです。もし私達がテストを行う事が良いことだと信じ、一連のテストを考えつき、6週間後にこれらのテストの結果に進歩が見られたとして、私達は一体本当に何を知っていることになるのでしょうか? スポーツイベント中のアスリート 彼らがスポーツをして動いている姿を観察していると、テストするには難しい動きや、彼らを素晴らしい選手にできるヒントを目撃することができます。例えばアスリートは相手選手を騙す戦術を用いたり、スピードに緩急をつけたり、相手チームの進路を変える為にフェイクを使用したりします。 また、素晴らしいプレーをする為に、対戦相手の前に身体を位置づける術を知っているアスリートも目にします。アスリートのプレーを見ている時、ボール、バット、スティックにおけるスキルレベルや、それがどのように彼らのムーブメントの潜在能力に影響を与えているかを見る事ができます。 テストはこうした全体像を私達に与えてくれるのでしょうか? テストはいったい何を行っているのでしょう? アスリートへのテストを行っている時、彼らの出発点と、どれほどの進歩、または進歩に失敗したかを見ることができます。問うべき事は ”これらのテストが彼らのプレーをいかに助けてくれるのかに関連しているとすれば、テストが本当に私に教えてくれることは何なのか?” ということです。私には、はっきりわかりません。私が見ているアスリートの中には、テストで驚く程進歩が見られたけれども、競技においてより良くプレーする助けとはならなかった者もいます。 これは単に、彼らがコントロールされたテストにおいて良い結果を出せるようになったということが表現されているだけなのです。本当に問うべき質問は “上手にできない動きを見つける為にこの選手達をテストする必要があったのか?” 私の答えはNO!です。これはトレーニングセッションの中で観察できるものです。再び私は問います。“トレーニングセッションで結局目にすることを見る為にテストを行う必要があるのだろうか?” 私の目は、それよりも良い仕事をすることができないだろうか? アスリートの最初のワークアウトセッション、試合や外で遊んでいる最初の数分間みると、彼らをテストするよりも早い段階で、私は彼らの欠点や強みを発見することができます。テストを行う際には様々な状況を作り出すことができますが、彼らが行うスポーツや練習での動きをみることで、非常に特定された動きを見ることができます。数字は、私が個人的に欲している答えを出してはくれない、というのが私のポイントなのです。 テストを行うかどうか? 私は決してテストに反対しているわけではなく、必要な時には行っています。しかし、もしアスリートがラテラルシャッフルや40ヤードダッシュが遅いのであれば、それはトレーニングや、さらにいうと彼らのスポーツをプレーしている時に見られることではないでしょうか? とすれば、テスト自体は本来の目的を果たしているのでしょうか?そうかもしれませんが、私は単に、即座にトレーニングにアプローチをして、現存している問題に働きかけるほうが、アスリートに対してより役立つのではないかと考え始めています。 ストレングスのテストにおいても同様です。ストレングスプログラムを始めるとき、明確にアスリートのストレングスレベルを見ることができませんか?もちろんです!私はその選手に対して即座に最大挙上量からはじめることはありません。ではなぜ、最初の数回のワークアウトでテクニックに働きかけ、どういった方向に進むべきかを見られる時に、最大挙上量でテストをしなければならないのでしょうか? 繰り返しますが、テストに反対しているわけではないのです。私がお伝えしたいのは、テストは必ずしも毎回必要ではない、ということです。私達はテストにおいて判断を下す社会でありがちです。多くの場合において、我々が求めている答えというのは私達の眼前にあるものなのです。

スリングシステムのトレーニングの実践的応用
先日ポストしたジョシュ・ヘンキンの記事”ファンクショナルトレーニングを再考する:身体のスリングシステム”に関連したビデオ記事です。私達の身体が良い機能的に働くためには、様々なシステムが共に働いて、安定させながらダイナミックに動くことが必要になります。記事の内容をより具体的に理解できるビデオをお楽しみ下さいね。
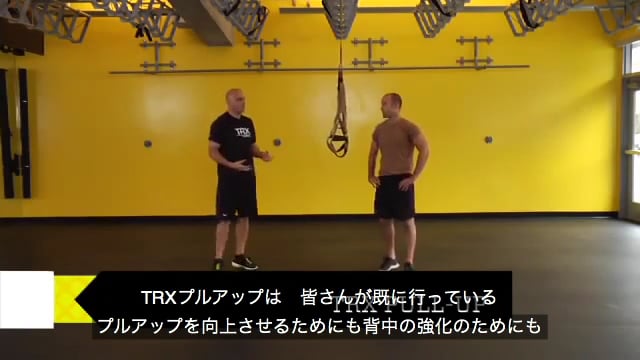
TRXプルアップ プログレッション(ビデオ)
自体重のプルアップがうまくできない人も、プルアップはできるけれど、もっとクオリティーを向上させたい人も、TRXサスペンショントレーナーでのプルアップのプログレッションを、段階的に確実に漸進させていけば、より良いプルアップができるようになります!

肩の外旋バリエーション(ビデオ)
野球場等の屋外の環境で、使える道具もない、パートナーもいない、というような状況でも、ピッチャーが投球を始める前に、あるいは、トレーニング前に、簡単に短時間で行える効果的なローテーターカフのウォームアップをご紹介します。

睡眠の断片化は、24時間の食欲と、それに関連するホルモン濃度にどのような影響を及ぼすのか?
研究論文:健康な男性における、24時間の食欲と、関連するホルモン濃度に対する睡眠断片化の影響、ゴニッセン、ハーセル、リュッタース、マートンズ、ウェスターテラップ・プランテンガ、英国栄養学ジャーナル、2013年 背景 今の時代における最も切迫した医療問題は、おそらく、肥満の急速な増加であろう。多くの研究者たちは、近年変化しているその他のライフスタイルとの関係性を見ることにより、この増加の正確な原因をつきとめようとしてきた。睡眠時間の減少傾向という一要因は、あまり頻繁に研究がなされてはいないが、肥満の増加に伴い、実際に睡眠時間が減少していることは明白である。しかしながら、これらの2つの傾向の間に因果関係があるのかどうかは明確ではない。 研究者たちは何を行ったのか? 研究者たちは、睡眠阻害が睡眠時間の減少を引き起こすのと同じように、食欲制御の低下につながるのかどうかを調査したいと考えた。そのため彼らは、睡眠阻害のあるコンディションと無いコンディションの2つのコンディションにおいて被験者を調査した。睡眠阻害の無いコンディションにおいて、被験者は夜を通して眠ることを許され、阻害のある(断片的な)コンディションでは、被験者は夜間に何度か起こされた。 何が起こったのか? 睡眠時間 研究者たちは、睡眠阻害のあるコンディションと無いコンディションの間で、睡眠時間、もしくは目覚めている時間において著しい違いはなかったと報告している。阻害のある夜において、被験者は平均5回起こされた。研究者たちは、阻害の無い夜に比べ、睡眠阻害のある夜においてはレム睡眠の時間が著しく短かったと報告している。 グルコースとインスリン濃度 研究者たちは、阻害のあるコンディションにおいては、阻害の無いコンディションよりも朝食後のインスリンの上昇が、著しく低かったが、夕食後では阻害のあるコンディションの方が高かった、と報告した。 コルチゾール濃度 研究者たちは、睡眠阻害のあるコンディションでは、阻害の無いコンディションに比べ、夕方のコルチゾール濃度が著しく高かったことを発見した。 実践的意義は何か? 睡眠阻害は、全睡眠時間や目覚めている時間を変化させはしないが、確実にレム睡眠の減少へとつながる。レム睡眠は健康と回復の為に大切だと信じられているため、これは、睡眠阻害が健康の妨げとなり得ることを示唆している。 加えて、睡眠阻害は、グルコースの分泌は変化させないが、一日の食後のインスリン分泌のパターンを変化させる。 睡眠阻害は朝のインスリン分泌を減少させ、午後のインスリン分泌を上昇させる。このことは夜の食料摂取量と間食を増加させることにつながる可能性がある。それゆえこれは、睡眠の質の低下が体脂肪増加を引き起こし得るメカニズムである。
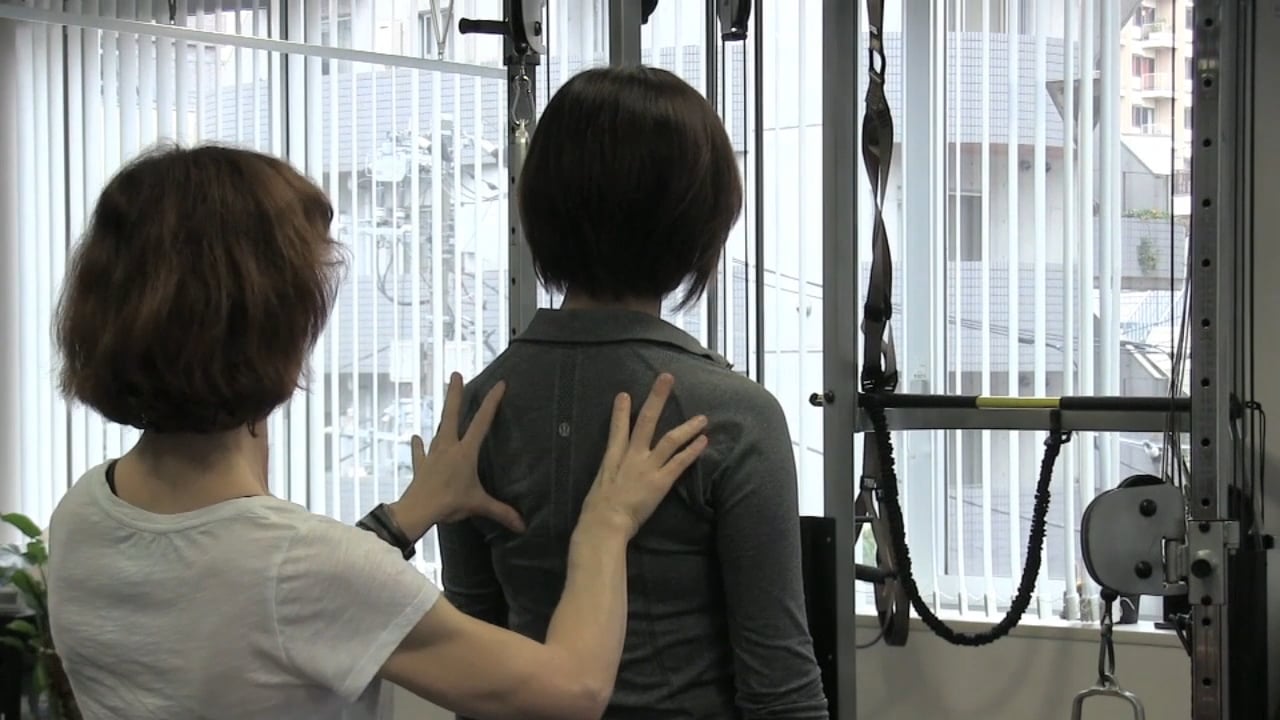
肩屈曲アセスメント パート1/2
2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGYで開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、立位での肩の屈曲のアセスメントの様子を2部に分けてお届けします。肩の脱臼の経験を持つ参加者モデルの方の肩の動きの左右差を、動きを通して観察していきます。

肩屈曲アセスメント パート2/2
2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGYで開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、立位での肩の屈曲のアセスメントのパート2/2 をお届けします。肩の脱臼の経験を持つ参加者モデルの方の肩の動きの左右差を、動きを通して観察しつつ、動きの向上を実現していきます。

筋膜の弾性リコイル
2013年の最後のポストは、今年9月に来日したトーマス・マイヤースのインタビュー。筋膜の持っている弾性リコイルのエネルギーは、加齢と共に失われて行くのをただ受け入れるのみではなく、弾性のエネルギーを蓄えてリリースする、バウンス能力を維持するために、トレーニングをすることも可能である、というアンチエイジングにも直結する、興味深いインタビューを是非御覧ください。

野球のウォームアップ 3つの間違い(ビデオ)
ピッチャー達が野球場で行うウォームアップの動きの中で、彼らの肩の障害を促進してしまうものがあるとすれば?レイバックの繰り返しで、弛緩している肩関節包の前部に対してストレッチをする必要があるのか?メジャーリーグの投手達の救世主として大人気のエリックが、実践的なアイデアの提供をしてくれます。

立位での姿勢のチェックポイント
2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGYで開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、立位での姿勢チェックポイントの確認の様子をお届けします。姿勢の外部指標を使って、側面から身体を観察することは良くありますが、矢状面のみではなく、前額面や横断面もチェックしていきます。
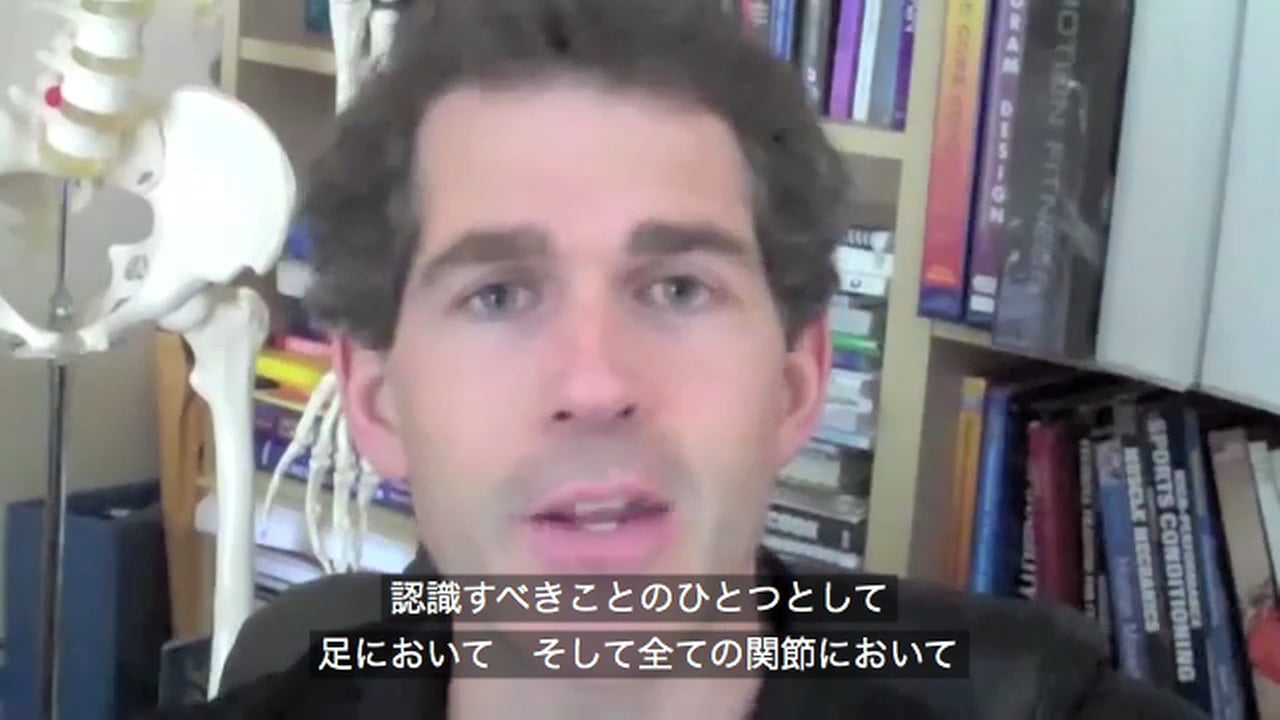
ベアフットランニングに関する推奨
アーチが高過ぎる足や、低過ぎる足にとって、ベアフットランニング、つまり裸足でのランニングや、五本指のミニマリストシューズを履いてのランニングは、どのような影響があるのでしょうか? ViPRの開発者でもあるミショールからのアドバイスです。