マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

なぜ我々は、ある関節角度において、その他の角度より強いのか? パート2/3
局部的筋サイズはいかにθτ影響を及ぼすのか? 幅広く知られてはいないが、筋肉の異なる部位は、筋束長の差違を含む、異なる構造上の特徴を示している(ブレゼビッチおよびその他、2006年)。 そして、もし1つの筋部位が他の部位よりも長い筋束を持っているならば、これはおそらく、この部位は異なる筋長・張力関係を持っているということを意味し、それゆえに、これらは異なる関節角度において最大力を産出する傾向にあるということとなる。 ゆえに局部的筋サイズの差違は、θτに影響を及ぼす。 ポイントの要約:筋肉の異なる部位は、力を生み出す最適な長さに影響を及ぼす、異なる筋繊維長を持ち得る。ゆえに、もしある部位が他の部位よりも大きい場合、それはθτに影響を及ぼすこととなる。 腱剛性はいかにθτに影響を及ぼすのか? 腱剛性は、収縮の際、筋肉がどれほど長さを変化させるかに影響を及ぼす。 腱剛性がより高い場合、それに関わる筋肉は同様の力を産出する収縮の際、より大幅に長さを変化する(カワカミおよびその他、2002年、クボおよびその他、2006年)。 ゆえに腱剛性は、長さ・張力曲線のプラトーに対応する関節角度を変化することによりθτ に影響を及ぼす。 実際に、クボおよびその他(2006年)は、40-110度の間の等尺性膝関節伸展収縮の際、関節トルク・角度カーブにおける個人間のばらつきは、主動筋もしくは拮抗筋活性化における差違、あるいはモーメントアームの長さのどちらによっても説明できないということを示している。しかしながら、一部、腱の歪み量による説明が可能である(R² = 18 – 23%)。 ポイントの要約:腱剛性は長さ・張力曲線のプラトーに対応する関節角度を変化することにより、θτへ影響を及ぼす。より剛性の高い腱は、剛性のより低い腱と比較し、適用された同等の筋力に対する伸張が少ない。 筋剛性はいかにθτに影響を及ぼすのか? 腱剛性のように、筋剛性は関節トルク・角度関係に影響を及ぼすが、作用は逆である。高い腱剛性はθτをより短い筋長へと移動させるが、高い筋剛性はそれをより長い筋長へと移動させる(ブルゲーリ&クローニン、2007年)。 高いレベルの筋剛性はほとんどの場合、筋肉に含まれる受動的要因の増加を反映しており、これは必然的に、より長い筋長において筋肉から生み出される力の量を増加する。 しかし、真に受動的なのは一部の受動的要因のみであり(細胞外基質および細胞骨格)、チチンは能動的収縮においてのみ力を産出するため、受動的要因剛性を測定することは、想像以上に複雑である。これは、受動的筋剛性の測定は、受動的要因剛性のθτへの影響を評価するために、実際は適切ではないかもしれないということを意味している。 実際、一部の研究は、筋剛性は(能動的収縮の際ではなく、受動的抵抗トルクにより測定された際)エキセントリックトレーニング後減少したと報告しており(マヒューおよびその他、2008年、ケイおよびその他、2016年)、これは、チチンが他の受動的要因よりもより重要であるかもしれないと示唆している。 ポイントの要約:筋剛性は、長さ・張力曲線のプラトーに対応する関節角度を変化することによりθτに影響を及ぼす。より剛性の高い筋肉は、より低い剛性の筋肉と比較し、より長い筋長においてより多くの力を産出し、腱をより伸張させる。 ニューラルドライブはいかにθτに影響を及ぼすのか? ニューラルドライブは自発的活性化(自発的および不随意トルクの間の差違)もしくは筋電図振幅により測定することが可能である。 主に我々は、主動筋活性化に興味を持っている(拮抗筋共収縮は、関節により異なるかもしれないが、それらは小さく、またトレーニングに伴う拮抗筋共収縮における変化は、わずかであるか、もしくは相反しているかのどちらかであり、ゆえに字数制限に適応させるため、今回はこれを除外する)。 ある研究は、自発的活性化もしくは筋電図振幅は、異なる関節角度においてあまり異ならないということを発見している(例:ガンデヴィア&マッケンジー、1998年、ビックランド・リッチおよびその他、1992年、リーダム&ダウリング、1995年、コウ&ヘルツォグ、1995年、プロドーエルおよびその他、2003年、バボートおよびその他、2003年、ニューマンおよびその他、2003年、リナモおよびその他、2006年、シモーノおよびその他、2007年、オブライエンおよびその他、2009年)。 その他多くの研究は、相違点を報告している。 重要なことに、これらの研究の一部は、その影響は筋長の長さに大きく起因するということを示している。彼らはこれを、2関節筋をテストすること、およびテストを行う関節を固定し、隣接している関節を動かすことにより筋長を変化させることで行った(ルネンおよびその他、1981年、ハスラーおよびその他、1994年、クレスウェルおよびその他、1995年、ミアキおよびその他、1999年、ケネディ&クレスウェル、2001年、マフューレッティ&レパーズ、2003年、ヌーバコッシュ&ククルカ、2004年、アラムパティスおよびその他、2006年、コング&バンハセレーン、2010年)。 どちらにせよ、研究者たちは差違を報告しており、それは、より短い筋長においてより大きなニューラルドライブを報告した研究、およびより長い筋長においてより大きなニューラルドライブを発見した研究におおまかに分類されている。実際には、両端および最適な長さのどちらかにおける最大値に伴い、これら両方が起こり得る(アルテンブルクおよびその他、2009年)。 短筋長におけるより大きなニューラルドライブ 多くの研究者は、自発的活性化(マーシュおよびその他、1081年、ズーター&ヘルゾーグ、1997年、ヒューバーおよびその他、1998年、カスプリシン&グラビナー、2000年)、もしくは筋電図の振幅(ヘッカスロン&チャイルドレス、1981年、バンダー・リンデンおよびその他、1991年、ガーランドおよびその他、1994年、ハスラーおよびその他、1994年、コミおよびその他、2000年、ベッカー&アウズース、2001年、ウォーレルおよびその他、2001年、オニシおよびその他、2002年、バボートおよびその他、2003年、クボおよびその他、2004年、デルバイエ&トーマス、2004年、パスケーおよびその他、2005年、ドヒニーおよびその他、2008年、アルテンブルクおよびその他、2009年)のどちらかは、より短い筋長においてより大きいと報告している。 より多くのニューラルドライブは、減少された力産出を補うため、短筋長において起こるのかもしれないと示唆されている。 この短筋長における力産出の減少は、一部には、収縮および弛緩時間の減少を含む、筋肉の機械的特性の変化により引き起こされている可能性がある(ガンデヴィア&マッケンジー、1998年、ハスラーおよびその他、1994年、バボートおよびその他、2003年)。運動単位の発火頻度はしばしば短筋長において増加するため(バンダー・リンデンおよびその他、1991年, クリストファおよびその他、1998年)、より早い発火率がより短い収縮および弛緩時間に伴うより頻繁なシグナルと適合する場合、これは理にかなっているであろう。 そうであっても、これは必ずしも、運動単位動員および発火頻度の間の関係が大幅に変化するということを意味しているわけではない。全ての研究がこの結果を支持してはいないが(アルデンブルグおよびその他、2009年)、運動単位動員の閾値もまた、短筋長において減少しており(パスケーおよびその他、2005年)、これは同様の最大トルクの比率に対し、短筋長における全体的により大きな筋活性化の存在の可能性を示唆している。 長筋長におけるより大きなニューラルドライブ 他の多くの研究者たちは、自発的活性化(ベッカー&アウィーズス、2001年、バンボーラスおよびその他、2006年、クルーカおよびそのた、2015年)もしくは筋電図振幅(ベッカー&アウィーズス、2001年、オニシおよびその他、2002年、クボおよびその他、2004年、アラムパティスおよびその他、2006年、シモーノおよびその他、2007年、アルテンブルクおよびその他、2009年、コング&バンハセレーン、2010年)は、長筋長においてより大きいということを報告している。 これは、ニューラルドライブは、アルファ運動ニューロンプールへの関節内における興奮性入力を引き起こす伸縮の際の筋紡錘反応のため、実際には長筋長においてより大きいかもしれないと示唆している(クルーカおよびその他、2015年)。 これは本質的には、伸張された筋肉に対する脊髄反射反応である。 ゆえに、最大Mウェーブ(筋肉の最大活性化能力の測定値)もまた、時折筋長の伸張と共に増加するということは偶然ではないのかもしれない(マフューレッティ&レパーズ、2003年)。これは、Mウェーブは、H反射および伸張反射同様、筋肉および脊髄のみに関わるため(ゼア、2002年)、筋長の変化に反応し、末梢要因は筋肉の最大活性化能力に対し影響を及ぼすべきであるということを我々に伝えてくれている。 ポイントの要約:ニューラルドライブは、筋長の変化に反応するため、関節角度に伴い変化する。異なる理由から、その増加は短筋長もしくは長筋長どちらにおいても起こる可能性がある。 参照文献 Alegre, L. M., Ferri-Morales, A., Rodriguez-Casares, R., & Aguado, X. (2014). Effects of isometric training on the knee extensor moment–angle relationship and vastus lateralis muscle architecture. European Journal of Applied Physiology, 114(11), 2437-2446. Altenburg, T. M., de Haan, A., Verdijk, P. W., van Mechelen, W., & de Ruiter, C. J. (2009). Vastus lateralis single motor unit EMG at the same absolute torque production at different knee angles. Journal of Applied Physiology, 107(1), 80-89. Amarantini, D., & Bru, B. (2015). Training-related changes in the EMG–moment relationship during isometric contractions: Further evidence of improved control of muscle activation in strength-trained men? Journal of Electromyography and Kinesiology, 25(4), 697-702. Arampatzis, A., Karamanidis, K., Stafilidis, S., Morey-Klapsing, G., DeMonte, G., & Brüggemann, G. P. (2006). Effect of different ankle-and knee-joint positions on gastrocnemius medialis fascicle length and EMG activity during isometric plantar flexion. Journal of Biomechanics, 39(10), 1891. Babault, N., Pousson, M., Michaut, A., & Van Hoecke, J. (2003). Effect of quadriceps femoris muscle length on neural activation during isometric and concentric contractions. Journal of Applied Physiology, 94(3), 983-990. Bampouras, T. M., Reeves, N. D., Baltzopoulos, V., & Maganaris, C. N. (2006). Muscle activation assessment: effects of method, stimulus number, and joint angle. Muscle & Nerve, 34(6), 740. Becker, R., & Awiszus, F. (2001). Physiological alterations of maximal voluntary quadriceps activation by changes of knee joint angle. Muscle & Nerve, 24(5), 667. Bigland‐Ritchie, B. R., Furbush, F. H., Gandevia, S. C., & Thomas, C. K. (1992). Voluntary discharge frequencies of human motoneurons at different muscle lengths. Muscle & Nerve, 15(2), 130-137. Blazevich, A. J., Gill, N. D., & Zhou, S. (2006). Intra‐and intermuscular variation in human quadriceps femoris architecture assessed in vivo. Journal of Anatomy, 209(3), 289-310. Blazevich, A. J., Cannavan, D., Coleman, D. R., & Horne, S. (2007). Influence of concentric and eccentric resistance training on architectural adaptation in human quadriceps muscles. Journal of Applied Physiology, 103(5), 1565-1575. Bohm, S., Mersmann, F., & Arampatzis, A. (2015). Human tendon adaptation in response to mechanical loading: a systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. Sports Med Open, 1(1), 7. Brughelli, M., & Cronin, J. (2007). Altering the length-tension relationship with eccentric exercise. Sports Medicine, 37(9), 807-826. Brughelli, M., Mendiguchia, J., Nosaka, K., Idoate, F., Los Arcos, A., & Cronin, J. (2010). Effects of eccentric exercise on optimum length of the knee flexors and extensors during the preseason in professional soccer players. Physical Therapy in Sport, 11(2), 50-55. Carolan, B., & Cafarelli, E. (1992). Adaptations in coactivation after isometric resistance training. Journal of Applied Physiology, 73(3), 911-917. Clark, R., Bryanta, A., Culgan, J. P., & Hartley, B. (2005). The effects of eccentric hamstring strength training on dynamic jumping performance and isokinetic strength parameters: a pilot study on the implications for the prevention of hamstring injuries. Physical Therapy in Sport, 6, 67-73. Christova, P., Kossev, A., & Radicheva, N. (1998). Discharge rate of selected motor units in human biceps brachii at different muscle lengths. Journal of Electromyography and Kinesiology, 8(5), 287-294. Cresswell, A. G., Löscher, W. N., & Thorstensson, A. (1995). Influence of gastrocnemius muscle length on triceps surae torque development and electromyographic activity in man. Experimental Brain Research, 105(2), 283-290. Del Valle, A., & Thomas, C. K. (2004). Motor unit firing rates during isometric voluntary contractions performed at different muscle lengths. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 82(8-9), 769-776. Doheny, E. P., Lowery, M. M., FitzPatrick, D. P., & O’Malley, M. J. (2008). Effect of elbow joint angle on force–EMG relationships in human elbow flexor and extensor muscles. Journal of Electromyography and Kinesiology, 18(5), 760-770. Franchi, M. V., Atherton, P. J., Maganaris, C. N., & Narici, M. V. (2016). Fascicle length does increase in response to longitudinal resistance training and in a contraction-mode specific manner. SpringerPlus, 5(1), 1. Frey-Law, L. A., Laake, A., Avin, K. G., Heitsman, J., Marler, T., & Abdel-Malek, K. (2012). Knee and elbow 3d strength surfaces: peak torque-angle-velocity relationships. Journal of Applied Biomechanics, 28(6), 726-737. Frigon, A., Thompson, C. K., Johnson, M. D., Manuel, M., Hornby, T. G., & Heckman, C. J. (2011). Extra forces evoked during electrical stimulation of the muscle or its nerve are generated and modulated by a length-dependent intrinsic property of muscle in humans and cats. The Journal of Neuroscience, 31(15), 5579-5588. Gandevia, S. C., & McKenzie, D. K. (1988). Activation of human muscles at short muscle lengths during maximal static efforts. The Journal of Physiology, 407, 599. Garland, S. J., Gerilovsky, L., & Enoka, R. M. (1994). Association between muscle architecture and quadriceps femoris H‐reflex. Muscle & Nerve, 17(6), 581-592. Hasler, E. M., Denoth, J., Stacoff, A., & Herzog, W. (1994). Influence of hip and knee joint angles on excitation of knee extensor muscles. Electromyography and Clinical Neurophysiology, 34(6), 355. Heckathorne, C. W., & Childress, D. S. (1981). Relationships of the surface electromyogram to the force, length, velocity, and contraction rate of the cineplastic human biceps. American Journal of Physical Medicine, 60(1), 1. Huber, A., Suter, E., & Werzog, W. (1998). Inhibition of the quadriceps muscles in elite male volleyball players. Journal of Sports Sciences, 16(3), 281-289. Kasprisin, J. E., & Grabiner, M. D. (2000). Joint angle-dependence of elbow flexor activation levels during isometric and isokinetic maximum voluntary contractions. Clinical Biomechanics, 15(10), 743. Kawakami, Y., & Lieber, R. L. (2000). Interaction between series compliance and sarcomere kinetics determines internal sarcomere shortening during fixed-end contraction. Journal of Biomechanics, 33(10), 1249-1255. Kawakami, Y., Kubo, K., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2002). Effect of series elasticity on isokinetic torque-angle relationship in humans. European Journal of Applied Physiology, 87(4-5), 381. Kay, A. D., Richmond, D., Talbot, C., Mina, M., Baross, A. W., & Blazevich, A. J. (2016). Stretching of Active Muscle Elicits Chronic Changes in Multiple Strain Risk Factors. Medicine & Science in Sports & Exercise. Kennedy, P. M., & Cresswell, A. G. (2001). The effect of muscle length on motor-unit recruitment during isometric plantar flexion in humans. Experimental Brain Research, 137(1), 58-64. Kilgallon, M., Donnelly, A. E., & Shafat, A. (2007). Progressive resistance training temporarily alters hamstring torque-angle relationship. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 17(1), 18. Kluka, V., Martin, V., Vicencio, S. G., Jegu, A. G., Cardenoux, C., Morio, C., & Ratel, S. (2015). Effect of muscle length on voluntary activation level in children and adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 47(4), 718. Kluka, V., Martin, V., Vicencio, S. G., Giustiniani, M., Morel, C., Morio, C., & Ratel, S. (2016). Effect of muscle length on voluntary activation of the plantar flexors in boys and men. European Journal of Applied Physiology, 116(5), 1043-1051. Koh, T. J., & Herzog, W. (1995). Evaluation of voluntary and elicited dorsiflexor torque-angle relationships. Journal of Applied Physiology, 79(6), 2007. Komi, P. V., Linnamo, V., Silventoinen, P., & Sillanpää, M. (2000). Force and EMG power spectrum during eccentric and concentric actions. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(10), 1757. Kong, P. W., & Van Haselern, J. (2010). Revisiting the influence of hip and knee angles on quadriceps excitation measured by surface electromyography. International SportMed Journal, 11(2). Kubo, K., Tsunoda, N., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2004). Activation of agonist and antagonist muscles at different joint angles during maximal isometric efforts. European Journal of Applied Physiology, 91(2-3), 349-352. Kubo, K., Ohgo, K., Takeishi, R., Yoshinaga, K., Tsunoda, N., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2006). Effects of series elasticity on the human knee extension torque-angle relationship in vivo. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(4), 408-416. Leedham, J. S., & Dowling, J. J. (1995). Force-length, torque-angle and EMG-joint angle relationships of the human in vivo biceps brachii. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 70(5), 421-426. Linnamo, V., Strojnik, V., & Komi, P. V. (2006). Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles. European Journal of Applied Physiology, 96(6), 672-678. Lunnen, J. D., Yack, J., & LeVeau, B. F. (1981). Relationship between muscle length, muscle activity, and torque of the hamstring muscles. Physical Therapy, 61(2), 190-195. Maffiuletti, N. A., & Lepers, R. (2003). Quadriceps femoris torque and EMG activity in seated versus supine position. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(9), 1511. Mahieu, N. N., Mcnair, P., Cools, A. N. N., D’Haen, C., Vandermeulen, K., & Witvrouw, E. (2008). Effect of eccentric training on the plantar flexor muscle-tendon tissue properties. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40(1), 117-123. Marsh, E., Sale, D., McComas, A. J., & Quinlan, J. (1981). Influence of joint position on ankle dorsiflexion in humans. Journal of Applied Physiology, 51(1), 160-167. Miaki, H., Someya, F., & Tachino, K. (1999). A comparison of electrical activity in the triceps surae at maximum isometric contraction with the knee and ankle at various angles. European Journal of Applied physiology and Occupational Physiology, 80(3), 185-191. Newman, S. A., Jones, G., & Newham, D. J. (2003). Quadriceps voluntary activation at different joint angles measured by two stimulation techniques. European Journal of Applied Physiology, 89(5), 496. Noorkõiv, M., Nosaka, K., & Blazevich, A. J. (2014). Neuromuscular adaptations associated with knee joint angle-specific force change. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(8), 1525-1537. Noorkõiv, M., Nosaka, K., & Blazevich, A. J. (2015). Effects of isometric quadriceps strength training at different muscle lengths on dynamic torque production. Journal of Sports Sciences, 33(18), 1952-1961. Nourbakhsh, M. R., & Kukulka, C. G. (2004). Relationship between muscle length and moment arm on EMG activity of human triceps surae muscle. Journal of Electromyography and Kinesiology, 14(2), 263-273. O’Brien, T. D., Reeves, N. D., Baltzopoulos, V., Jones, D. A., & Maganaris, C. N. (2009). The effects of agonist and antagonist muscle activation on the knee extension moment-angle relationship in adults and children. European Journal of Applied Physiology, 106(6), 849. Onishi, H., Yagi, R., Oyama, M., Akasaka, K., Ihashi, K., & Handa, Y. (2002). EMG-angle relationship of the hamstring muscles during maximum knee flexion. Journal of Electromyography and Kinesiology, 12(5), 399-406. Pasquet, B., Carpentier, A., & Duchateau, J. (2005). Change in muscle fascicle length influences the recruitment and discharge rate of motor units during isometric contractions. Journal of Neurophysiology, 94(5), 3126-3133. Prodoehl, J., Gottlieb, G. L., & Corcos, D. M. (2003). The neural control of single degree-of-freedom elbow movements. Experimental Brain Research, 153(1), 7-15. Rabita, G., Pérot, C., & Lensel-Corbeil, G. (2000). Differential effect of knee extension isometric training on the different muscles of the quadriceps femoris in humans. European Journal of Applied Physiology, 83(6), 531-538. Reeves, N. D., Narici, M. V., & Maganaris, C. N. (2004). In vivo human muscle structure and function: adaptations to resistance training in old age. Experimental Physiology, 89(6), 675. Roman, W. J., Fleckenstein, J., Stray-Gundersen, J., Alway, S. E., Peshock, R., & Gonyea, W. J. (1993). Adaptations in the elbow flexors of elderly males after heavy-resistance training. Journal of Applied Physiology, 74(2), 750-754. Simoneau, E., Martin, A., & Van Hoecke, J. (2007). Effects of joint angle and age on ankle dorsi-and plantar-flexor strength. Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(3), 307. Smith, C., & Rutherford, O. M. (1995). The role of metabolites in strength training. I. A comparison of eccentric and concentric training. European Journal of Applied physiology and Occupational Physiology, 71(4), 337-341. Suter, E., & Herzog, W. (1997). Extent of muscle inhibition as a function of knee angle. Journal of Electromyography and Kinesiology, 7(2), 123. Timmins, R. G., Shield, A. J., Williams, M. D., & Opar, D. A. (2016). Is There Evidence to Support the Use of the Angle of Peak Torque as a Marker of Hamstring Injury and Re-Injury Risk?. Sports Medicine, 46(1), 7-13. Ullrich, H. Kleinöder, G. P. Brüggemann (2009). Moment-angle Relations after Specific Exercise International Journal of Sports Medicine, 30: 293–301. Vander Linden, D. W., Kukulka, C. G., & Soderberg, G. L. (1991). The effect of muscle length on motor unit discharge characteristics in human tibialis anterior muscle. Experimental Brain Research, 84(1), 210-218. Vigotsky, A. D., Contreras, B., & Beardsley, C. (2015). Biomechanical implications of skeletal muscle hypertrophy and atrophy: a musculoskeletal model. PeerJ, 3, e1462. Wakahara, T., Miyamoto, N., Sugisaki, N., Murata, K., Kanehisa, H., Kawakami, Y., & Yanai, T. (2012). Association between regional differences in muscle activation in one session of resistance exercise and in muscle hypertrophy after resistance training. European Journal of Applied Physiology, 112(4), 1569-1576. Worrell, T. W., Karst, G., Adamczyk, D., Moore, R., Stanley, C., Steimel, B., & Steimel, S. (2001). Influence of joint position on electromyographic and torque generation during maximal voluntary isometric contractions of the hamstrings and gluteus maximus muscles. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 31(12), 730-740. Zehr, P. E. (2002). Considerations for use of the Hoffmann reflex in exercise studies. European Journal of Applied Physiology, 86(6), 455-468.

なぜ我々は、ある関節角度において、その他の角度より強いのか? パート1/3
いかなる関節においても、我々はある関節角度において、その他の関節角度よりも強い。実際に、可動内全域において、他の関節角度よりも強い1つの関節角度が通常存在する。 更に興味深いことに、この最も強い関節角度は、ストレングストレーニング後に変化し得る。それは、頻繁に筋腱単位がより長いところへと移動するが、まれに筋腱単位がより短いところへと変化することがある。 なぜそれが起こるのだろうか? この記事では、これら両方の疑問に対するよくあげられる要因に取り組み、また、いくつかのそれほどありきたりではないものへも言及してゆく。 我々が最も強い関節角度とは何か? 我々が最も強い関節角度は、瞬時最大トルク角度と呼ばれる。繰り返し書くことを避けるため、これをθτと呼ぶことにしよう。θτを発見するために、下のような関節角度に対するトルクのグラフを描くことができる。 瞬時最大トルク角度 この曲線は「関節トルク・角度」の関係である。このような曲線を生み出すために研究者たちは通常、動力計において異なる関節角度の等尺性関節トルクを測定しており、異なる関節は異なる曲線を表示している。 全体の関節角度可動域における最初、もしくは最終域において最大となるものもあり、中域において最大となるものもある。 これらがその例である: 膝関節屈筋群(ハムストリングス)のθτは、(股関節が中立位にある際)膝が長筋長において完全に伸展したところである(ウォーレルおよびその他、2001年)。 股関節伸筋群(大臀筋)のθτ は、股関節が屈曲しているところ(膝関節が屈曲している際)である(ウォーレルおよびその他、2001年)。 膝関節伸展群(大腿四頭筋)のθτ は、どちらの最終関節可動域でもないが、完全伸展よりは完全屈曲により近い(フライ・ローおよびその他、2012年)。 肘関節の屈筋群(上腕二頭筋)および、伸筋群(上腕三頭筋)のθτ は、全体の肘関節可動域のおよそ中程である(フライ・ローおよびその他、2012年)。 何がθτを決定するのか? ここまででθτが何を意味するかは分かったと思うが、なぜ我々は、他の関節角度と比較し、1つの関節角度においてより強いのだろうか?末梢および中枢において、それに貢献している要因は数多く存在し、下記のものを含むが、これらに限定されているわけではない。 筋肉のモーメントアームの長さ 正規化された繊維長 局部的筋サイズ 腱剛性 筋剛性 神経伝達 もちろん、ある要因がθτに影響を及ぼし得るからといって、それがストレングストレーニング後におけるθτの変化の原因であるという意味ではない。実際にこれから見てゆくように、他の要因は大きく変化するが、θτを制限するのに非常に重要ないくつかの要因は、ストレングストレーニングの結果として変化する傾向にはない(ブルゲーリ&クローニン、2007年)。 もしこれから述べてゆくよりも早くに要因についての結論を知りたい場合は、各章の終わりに要約をしてある「ポイントの要約」まで飛ばすとよい。 モーメントアームの長さはどのようにθτへ影響を及ぼすのか? 関節は角運動に関わり、軸を中心に回旋する2つの骨を含むため、力ではなくトルクを産出する。ゆえに関節トルクの大きさは、筋肉により生み出される収縮力だけではなく、旋回軸からの垂直距離にも依存している。 この距離は、モーメントアームと呼ばれている。 モーメントアームの長さが関節角度により異なる理由の1つは、生体構造のためであるが、それらは筋肉のサイズにも依存している。より大きな筋肉はより長いモーメントアームを持つ(ヴィゴスキーおよびその他、2015年)。 モーメントアームは、より大きな筋肉においてより長い((ヴィゴスキーおよびその他、2015年)。 モーメントアームの長さは、関節トルクを決定するために、筋力そのものと同様に重要である。これは関節トルクが、力とモーメントアームの長さを掛け合わせたものであるためである。 ゆえに、モーメントアームの長さは関節角度により大幅に変化し得るため、θτに非常に大きな影響を及ぼす。 例えば、我々は大臀筋のモーメントアームの長さが、股関節角度と共にどのように変化するのかをグラフにすることができる。我々はグラフから、大臀筋は股関節屈曲(90度の股関節角度)において最も短いモーメントアームを持ち、股関節伸展(0度の股関節角度)において最も長いモーメントアームを持つということがわかる。 大臀筋は、直立時に長いモーメントアームを持つ。 ちなみに、モーメントアームが股関節角度と共に変化するということは、直立している際、もしくは走行周期の立脚相において、大臀筋を非常に優れた股関節伸筋にし、また、スクワットの下部においては、股関節伸筋としてそれほど効果的ではないものにしている。 モーメントアームの長さは重要ではあるが、θτ.の唯一の決定要因ではない。我々は、2関節筋群が、同様の関節角度ではあるが異なる筋長において(筋長は隣接する関節角度を変化させることにより変わる)テストされた際、関節トルクが異なることから、このことをわかっている。 例として、研究者たちは、異なる座位における膝関節屈曲トルクを比較している。彼らは、膝関節角度を固定し、体幹を前屈位、直立位、もしくは後屈位へと動かすことにより股関節角度を変化させた(ラネンおよびその他、1981年)。膝関節角度は異なる体位の間で変化しないため、モーメントアームの長さが膝関節屈曲トルクにおける差違を生み出すことは不可能であった。しかしながら、それは2関節筋のハムストリングスの長さを変化させ、それらが産出できる力の量を変化させたのである。 同様に研究者たちは、異なる座位における膝関節伸展トルクを比較した。膝関節角度は固定し、彼らは仰臥位(仰向け)もしくは直立座位どちらかの間で体幹を変化させることにより、股関節角度を変化させた(ハスラーおよびその他、1994年、マフィルッティ&レパーズ、2003年)。膝関節角度は異なる体位の間で変化しないため、モーメントアームの長さが膝関節伸展トルクにおける差違を引き起こすことは不可能であった。しかしそれは2関節筋の大腿四頭筋(大腿直筋)の長さを変化させ、生み出し得る力の量を変化させた。 そしてもちろん同様に、足関節は同位置であるが、腓腹筋の長さを変化させるために異なる膝関節位をとり、ふくらはぎの筋肉の力生成を比較することは可能である(クレスウェルおよびその他、1995年、ミアキおよびその他、1999年、ケネディ&クレスウェル、2001年、ヌーバクッシュ&ククルカ、2004年、アラムパティスおよびその他、2006年、コング&バンハセレーン、2010年)。 つまり、モーメントアームの長さと同様に、筋長は重要なのである。 ポイントの要約:モーメントアームの長さは、関節トルクの鍵となる決定要因であり、関節角度により異なる。しかし、隣接している関節角度が変化した場合、2関節筋における関節トルクは異なるため、このことは、モーメントアームの長さと同様に筋長は独立した要因であるということを示している。 正規化された繊維長はどのようにθτに影響を及ぼすのか? 筋繊維は、末端と末端を結合した各筋節の連鎖により構成されている。正規化された筋繊維長とは、その連鎖において結合している単一筋繊維に対する筋節の数である。 アクチンおよびミオシン繊維が互いに滑り合う際、連鎖における各筋節は短縮し、能動的に張力を生み出す。 各筋節が能動的に産出する張力の量は、アクチンおよびミオシン繊維間の重なりの量に依存する。 我々はこれを、能動的筋長・張力関係と呼ぶ。 筋節が短すぎる場合、重なりは理想的ではなくなり、より小さい力しか産出せず、筋節が長すぎると、重なりはまた理想的ではなくなり、より小さい力しか産出しない。しかし、筋節の長さが適切である場合、重なりは最適となり、これが、筋節が最大の力を産出できる長さとなる。この最適な筋長には幅があり、プラトーと呼ばれている。 これらの3つの段階は下のグラフにおいて見ることができる。 筋繊維は、その長さが「ちょうど良い」時に最大の力を生み出す! 能動的な力産出に加え、筋繊維における筋フィラメントもまた、伸張することに対抗するため受動的に力を産出する。この力は、筋節がその最適な長さを超えて伸張されると、非常に素早く増加する。 我々はこれを、受動的筋長・張力関係と呼んでいる。 我々は、実際にどのように筋繊維が実生活における筋長の変化に反応するかを示すため、能動的および受動的関係を組み合わせることができる。 このグラフでは複合の関係を見ることができる。 筋繊維は伸張されることに抵抗し、同時に能動的に力を生み出す。 連鎖における全ての筋節はこのような反応を示すため、筋繊維は全体的に多かれ少なかれ同様の反応を示す(後に筋節の不均一性について書く時間を作ろうと思う)。 筋繊維が比較的長い正規化された繊維長を持つ場合、その筋繊維はその筋繊維長に対し、連鎖においてより多くの筋節を持つ。そのため、それが収縮し始めると、たるみからスタートする(その最初の長さは上行脚のかなり下となるだろう)。ゆえにそれはθτに達する前に、より長い間短縮することとなる。 対照的に、筋繊維が比較的短い正規化された繊維長を持つ場合、それはその筋繊維長に対し、より少ない筋節を持つ。そのため、それが収縮を始める際、張りからスタートする(その最小の長さは、上行脚のかなり上となるだろう)。ゆえにそれは θτ.に達する前には、非常にわずかにしか短縮しない。 ポイントの要約: 正規化された筋繊維長は、筋繊維における連鎖内の筋節の数を反映するため、θτ 関節の決定要因である。連鎖におけるより多くの筋節は、力生成に対する最適な長さは関節可動域における後半におこり、また逆も同様であるということを意味している。 参照文献 Alegre, L. M., Ferri-Morales, A., Rodriguez-Casares, R., & Aguado, X. (2014). Effects of isometric training on the knee extensor moment–angle relationship and vastus lateralis muscle architecture. European Journal of Applied Physiology, 114(11), 2437-2446. Altenburg, T. M., de Haan, A., Verdijk, P. W., van Mechelen, W., & de Ruiter, C. J. (2009). Vastus lateralis single motor unit EMG at the same absolute torque production at different knee angles. Journal of Applied Physiology, 107(1), 80-89. Amarantini, D., & Bru, B. (2015). Training-related changes in the EMG–moment relationship during isometric contractions: Further evidence of improved control of muscle activation in strength-trained men? Journal of Electromyography and Kinesiology, 25(4), 697-702. Arampatzis, A., Karamanidis, K., Stafilidis, S., Morey-Klapsing, G., DeMonte, G., & Brüggemann, G. P. (2006). Effect of different ankle-and knee-joint positions on gastrocnemius medialis fascicle length and EMG activity during isometric plantar flexion. Journal of Biomechanics, 39(10), 1891. Babault, N., Pousson, M., Michaut, A., & Van Hoecke, J. (2003). Effect of quadriceps femoris muscle length on neural activation during isometric and concentric contractions. Journal of Applied Physiology, 94(3), 983-990. Bampouras, T. M., Reeves, N. D., Baltzopoulos, V., & Maganaris, C. N. (2006). Muscle activation assessment: effects of method, stimulus number, and joint angle. Muscle & Nerve, 34(6), 740. Becker, R., & Awiszus, F. (2001). Physiological alterations of maximal voluntary quadriceps activation by changes of knee joint angle. Muscle & Nerve, 24(5), 667. Bigland‐Ritchie, B. R., Furbush, F. H., Gandevia, S. C., & Thomas, C. K. (1992). Voluntary discharge frequencies of human motoneurons at different muscle lengths. Muscle & Nerve, 15(2), 130-137. Blazevich, A. J., Gill, N. D., & Zhou, S. (2006). Intra‐and intermuscular variation in human quadriceps femoris architecture assessed in vivo. Journal of Anatomy, 209(3), 289-310. Blazevich, A. J., Cannavan, D., Coleman, D. R., & Horne, S. (2007). Influence of concentric and eccentric resistance training on architectural adaptation in human quadriceps muscles. Journal of Applied Physiology, 103(5), 1565-1575. Bohm, S., Mersmann, F., & Arampatzis, A. (2015). Human tendon adaptation in response to mechanical loading: a systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. Sports Med Open, 1(1), 7. Brughelli, M., & Cronin, J. (2007). Altering the length-tension relationship with eccentric exercise. Sports Medicine, 37(9), 807-826. Brughelli, M., Mendiguchia, J., Nosaka, K., Idoate, F., Los Arcos, A., & Cronin, J. (2010). Effects of eccentric exercise on optimum length of the knee flexors and extensors during the preseason in professional soccer players. Physical Therapy in Sport, 11(2), 50-55. Carolan, B., & Cafarelli, E. (1992). Adaptations in coactivation after isometric resistance training. Journal of Applied Physiology, 73(3), 911-917. Clark, R., Bryanta, A., Culgan, J. P., & Hartley, B. (2005). The effects of eccentric hamstring strength training on dynamic jumping performance and isokinetic strength parameters: a pilot study on the implications for the prevention of hamstring injuries. Physical Therapy in Sport, 6, 67-73. Christova, P., Kossev, A., & Radicheva, N. (1998). Discharge rate of selected motor units in human biceps brachii at different muscle lengths. Journal of Electromyography and Kinesiology, 8(5), 287-294. Cresswell, A. G., Löscher, W. N., & Thorstensson, A. (1995). Influence of gastrocnemius muscle length on triceps surae torque development and electromyographic activity in man. Experimental Brain Research, 105(2), 283-290. Del Valle, A., & Thomas, C. K. (2004). Motor unit firing rates during isometric voluntary contractions performed at different muscle lengths. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 82(8-9), 769-776. Doheny, E. P., Lowery, M. M., FitzPatrick, D. P., & O’Malley, M. J. (2008). Effect of elbow joint angle on force–EMG relationships in human elbow flexor and extensor muscles. Journal of Electromyography and Kinesiology, 18(5), 760-770. Franchi, M. V., Atherton, P. J., Maganaris, C. N., & Narici, M. V. (2016). Fascicle length does increase in response to longitudinal resistance training and in a contraction-mode specific manner. SpringerPlus, 5(1), 1. Frey-Law, L. A., Laake, A., Avin, K. G., Heitsman, J., Marler, T., & Abdel-Malek, K. (2012). Knee and elbow 3d strength surfaces: peak torque-angle-velocity relationships. Journal of Applied Biomechanics, 28(6), 726-737. Frigon, A., Thompson, C. K., Johnson, M. D., Manuel, M., Hornby, T. G., & Heckman, C. J. (2011). Extra forces evoked during electrical stimulation of the muscle or its nerve are generated and modulated by a length-dependent intrinsic property of muscle in humans and cats. The Journal of Neuroscience, 31(15), 5579-5588. Gandevia, S. C., & McKenzie, D. K. (1988). Activation of human muscles at short muscle lengths during maximal static efforts. The Journal of Physiology, 407, 599. Garland, S. J., Gerilovsky, L., & Enoka, R. M. (1994). Association between muscle architecture and quadriceps femoris H‐reflex. Muscle & Nerve, 17(6), 581-592. Hasler, E. M., Denoth, J., Stacoff, A., & Herzog, W. (1994). Influence of hip and knee joint angles on excitation of knee extensor muscles. Electromyography and Clinical Neurophysiology, 34(6), 355. Heckathorne, C. W., & Childress, D. S. (1981). Relationships of the surface electromyogram to the force, length, velocity, and contraction rate of the cineplastic human biceps. American Journal of Physical Medicine, 60(1), 1. Huber, A., Suter, E., & Werzog, W. (1998). Inhibition of the quadriceps muscles in elite male volleyball players. Journal of Sports Sciences, 16(3), 281-289. Kasprisin, J. E., & Grabiner, M. D. (2000). Joint angle-dependence of elbow flexor activation levels during isometric and isokinetic maximum voluntary contractions. Clinical Biomechanics, 15(10), 743. Kawakami, Y., & Lieber, R. L. (2000). Interaction between series compliance and sarcomere kinetics determines internal sarcomere shortening during fixed-end contraction. Journal of Biomechanics, 33(10), 1249-1255. Kawakami, Y., Kubo, K., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2002). Effect of series elasticity on isokinetic torque-angle relationship in humans. European Journal of Applied Physiology, 87(4-5), 381. Kay, A. D., Richmond, D., Talbot, C., Mina, M., Baross, A. W., & Blazevich, A. J. (2016). Stretching of Active Muscle Elicits Chronic Changes in Multiple Strain Risk Factors. Medicine & Science in Sports & Exercise. Kennedy, P. M., & Cresswell, A. G. (2001). The effect of muscle length on motor-unit recruitment during isometric plantar flexion in humans. Experimental Brain Research, 137(1), 58-64. Kilgallon, M., Donnelly, A. E., & Shafat, A. (2007). Progressive resistance training temporarily alters hamstring torque-angle relationship. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 17(1), 18. Kluka, V., Martin, V., Vicencio, S. G., Jegu, A. G., Cardenoux, C., Morio, C., & Ratel, S. (2015). Effect of muscle length on voluntary activation level in children and adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 47(4), 718. Kluka, V., Martin, V., Vicencio, S. G., Giustiniani, M., Morel, C., Morio, C., & Ratel, S. (2016). Effect of muscle length on voluntary activation of the plantar flexors in boys and men. European Journal of Applied Physiology, 116(5), 1043-1051. Koh, T. J., & Herzog, W. (1995). Evaluation of voluntary and elicited dorsiflexor torque-angle relationships. Journal of Applied Physiology, 79(6), 2007. Komi, P. V., Linnamo, V., Silventoinen, P., & Sillanpää, M. (2000). Force and EMG power spectrum during eccentric and concentric actions. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(10), 1757. Kong, P. W., & Van Haselern, J. (2010). Revisiting the influence of hip and knee angles on quadriceps excitation measured by surface electromyography. International SportMed Journal, 11(2). Kubo, K., Tsunoda, N., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2004). Activation of agonist and antagonist muscles at different joint angles during maximal isometric efforts. European Journal of Applied Physiology, 91(2-3), 349-352. Kubo, K., Ohgo, K., Takeishi, R., Yoshinaga, K., Tsunoda, N., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2006). Effects of series elasticity on the human knee extension torque-angle relationship in vivo. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(4), 408-416. Leedham, J. S., & Dowling, J. J. (1995). Force-length, torque-angle and EMG-joint angle relationships of the human in vivo biceps brachii. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 70(5), 421-426. Linnamo, V., Strojnik, V., & Komi, P. V. (2006). Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles. European Journal of Applied Physiology, 96(6), 672-678. Lunnen, J. D., Yack, J., & LeVeau, B. F. (1981). Relationship between muscle length, muscle activity, and torque of the hamstring muscles. Physical Therapy, 61(2), 190-195. Maffiuletti, N. A., & Lepers, R. (2003). Quadriceps femoris torque and EMG activity in seated versus supine position. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(9), 1511. Mahieu, N. N., Mcnair, P., Cools, A. N. N., D’Haen, C., Vandermeulen, K., & Witvrouw, E. (2008). Effect of eccentric training on the plantar flexor muscle-tendon tissue properties. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40(1), 117-123. Marsh, E., Sale, D., McComas, A. J., & Quinlan, J. (1981). Influence of joint position on ankle dorsiflexion in humans. Journal of Applied Physiology, 51(1), 160-167. Miaki, H., Someya, F., & Tachino, K. (1999). A comparison of electrical activity in the triceps surae at maximum isometric contraction with the knee and ankle at various angles. European Journal of Applied physiology and Occupational Physiology, 80(3), 185-191. Newman, S. A., Jones, G., & Newham, D. J. (2003). Quadriceps voluntary activation at different joint angles measured by two stimulation techniques. European Journal of Applied Physiology, 89(5), 496. Noorkõiv, M., Nosaka, K., & Blazevich, A. J. (2014). Neuromuscular adaptations associated with knee joint angle-specific force change. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(8), 1525-1537. Noorkõiv, M., Nosaka, K., & Blazevich, A. J. (2015). Effects of isometric quadriceps strength training at different muscle lengths on dynamic torque production. Journal of Sports Sciences, 33(18), 1952-1961. Nourbakhsh, M. R., & Kukulka, C. G. (2004). Relationship between muscle length and moment arm on EMG activity of human triceps surae muscle. Journal of Electromyography and Kinesiology, 14(2), 263-273. O’Brien, T. D., Reeves, N. D., Baltzopoulos, V., Jones, D. A., & Maganaris, C. N. (2009). The effects of agonist and antagonist muscle activation on the knee extension moment-angle relationship in adults and children. European Journal of Applied Physiology, 106(6), 849. Onishi, H., Yagi, R., Oyama, M., Akasaka, K., Ihashi, K., & Handa, Y. (2002). EMG-angle relationship of the hamstring muscles during maximum knee flexion. Journal of Electromyography and Kinesiology, 12(5), 399-406. Pasquet, B., Carpentier, A., & Duchateau, J. (2005). Change in muscle fascicle length influences the recruitment and discharge rate of motor units during isometric contractions. Journal of Neurophysiology, 94(5), 3126-3133. Prodoehl, J., Gottlieb, G. L., & Corcos, D. M. (2003). The neural control of single degree-of-freedom elbow movements. Experimental Brain Research, 153(1), 7-15. Rabita, G., Pérot, C., & Lensel-Corbeil, G. (2000). Differential effect of knee extension isometric training on the different muscles of the quadriceps femoris in humans. European Journal of Applied Physiology, 83(6), 531-538. Reeves, N. D., Narici, M. V., & Maganaris, C. N. (2004). In vivo human muscle structure and function: adaptations to resistance training in old age. Experimental Physiology, 89(6), 675. Roman, W. J., Fleckenstein, J., Stray-Gundersen, J., Alway, S. E., Peshock, R., & Gonyea, W. J. (1993). Adaptations in the elbow flexors of elderly males after heavy-resistance training. Journal of Applied Physiology, 74(2), 750-754. Simoneau, E., Martin, A., & Van Hoecke, J. (2007). Effects of joint angle and age on ankle dorsi-and plantar-flexor strength. Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(3), 307. Smith, C., & Rutherford, O. M. (1995). The role of metabolites in strength training. I. A comparison of eccentric and concentric training. European Journal of Applied physiology and Occupational Physiology, 71(4), 337-341. Suter, E., & Herzog, W. (1997). Extent of muscle inhibition as a function of knee angle. Journal of Electromyography and Kinesiology, 7(2), 123. Timmins, R. G., Shield, A. J., Williams, M. D., & Opar, D. A. (2016). Is There Evidence to Support the Use of the Angle of Peak Torque as a Marker of Hamstring Injury and Re-Injury Risk?. Sports Medicine, 46(1), 7-13. Ullrich, H. Kleinöder, G. P. Brüggemann (2009). Moment-angle Relations after Specific Exercise International Journal of Sports Medicine, 30: 293–301. Vander Linden, D. W., Kukulka, C. G., & Soderberg, G. L. (1991). The effect of muscle length on motor unit discharge characteristics in human tibialis anterior muscle. Experimental Brain Research, 84(1), 210-218. Vigotsky, A. D., Contreras, B., & Beardsley, C. (2015). Biomechanical implications of skeletal muscle hypertrophy and atrophy: a musculoskeletal model. PeerJ, 3, e1462. Wakahara, T., Miyamoto, N., Sugisaki, N., Murata, K., Kanehisa, H., Kawakami, Y., & Yanai, T. (2012). Association between regional differences in muscle activation in one session of resistance exercise and in muscle hypertrophy after resistance training. European Journal of Applied Physiology, 112(4), 1569-1576. Worrell, T. W., Karst, G., Adamczyk, D., Moore, R., Stanley, C., Steimel, B., & Steimel, S. (2001). Influence of joint position on electromyographic and torque generation during maximal voluntary isometric contractions of the hamstrings and gluteus maximus muscles. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 31(12), 730-740. Zehr, P. E. (2002). Considerations for use of the Hoffmann reflex in exercise studies. European Journal of Applied Physiology, 86(6), 455-468.

ファンクショナルな柔軟性とは パート2/2
実際の機能に即した柔軟性とは?モビリティーと共にスタビリティーを必要とする私たちの身体と動き。グレイインスティチュートでは、これをモスタビリティーと呼びます。股関節前側の組織を例にとってギャリー・グレイが機能的柔軟性の重要性を解説します。

FMSスコアで何をみるか? パート2/2
誰かがFMSについてリーサーチをする時、私たちが彼らに1つ伝えることは、研究する前にスコア0を除いてもらうということです。その人達はすでに怪我をしているのです。それを研究に加える事は何のメリットにもなりません。 研究からすでに痛みがある方達を除き、スコア1の人達が他のグループより先に故障するかどうかを調べる、これが研究というものです。 私はFMSに批判の余地がないと言っているわけではありませんが、多くの批判はスコア3がスコア2よりも優れているという推測を前提としています。そうではないのです。全く違うのです。スコアは下から上へと、一方向へのみ見るのみです。上(ハイスコア)から下(ロースコア)へではありません。FMSスコアに目を通す時ー0からです。次に見るべきなのは1です。 FMSのパターンにおけるスコア2と3の競合相違は、恐らく異なる環境において最も現れるでしょうが、0もしくは1はどんな環境でも有害となるのです(0か1のない人と比べた場合)。 身体の非対称性無しにはスコアは語れません。もしスコア1を機能不全、2を許容範囲、そして3を最適と定義した場合、私達は異なる3つの非対称性がありえます。1点と3点、1点と2点、または2点と3点の組み合わせです。 投球系のアスリートにおいては、1点と3点の非対称を多く見かけます。私達は、それが2点と3点の組み合わせになるようにコレクティブエクササイズを行いますが、日常生活動作が非対称である以上、それ以上の改善は難しくその非対称性は残ることでしょう。加えて、恐らくその選手達は人生のほとんどの長さにわたって投球動作を続けてきたはずで、いくらかの骨の変形もあるでしょう。 私は機能障害に比べれば、左右非対称性(片側が許容範囲に対し、逆側が最適、デフォルトとして両側許容範囲)はさほど問題だとは思っていません。繰り返しますが、左右非対称性を議論する必要もないのです。もし左右のランジのように左右の非対称性で1であったり、プッシュアップで1だったなら話は別ですが。 我々のFMSにおける命題は: 0点を除外すること。彼らには更なるアセスメントが必要です。 スコア1に関しては負荷をかけてはいけません。負荷をかける前に、パターンを修正するのに効果的な試みにトライしてみてください。もしスコア1を修正するのならば、非対称性を安定させるか、少なくとも安全な可動域で動かしましょう。もしスコア1を取り除けたら、いい調子です。左右差のあるアスリートをいつもみかけます。円盤投げ選手、槍投げ選手または素早く左回旋する人達には非対称性が見られるでしょう。 ここにアメリカで直面する問題があります。運動競技というものはいつにおいても多少の非対称性を作ってしまうものなのですが、アメリカでは他のどこよりも対称的な負荷を非対称のアスリートにかけてしまう傾向があります。もしあなたがジャマイカ出身のスプリンターでとてつもなく速く、リフティングをする気分でないのであればしなくて良いのです。これは他国の文化が柔軟性に欠けるとか、そういうことではありません。もしあなたに生まれ持った才能があるのであれば、誰もが皆新しいものに関して慎重になるはずですから。 左右の股関節に非対称性(ハードル選手のケース)がある場合、ディープスクワットをすればシフトするでしょう。あなたが尋ねるべき質問は:この非対称性は競技上危険であるかどうか?修正すべきか?でも負荷はかけないべきか?なぜならハードル選手を決してシフトさせない負荷は沢山あるからです。 もしバックスクワットでのシフトに対処すると考えているのなら、なぜスプリットスクワットをしないのでしょう?そしてなぜフロントに負荷をかけて脊柱を真っすぐに保ち、非対称性を “こちら側は8レップできてこっちは15レップ”という形で扱わないのでしょうか? 知らず知らずのうちに、私達は対称的な負荷を非対称的にかけてしまっています。 もしもアスリートが非対称性で故障しているのであれば、それはもしかすると私達がやっていることが原因にもなり得るのです。 しかし、もしも片側が機能不全で逆側は許容範囲もしくは最適であった場合には、私はこれにアタックするでしょう-それは非対称だからではなく、機能不全だからです。これはより明瞭な指導方法だと思います。操作の寛容度を広げてくれます。スコア1に取り組んで下さい。まずはじめの2パターンで、FMSの全てのテストで1点をだしたならば、アクティブストレートレッグレイズをまず先に行うことをお薦めします。骨盤を均等にし、スコアに素早く変化をもたらすでしょう。 レッグレイズと肩関節の可動性は、まず最初に片付ける最初の2つです。次に回旋スタビリティーで、運動制御のチェックとなります。その次はプッシュアップです。立位ではないもの全てが優先となります。もしあなたが全てにおスコア1をとったとして、スクワットの1とランジの1でさえ、レッグレイズや肩関節の可動性に取り組めばスクワットに真正面から取り組むよりも変化を与える可能性があります。基本的ですがしっかりとしています。 ムーブメントスクリーンを最初に発表した時、ディープスクワットは “ディープスクワットを修正すれば全てがうまくいく”と私達が豪語していた程、他の不良スコアの代名詞でした。ですが私達は真正面からディープスクワットに取り組むことはできないことを学んだのです。なぜならその他のムーブメントスクリーンパターンは全て、オーバーヘッドディープスクワットに含まれているからです。 ハードルステップ、ランジ、プッシュアップ、肩の可動性、そしてレッグレイズ、全てがそこにあります。ですからディープスクワットは、全ての複合動作なのです。ディープスクワットで3の場合、他の種目でも3、もしくは3に近い2を見ることができるでしょう。関節の過可動性がある人にとってはプッシュアップで1をだすかもしれませんが、ディープスクワットで1だった場合は他でも1を出すことになるでしょう。 スクリーンを下から上に評価していけば、まさに時間の節約となるでしょう。 その後によく聞かれる質問といえば: “ではなぜ7つ全てのテストを行うのか?”ということです。 私達は他のテストを約7分半で行うか否かで議論していますが、全てのベースラインを設定しながらも痛みを誘発する機会はあるのです。 “もし私が70人の女子のウェルネス指導をしている場合は?” やはり全てのスクリーンを痛みの誘発性とベースラインの為におこなうでしょう。全てのベースラインがとれるチャンスがあるのなら、中途半端はベースラインをとるのは止めておきましょう。なぜならあなたの内的データが次の効果的な動きを教えてくれるからです。 ここでのルールは決して推測しないということです:かなり注意深く、いつでも出来る限りのことを知っていることです。あなたが費やした時間や継続性に目を向けた時、他のパターンは何であったのかということを不思議に思うことでしょう。 単に、知ることはより良いことです。そうすれば、変化を見ることができるようになります。
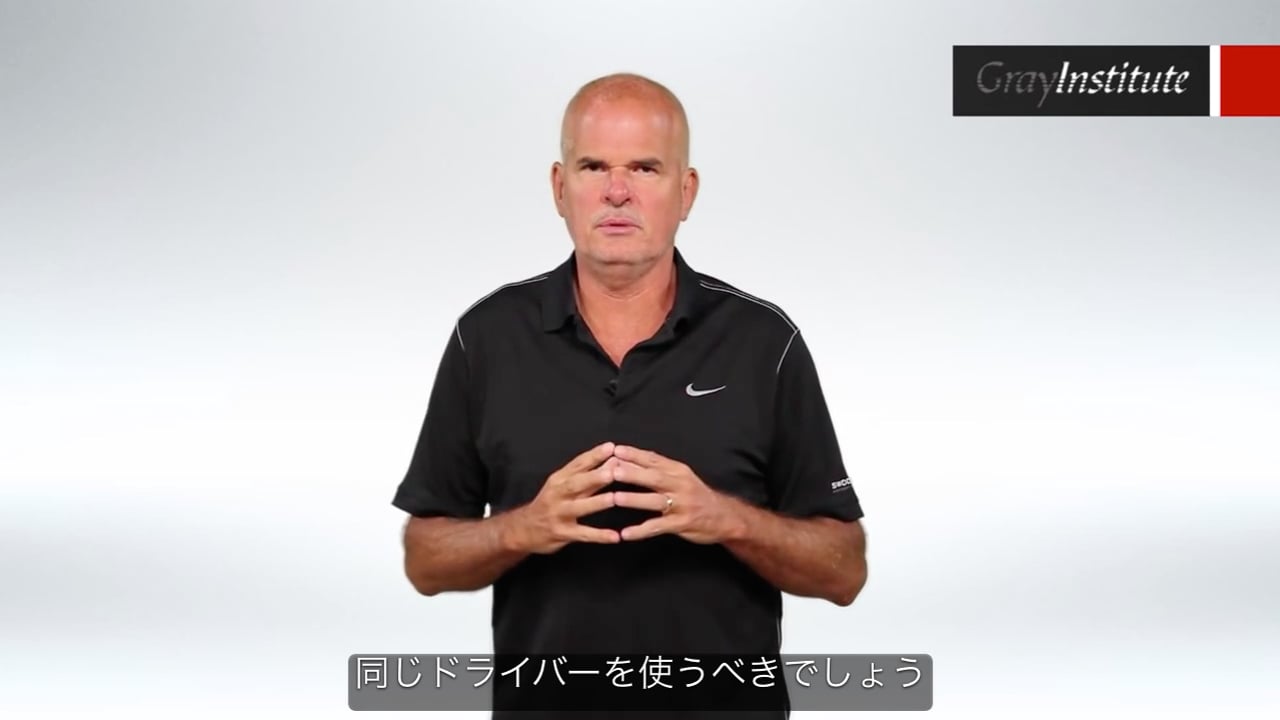
ファンクショナルな柔軟性とは パート1/2
実際の機能に即した柔軟性とは?モビリティーと共にスタビリティーを必要とする私たちの身体と動き。グレイインスティチュートでは、これをモスタビリティーと呼びます。股関節前側の組織を例にとってギャリー・グレイが機能的柔軟性の重要性を解説します。

FMSスコアで何をみるか? パート1/2
“ファンクショナルムーブメントスクリーンスコアで何を探しているのか?” これがファンクショナルムーブメントスクリーンにおいて私が最も頻繁に聞かれる質問でしょう。 グレイクックはスクリーンをする時に何を探しているのでしょう? 私はムーブメントスクリーンでゼロを探しています。 アメリカ海軍SEALのトレーニングにいようが、ボーイスカウトのキャンプにいようが関係なく、ムーブメントスクリーンではゼロを探します。 FMSには、ムーブメントパターンが痛みを引き起こすことによる、かなりの失格率があります。これは筋肉痛や一般にいう硬さのことを言っているのではなく、ほとんどの子供ができるようなムーブメントパターンに伴う痛みに、いくらか驚かされてしまう人達のことです。 考えてみて下さい...痛みが原因による失格率が20%あり、この人達のほとんどはシーズン前のメディカルチェックにパスしているのです。彼らは自体重を超えない負荷で、基本的な動作を必要とするムーブメントパターンに痛みを持っていながらも、自由に動いて良いと医療的に許可を受けているのです。 これはまるで災害を作るレシピのように聞こえるかもしれません...実際その通りなのです。 シーズン前のメディカルチェックはムーブメントについてよりも、目や耳、鼻や喉に関してのものでしょう。しかし怪我の大半はどこにおきるでしょうか? 毎年夏にフットボール中に心臓発作を起こす学生がわずかにいるでしょう。これは痛ましいことであり、それゆえに私達は血圧と脈のスクリーンをするのです。 しかし、どれだけの人数の人達が、もうスポーツに関われなくなるような深刻な膝の怪我をするでしょうか?なぜ私たちは、ムーブメントのスクリーニングをしないのでしょうか?どれくらいの人が足首の捻挫をして、リハビリで完治しないまま競技復帰しているでしょう? もしファンクショナルムーブメントスクリーンに点数をつけるシステムがなく、動作で痛みを伴う人々を見分けるだけだったとしても(動作がスポーツやアクティビティに関わる前であれば)、それでも私はとても価値のあることだと思います。 その10分間の投資が価値のあることなのです。なぜなら自分の娘がスクリーンにひっかかる一人になるかもしれないのですから。 もし痛みがある場合、SAIDの法則(特異性の原則)- 私達がエクササイズから得られると思う全ての利益 – は不確定で予測不可能です。痛みがあっても、我慢できないというわけではありません。 “残りあと60秒、文句を言わない!”とか。 もしもディープスクワットをする度に膝の後ろ側が痛むのだとしたら、私の解決策は “そこまで深くしゃがまない”こと。運動制御は痛みに直面するかどうかに関わらず、まだそのパターンにおいて歪んでいるからです。 まず最初に動作の健康をみなくてはいけません。もし動いた時に痛みがあるなら、あなたが健康かどうかもわかりません。あなたがフィットしていないという意味ではありません。見た目は鍛えていても、とても不健康だということです。肩のインピンジメントの兆候や、プレスアップ時の腰痛、またはランジの際の足首の痛み...それらは医療従事者が違うと言わない限り健康問題なのです。 過剰に警戒しようとしているわけではありません。私はムーブメントへの軽視/不注意が多くの傷害の原因になっていると言っているのです。 それが、エクササイズそのものがリスクの原因となっている理由でもあるのです。エクササイズがリスクファクターであってはなりません。その状況をコントロールできない競技や戦術がリスクファクターであるべきです。 周りの人は私に、“あなたはNFLの傷害予防をしようとしている”と言いますが、そうではありません。 NFLは100%の傷害率を持ちます。そこで仕事をする誰もが皆怪我をするのです。私達は傷害管理の話をしています。その人がどのように動くかを怪我の前に理解する事はとても重要なのです。 今では脳震盪を起こす前に認識力はチェックしますが、怪我の前の動作は見ようとはしないのです。 まず初めに、痛みがあるのにトレーニングをやりたがっている人がいます。痛みは不規則で予測できないものですから、彼らはあなたの成績率(そして彼ら自身の成績率)を損なわせるでしょう。次に、誰かがリスクの高い試みをすることがわかっている時に、見直しが可能なベースラインを設定することは確実に重要なことです。 ここから、議論のエリアになります。私はムーブメントの著書の始めに “まず上手に動き、それから沢山動きなさい”と話しました。これはとてもそっけない発言ですが、もし私がはっきりと定義しなければ、私のした事の全ては、解決策を持たない、別の問題を作っただけになってしまいます。 これらのパターンにおいて、私たちが何を言おうとしたのかというと、もしムーブメントスクリーンで1をとった場合、それはあなたが自分の体重でそのパターンをこなせなかったということを示します。ですからメディカルチェックでは痛みの可能性が無しとはいえないというのが私の仮説となります。 恐らく、痛みは私達にとって考えられる最大のリスクファクターでしょう。 次に、合理的なベースラインは、合理性なベースラインの不在よりも理にかなっています。私はムーブメントスクリーンというものにおいて明確な意志を示しました。もし機能不全があるなら、あなたは恐らくパフォーマンス向上の測定で良い反応を出せず、そういったパターンよりも前の段階で、疲労や、下手をすると怪我によって早々と故障してしまうかもしれません。 FMSスコアで2は許容範囲、3は最適を意味します。 私は、耐久性という観点から評価した場合、どちらが好ましいかという統計データを持っていません(特別な環境下の場合は除きますが、これはまた後でお話します)。 優れたストレングスコーチなら誰でも、FMSスコアで2の選手には出来る限り身体に余裕を作ろうと努力するのではないかと思います。シーズン中に何が起きるかはわかっています。消耗との戦いであり、私達は彼らに動く事を期待するのです。 ムーブメントは、優れた回復のバイオメーカーであると私は考えます。もし誰かがムーブメントスクリーンで18点をだして、私達が3日間のハードトレーニングを課し、スコアが12点に下がったのなら、その日のスケジュールがハードトレーニングの日だとしても追い込むべきではないでしょう。ムーブメントの比較として心拍変動や呼吸の効率性などのデータを是非チェックしたいと思います。 私は底辺のスコアよりも、ムーブメントスクリーンの高スコアに関しての批判には寛容です。なぜなら私達は “痛みが無い”と言っている人達の痛みを探しているからです。 “スクワットをしていない時は痛みがありませんよね?ですがスクワットをした時はどうでしょう?だってそのポジションは週末を迎えるまでに300回はするのですよ?” 痛みを除外し、信頼のおけるベースラインを確立しましょう。例えスコアリングシステムがなかったとしても、私はこの2つの情報において強く主張するでしょう。

ウェイトを素早く持ち上げればあなたは迅速になるのか?(強さは特異的)パート4/4
なぜ筋力増加は速度特異性であるのか?(パート2 続き) #3. 腱剛性 剛性とは、物質が伸長されることに抵抗する程度である。剛性の高いバネは負荷を付けたとしても、少ししか伸長しない。一方、柔軟なバネは非常に長く伸長する。 システムに含まれる際、剛性のより高いバネは、端から端まで迅速に力を伝達するため、より優れた力開発速度を持つ。より柔軟なバネは、力開発速度が遅く、ゆえにシステムに伝達する前に力のいくらかを吸収してしまう。 ストレングストレーニングは腱剛性の増加につながり(ベームおよびその他、2015年)、また、力開発速度の上昇にもつながる(ブレゼビッチ、2012年)。 より高い負荷は腱剛性の増加につながるため、ストレングストレーニングの効果は負荷により影響を受け(ベームおよびその他、2015年)、強度レベルは腱特性と関連がある(ムラオカおよびその他、2005年)。一部の研究者たちは、より高い負荷はより軽い負荷と比較し力開発速度のより優れた上昇を生み出す可能性があり(ブレゼビッチ、2012年)、腱剛性の増加はこの適応が起こるメカニズムである可能性があると提議している。 ポイントの要約:腱剛性の増加は力開発速度を上昇するようであるが、速度重視のトレーニングではなく、力重視のトレーニングに反応して起こる可能性が高い。ゆえに、高速トレーニング後における速度の特異性に貢献しているとは思えない。 #4. 単一繊維速度 筋肉構造、筋繊維タイプ、腱剛性は速度の特異性に対する貢献要因としては弱いものであるということを考えると、筋肉に内在するものの変化が、速度重視トレーニング後の、高速における力のより大きな増加に貢献しているということを思い出させることには価値があるであろう。 彼らの有名な研究の中でデュシャトウ&エノー(1984年)は、力重視および速度重視のトレーニングを比較し、力重視のトレーニング後における最大筋力のより大幅な増加(20% 対 11%)を報告しているが、最大短縮速度は速度重視のトレーニング後にのみ向上していた(21%)。さらにこの最大短縮速度は、不随意収縮において測定されており、末梢要因が含まれていることを示唆している。 忘れるべきでない1つの末梢要因は、単一筋繊維の収縮性である。 素晴らしい研究においてマリソーおよびその他(2006年)は、長期のプライオメトリックトレーニングの影響を評価した。彼らは、単一繊維速度は、タイプI筋繊維においては18%、タイプIIA筋繊維においては、29%、またタイプIIX筋繊維においては22%といったように、各筋繊維タイプにおいて増加するということを発見している。単一繊維力もまた増加しているが、これは筋断面積の増加により引き起こされており、断面積に対し正規化された単一繊維力は変化していなかった。 通常の高負荷レジスタンストレーニングにおける以前の研究は、単一繊維力の増加を報告しているが、単一繊維速度ではなく(ウィドリックおよびその他、2002年)、速度重視のトレーニングが速度の特異性を生み出す1つの方法は、おそらく個々の筋繊維の収縮要素を変化することによってであろうと示唆している。 ポイントの要約:単一繊維収縮速度は、速度重視のトレーニングにより上昇することが可能であり、速度特異性は、個々の筋繊維の収縮性の変化に起因するかもしれないということを示唆している。 #5. 神経適応 神経適応および速度特異性に関連して数多くのことが起こっているため、このセクションは長くなるということを覚悟しておくと良いだろう(もしくは、この章の最終にあるポイントの要約まで飛ばすと良い)。 ニューラルドライブの変化 ニューラルドライブとは、筋肉を収縮させるための脳から筋肉への信号である。それはコンポジット信号であり、運動単位動員(いくつの運動単位を起動させるか)および、運動単位発生頻度(1秒間にどれほどの頻度で作動されるか)から構成されている。我々は、自発的活性化(自発的および不随意力の間の差違)および筋電図振幅(筋肉内において記録された電圧)という2つの方法により、間接的にのみニューラルドライブを測定することができる。 全体的に、最大等尺性収縮の際の筋電図振幅は、高速、もしくは爆発的を意図したトレーニング後と比較し、高い力もしくは高い力を意図したトレーニング後において異なる変化はしないようである(ラマスおよびその他、2012年、ティリン&フォランド、2014年、バルシャウおよびその他、2016年)。しかしながら、収縮の異なる時点における心電図振幅は、下記に見られるように確実に影響を受けているようである。 爆発的トレーニングは初期段階における心電図振幅のより大きな増加を生み出す グラフからみてとれるように、爆発的トレーニングは初期段階における心電図振幅のより大きな増加を生み出している。一方、最大負荷トレーニングは、すべての収縮の際の心電図振幅の全体平均におけるより大きな増加を生み出している。 ゆえに、より高くピークを迎え降下する「パルス状効果」への移動を引き起こす爆発的トレーニングに伴い、ニューラルドライブ戦略における変化が確実に起こっている。 共活性化の変化 共活性化の増加はパフォーマンスを低下すると考えられているが、関節安定化の助けになるかもしれない。ゆえに共活性化の低下は、筋力を増加することのできる1つの方法であり、トレーニングにより変化するようであるが(ティリンおよびその他、2011年)、それが力開発の増加にどれほど貢献するのかどうかは明確ではない。 もし共活性化が、力重視のトレーニング後ではなく、速度重視のトレーニング後に特に観察することが出来るのであれば、それは速度特化の筋力変化に貢献している可能性がある。そしてこれにはあるヒントが隠されている。 実際に、プーソンおよびその他(1999年)は、共活性化は、高速が使用されている場合、トレーニングにおいて使われているものと同様の速度において等速性にテストされた際にのみ減少するということを発見している。ゲールツェンおよびその他、(2008年)もまた、速度重視トレーニング後における等尺性収縮の際の、抑制された共活性化の兆候を報告している。また、アラバッジ&ケリス(2012年)は、従来のレジスタンストレーニングは、垂直ジャンプの際、膝周囲の筋肉の共活性化の増加を生み出し、一方オリンピックウェイトリフティングは変化を生み出さなかったか、もしくは多少の減少を生み出したということを発見している。 協調の変化 協調の変化は、速度特化において示される筋力に貢献することができる、より基本的な身体的質(力生成および力開発速度のような)がどれほど増加するかに影響を与える可能性がある。 短い概要の中でブレゼビッチおよびその他(2012年)は、研究は、テストエクササイズがトレーニング期間中に行われなかった場合、ストレングストレーニング後の力開発速度における上昇は報告される可能性が低いと記述している。ゆえに、異なるエクササイズ後において、トレーニングの際に達成された力開発速度の上昇を表示するためには、テストエクササイズの練習が必要であるのかもしれない。 これは、垂直跳びにおけるトレーニングにおいて達した力生成の増加を使用することは、いったん筋力が増加した後に垂直跳びの練習を必要とするという考えと同様である(ボビー&ゾエスト、1994年)。 より高速のエクササイズには高速協調要素が含まれており、より低速のエクササイズと比較し、スポーツ動作により良く移行することから、これは低速エクササイズよりも高速エクササイズの方がスポーツパフォーマンスへより良く移行するようであることの理由の1つであるかもしれない(モーラ・クストーディオおよびその他、2016年)。異なる筋肉は、速度の異なるほとんどのスポーツ動作における全体的なパフォーマンスに貢献しているため、これはそれほど現実離れしたものではない(ビアズリー&コントレラス、2014年)。 ポイントの要約:初期段階のより大きなニューラルドライブ(および力開発速度の上昇)、より抑制された共活性化、そしてより優れた協調はすべて、力重視トレーニングと比較し、速度重視トレーニングにより達成することが可能である可能性があり、各要素が速度特異性に貢献しているということを示唆している。 結論 実際の速度および迅速に動こうという意図は、個々で速度特化の筋力増加を引き起こしている。速度特化の筋力増加はおそらく、力開発速度の上昇、および最大収縮速度の上昇を通じて起こるのであろう。 力重視トレーニングと比較し、速度重視トレーニング後における速度特化の影響に対する主な貢献要素はおそらく、筋束長のより大きな増加、単一繊維速度のより大きな変化、初期段階におけるニューラルドライブのより大幅な増加、より抑制された共活性化、そして協調のより大きな向上であるだろう。 しかし結局のところ、速度重視および力重視トレーニングの両方ともに、高速における力生成能力を向上するために有益であるような異なる適応を生み出すことができる。これは、力重視トレーニングを使用して達成した、断面積および腱剛性の大幅な増加により裏付けされている。

ウェイトを素早く持ち上げればあなたは迅速になるのか?(強さは特異的)パート3/4
なぜ筋力増加は速度特異性であるのか?(パート2) 速度特化の筋力増加を引き起こす可能性のある要因は多数存在する。下記は有力な候補の一部である。 筋肉構造 筋繊維タイプ 腱剛性 特定繊維速度 神経適合 我々は、これらの個々の要因は、速度重視(例:高速バリスティック動作もしくは爆発的な等尺性収縮のどちらか)、もしくは力重視(例:高力ストレングストレーニングもしくは持続的等尺性収縮のどちらか)のいずれかの後、異なる方法にて変化するのかどうかということを解明しようとすることができる。 我々はまた、それらが理論的に初期段階の影響(力開発の速度)もしくは後期段階の影響(高速の筋力)を生み出す傾向が強いかどうかを検証することも可能である。 #1. 筋肉構造 速度重視および力重視両方のアプローチを含む、全てのタイプのストレングストレーニングは、筋肉構造を変化させる(筋束長、羽状角度、および断面積)。 筋束長の変化 より長い筋束長はより高い収縮速度を意味するため、筋束長の増加は、高速筋力増加の助けとなる可能性がある。(ウィッキィウィックスおよびその他、1984年)。これは、筋原繊維における全ての筋節が同時に収縮するためであり、より大きな全体の長さの変化が同じ時間内に起こるということを意味している。 一方、より長い繊維は、筋収縮の開始において、緩んだ状態から張った状態になるまでにより長い時間が必要であるため、より長い筋束長は力開発の速度の減速につながるようである(ブレゼビッチおよびその他、2009年)。 ゆえに、初期段階の影響は不利益であり、後期段階の影響は有益であるといったように、筋束長伸長の影響においてのトレードオフがあるかもしれない。 そうだとしても、筋束長は、力重視のトレーニングと比較し、速度重視のトレーニング後により増加するかもしれないという兆候は存在する(ブレゼビッチおよびその他、2003年、アレグレおよびその他、2006年)つまり、これは起こり得る全体の変化において有益な適応である可能性があるということを示唆している。 断面積の変化 断面積の増加は、より大きく強い筋束はより大きな力を生み出すことができることから、高速筋力の増加を助ける。これは、すべての力・速度カーブを上向きにし、与えられた速度において力を産出しやすくしている。 筋肥大のためのトレーニングを行う際、低負荷は高負荷と同様の断面積の増加を生み出すかもしれないが、これには筋限界に至るまでのトレーニングが必要である可能性がある(シェーンフェルトおよびその他、2014年)。速度を向上させる際、低負荷でのセットは筋限界まで到達せず、同程度まではサイズを発達させないようである。これは断面積の変化は、速度特異性の要因ではないということを示唆している。 羽状角度の変化 筋羽状角度は、筋束長と比較し、理解するのがそれほど簡単ではない。羽状角度の増加は筋束長の短縮を意味しているが、これは筋収縮速度が必ずしも減少するということを意味しているわけではない。 羽状の筋束は実際には収縮の間回旋し、効果的な羽状角度を減少しており(ブレイナード&アジジ、2005年)、この回旋の量はより速い収縮においてより大きい(アジジおよびその他、2008年)。この繊維回旋は、その中における個々の筋繊維の収縮速度より、筋肉自体がより速い収縮速度に達することを可能にし、羽状に伴う不利益を無効にしている。 そうだとしても、羽状角度は、速度重視のトレーニング後と比較し、力重視のトレーニング後においてより多く増加する兆候があるが(ブレゼビッチおよびその他、2003年、アレグレおよびその他、2006年)、これはおそらく単に、羽状角度の変化が筋サイズの変化を追う傾向にあるためであろう。 ポイントの要約:筋束長の伸長は力開発の速度を低下するかもしれないが、同時に最大収縮速度を上昇する可能性がある。断面積および羽状角度の変化は速度の特異性に貢献しているわけではないようである。 #2. 筋繊維の種類 速度重視のトレーニングは、タイプI ⇒タイプIIA ⇒タイプIIXの方向において、(MHC構成、もしくは筋繊維タイプの分布のどちらかにより測定された)筋繊維の種類の移行、もしくは優先的筋繊維タイプの部位における筋肥大を生み出すことができる可能性がある。筋繊維は、タイプ IIX >タイプIIA >タイプI の順に速く収縮するため、速度特異性に貢献している可能性がある(例:トラッペおよびその他、2006年、バーバー&トラッペ、2008年)。 一部の研究は、筋繊維タイプもしくは繊維タイプ分布の移行に伴う速度特化の筋力増加を報告しているが(リューおよびその他、2003年、ザラスおよびその他、2013年)、ほとんどのものは、速度特化の筋力増加を報告しているものの、繊維タイプ分布における変化は発見していない(コイルおよびその他、1981年、トミーおよびその他、1987年、ユーイングジュニアおよびその他、1990年、マリソーおよびその他、2006年、ヴァイシングおよびその他、2008年)。さらに、より高速でのトレーニング後、タイプII 筋繊維部分における優先的増加の兆候は存在するが(コイルおよびその他、1981年、トミーおよびその他、1987年、ザラスおよびその他、2013年)、これもまた、決して統一された発見ではない(ユーイングジュニアおよびその他、1990年、マリソーおよびその他、2006年、ヴァイシングおよびその他、2008年、ラマスおよびその他、2012年)。 これは、初期段階の影響が不利益であり、後期段階の影響が有益であるということに伴う、繊維タイプ変化の影響のトレードオフによるものかもしれない。 最大力産出は筋サイズにより影響を受け、筋サイズの変化は、タイプIIX繊維分布の減少と並行し、タイプIIA繊維においてより多く起こる。ゆえに我々は、タイプIIXの損失は、初期段階における力開発の速度を低下し、タイプIIAの増加は、後期段階における力開発および力生成の速度を上昇することから、初期の速度特異性および後期の速度特異性においてトレードオフが存在するということを予測できるかもしれない。 研究が非常に限られてはいるものの、これが多かれ少なかれ我々が発見したことである。 例えば、ハッキネンおよびその他(2003年)は、タイプIIX繊維の部分は減少し、タイプIIA繊維の部分は増加しているなか、初期段階および後期段階の総合(500ms)において、力開発速度の上昇を発見している。アルガードおよびその他、(2010年)は、ここでもタイプIIX繊維の部分が減少し、タイプIIA繊維の部分が増加しているなか、初期段階( さらに興味深いことに、ファーラップおよびその他(2014年)は、力開発の速度とタイプIIX筋繊維の相対領域間の関係の強さは、時間周期が収縮開始からさらに離れるにつれ着実に減少するということを発見している(r = 0.61, 0.56, 0.46, 0.26 for 30ms, 50ms, 100ms and 200ms)。またアンダーソンおよびその他(2010年)は、トレーニング後のタイプIIX筋繊維の相対領域の減少は、初期段階(100ms)における力開発速度の変化と関連があるが、後期段階(200ms)におけるものとは関連がないということを報告している。 ゆえに繊維タイプ(繊維、分布および相対領域)の変化は、どの時期に筋力を測定したのかにより、速度特化の筋力増加の減少および増加の両方を生み出すかもしれないが、速度重視および力重視のトレーニングは、異なる影響は生み出さないようである(マリソーおよびその他、2006年、ヴァイシングおよびその他、2008年)。 ポイントの要約:トレーニングの異なる速度は筋繊維タイプの変化に影響しないようであるが、いつの時点で力を測定したかにより、いかなる種類のトレーニング後であっても筋繊維の影響は異なるであろう。

ウェイトを素早く持ち上げればあなたは迅速になるのか?(強さは特異的)パート2/4
それでは意図のみが、速度特化の筋力増加を生み出す要因であるのか?(パート1) おそらく最も有名であろう速度特異性の研究において、ベーム&セール(1993年)は被験者に2つの方法(等尺性および等速性)を用い、両方の状況が被験者に「課された負荷にかかわらず、可能な限り迅速に動く」ことを必要とした、足首の背屈トレーニングを行わせた。 等尺性トレーニングは、最大速度を意図して行われたが、動きは伴わなかった。一方等速性トレーニングは、比較的高角速度(1秒間に300度)において最大速度を意図して行われた。 筋力は角速度の範囲(1秒間に0度から300度)においてテストされた。しかしながらいかなる速度においても、筋力の変化に関し、両方のグループ間に差違はなかった。両方のトレーニングプログラムは、速度特異的筋力増加を表したが、両者間に差異がなかったために結果は、単一のデータセットにまとめられた。 このデータは下記に示されている: 迅速に動くという意図はそれほど重要なのか? 意図のみが重要な要因なのだろうか? 今のところ私は、意図が唯一重要な要因だとは考えていない。 この重要な研究がこのような形で行われた理由を理解することはできるが、そこには、私を躊躇させるいくつかの制限要素がある。 最初に、その研究は、一方の脚は等尺性トレーニングプログラムを使用し、他方の脚は等速性トレーニングプログラムを使用していたというように、被験者内設計を使用していた。これは、片方の四肢からもう片方への特定筋力増加のクロスオーバー効果の危険を残している。2つめに、両方が30度の底屈から開始した際、最大収縮の関節角度は筋肉間で異なったが、等速性トレーニングプログラムは、目標速度へ達するまで負荷無しで加速しなくてはいけなかった。 この研究はまた、いくつかの予期せぬ結果も報告している。 通常、等尺性トレーニングは最大等尺性力の大幅な増加を生み出す(デル・バルソ&カファレーリ、2007年)。意図が爆発的な場合においても、最大等尺性力の増加は通常見られる(マフューレッティ&マルティン、2001年、ティリンおよびその他、2012b、ティリン&フォランド、2014年、バルシャウおよびその他、2016年)。しかし、各収縮に対し500msが許されていたにもかかわらず(最大力に達していたことを意味する)、ベーム&セール(1993年)は、トレーニング後における最大等尺性力の減少に関して、少なくとも1つの結果を報告していた。 さらに、等尺性収縮によるトレーニング後の最大等尺性力の増加は、ダイナミック収縮後の最大等尺性力と比較し、通常、大幅に大きい(ジョーンズおよびその他、1987年、フォランドおよびその他、2005年)。しかしベーム&セール(1993年)は、その2つの状況間の差違はなかったと報告している。 ポイントの要約:意図はおそらく速度特異性へ作用する唯一の要因ではない。 意図のみが、速度特化の筋力増加を生み出す要因なのか?(パート2) 明確にしておくが、総体的に、下記の2つの主な理由により、速度特化の筋力増加は、実際の収縮速度および意図に反応し確かに起こると私は考えている。 最初に、上記に参照したほぼ全ての等速性の研究における被験者たちは、「最大の努力」においてレップを行う、もしくはそれに類似した指示を受けているが、異なる負荷を伴うトレーニングの際、速度特異性は依然として存在する。 次に、そしておそらく実際により重要なこととして、我々は、ここでも全ての(高もしくは低負荷を使用した)レップが最大の努力のもと行われた場合、レジスタンストレーニング、もしくはフレーウェイトを伴うバリスティックトレーニング後における速度特化の筋力増加の根拠は存在するということを知り得ている(モスおよびその他、1997年、インゲブリグトセンおよびその他、2009年)。 ポイントの要約:おそらく実際の速度および意図の両方が重要であろう。 なぜ筋力増加は速度特化なのか?(パート1) それでは、速度特化の筋力増加は、おそらく実際の動作速度および迅速に動く意図の両方に反応して起こるのだろうということに落ち着いたが、その適応は何によるものなのであろうか? 理論的には、筋肉は、その力開発の速度を上昇させる、もしくはある一定の張力を生み出しつつ、その最大収縮速度を上昇させることができる(もしくは同時に両方を行う事ができる)。 下記のグラフは2つの適応の可能性を示している。 これが理論上のものであるということは述べただろうか? このモデルで見られるように、いつ力を測定するかは、トレーニング後に高速で表現された力の増加を観察することを期待しているのか、もしくは減少を期待しているのかどうかに影響を与える。 初期段階(100msのあたり)において、まだ力が上昇している間に測定した場合(例:ティリン&フォランド、2014年)には、力開発の速度が上昇した時のみ変化をみることができるだろう。一方、後期段階(300msのあたり)において、力が最大に達した後に測定した場合(ベーム&セール1993年)、高速における力開発が変化した場合のみ、最大力の変化を見ることになるだろう。 しかしながら、実際にはこの理論的なモデルのように単純ではなく、2つの複雑な要因が存在する。 最初に、爆発的な収縮に対する運動プログラムは、前もってプログラムされているということは周知のことである(デュシャトー&エノー、2008年)。それは一度誘発されると、停止する前に最後まで実行されてしまう。ゆえに多くの種類の爆発的もしくはバリスティックなトレーニングは、力開発速度および高速筋力の両方を同時に十分に開発する可能性がある。 次に、収縮の種類は、いかに早く最大力に達するかに影響を及ぼす。最大力へは250ms-300ms後にのみ達するということは周知のことであるが、現実にはこれは等尺性収縮およびエキセントリック収縮へのみ適用されるものである。コンセントリック収縮における最大力は、150ms以内で達する(ティリンおよびその他、2012年a)。ゆえに、等尺性収縮およびエキセントリック収縮と比較し、コンセントリック収縮において、高速筋力は力開発速度よりもより関連性があるのかもしれない。 ポイントの要約:速度の特異性は力開発速度の上昇、もしくは最大速度における力生成の向上により、理論的に起こり得る。ゆえに、爆発的動作の初期もしくは後期のどちらで力を測定するかは、そのストレングステストから得る結果に影響を及ぼすかもしれない。

ウェイトを素早く持ち上げればあなたは迅速になるのか?(強さは特異的)パート1/4
高速での力生成能力を発達させるために、ほとんどのコーチたちは、ジャンプスクワットや、オリンピック・ウェイトリフティングバリエーションのような、負荷をかけて素早く動くことを含むバリスティックエクササイズを使用する。 一方、多くの人々は、アスリートを高速でより強くするのは、素早く動く意図によるものだと答えるだろう。 しかしそれが正しいとすると、バリスティックトレーニングは必要が無くなり、全ては単に従来の高負荷レジスタンストレーニングのみを通じて達成することができるかもしれないということになる。 それでは、筋力の増加は速度特化したものであるのか、もしくはそうではないのだろうか? 下記がそれに対する私の考えである。 「速度特化」の筋力増加とは何を意味するのか? 速度特化の筋力増加が起こるために我々は、トレーニングで使用しているものと同様の動作速度における力生成をテストする際に、最大の筋力増加を見る必要がある。 ゆえに、我々が高速においてトレーニングしている場合、高速において筋力をテストした際に最大の筋力増加、そして低速においてテストした際には最小の筋力の増加を見るべきである。 同様に、我々が低速でトレーニングをする場合、我々は低速において筋力をテストした際に最大の筋力の増加、そして高速においてテストした際には最小の筋力の増加を見るべきである。 もちろん我々は実際には、高速のバー速度を使用してトレーニングすることにより、高速におけるより大きな筋力の増加を生み出すことができるかどうかということに最も興味を持っている。 それほど単純なことなのである。 それでは何故、速度の特異性はそれほどまでに複雑なのだろうか? 負荷を動かしている速度を変化させることができる方法は2つ存在することによって、速度の特異性を解明することは途端に複雑になる。 まず、あなたはバーに対し単に負荷を追加することが可能である。あなたが低負荷および高負荷のどちらに対しても最大の努力をしている場合、これは、力・速度関係により、その動作を遅くする。低負荷と同様な素早さで高負荷を動かすことはできない。これは、ただ不可能なのである。 次に、あなたはどのようにレップを行うのかという意図を変えることができる。それを最大の努力で行うのか、もしくは最大下の努力により行うのかを選択することが可能である。 どちらのアプローチを選択するかにより、結果は異なる。これを理解する最善の方法は、あなたがバーベルにかけている力は、重量(重力による力)および慣性(物質を加速するために必要な力)という2つの部分から成っているということを認識することである。 もしあなたが最初の方法をとり、減速するためにバーにプレートを追加した場合、追加のプレートはより重いため、重量は増加するが、重いバーベルを同様に素早く加速することは不可能なため、(その質量はより大きいにもかかわらず)慣性はわずかに減少することとなる。正味の効果は総力の増加である。 2番目の方法をとり、負荷は同じままであるが、減速するために故意に制御したテンポを使用した場合、重量は同様でありながらもバーベルをより低速で加速することを選んだため、慣性は減少することとなる。正味の効果が総力の減少であることは明白である(ベントレーおよびその他、2010年)。 最初の方法においては、力および速度は筋肉の根本的な能力に適合しているが、2番目の方法においては、力は本来得られるものよりも低い。 ここまでは大丈夫だろうか? バーの負荷を変えることは速度特化の筋力増加を生み出すのか? もしバーへの負荷が速度特化の筋力増加を生み出すのであれば、我々は、低い力を伴う(低負荷)トレーニングは、高い力を使用する場合(高負荷)と比較し、より高速においてより大きな筋力の増加を生み出すということを発見するはずである。 基本的に我々は、ストレングストレーニングプログラムの前後に、低速および高速のグループが同じ速度において筋力をテストした際、おおよそこのようなことを発見するはずである: 理論的な速度特化トレーニングの反応! 多くの研究者たちは、50年近くにわたりこの質問を探求する研究をしてきている。 彼らは、1つのグループは低角速度を使用し、他のグループは高角速度を使用するが、両方のグループは最大の努力をするといったような、2つ以上のグループを比較した際、通常、等速性ストレングストレーニング後において速度特化における結果を発見している。 常にではないが(ファーシング&チリベック、2003年)、概して高速トレーニングは、高等速性速度においてテストした際、より大きな筋力増加につながる(モフロイド&ウィップル、1970年、カイオッツォおよびその他、1981年、コイルおよびその他、1981年、ジェンキンスおよびその他、1984年、ガニカ、1986年、トミーおよびその他、1987年、ピーターセンおよびその他、1989年、ベルおよびその他、1989年、ユーイングジュニアおよびその他、1990年)。 異なる負荷を伴うトレーニングの速度特化の効果は、フリーウェイトを使用する際にはより一貫性が低く観察されるものの、やはり明白である。 興味深いことに、被験者が単関節エクササイズを使用した際(カネコおよびその他、1983年、アーガードおよびその他、1994年、1996年、モスおよびその他、1997年、インゲブリグトセンおよびその他、2009年)、多関節エクササイズを使用した際(アルマスバック&ホフ、1996年、マックブライドおよびその他、2002年、モーラ・クストーディオおよびその他、2016年)よりも、より明らかな速度特化のパターンが存在する傾向にある。このようなことが起こる原因はいくつかあるが、その分析は他の記事において行うこととする。 ポイントの要約:はい、より軽い負荷を使用することは、速度特化における筋力増加を引き起こす。 意図を変えることもまた、速度特化の筋力増加を生み出すのか? 意図が速度特化の筋力増加を生み出すかどうかを解明するのは、非常に困難である。 もちろん、高速において測定された際、最大速度においてフリーウェイトを使用しトレーニングを行ったグループは、最大下速度においてトレーニングを行った同様のグループと比較し(ジョーンズおよびその他、1999年、モリッシーおよびその他、1998年、インゲブリグトセンおよびその他、2009年、ゴンザレス・バディロおよびその他、2014年)、より大きな筋力増加を経験する傾向にあるということを示している研究を探すのは容易である。 この方法に伴う問題は、それが意図のみを測定しているのではないということである。それは意図と実際の筋収縮速度の両方を測定している。 それゆえこれを確かにするために、研究者たちは速度を制御することにより意図の影響を隔離した。彼らは速度をゼロにセットすること、つまり等尺性収縮によりこれを行った。 実際には、筋収縮速度は等尺性収縮においてのみほぼ制御することができる。等尺性収縮は、関節角度が変化しない場合においても一部の筋肉の短縮を含んでいる。等尺性収縮においても、収縮する際、筋は短縮するが、腱は伸長するため、総筋腱単位の長さにおける変化はない。ゆえに速度はゼロではなく、筋肉は力生成の増加に伴いより短縮する(ナリチおよびその他、1996年)。 そうであったとしても、最大速度を意図したトレーニングは高速における筋力測定においてより大きな増加につながり、最大速度を意図、および最大下速度を意図した等尺性収縮によるトレーニングは実際に異なる結果を生み出す。(ティリンおよびその他、2012年b、ティリン&フォランド、2014年、バルシャウおよびその他、2016年)。 ポイントの要約:はい、意図もまた、速度特化における筋力増加を生み出すことができる。

コンディショニングが命を救い得る理由 パート4/4
ポイント#2: 体系的炎症の指標を記録し続ける 母が脳卒中にかかった後で、私が最初にしたことの一つは、心拍変動(HRV)の使用に加え、自分の炎症指標を定期的に確認することでした。 HRVと寿命の強い相関性は、私がバイオフォースHRVの製作を始めた主な理由の一つです。バイオフォースHRVは、市場において本当に手に入りやすく、簡単に使えるシステムの先駆けでした。 ご存知ない方のために短く説明すると、HRVは迷走神経の全体的な機能を示す最も優れた指標です。この機能により、HRVは体系的炎症の驚くほど強力な尺度になっています。 毎日たった数分でHRVを計ることができるのなら、健康とウェルネスに価値を見出している人は誰でも取り組むべきです。 これに加え、私は四半期に一度、高感度CRP(高感度C反応たんぱく質)やホモシステイン、線維素原、その他標準的なコレステロール指標など、組織的炎症の指標を確認する血液検査をするようになりました。 これは私が残りの人生の間ずっと行うことであるとともに、35歳あるいは40歳以上の人、特に私のように家族が心臓血管系の疾患や脳卒中を患ったことがある人に強く勧めたいことです。 血液検査に関しては、いい医者に相談するのが一番です。ポイントは、健康に率先的でいることで、何かが悪くなるまで待たないことです。 長期的に炎症の指標を確認することは、自分の健康状態が悪い方向に向かっていないかを確かめ、トレーニングから栄養、人生のストレスまであらゆるものの結果を評価するのに、非常に効率的で大切な方法です。 ポイント#3: 交感神経系を静める方法を学ぶ ここまでくれば、必要ないときに交感神経系を静める能力が重要だということがわかっていると思います。実際、有酸素性フィットネスを発達させることと、身体が炎症を抑える能力を発達させることは同じくらい大切です。 この能力は過小評価されています。そして他のスキルと同様に習得するには努力と練習が必要です。 この能力を発達させるためには、まずワークアウトの終わりの時間を使います。心拍計を使って、クールダウンを行い、できるだけ早く心拍数を休息時の通常のレベルに下げるようにしてください。90/90呼吸ドリルを行い、どのくらい早く心拍数を落とせるかを確認してください。 意識的にエネルギー消費をコントロールし、交感神経系の活動を減少する方法を学ぶことが重要です。少しの練習で、最短3-5分程度で休息時心拍数の+/-5~10以内に戻すことができるようになるでしょう。 これが難しい場合には、PRIの呼吸エクササイズを行うのが最適です。自分自身でコースに参加するか、経験したことのある誰かに教えてもらい、最大限の効果を得てください。 運動後に交感神経系の活動を素早く静めることは、価値ある能力を発達できるだけでなく、回復を早めるのにも役立ちます。交感神経系が静まるのが早ければ早いほど、副交感神経系が素早く活動的になり、炎症を抑えて、回復と再生を促進してくれるのです。 ワークアウトの後に交感神経系を静める方法を学ぶことができたら、次のステップは、毎晩眠る前に同じ練習をすることです。これは、長期的に、炎症の抑制、回復の促進の大きな役割を担っている睡眠の質を高めることにつながります。 また、ワークアウトの後および就寝時間の数時間前にはできる限りカフェインを避けることが重要です。刺激物は交感神経系の働きを強め、前述の通り、この交感神経系の活動が炎症を促進します。 ワークアウトの後、ベッドに入るまでの数時間は、交感神経系の働きを促進するものを一番避けたい時間です。アメリカの人口の3/4が継続的にカフェインを摂取して暮らしていると聞きます。もしあなたもその一人だとしたら、その習慣を変えることを強く推奨します。 より良く食べ、より賢くトレーニングをし、交感神経系を意識的に静めるために何かをすることは、健康とウェルネスをコントロールする為の非常に強力な方法です。 全てが良ければ、終わりも良いーある程度は 残念な事に私の母は完全には回復していませんが、誰もが経験できるわけではない最も困難なことは乗り越えることができ、死を免れました。母は現在、退職者コミュニティーで多くの友達を作り、幸せそうに生きています。客室乗務員の仕事に戻ることはできませんでしたが、ソーシャルメディアを発見し、絵文字の使い方を学び、みんなとつながりを持ち続けています。 母は、私が望んでいるほどには外出していませんが(およそ半分の時間をアマゾンに頼って生きていることもそれを助長していますが)、少なくとも週に3日はジムに行き、活動的でいるための努力を続けています。 栄養面も劇的に改善され、十分すぎるほどの睡眠も得られています。母にとっては、今でもこの変化は楽なものではありませんが、前に進む為に前向きな見通しを持っています。 私の母の話は、ありふれたものの一つに過ぎません。この国では4分ごとに誰かが脳卒中で亡くなっています。それは、この記事を読んでいるほぼすべての人が、少なくともどこかの時点で友達や愛する人が似たようなことを経験するような確率です。 この悲しい真実は、避けられないわけではありません。研究では、心臓の病気や脳卒中に関連する死の最大80%は、予防できる原因に起因していることが示されています。 このような個人的な話を共有したのは、愛する誰かがあまりにも多くのストレスと、コンディショニングを軽視した生活による必要ない結末を経験するのを目の当たりにした私の経験を追体験してもらうためです。 私が人生で学んだ教訓を共有することで、ストレスに対する見方を変え、コンディショニングの真の価値と健康に与える影響を認識していただければ幸いです。 コンディショニングは魔法の薬ではないかもしれませんが、現時点ではその魔法の薬に一番近いものなのです。

コンディショニングが命を救い得る理由 パート3/4
有酸素性フィットネスの利点―コンディショニングがアスリートのためだけのものではない理由 ここまで読んでくださったのなら、身体が生きるために必要な炎症促進力および抗炎症力を均衡に保つ大切さがわかっていただけると思います。急性の炎症が、慢性的、体系的、及び、低度な炎症へと移行するのを防ぐことが、社会を停滞化する多くの病気を予防するために、愛する多くの人々を救うために、絶対的に必要なのです。 科学は、なぜ、どのように、に対する完璧な答えを示せてはいませんが、一つだけはっきりわかっていることは、高いレベルの有酸素性フィットネスが、身体が炎症を静める能力を高めることのできる最も強力な武器であるということです。これは、有酸素性フィットネスが、迷走神経緊張と呼ばれる休息時の迷走神経の全体的な機能に直接関係しているからです。 このことを確かめるために、寿命と身体的運動に関する11の論文の興味深いレビューを見ることができます。 持久性はまさに命を救うことができる “Does Physical Activity Increase Life Expectancy? A Review of the Literature(身体的運動は寿命を延ばすか?文献レビュー)“という論文では、一般的に活動的であることは寿命を延ばすかどうか、そしてアスリートであるということがそこにさらなる違いをもたらすかについて考察しています。 皆さんが想像する通り、この論評では、活動的な人はそうでない人に比べ、0.4年から4.2年ほど長く生きることがわかりました。ここには大きな驚きはありません。 しかし、驚いたことに、様々なアスリート(大半は一流のアスリート)の寿命を見てみると、平均的な人よりも一貫して長生きだった唯一のグループは持久系アスリートでした。実際、持久系アスリートは、平均的な人よりも4.3年から8年も長く生きるとされています。 さらに興味深いことには、この論評で扱われた研究のいくつかでは、チームスポーツアスリートの寿命は、程よく活動的な人の平均に比べ、最大5年も短いことがわかりました。 もちろんこのレビュー以外にも、高い有酸素性フィットネスを持つ人は、心臓血管系疾患、脳卒中、糖尿病などにはなりにくく、認識機能などが高いことを支持する研究が豊富にあります。従来は、この関係は、心臓血管系システムの変化そのものによると思われていました。しかし、高い有酸素フィットネスが多くの病気のリスクを下げる大きな理由は、それが身体を慢性的な炎症から守っているからだということが明らかになってきました。 例えば、“Markers of inflammation are inversely associated with V̇o2 max in asymptomatic men”(炎症の指標は、症状のない人のVO2 maxと反比例する)という研究では、有酸素性フィットネス(VO2 max)とC反応たんぱく質や線維素原などの炎症指標の間には、驚くほどはっきりとした比例関係があることを示しています。 研究を掘り下げていくと、有酸素性フィットネスを高める最も大切な利点は、その過程で起こる抗炎症性能力にあることが明らかになっています。この大切さは強調してもしきれません。 大きくて強いことはかっこいいかもしれませんが、コンディショニングは生死を分けるものにさえなります。 私が優先順位を考え直した理由-あなたも考え直した方がいいかもしれない理由 ストレス、炎症、病気に関する事柄を集め、私の母のような一見何の問題もない人がどのようにして脳卒中を患うのかを理解すればするほど、私は、私自身のトレーニングやライフスタイルを見直し始めました。 自分自身の死を実感することよりも強い変化の薬はありません。 私は自分の優先順位を変え、トレーニングを見直す必要があるとわかっていました。ハイレベルの格闘家たちのコンディショニングには慣れていたものの、自分自身のトレーニングは、主にウエイトリフティングとほんの少しまたはゼロの有酸素運動で成り立っていました。 さらに悪い事に、母の脳卒中のケアから来るストレスと、母を数カ月にわたって医者から医者へと連れて行くストレスからも大きな打撃を受けていました。 食習慣および睡眠も相当悪化していました。気分が優れず、私の体重は脂肪だけで5-7kgほど増加しており、この生活を変えなければいけないことは自覚していました。 その2008年の悲惨な一日から数週間、数か月、数年を経て、私のトレーニングと優先順位は劇的に変わりました。私にとってどれだけのウエイトを持ち上げられるかはどうでもいいことになり、コンディショニングはトレーニングの日課になりました。 これまでに格闘家が試合でパフォーマンスを発揮するのをサポートするために、相当な時間をコンディショニングの勉強に費やしてきたのにもかかわらず、自分自身のコンディショニングを改善したい、健康でありたいという願望が、もっと研究をしたいという思いを強くしました。 一年後の2009年、私はこのウェブサイトを始め、コンディショニングについて書いたり話したりすることを始めました。 そうして私は、目指しているフィットネスの目標が何であっても、健康で長生きしたいと考えるのなら誰もが行うべき3つの結論に達しました。 これらの3つの領域は健康とウェルネスの出発点だと考えています。あなたが先ほどの統計の数字の一部になることを避けたければ、これらは間違いなく非常に重要なことです。 ポイント1:高強度トレーニングをやり過ぎない。80/20ルールに従う。 コーチとして15年間以上活動し、数千人の人々を見てきた中で私が学んだことは、長期間にわたる成功には、強度よりも一貫性の方がはるかに大事だということです。 ここ5年間くらいで、ほぼ全ての人が高強度という流行の波に乗りました。米国中の人々がみな、理想の身体を手に入れたければ、ジムでは毎回死ぬほど追い込まなければいけないと信じるようになりました。 私は過去にもこのことについてたくさん書いてきましたが、この傾向は一向に減りません。確かに強度は大事ですが、大事なのはそれだけではないのです。 高強度の一番の問題は、それにより全ての組織や免疫システムに多大なストレスがかかり、それが炎症を起こす大きな元凶になるということです。 長期的な成功のためには、強度よりも一貫性が圧倒的に重要なのです。 これこそ、強度が強すぎると簡単にトレーニングのやりすぎになってしまう理由です。慢性的な低レベルの炎症を加速し、放っておけばプラトーや、怪我などにつながってしまうのです。 前回の記事では、クロスフィットがした正しいことと、何がクロスフィットを成功させたのかについて話しました。しかし、クロスフィットの高強度への飽くなき執着は、完全に間違ったものであり、為になるどころか害にさえなっています。 母の脳卒中の後、私は高強度トレーニングを行うのをせいぜい週に2日までに減らしました。また、量よりも質を重視する一方で、定期的にスイミングなど低強度でストレスを低減するトレーニングを始めました。 先に紹介した文献では、持久系競技のアスリートは一貫して低い疾患率を持ち、長生きをしていることがわかりました。私の目標が同じ利益を享受することだとすれば、彼らがどのようにトレーニングをしているのかを知る必要がありました。 この話題に関する素晴らしいレビューが、“Intervals, Thresholds, and Long Slow Distance: the Role of Intensity and Duration in Endurance Training.(インターバル、限界、長距離:持久性トレーニングにおける強度と時間の役割)です。 このレビューによると、成功している持久系アスリートのほぼ全ての強度の分布をみると、魔法の割合は80%の低強度と20%の高強度でした。 世の中で推奨されている多くのプログラムはその全く逆で、80%の高強度と20%の低強度です。そしてなぜパフォーマンスが上がらないかを疑問に思い、関節を痛めています。 あなたは持久系のアスリートになりたいとは思っていないかもしれませんが、病気をせずに健康で長生きすることが目標であるのなら、こういったアスリートのようにトレーニングをすることには大きな意味があります。