マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

運動制御に関するシステム論的視点 パート1/2
ダイナミックシステム理論(Dynamic systems theory:DST)は、運動学習を最大限に習得する方法として、運動リハビリテーションとパフォーマンスの業界で影響力を持ち始めています。運動行動は、身体のさまざまなサブシステムや目前の課題、環境などの複合的な相互関係により生じるということが大前提です。この複雑性を前提として、運動行動がどのように変化するか、その学習がどのように起こるのかを分析するのにダイナミックシステム理論は適しています。 この投稿と次作では、ダイナミックシステム理論の基本概念とクライアントへの適用方法についてレビューします。これをお読みになれば、著名なムーブメントコーチの臨床での実践や直感的な能力を理解するのに役立つでしょう。 (ところで、この投稿の内容に関するバックグラウンドや、痛みの状況への適用方法についてもっと知りたい方は、「システム論的視点からの慢性疼痛」という投稿をご覧ください)。 複合システム、自己組織化、トップダウン制御 ダイナミックシステム理論の大前提として、身体は数百万もの相互に影響し合う部分で構成されている複合的システムであるということがあります。身体を協調する知性は、ある特定の部位に局在しているものではなく、すべての異なる部位の複合的な相互作用から生まれます。ですから、たとえばサーモスタットのような単純な機械とは異なり、複合システムは、ひとつの中枢制御装置に制御されることなく行動を起こします。 この一見矛盾していることを説明するために、ダイナミックシステム理論では自己組織化、(制御の)出現、多重的因果関係という用語を使います。これらはあまり聞き慣れない用語ですが、魔法のようなものではありません。自己組織化は、物理法則に反する生命維持のための活力のようなものを意味するものではありません。ですが、制御装置なしでどうやって制御できるのでしょうか? 蜂の巣のような昆虫社会の知的行動を思い浮かべてみてください。巣を造り、蜂蜜を作り、蜂の子を育て、敵を撃退したりなど、成すべき重要な仕事をどのようにすればよいかすべて知っている一匹の蜂がいるわけではありません。その代わりに、これらの仕事は、何千匹の蜂の複合的相互作用によって行われます。これら蜂の行動はただひたすら無心にアルゴリズムに従っているだけです。同様に、私たちの動きを制御する知性は、何百万個の身体部分と環境の複合的相互作用によって出現します。 では、中枢神経系についてはどうでしょうか? 中枢神経系こそが身体の中枢制御装置ではないでしょうか? ある意味ではそうであると言えます。つまり、中枢神経系が、意味のあるパターンで筋を発火させる指令を司っています。しかし、中枢神経系そのものも多くの部分によって成り立つ複合システムです。その行動は、免疫系、内分泌系、筋骨格系など、そのほか多くの体系と環境によって変化します。 このような理由から、ダイナミックシステム理論では中枢神経系や“モータープログラム”のような“トップダウン”で動きを決定させる役割を重視しません。むしろ、身体の構造や環境、そしてそこにある課題の特質など、“ボトムアップ”の要素に焦点を当てています。 協調された動きをするために、これらの要素がどれだけ重要であるかを示す一例として、内蔵コンピューターやモーターが設置されていないロボットが歩いている、このビデオを観てみてください。ロボットを制御する知性は、その構造の中に組み込まれています。その構造が適切な状況に設置されれば、その通りに作動してくれるのです: このロボットは、歩くことを学習する必要はありませんでした。環境を整えて(斜めにした床)そして、お父さんが少し押してあげればいいだけです。人間の赤ちゃんは違っていますか? エスター・テーレンによる興味深い研究によると、赤ちゃんを歩かせるのに必要なことも似たようなものだということです。 構造、環境、足踏み行動 エスター・テーレンは、発達心理学の分野で斬新な考え方を持っていました。(興味深い注釈:彼女は、フェルデンクライス・メソッドが自分の多くの考えを効果的かつ実践的に応用したものであると分かってから、自分もフェルデンクライス・プラクティショナーになりました。) テーレンの重要な研究のひとつは、乳幼児の発達過程における足踏み行動の変化が重要であるとしています。乳幼児は、まるで歩きたいと思っているかのようにつかまり立ちをし、よちよち歩きを始めるということを、研究者は長い期間観察してきました。この行動は、その後数ヶ月間は消えてしまいますが、その後再び出現します。 これらの変化を説明する有力な説は、神経系の発達にあります。それによると、反射が抑制され、次の運動制御パターンが発達する時、乳幼児はどういうわけか足踏みの運動制御プログラムを習得してそれから失ってしまうようです。しかし、テーレンは、中枢神経の発達が完全ではないと考えられている子どもたちに、この足踏み行動を起こさせることができました。子どもたちの脚を水中に入れ、脚が軽くなることで、自発的に足踏みをするようになる、という方法です。 このように、足踏み行動を制御している決定的な要素は、中枢神経からの“トップダウン”プログラミングの変化ではなく、太ってしばらく怠け、それからスリムになって動き回り始める、子供達の脚の重量効果による“ボトムアップ”の変化だったのです。 テーレンはまた、環境を変えることにより足踏み行動を変化させることができました。乳幼児がトレッドミルの上で歩く、次のビデオをご覧ください。従来の見解では、このような足踏み行動は、この月齢の神経系発達レベルでは通常あり得ないことですが、その子をトレッドミルに乗せると、動き始めるのです。 テーレンにとってこれは、乳幼児の発達には通過すべき段階や一定の規則があるという考えに直接的に挑戦することなのです。それよりも、発達は個人差が大きく、状況によってかなり変化し、成功するための発達の仕方には何通りもあるということです。 これらの考え方は、発達に関する従来の見解とは対照的です。従来は、トップダウンや遺伝で決定され、中枢神経系を介したプログラムに則って、ひとつひとつ段階を踏んで進んでいくものが、最も好ましい発達であると考えます。しかし、そうではないかもしれません。ローマにつながる道はいくつもありますし、すべての子供が這い這いの道を通るとは限りません。

予測的コーディング、なぜ期待が運動と疼痛に重要なのか パート2/2
疼痛 予測的コーディングの枠組みは、なぜ疼痛がただ組織の損傷のみでなく、過去の経験、考え、予想、感情に影響されるのかを説明するのに役立ちます。 例えば、腰部の屈曲が疼痛を引き起こす経験をたくさんしていれば、屈曲すると痛みが伴うと予測する腰部の内的モデルを作り始めます。これは、実際に腰部が侵害受容を生み出してないのにもかかわらず、屈曲するたびに痛みを感じさせる強い先入観を作ります。 腰部のモデルを更新することで、トップダウンの要因の痛みへの影響を軽減できます。これを行うには屈曲すると痛くなる予想にそむき、予測エラーを促す必要があります。いい方策として屈曲する時どう感じるか注意を払い、腰椎の屈曲を例えば四つ這い位や背臥位など、何らかの新しい方法で行い、予測エラーを無視できなくします。要するにこれは、運動療法の大半のように聞こえますね。 より積極的で危険な方策は、重いデッドリフトのような背筋群が屈曲を防ぐために非常に強く働かなければいけない運動を行うことです。屈曲を防ぎながら正しいフォームでデッドリフトを行うかもしれません。少し痛むけれど、予想していたほど痛くはなかった。実際に、自分がどれだけ強く感じるのかに、心底驚きます。これは、腰が弱すぎてかなりの力を扱うにはもろいという予想を覆した証拠です。そして、あなたの腰の地図は予測エラーのために更新されます。良い兆しですね! 肝心なのは、短期的に疼痛を和らげてくれるものは、痛みを促すという予想を覆していることが多いということです。それにはたくさんの方法があるでしょう。マッサージ、デッドリフト、キャット・カウ、ストレッチ、等尺性抵抗エクササイズ、自動的あるいは介助関節可動性エクササイズなどです。これらに全て共通していることは(もし痛みが和らいだ場合)、予想しているよりもそれほど痛くないということです。 よりよく動く、予測と行動 予測的コーディングモデルによると、知覚と運動には深いつながりがあります。なぜなら、それぞれが予測エラーの修正に役立っているから、そして全てのシステムが最も注目していることは予測エラーを最小限にすることだからです。システムが予測エラーに直面すると、次の二つのうちのどちらかが起こります。新しい情報を反映するためにモデルを更新する(知覚を変化する)か、あるいは予測と一致した感覚情報を集めるように行動を変化するかどちらかです(運動を変化する)。 例えば、バーベルを背中に乗せた状態でボックスへ向かってスクワットを行うとしましょう。ある程度の深さまでスクワットをすると、ボックスにタッチダウンしたことを示すお尻からくる感覚フィードバックを期待します。しかし、ここで、私の尻が何も伝えてこないという予測エラーがありました。ここで私ができることは二つ。ボックスの位置の知覚を変えることができます(あれ、ボックスをそこに置くのを忘れていた!)。あるいは、予測されていたフィードバックが起きるまでさらにお尻を下に降ろし、行動を変えることができます。 どちらにせよ、主要な目標は、常に予測エラーを軽減することであり、それができれば知覚を変えても行動を変えてもどちらでも構わないのです。重要なのは、バーベルを背中に乗せたまま床に落っこちないことです。どちらにしても、良い内的モデルと正しい予測が機能的知覚と行動を生み出す基盤になっています。 ですから、運動を改善することは、運動の内的モデルや運動中に感じられる感覚フィードバックの予測を向上することなのです。より良い知覚と行動を通して、間違いを認識し修正するためには、多くの経験を必要とし、ミスをし、そして正しい感覚情報の流れに注意する必要があります。もちろん、私たちはこれらほとんどについてどうせ知っていますが、予測的コーディングの枠組みの応用が正しい答えに導いてくれることは素晴らしいと思います。 次に、他のモデルでは簡単に説明できない、予測的コーディングのまだ知られていない部分から学べる素晴らしい情報をご紹介します。 統合失調症、自閉症、そして赤ちゃん このアルバート・アインシュタインの写真をみてください。彼の鼻はあなたに近づいていますか、それとも遠ざかっていますか? 私達は、鼻はこちらに近いと予想するので、ほとんどの人はこのマスクが凸形に見えますが、実は凹形です。面白いことに、統合失調症の人(そしてマリファナでハイになっている人)では、実際にこのような間違いが少ないのです。なぜなら、彼らの世界に対する知覚はトップダウンモデルよりもボトムアップの感覚によってコントロールされているからです。そして、このために彼らは妄想症になる傾向があるのかもしれません。 統合失調症は、毎日の出来事が顕著で信じられないほど重要だと錯覚を起こしてしまいます。混雑した喫茶店に座っていて、近くの会話であなたの名前が聞こえてきたと想像してみてください。これはあなたの注目を引くかもしれませんが、多分あなたの意識にはそれほど驚くものとしては捕らえられていないでしょう。しかし、予測しなかった入力感覚情報の関連性が、かなり大幅に誇張されるという問題を持っていれば、あなたの名前を挙げられることは非常に重要に感じられ、もしかすると言及や妄想などの錯覚に貢献するかもしれません。ですから、妄想的錯覚は、些細な予測エラーに重要性を置きすぎているのかもしれません。 自閉症もまた、トップダウンの予測以上にボトムアップの感覚が優勢である状態だと理解することができます。ほんのわずかな予測エラーでも重要だと捉えられます。ですから、入ってくる感覚情報は全て“報道価値のある”ものであり、自閉症を持つ人たちは“感覚の奴隷”として、洋服のラベルやランダムな騒音などの些細な入力によって常に取り乱されたりイライラしたりしてしまうのです。 興味深いことに、自閉症を持つ人たちは反復的でリズミカルな運動を行うことで自分を落ち着かせることをよく行います。これらの運動は非常に予測しやすい感覚情報の流れを生み出します。より良い予測は、圧倒されてしまうような感覚情報を抑制することを可能にします。 赤ちゃんがリズミカルな運動を好んだり、いつも抱っこされたり、包まれることを好むのはこのせいなのかもしれません。なぜなら、彼らは世界での経験が少なく、入ってくる感覚データについて自信を持って予測するような強い内的モデルを持ち合わせていないため、予測できない腕や脚の運動、背中がチャイルドシートと触れる変化、そしてテレビや交通が生み出すランダムな騒音など、全ての情報にびっくりしてしまっているのです。大人もこれらの情報全てにさらされていますが、私たちは簡単に予測できるので、これらを無視することもできます。しかし世界の内的モデルをしっかり持っていない赤ちゃんにとっては、全てが活発でざわめいて混乱しているのです。赤ちゃんは、予測できるリズミカルな感覚情報のいい流れによって落ち着かされるのかもしれません。 私たちみんなそうではないでしょうか?

予測的コーディング、なぜ期待が運動と疼痛に重要なのか パート1/2
予測的コーディングは、最近私が勉強している新しい知覚のモデルです。ある意味、これは常識的で直感的なことですが、とても難しく思考を広げるものでもあります。この投稿では、私が学んだことと興味深く実践的なことを説明します。 その前に、なぜこのトピックが、運動と疼痛に関連している人たちに興味あるべきものなのかをみてみましょう。 はじめに、良い運動は良い知覚を必要とします。身体を協調して動かす技術は、空間のどこに身体がありどのように動いているのかを知覚する技術と切り離せません。私たちは動くために知覚し、知覚するために動くので、動きが見事な人を“身体感覚”や“固有感覚”が素晴らしいとよく言うのです。 二つ目に、疼痛は知覚の性質に含まれています。身体が危険に陥っているのか、そして身体を保護するために何をするべきか、脳の判断によって疼痛は変化します。もし足が痛ければ、それが正しくても間違っていても、脳が足のケガを知覚しているということを意味します。身体に関する知覚は(他の全てと同様に)誤っている場合もあり、そのため損傷のない部分が痛かったり、損傷している部分が痛くなかったりするのです。知覚の科学についてさらに学ぶことで、疼痛と疼痛の治療方法を必然的に学ぶことになります。 従来の知覚モデル:ボトムアップ 従来の知覚モデルは、おおよそ以下の通りです。私達は、目、耳、皮膚、筋などにある神経終末から知覚情報を集めます。この情報が脳に伝達され、そこで情報が処理され、意味が解釈され、さらに原因についての知覚が作り出されます。 例えば、私の妻の顔を目の前に見るとき、彼女の顔に光が反射し、その光のパターンを私の目が認識して脳に送られ、私の脳はそのパターンが妻の顔から来ているものだと認識し、そのため彼女がそこにいるのだという知覚を作り出すのです(私が誰の指図を受けたらいいのかわかるように)。 あるいは、もし誰かが足を踏み出して膝に痛みを感じたとき、それは、その一歩からの機械的な力が侵害受容(痛覚)を刺激し(損傷の可能性に関する神経シグナル)、そのシグナルが脳に届きます。脳は膝への脅威があると判断し、保護を促すために疼痛を作り出したのです(足を引きずって歩くかもしれません)。 ですから、このモデルは、非常に“ボトムアップ”あるいは“外側から内側”のものです。外の世界から身体の末梢までの情報の流れ、そして身体の末梢から脳までの情報の流れを強調しています。 このストーリーには何が欠けているでしょうか?このモデルがうまく説明できないのは、入ってくる感覚情報の意味を脳が判断するときの、過去の経験の役割に関してです。そこで予測的コーディングのモデルに価値が加わります。このモデルは“トップダウン”の要因がどのように入ってくる感覚情報を修正するのかを説明します。 予測的コーディング:期待は重要 予測的コーディングモデルによると、脳は外の世界(および私たちの身体)の表象やモデルを常に作り、改良しています。私たちの知覚は単に入ってくる感覚データだけではなく、これらのモデルに大きく左右されます。 例えば、私の家の内面モデルは、私の犬のリーバイという四つ足の動物を一匹だけ含んでいます。もし薄暗いリビングを歩いていて、狼をちらっと見たとすれば、実際にはたぶん自分の犬リーバイを見るでしょう。つまり、私の知覚は実際に私の目からの知覚データよりも私の期待によって決定されているのです。 期待が知覚をどのように決定しえるのか、いくつかの例を以下の写真で見てください。 最初の二つの写真では、あなたの目が伝えたことと非常に異なるものを知覚しました。これは言葉が通常どう綴られているかに関する、あなたの今までの推測に基づいています。3つ目の写真では、今までの経験に基づいた顔の部位がある一定に配置されている 、二つの正常な顔を見ました。(写真を逆さまから見ると非常に違う配置が見えます) これは他の種類の感覚でもよく見られます。悪魔のメッセージが歌詞に隠されていると考えていると、レッド・ゼッペリンの“天国への階段”を逆に演奏するとそれが聞こえてきます。後ろから誰かの腕に氷をのせ、同じタイミングで“熱い!”と言えば、その人は熱を感じます。 プラシーボの鎮痛効果は、それが疼痛を軽減するだろうという期待に純粋に基づいているのです。ノセボは、その逆の作用で、疼痛を予期することが疼痛を促します。ある程度、私たちは予測していることを知覚しているのです。 トップダウンとボトムアップの比較 予測的コーディングモデルは、期待が知覚にどのように影響するのかを正確に説明できます。神経系は、脳の皮質が一番上で神経終末が一番下というように、序列的に整理されています。神経系のより高いレベルでは、下のレベルから入ってくる感覚データの流れを常に予測しています。これらの予測は、入ってくる感覚データ(ボトムアップ)に見合う下方に流れる神経活動(トップダウン)を作ります。神経活動がすれ違うと、予測されたことと感じられたことが比較され、それによって予測エラーが発生します。言い換えれば、トップダウンがボトムアップと“握手”をし、相違が話し合われ、妥協に行き当たるのです。 エラー(あるいは相違)が比較的小さければ、ランダムな騒音か、“かなり近いもの”として無視されます。神経系のさらに高いレベルには予測エラーは伝達されず、予期していたその通りの世界が知覚されます。エラーが大きければ、さらに高いレベルまでミスが伝達され、世界のモデルを更新できるようにします。驚くことや重要なことが起こったという主観的な感情が生まれ、入ってくる感覚データの方へ自動的に注意がシフトし、知覚と行動がそれに応じて調整されます。 予測の強さや自信は、予測エラーの扱われ方に大きく影響します。入ってくる感覚データの予測の確信が非常に高ければ、(たくさんの過去の経験に基づいているかもしれない)有意なエラーであっても無視されます。しかし予測の確信が低ければ(状況が新しく、エラーが予想されているかもしれない)、ボトムアップの感覚情報が神経系の高いレベルまで上がる可能性は高く、知覚の変化を促します。注意力もまた、予測エラーの処理のされ方と重要な関係を持っています。もし私が、ある感覚情報の流れに注意を払えば、予測エラーを無視するのではなく、エラーに気づく可能性が高くなります。そのため、システムは、相対的な確信のレベルやどちらかへの注意力に基づいて、知覚にトップダウンあるいはボトムアップの要因を支持する偏見をもたらします。 例えば、私の世界のモデルによると、私のガレージの中にある黒いSUVは私の車のみです。違う車に交換したとしても、私はたぶん気づかずに車に乗ってしまうでしょう。私の知覚は、目からくる情報ではなく予想によってコントロールされています。しかし、トップダウンの予測よりもボトムアップの感覚がはるかに私の知覚をコントロールしている混んだ駐車場では、同じ錯覚に苦しまないでしょう。 このモデルがどう働いているのか基本的なことが理解できたところで、これからこのモデルが知覚に関連している一般的な現象とあまり一般的ではない現象をどのように説明するのか見ていきましょう。
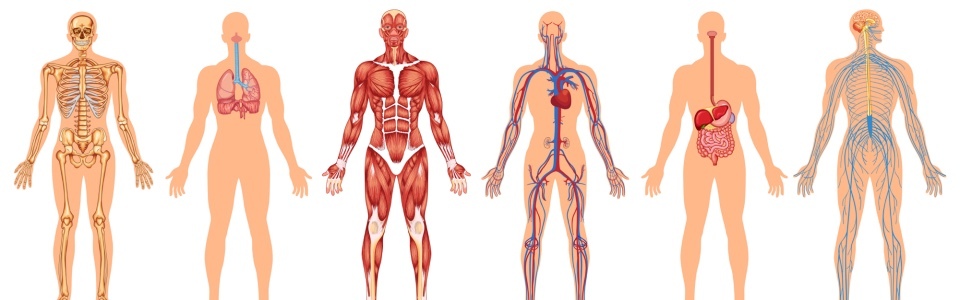
意図的スタンス パート2/2
意図的スタンス システムを考察する上で、分析の最も高いレベルをデネット氏は意図的スタンスと呼んでいます。最小限の測定と計算によって最大の予測力を提供してくれますが、エラーのリスクも最大になります。ある程度の主体性や意図、合理性を持つ十分な知性があるシステムに適用されます。 たとえば、ハイキング中に熊に遭遇したとしたら、相手の次の行動を予測したくなり、直ぐさま熊の意図を推測し始めるでしょう――私を食べたいのか? または、私が持っているサンドイッチを? 私を怖がっていて逃げようとしているのか? 子熊を守ろうとしているのか? もしその熊の信念や意図が分かれば、次に熊がどのような行動を起こすか的確に推測ができるでしょう。その情報は、客観的に測定できるような確かな物理的データよりもずっと有用になるでしょう。しかし、もちろん推測した意図が間違っていることもあります。 通常、意図を持ち合わせないと思われているような機械や内臓、単細胞さえも含む準知能が備わったものの行動を予測するために、これと同じ方法を使うことができます。植物はあまり知的なものと評価されていませんが、植物が目標を目指していると考えることでより植物を理解することができます。植物は、日光を“浴びたい”から枝を太陽の方向へ伸ばすのです。害虫に“食われたくない”ので、食われそうだと“気づく”と天然の殺虫成分の分泌を増やします。骨のように知能がないものでさえも、ある種の合理性を持っています―― 圧迫性の衝撃を多く受ける部分を強くするような賢さがあります。仮にあなたが骨だとしたら、自分の構造的完全性を保ちたいと思い同じことをしますね? 意図的スタンスは、実際とても一般的な動きであり、私たちは絶えずそれを考えずに実施しています。たとえば、私たちは、携帯やパソコンなどのスマートマシーンに精神的な要素を付与せずにはいられません。もし、私がコンピューター相手にチェスをしていて、私のクイーンが危ない状況になった時、相手は次の順番で私のクイーンを取ると私は確信するでしょう。なぜなら、コンピューターも勝ちたいと“思って”いて、そのゴールを合理的に遂行するように作動するとわかっているからです。そうは言っても、その挙動は当然、その“意図”によって制御されるということではなく、プログラミングコードによって制御されています。しかし、すべてのコードを読み解くことや、この特定な状況下でコンピューターがどうするか見つけ出すことは、計算上ほぼ不可能です。コンピューターが“あたかも”頭の良い人間であるとして対応した方がよっぽど簡単です。 結局、意図的スタンスは次のように機能します: まず、合理的な物体として挙動が予測可能なものを扱うこととします;それから、その物体が、その場や目的の中で、何の信念を持っているのかを探ります。そして、同様に、どんな欲求を持っているはずなのかを探ります。こうして最終的に、この合理的な物体が、その信念から目標に向かって行動をとると予測します。選択された一連の信条と欲望から得られたちょっとした実践的な推論によって、ほとんどの場合、その物体が何をしそうであるかについての結論を引き出すことができるでしょう;このようにして、その物体がどうなるのか推測するのです。 神経系や免疫系、運動制御系のような身体のほとんどの知的システムの機能を理解するために、私達はこれとまったく同じ方法を利用します。これらのすべての部分をしらみつぶしに測定したのでは、複雑すぎて理解できませんから、全体を擬人化する必要があるのです:それらがあたかも意図や目的や、異なる選択肢を考慮して行動を起こす知力を持っているかのように。それらがどのような種類の情報を基に行動しているのか、またそれらが判断を下すためにどのような論理が使われるのかを観察することによってさらなる洞察を得ることができます。 私の意見では、臨床に関連する近年の痛みの科学の進歩のほとんどは、痛みに対する意図的スタンスを適用しています。メルザックやギフォード、モズリーらのような研究者たちは、まさにデネット氏が提唱するような質問を行っています。 たとえば、痛みを理解するために、問うべき最も重要な質問:痛みの目的はなんでしょうか? 痛みの役割とは? 痛みを発生させるシステムは何を意図しているのでしょうか? これらの質問に答える客観的な方法はありませんが、痛みの目的は物理的な脅威から身体を守ろうとして行動を起こさせるためにあるということにおいて、皆同意するようです。この目的が明確になれば、説明が難しい痛みの現象を理解するために、ある程度の進歩をすでに成し遂げたことになります。なぜ緊急事態で重大なケガを負ったにも関わらず痛みをまったく感じないことがよくあるのでしょうか? なぜなら、身体を防御するといった本来の痛みの“目的”のためにならず、自らを守ることができなくなるからです。よって、痛みには“意図”があると認識することで、痛みは単なる組織の損傷によって活性化される単純な反射作用によって制御されるという、時代遅れの物理的スタンスのような考え方を越えて理解することができます。 痛みについての次の一連の重要な質問: 痛みのシステムはどのように考えるのでしょうか? どのような“信条”を持っているのでしょうか? どんな情報にアクセスし、そしてその情報をどうやって処理するのでしょうか? ニューロマトリックスモデルは、このような疑問に的確に答えようとしています。このモデルは、システムが思考を形成するための情報源と情報の本質を明らかにし、また、その意図を達成するための思考を土台にした潜在的行動を特定しています。 また、すばらしい本である「Explain Pain(痛みの説明)」を読んでみてください。痛みのシステムを論理的に説明しています:そのシステムがどのように考えて、どうしたいのか、何を信じているのか、そして、どのような裏付けがあって判断を下しているのかを説明しています。さらに重要なことに、そのシステムがどのように間違えを起こすのか、そして、この間違えは新たな情報を与えることによって修正可能であることなど説明しています。ある人のことを知ろうとすることと同じようなものです。もう痛みは必要ないということを、どのようにその人に納得させますか? この問いかけに答えるのに、みなさんはきっと道理にかなったよい治療についてちょうど考えていたのではないでしょうか? 運動制御システムを理解する上でも同様の考え方を使うことができます。運動の問題を解決するのにどのような種類の情報が必要でしょうか? これらの情報はどこから送られてくるのでしょうか? このシステムの考え方を考慮すれば、どのような種類の情報がより価値を持つでしょうか? それを学習させ適応させるモチベーションは何でしょうか? 繰り返しになりますが、この観点にはリスクがあります。痛みと運動制御を管理している身体のシステムの“マインド”に自分を置き換えてみることは容易なことではありません。しかし、そう試みることは、これらを理解する上で重要な要素になるでしょう。
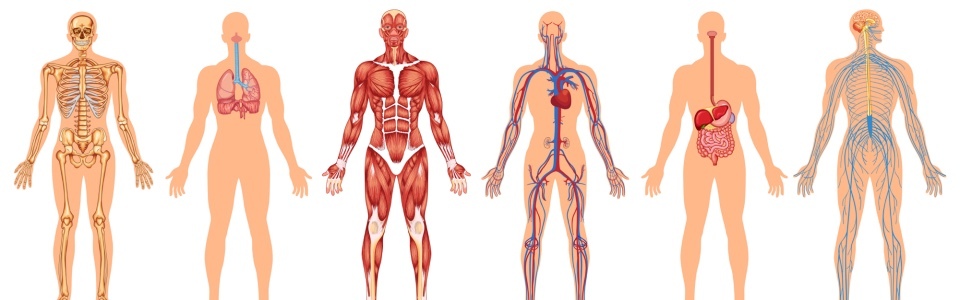
意図的スタンス パート1/2
この論稿では、痛みと動きを解釈するためのいくつかの観点について簡単に論じます。それによって、多くの複雑な生理的現象を分析する近道となるかもしれません。ただ、前もって断っておきますが、このためにはダニエル・デネット氏による複雑な哲学の分析が必要になります。 私が思うに、これはフェアートレードでしょう。隠すまでもなく私はデネット氏の大ファンです。彼は素晴らしいひげを生やした大変聡明な人物です。彼の多くの有名な着想のひとつに、複雑性と知性の異なるレベルが存在するシステムを理解するには、私たちはさまざまな観点や“スタンス”を持つべきということがあります。彼は、分析を3つのレベルに分けて述べています:物理的スタンス、設計的スタンス、意図的スタンスです。 これらすべては、考え方としては至って一般的で、一度説明されれば、すんなりと理解できるでしょう。日々の生活や場面で、それらすべては広く使われています。3つの中で、一つめ(物理的スタンス)は、理にかなった科学的なやり方として最も尊重される傾向にあります。二つめ(設計的スタンス)は、懐疑的に見られる傾向にあります。三つめは、明らかに虚偽であると思われることが多いようです。デネット氏によると、それぞれの観点や分析のレベルには短所と長所があり、それぞれ異なったタスクに適しています。意図的スタンスは、一般常識としても痛みや動きの抑制を理解するための効果的な方法としても、十分に活用されていないことが多いと私も思います。 物理的スタンス 仮に、あるとても単純な出来事から生じる結果を予測したいとします。たとえば、石を手から離すなど。自然の法則についてのみなさんの知識を使えば、その石は上に向かうのではなく落下するだろうと推測するでしょう。デネット氏は、この考える過程を“物理的スタンス”と呼んでいます。なぜなら、物理的法則の制御をもとにその物体の挙動を予測すると見るからです。この見方は、驚くほどの正確性を持った予測を提供してくれます。もし、主要な変数についての正確な情報(石を手から離す時の角度や速度など)があれば、石が手から離れた後、どのようなことが起こるのかほぼ正確に特定できます。物理学者や化学学者、技術者は、主に物理的スタンスを仕事に取り入れています。私たちが “科学”であると考えているものは、たいてい物理的スタンスに当てはまります。 設計的スタンス 今度は、手から鳥を放すことを想像してみてください。物理的スタンスに当てはめてみても、あまり実践的ではありません。鳥は物理的および化学的法則にしたがっているはずの物理的なものではありますが、鳥には部位がたくさんあり、それらはすべて複雑に作用し合っていて、これに物理的スタンスを当てはめるのは、実際問題として不可能です。 鳥の挙動を予測するには、 “設計的スタンス”を使います。鳥が飛ぶように“設計”されていることは知られています。だから、手から離せばその設計通りに動くだろうと推測するわけです。 機械の挙動を予測するのに、設計的スタンスは頻繁に使われます。コーヒーメーカーのスイッチを入れれば、コーヒーが作られ始めると予測します。爆発するとは思いませんね。なぜならコーヒーメーカーは、爆発するようには設計されておらず、コーヒーを作るように設計されているからです。これは、私が勝手に仮定しただけなので、私が間違っていることも考えられます。もしかしたら、実際は意地悪な人によって設計されたかもしれず、あるいは、今その設計が壊れてしまうかもしれません。それを確かめるために、それを分解し、もっと“物理的スタンス”で分析する必要があるかもしれませんが、これは実践的ではありません。 生物学では、設計的スタンスは遍在します。内臓は機能と目的を持っていると認識することがこれに関わります。心臓は、血液を送り出すように“設計”されています;腎臓はフィルターです;肺の“目的”は働いている筋肉に酸素を送り、そして筋肉は、身体を動かす“ために”筋収縮という“仕事”をすることができるのです。これらの内臓はたいていの場合、これらの目的に従って働くと私たちは予測します。たとえば、筋が頑張って働いている時、肺もそれを“補う”ためにより多くの酸素を取り入れるようになるということを知ったところで、私達は驚きませんね。機能と目的、設計という考え方は、やや曖昧な概念を含み、精密な測定や正確な証拠を条件とはしませんが、身体を科学的に理解するために必要不可欠です。虫垂の目的はなんでしょうか? 解明されていません。 (ところで、上記で使われたすべての引用符は、心臓や肺がDVDプレーヤーと同じように“設計”されておらず、また人間が行うような“目的”も持っていないということを確認するためのものです。しかし、デネット氏は、その違いは想像以上に小さな度合いの違いである、と言うでしょう。さらに詳しくお知りになりたい方は、デネット氏の著書を読んでみてください。) 設計的スタンスの素晴らしいことのひとつに、ある対象物が何をするために設計されたものかが分かれば、内蔵された機能について一切知らなくても、それがどのように挙動するか正確に予測できるということがあります。DVDをDVDプレーヤーに差し込む時、それが何をするのか推測するのに電子工学を理解している必要はありません。また、私の身体が、あるタイプのエクササイズの身体的負荷に耐えられるように適応していくことを知るために、運動生理学を理解している必要はありません―― そうなるように設計されているからです! ですから、生態において設計的スタンスはあらゆるところにあり、まさに必要なことなのですが、 私たちが分析している設計の性質や質への推測が間違ってしまうこともあるために、本質的にリスクを伴います。 心臓が軽いランニング負荷に対応するように設計されていることは明らかですが、マラソンにはどうでしょうか? 過剰な持久走は心臓に悪いという議論もあります。なぜなら、そのように機能するために“設計”されていないから。わたしたちは、裸足で“走るために生まれた”のでしょうか? ダニエル・リーバーマンのような専門家は、肯定するでしょうが、自然の摂理に従う方が人工的に設計されたランニングシューズより良いのかどうかは、まだ結論は出ていません。もしそうだとしても、疑問が残ります―― 裸足はコンクリートの上で上手に走れるように設計されているのでしょうか? 長年のシューズ生活によってそれらの機能は失われるのでしょうか? 設計的スタンス VS 物理的スタンス 何かを説明する時、最も“科学的”な方法として、設計的スタンスよりも物理的スタンスの方が好まれる傾向があります。これには、客観的測定や正確な説明、顕微鏡などのかっこいい技術が含まれます。分析のこの段階で、たいへん興味深い物理的事象が起こることが分かります。たとえば、負荷に反応する筋膜の変化や、微小外傷を負っている椎間板、反復性の屈曲による炎症などは顕微鏡で把握することができます。たしかに、身体のごく微小な変化はとても興味深いものですが、もっと広く全体として捉えると、それが意味することを推定するのは困難です。 これらの事実は、筋膜はフォームローラーによって溶かすことができるということを意味するのでしょうか? また、私たちは脊柱をできる限りニュートラルに保って生活しなければならないということを意味するのでしょうか? 物理的スタンスから集められるエビデンスは、このような訴えを支持してくれるように見える一方で、設計的スタンスはそれらが現実的であるかをチェックする役割をしてくれます。筋膜の機能のひとつは、身体の安定化を提供することですから、硬いものに数分間当てるたびに、筋膜が溶けてしまうというのは、意味が通りませんね。背中には24の関節があります―― 動くために設計されたもののように見えます! もし、その役割がいつでも真っすぐに保っていることであれば、大腿骨のような形状をしていたでしょう。このように、顕微鏡から収集されるエビデンスは、とても興味深くはあるものの、そこから導かれるすべての結論は、もっと高いレベルの見地から見ても理屈が通るかどうか慎重である必要があります。
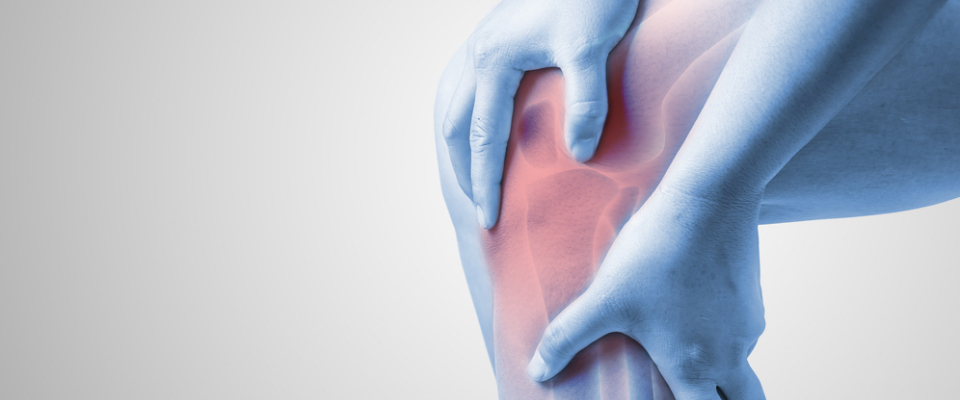
多くの整形外科手術は効果がない パート2/2
(パート1はこちらへ) 腰部の手術 膝同様に、腰部にかなり大きな構造的損傷がありつつも痛みを伴わないことに関する豊富なエビデンスは存在しています。更に、腰部には特に明白な損傷がない時であっても痛みも持つこともあります。事実、これはかなりよく見られることであり、慢性腰痛のほとんどは、“非特異的”と識別される、つまり、その痛みは力学的または構造的な要因では説明できないということを意味しています。腰痛と腰部の構造的損傷間には、あまり関連性がないにも関わらず、MRIに現れたあらゆる損傷を修正するための手術は数多く存在します。手術は保存療法よりも優れているわけではありませんが。 例えば、椎体形成術は骨折した椎骨に骨のセメントを注入することで腰痛を治療しようと試みるものです。2003年に出版された研究では、手術後6週間において、全く治療を行わなかったと同様の効果を表したことを示しています。(8) 2009年、骨粗鬆症に関連する骨折への偽手術と同程度の効果があったことを2つの研究が報告しています。(9) 腰椎固定術は、一般的な術式であり、神経のような感受性の高い構造との接触をすることのないように、椎骨を安定させることを意図したものです。2013年、Spine journal は、認識的行動セラピーやエクササイズのような手術以外の治療と脊椎固定術を比較した研究論文を出版しました。この研究では、長期的な結果における差異がないことを発見しており、保存的療法やエクササイズに対して“慢性腰痛患者への腰椎固定術の適用は好意をもたれるべきではない。”と結論づけています。(10) 2014年のあるメタ分析は下記のように結論づけています: 腰椎の変性疾患を持つ患者の、慢性腰椎による認識された身体不全の低減において、腰椎固定術が保存的療法よりも効果的ではないという強力なエビデンスが存在する。この題材に関するさらなる研究が、この結論に考慮するほどの影響を与えることはないであろう。 (11) 膝の手術に関して、手術の相対的な効果の低さを示す研究結果が実践に影響を与えるのには時間がかかっています。国際的に著名な解剖学者であり、疼痛専門家であるニコライ・バグダックは、次のように説明しています: 外科医その他は、手術が腰痛に効果的であると信じている。彼らのこの信念は、自らの経験、あるいは主観的研究に基づいたものである。この信念は、おおむね詳細に報告された臨床実験の結果に立証されているものではない。これらの臨床実験は、手術の効果を得られている患者は一部であることを表示している。 (12) 肩の手術 肩の手術に関する研究は、同様の(しかし多少明確性にかける)パターンを示しています。MRIが一貫して示すのは、痛みを持たない多くの人たちにおいて、回旋腱板損傷や、肩の構造の損傷がみられるということです。この事実にも関わらず、肩の痛みを説明する一般的な診断は、回旋腱板損傷あるいは、肩峰による回旋腱板の“インピンジメント”を含んでいます。 これらの状態を修復するための手術は、回旋腱板修復、あるいは肩峰の一部を切除する肩峰形成術を含みます。アメリカ合衆国において、これらの手術は、毎年ほぼ50万件近く行われていますが、これらのうちのほとんどは外傷ではなく変性による損傷です。(13) これらの手術は、エクササイズや休息よりも効果的なのでしょうか?これに関するエビデンスは、腰部や膝と比較して明確さに劣りますが、これらの手術に本当に効果があるのか、そして良い結果は、肩にメカニカルな変化を与えたことに関連があるのか、といった深刻な疑問が生まれています。 特定の患者達に対して、手術はエクササイズよりもかなり有意に効果的であるという可能性を認めないわけにはいきませんが、(14)いくつもの研究が肩峰形成術のような一般的な肩の手術が、エクササイズよりも効果的であるとはいえないことを発見しています。(15) さらに、関節唇修復および二頭筋腱固定術は、偽手術より優れているわけではないことも示されています。(16) また、手術が痛みの緩和に効果的であるのは、実際の構造修復のためではないことを示唆するエビデンスも存在します。(17) 修復された手術の一年後に撮影された回旋腱板のMRIは、多くの場合、患者の回復にも関わらず、再び断裂している状態を示します。Dr.ローレンス・ガロッタによれば、“回旋腱板が損傷している時、全ての痛みと機能不全は回旋腱板の損傷に起因すると考えるが、その損傷を修復し状態が良くなったと感じる場合でも、時に、超音波やMRIを撮ってみると、回旋腱板は、手術前と全く同じ状態である。”(18) British Journal of Sports Medicineの 掲載されているブログ投稿は、この状況を次のように要約しています:“近年のエビデンスに基づけば、[肩の痛み]の治療としての手術的介入の効果は、見せかけの過大評価されたもののようである。”(19) 結論 はっきりとさせておきたいのですが:上記の内容は、私たちが整形外科医を信頼すべきでないとか、手術は慢性疼痛の治療として決して良いアイデアではないということを意味していると解釈されるべきものではありません。数多くの手術が効果を証明しており、特定の状況においては確実に優れたアイデアです。私は個人的に、担当の外科医から現在のエビデンスの状況、そして様々なアプローチの良い点と悪い点に関する優れた倫理的なアドバイスを受け取った人たちを数多く知っています。そしてまた、慢性痛に対しての手術的介入の劇的な効果をはっきりと得ることができた人たちも数多く知っています。一方で、私はまた、効果的でないことが証明されている手術を受け、関連のある研究に関するアドバイスをもらえず、最終的に良い結果を得ることができなかった人たちも数多く知っています。 ここで覚えておくべき主なポイントは、医学界において、慢性痛の治療の方法に関するいくつかの大きな盲点や偏見が存在するということです。疼痛の説明と治療を、より重要である複合的な神経生理学を無視して、常に単純な構造の“不全”に言及することに求めようとしています。臨床家は、これらの偏見に気づき、その治療方法を改善することを助けることができるように、疼痛の複合性に関してできる限り学習すべきです。そして慢性痛の患者達は、手術を受ける前に担当の外科医に、いくつかの良い質問を問いかけるべきなのです。 参照文献 8. Diamond, Terrence H, Bernard Champion, and William A Clark. 2003. “Management of Acute Osteoporotic Vertebral Fractures: A Nonrandomized Trial Comparing Percutaneous Vertebroplasty with Conservative Therapy.” The American Journal of Medicine 114 (4): 257–65. doi:10.1016/S0002-9343(02)01524-3. 9. Kallmes, David F., Bryan A. Comstock, Patrick J. Heagerty, Judith A. Turner, David J. Wilson, Terry H. Diamond, Richard Edwards, et al. 2009. “A Randomized Trial of Vertebroplasty for Osteoporotic Spinal Fractures.” New England Journal of Medicine 361 (6): 569–79. doi:10.1056/NEJMoa0900563. 10. Mannion, Anne F., Jens Ivar Brox, and Jeremy C.T. Fairbank. 2013. “Comparison of Spinal Fusion and Nonoperative Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain: Long-Term Follow-up of Three Randomized Controlled Trials.” The Spine Journal 13 (11): 1438–48. doi:10.1016/j.spinee.2013.06.101. 11. Saltychev, Mikhail, Merja Eskola, and Katri Laimi. 2014. “Lumbar Fusion Compared with Conservative Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain.” International Journal of Rehabilitation Research 37 (1): 2–8. doi:10.1097/MRR.0b013e328363ba4b. 12. Bogduk, Nikolai, and Gunnar Andersson. 2009. “Is Spinal Surgery Effective for Back Pain?” F1000 Medicine Reports 1 (July): 27–29. doi:10.3410/M1-60. 13. Jain, Nitin B, Laurence D Higgins, Elena Losina, Jamie Collins, Philip E Blazar, and Jeffrey N Katz. 2014. “Epidemiology of Musculoskeletal Upper Extremity Ambulatory Surgery in the United States.” BMC Musculoskeletal Disorders 15 (1): 4. doi:10.1186/1471-2474-15-4. 14. Steuri, Ruedi, Martin Sattelmayer, Simone Elsig, Chloé Kolly, Amir Tal, Jan Taeymans, and Roger Hilfiker. 2017. “Effectiveness of Conservative Interventions Including Exercise, Manual Therapy and Medical Management in Adults with Shoulder Impingement: A Systematic Review and Meta-Analysis of RCTs.” British Journal of Sports Medicine, bjsports-2016-096515. doi:10.1136/bjsports-2016-096515. 15. Ketola, S., J. Lehtinen, T. Rousi, M. Nissinen, H. Huhtala, Y. T. Konttinen, and I. Arnala. 2013. “No Evidence of Long-Term Benefits of Arthroscopicacromioplasty in the Treatment of Shoulder Impingement Syndrome: Five-Year Results of a Randomised Controlled Trial.” Bone and Joint Research 2 (7): 132–39. doi:10.1302/2046-3758.27.2000163. 16. Brox, Jens Ivar, Cecilie Piene Schrøder, Øystein Skare, Petter Mowinckel, and Olav Reikerås. 2017. “Author Response—sham Surgery versus Labral Repair or Biceps Tenodesis for Type II SLAP Lesions of the Shoulder: A Three-Armed Randomised Clinical Trial.” British Journal of Sports Medicine, bjsports-2017-098251. doi:10.1136/bjsports-2017-098251. 17. McElvany, Matthew D., Erik McGoldrick, Albert O. Gee, Moni Blazej Neradilek, and Frederick A. Matsen. 2015. “Rotator Cuff Repair.” The American Journal of Sports Medicine 43 (2). SAGE PublicationsSage CA: Los Angeles, CA: 491–500. doi:10.1177/0363546514529644. 18. Large Study of Arthroscopic Rotator Cuff Repair Reveals Some Surprises. http://www.hss.edu/newsroom_study-arthroscopic-rotator-cuff-repair-surprises.asp 19. “Unnecessary Shoulder Surgery on the Rise - BJSM Blog - Social Media’s Leading SEM Voice.” Accessed October 18. http://blogs.bmj.com/bjsm/2015/01/06/the-sexy-scalpel-unnecessary-shoulder-surgery-on-the-rise/.
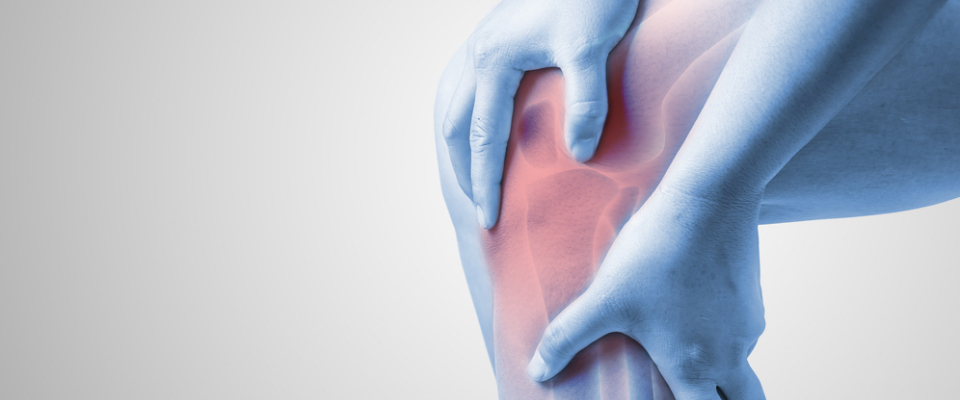
多くの整形外科手術は効果がない パート1/2
(パート2はこちらへ) 薬とは異なり、整形外科手術は、その安全性と効果を確信するための厳密なテストを実施する前に一般大衆に提供されています。それゆえに、何百万件もの膝や肩、腰痛のための手術が、その実際の効果を確認するリサーチを行うこともないまま、実施されてしまっています。最近では、こういったリサーチが数多く実施されており、人気のある手術の多くがプラセボ同様であることが明らかにされています。にもかかわらず、これらの手術の多くは現在でもまだ、年間何百件も何千件も実施され続けているのです。 そう、がっかりしてしまうことですが、これは、もしあなたが慢性痛を治療する仕事に関わっていたり、あるいは慢性痛を患っていて手術を検討しているのであれば、知っておくべきことです。関連性のあるリサーチの総論をお読みください(ところで、下記の内容のほとんどは、近日中に出版される私の著書, Playing With Movement からの抜粋となります)。 膝の手術 膝の関節炎はよくみられるものですが、必ずしも疼痛という結果になるわけではありません。重症の関節炎を持っていても全く痛みのない人たちも多く存在しています。そして、膝に痛みを抱える人たちの多くは関節炎を患っていません。こうした関連性の低さにも関わらず、関節炎のための手術はかなり普及しており、その数は年間50万件にものぼります。(1) 15年ほど前に最も一般的であった膝の関節鏡手術は、創面切除術(損傷した軟骨や骨の切除)と洗浄(生理食塩水による洗浄)の2つでした。これらの手術の目指すゴールは関節に炎症を起こしているかもしれない軟骨の粗い断片を取り除くことです。手術の効果は、それほど目覚ましいものではなく、人々は、これらはプラセボに起因しているのではないか?あるいは、エクササイズや理学療法、休息といったより侵害性の低い治療でも効果は得られるのではないか?と考え始めました。 この可能性をテストするために、研究者たちは“偽”手術を取り入れた研究を指揮したのです:あるグループの患者たちは実際に膝の手術を受け、もう一つのグループは、皮膚を切開するのみの偽の手術を受けました。患者たちは、自分が受けたのが実際の手術かを知る由はありません。2~3年間に数回にわたって、これら2つのグループの患者たちは膝の痛みのレベルと膝の機能に関して報告を行いました。どうだったと思いますか?期間内のどのポイントにおいても、偽手術のグループは、実際に手術を受けたグループと同様にうまくいったのです。(2)これは、手術は身体構造ではなく心理学を変えることによって効果があるということを強く示唆しています。 この研究は手術が役に立たないことを効果的に証明したにも関わらず、外科医たちの行動に影響を与えるのには遅延がみられました。それから何年もの間にわたり年間30億円の費用をかけて何百、何千という数のこれらの手術が行われています。(3)これに続く研究では、この手術が、エクササイズ、体重減、市販の痛み止めの使用など、一般常識的介入より優れた効果を提供しないことが確認されています。(4) 創面切除術と洗浄は、あまり一般的ではなくなってきましたが、関節鏡半月板一部切除と呼ばれる術式がこれに取って代わりました。しかし先行の術式同様、この新しい手術も偽手術と同程度の効果しか報告されていません。 2015年、研究者達は膝の関節鏡手術に関する9つの研究論文の結果を要約し、これらの手術は効果があるとすれば少しであり、深刻な悪影響の可能性を持つという結論に達しました。(5) 最近のBritish Journal of Medicine の声明では、膝の痛みに対する関節鏡手術は“手術を支持する中庸の質のエビデンスさえ存在しない、かなり疑問視されるべき行為である”という批判的意見を提供しています。(6) 2017年のある臨床ガイドラインは、次のように述べています:“我々は変性膝疾患を患う患者のほぼ全てに対して、関節鏡手術の使用をすべきではないという勧告をする。さらなる研究がこの勧告を修正することはないであろう。”(7) この抵抗し難い研究結果にもかかわらず、アメリカにおいて関節鏡膝手術は、各年700,000件近く行われる最も一般的な手順であり続けています。(6) なぜこのようなことが起こり得るのでしょうか?単純な答えは、多くの医師達が研究よりも自らの個人的な経験を信頼しているからです。彼らは、保存療法が失敗し続けた後に、手術が劇的な効果を提供したと言うでしょう。これは時に起こることではあるでしょうが、私達は、痛みの起因が膝の構造的変化であることに関してかなり懐疑的であるべきです。慢性的な膝痛の成功する治療は、それが手術であれ、何か他のことであれ、関節の構造を修正することではなく、心理学的あるいは神経学的過程に複合的な変化を生み出すことにあるのではないでしょうか。このポイントは、腰部の手術が、腰痛への純粋に心理学的な介入よりもより大きな効果を与えることがないという発見をした同様の研究によって強く確認をされています。 参照文献 1. Heidari, Behzad. 2011. “Knee Osteoarthritis Prevalence, Risk Factors, Pathogenesis and Features: Part I.” Caspian Journal of Internal Medicine 2 (2): 205–12. 2. Lubowitz, James H. 2002. “A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee.” Arthroscopy 18 (8): 950–51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12368798. 3. Why ‘Useless’ Surgery Is Still Popular. http://www.nytimes.com/2016/08/04/upshot/the-right-to-know-that-an-operation-is-next-to-useless.html?_r=2 4. Kirkely, Birmingham, et al. 2008. “A Randomized Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee." New England Journal. Vol. 359, 1097. 5. Thorlund, J. B., C. B. Juhl, E. M. Roos, and L. S. Lohmander. 2015. “Arthroscopic Surgery for Degenerative Knee: Systematic Review and Meta-Analysis of Benefits and Harms.” Bmj 350 (jun16 3): h2747–h2747. doi:10.1136/bmj.h2747. 6. Järvinen, Teppo L N, and Gordon H Guyatt. 2016. “Arthroscopic Surgery for Knee Pain.” BMJ (Clinical Research Ed.) 354 (July). British Medical Journal Publishing Group: i3934. doi:10.1136/BMJ.I3934. 7. Siemieniuk, Reed A C, Ian A Harris, Thomas Agoritsas, Rudolf W Poolman, Romina Brignardello-Petersen, Stijn Van de Velde, Rachelle Buchbinder, et al. 2017. “Arthroscopic Surgery for Degenerative Knee Arthritis and Meniscal Tears: A Clinical Practice Guideline.” Bmj, j1982. doi:10.1136/bmj.j1982.
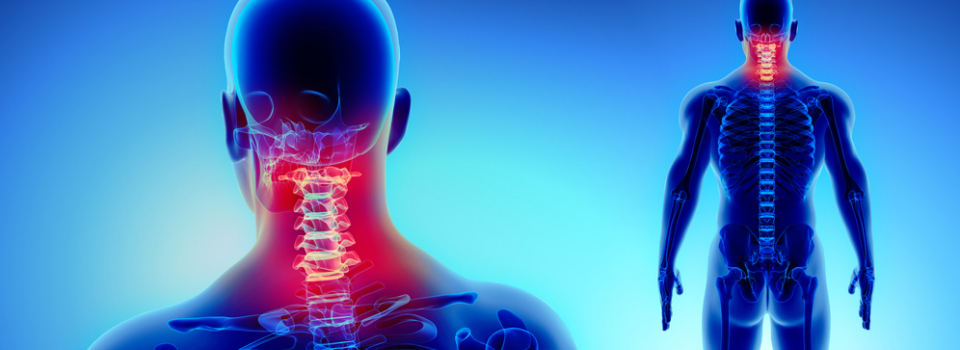
痛みの科学と身体力学についての本当の真実:批判への対応 パート2/2
3. 姿勢は、痛みを誘発する要因として過度に強調されてきました。 姿勢のアライメント測定と痛みの関連性を見つけようとする大規模な調査がありましたが、ほとんど何も見つけることはできませんでした。私が手がけている本、『Playing With Movement(動きと遊ぶ)』(近日リリース!) から抜粋したものを紹介します。ここでは、30年以上の研究からの調査をまとめてあります: 脚長差と腰痛の関連性はない。(Grundy 1984) 重度の腰痛、中度の腰痛、腰痛なしの321人の男性において、腰椎前弯の程度や脚長差に違いはない。(Pope 1985) 45歳以上の107人において、頚部痛と頚椎の弯曲に関連性はない。(Grob 2007) 腰痛を持つまたは持たない600人の被験者において、腰椎の弯曲、骨盤の傾き、脚長差、腹筋やハムストリング、腸腰筋の長さに顕著な差はない。(Nourbaksh 2002) 胸椎や腰椎の弯曲亢進があり姿勢に左右非対称のある10代の若者が、大人になってから腰痛を発症する可能性は“より良い”姿勢の同年代と比べて高いわけではない。(Dieck 1985) 腰椎の前弯が亢進している妊婦が、腰痛を発症する可能性は高いわけではない。(Franklin 1998) 10件の研究のレビューでは、胸椎後弯と肩の痛みには関連性がないことが発見された。(Barrett 2016) 頭部前方位で猫背の10代に、頚部痛が多く見られることはなかった(しかし、鬱であることは多かった)。(Richards 2016) 腰痛と脊椎分離すべり症(脊椎が前方に滑り、たいてい固定手術で治療される)には関連性がない。(Andrade 2015) 年齢65-91歳の女性において、顕著な胸椎後弯があっても腰痛や行動に困難が多いということはなかった。(Ettinger 1994) 理学療法士が指摘するような“スマホ頚椎”と頚部痛には関連性がない。(Damasceno 2018) 人間工学に基づいたプログラムは、頚椎症の将来的な発症リスクを減らさないが、エクササイズは半分までリスクを減少する。(Campos 2018) 脊柱のアライメント測定と痛みの関連性を肯定する研究がいくつかありますが、規則の例外とも言え、関連性は比較的低いとされています(Chaelat-Velayer 2011; Smith 2008)。エビデンスの重要性は、恐らく、痛みと姿勢の関連性を扱った54件もの研究に対して2008年に行われたシステマティックレビューに表れているかもしれません。同時に、ここでは矢状面における脊柱アライメントの測定と痛みの関連性を支持するエビデンスは提示されませんでした(Christensen 2008)。腰痛の側彎症との関連性はあるにしても、これは比較的顕著な側方への非対称を呈する病状であり、人口の98パーセントには存在しません(Theroux 2015)。 さらに、関連のある研究として、悪いとされる姿勢や負荷が多いと考えられている姿勢を反復して行う職業の影響を調べたものがあります。これらの見解は: 職場で座っていることは腰痛と関係がない。(Hartvigsen 2010) 重いものを持ち上げる作業をしなくてならない職業が腰痛を引き起こすことはないだろうと、35件の研究におけるシステマティックレビューが示した。(Wai 2010) 妙な姿勢、荷物の持ち上げ作業、曲げたり捻ったりする作業を伴う職業と腰痛の間に因果関係を示す十分なエビデンスはないと、99件の研究におけるシステマティックレビューが示した。(Kwon 2011) 日常的に重いものを持ち上げる作業を伴うような職業は、腰痛のリスクを高くすると関連付けられているが、その影響はわずかである。(Waddell 2001) 上記の研究は、姿勢と痛みの間に何らかの関連性が存在したとしても、その関連性は低いということを示しています。さらに、もし姿勢と痛みの関連性が実際存在したとしても、これでは因果関係を証明することにはならないでしょう。痛みがあるから悪い姿勢になるのかもしれませんし、何か原因不明な要因がこれら両方を引き起こすのかもしれません。これはとても説得力があります。腰痛を誘発する液体を注射された人は、不快感を避けるために無意識のうちに異なる姿勢をするようになります(Hodges 2003)。他にもまだ立証されていないこととして、姿勢は矯正することができ、矯正によって痛みの軽減に役立つかということがあります。 これは、姿勢は痛みに全く関係がないということを意味しているのでしょうか? いいえ、痛みの科学の教育者たちはそれを認める準備ができているでしょう。たとえば、痛みをコントロールできると期待している様々な要因を示しているグレッグ・リーマンのワークブックからの図がここにあります。姿勢もこの中の一つであることに注目してください。しかし、重要なのは、それが数多くの要因の一つにすぎないということです。 溢れているカップ:信念、姿勢、睡眠、習慣、組織の健康、心配、ストレス、恐れカップを大きく作り直すか、カップの中身を減らすか。つまり:落ち着かせ、作り直す。 4. 生体力学は複雑で“修正”は容易ではない 痛みの科学が、物理学の基本的法則を覆すことはありません。したがって、高負荷下で悪い技術での運動は、明らかに深刻なケガにつながります。しかし、座ったり立ったり、呼吸をしたり、曲げたり、物を取ったりといった低負荷下であっても日々の習慣的な運動パターンによって慢性腰痛になる可能性があるのかといった疑問が残ります。これらは反復性のストレスを与えたりやケガを引き起こしたりするのでしょうか?または、エクササイズでのストレスに私たちの身体が適応していくのと同じように、定期的に遭遇するストレスにも対処できるよう、私たちは単に適応していくのでしょうか? 上記で論じられている姿勢についての研究と同様、大規模な研究を参考にしながら解決するのが最善策でしょう。次のように示しています: 一般的に機能不全と言われている運動パターンは、痛みや怪我のリスクの増加と関連性はない; ある特定の機能不全を修正することに重点を置いた治療は、たいてい一般的なエクササイズより優れているわけではない;そして 修正することに重点を置いた方法は、“修正”がされていなくても良い結果が出ることがある。つまり、これらの方法は何らかの他のメカニズムによって効果が出ることを示している。 たとえば、腰痛のための一般的なエクササイズでも、安定化エクササイズや運動制御エクササイズと同じぐらい効果があります(Smith 2014; Ferreira 2007; Saragiotto 2016.)。これは、診断された特定の動きの“障害”を修正しようとする治療であっても同様です(Riley 2018, Dillen 2016, Azevedo 2018)。 肩においても似たようなパターンが見られます。一般的なストレッチやストレングスは、 肩甲骨の“運動障害”を修正するための 運動制御エクササイズと同程度効果があります。さらに、運動パターンに変化がなくても、運動制御プログラムで改善します。つまり、有効成分は、単にエクササイズをするということで、協調性の欠如を修正することではないことを示しています(Camargo 2015, McClure 2005, Timmons 2012, Ratcliffe 2014, Struyf 2013を参照)。たとえば、Struyf 2013では、機能不全と言われている肩甲骨の運動パターンのほとんどは、 恐らく“正常な運動の変動性”を示しているのではないかと結論付けています。 膝の痛みに最も有効な治療は、単純に膝と股関節周辺の筋群を強化することのようです。たとえそれがニーエクステンションマシーンで行う“機能的でない”エクササイズといわれるもので行われたとしても同様です(Willy 2016, Rabelo 2018)。 シードマンは、正常に機能していない運動パターンを修正することの重要性について延々と論じていますが、彼の記事ではどのようなパターンを指しているのか、それをどうやって評価し修正するのか明確にしていません。腰痛のために臀筋とコアの強化が重要であると、漠然と言及しているのですが、この問題における研究をひとつも引用していません。事実、平均するとコアの強化の効果は一般的な腰痛のためのエクササイズより優れているとは限りません(Lederman)。さらに、不活発な臀筋群が痛みを引き起こすと言った考え方は、研究によって十分に裏付けされていません。研究では、たいてい痛みは、臀筋の活動の少なさではなく多さとの関係が深いと示しています。 (Kim 2014, Lehman 2006, Suehiro 2015, Dwyer 2013)。 ここでの教訓は、動きと痛みの関係は複雑だということです。エクササイズで痛みを軽減でき、機能を改善し、怪我の予防に役立つことには疑う余地はありません。しかし、“機能不全”の評価やその修正、そして、それらの日常の動きで起きる痛みとの関係について、私たちは懐疑的であるべきです(Tuminello 2017)。 5. 炎症 シードマンは、痛みの科学者たちは痛みにおける炎症の役割について無視していると言っています。ここで彼が何を意味しようとしているのか私には想像がつきません。侵害受容器を感作させる炎症の役割は、痛みの生理学において最も基本的な事実のひとつです。また、それは痛みの教育の重要な原理を説明しています—疼痛感受性は、組織損傷の状況が変わらなくても、変化します。 非常に長期にわたる慢性的な炎症は、健康不良、疼痛、歩行パターンの機能低下、歩行スピードの減速、筋力や安定性、運動性などの低下につながるとシードマンは述べています。これは驚くべきことでもありません。もし、健康不良で、しかも深刻な炎症があったとしたら、当然、そのような人が上手く動けるはずはなく気分も良くないことは想像できます。シードマンが引用しているエビデンスは、このような分かりきった関連性を示していますが、その炎症が不良姿勢や運動パターンが原因であるとは示していません。もしそうであるのなら、研究が姿勢と痛みの関係を簡単に発見したことでしょう。しかし、未だ発見されていないのです。 結論:痛みの重要性の真実 この情報を正しく把握することが非常に重要であると私は思います。慢性疼痛は、世界的にも最も大きな健康問題です。これを治す特効薬はないのですが、科学を通してより理解を深め、人々に運動をさせることで進歩できることを何よりも期待しています。この両方を行える絶好の立場にいるのがパーソナルトレーナーです。まだ多くのことが解明していません。前進するためにも健全な批評が必要です。私たちは行動に移すための十分な知識を兼ね揃えていますが、ここにはまだ慣行と確立された証拠との間の大きなギャップがあり、私達はそれを埋めていく必要があるのです。 参照 O’Sullivan, P. B., Caneiro, J. P., O’Keeffe, M., Smith, A., Dankaerts, W., Fersum, K., & O’Sullivan, K. (2018). Cognitive Functional Therapy: An Integrated Behavioral Approach for the Targeted Management of Disabling Low Back Pain. Physical Therapy, 98(5), 408–423. Melzack, R. (2010). Pain and the neuromatrix in the brain. Journal of Dental Education, 65(12), 1378–1382. Brinjikji, W., F. E. Diehn, J. G. Jarvik, C. M. Carr, D. F. Kallmes, M. H. Murad, and P. H. Luetmer. 2015. “MRI Findings of Disc Degeneration Are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis.” American Journal of Neuroradiology 36 (12). Lederman, E. (2011). The fall of the postural-structural-biomechanical model in manual and physical therapies: Exemplified by lower back pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(2), 131–138. Foster, N. E., Anema, J. R., Cherkin, D., Chou, R., Cohen, S. P., Gross, D. P., … Woolf, A. (2018). Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. The Lancet, 391(10137), 2368–2383; Riley, S. P., Swanson, B. T., & Dyer, E. (2018). Are movement-based classification systems more effective than therapeutic exercise or guideline based care in improving outcomes for patients with chronic low back pain? A systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 1–10. O’ Sullivan, P., & Caneiro, J. P. (2016). Unraveling the Complexity of Low Back Pain. J Orthop Sports Phys Ther 2016;46(11):932-937. Smith, B. E., Littlewood, C., & May, S. (2014). An update of stabilisation exercises for low back pain: A systematic review with meta-analysis. BMC Musculoskeletal Disorders, 15(1); Ferreira, M. L., Ferreira, P. H., Latimer, J., Herbert, R. D., Hodges, P. W., Jennings, M. D., … Refshauge, K. M. (2007). Comparison of general exercise, motor control exercise and spinal manipulative therapy for chronic low back pain: A randomized trial. Pain, 131(1–2), 31–37. Marcuzzi, A., Wrigley, P. J., Dean, C. M., Graham, P. L., & Hush, J. M. (2018). From acute to persistent low back pain: a longitudinal investigation of somatosensory changes using quantitative sensory testing — an exploratory study. Pain reports, 3, 1–10. Louw, A., Zimney, K., Puentedura, E. J., & Diener, I. (2016). The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. Physiotherapy Theory and Practice, 3985(September). Borenstein, D G, J W O’Mara, S D Boden, W C Lauerman, A Jacobson, C Platenberg, D Schellinger, and S W Wiesel. 2001. “The Value of Magnetic Resonance Imaging of the Lumbar Spine to Predict Low-Back Pain in Asymptomatic Subjects : A Seven-Year Follow-up Study.” The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume 83–A (9): 1306–11. Connor, Banks et al. (2003) Magnetic Resonance Imaging of the Asymptomatic Shoulder of Overhead Athletes. A 5-Year Follow-up Study. Am J Sports Med September 2003, Vol. 31, No. 5, 724–727. Hill, A. L., Aboud, D., Elliott, J., Magnussen, J., Steffens, D., & Hancock, M. (2018). Recover Injury Research Centre and Centre of Research Excellence in Recovery Following Surgical Outcomes Research Centre ( SOuRCe ), Royal Prince Alfred Hospital , Sydney. The Spine Journal. Tonosu, Juichi, Hiroyuki Oka, Akiro Higashikawa, Hiroshi Okazaki, Sakae Tanaka, and Ko Matsudaira. 2017. “The Associations between Magnetic Resonance Imaging Findings and Low Back Pain: A 10-Year Longitudinal Analysis,” 1–10. Grundy, P F, and C J Roberts. 1984. “Does Unequal Leg Length Cause Back Pain? A Case-Control Study.” Lancet (London, England) 2 (8397): 256–58. Pope, M H, T Bevins, D G Wilder, and J W Frymoyer. 1985. “The Relationship between Anthropometric, Postural, Muscular, and Mobility Characteristics of Males Ages 18-55.” Spine 10 (7): 644–48. Grob, D., H. Frauenfelder, and A. F. Mannion. 2007. “The Association between Cervical Spine Curvature and Neck Pain.” European Spine Journal 16 (5): 669–78. Nourbakhsh, M R, and A M Arab. 2002. “Relationship between Mechanical Factors and Incidence of Low Back Pain.” The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 32 (9): 447–60. Dieck, G S, J L Kelsey, V K Goel, M M Panjabi, S D Walter, and M H Laprade. 1985. “An Epidemiologic Study of the Relationship between Postural Asymmetry in the Teen Years and Subsequent Back and Neck Pain.” Spine 10 (10): 872–77. Franklin, Mary E., and Teresa Conner-Kerr. 1998. “An Analysis of Posture and Back Pain in the First and Third Trimesters of Pregnancy.” Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 28 (3): 133–38. Barrett, Eva, Mary O’Keeffe, Kieran O’Sullivan, Jeremy Lewis, and Karen McCreesh. 2016. “Is Thoracic Spine Posture Associated with Shoulder Pain, Range of Motion and Function? A Systematic Review.” Manual Therapy 26 (December): 38–46. Richards, K. V., D. J. Beales, A. J. Smith, P. B. O’Sullivan, and L. M. Straker. 2016. “Neck Posture Clusters and Their Association With Biopsychosocial Factors and Neck Pain in Australian Adolescents.” Physical Therapy 96 (10). Oxford University Press: 1576–87. Andrade, Nicholas S., Carol M. Ashton, Nelda P. Wray, Curtis Brown, and Viktor Bartanusz. 2015. “Systematic Review of Observational Studies Reveals No Association between Low Back Pain and Lumbar Spondylolysis with or without Isthmic Spondylolisthesis.” European Spine Journal 24 (6). Springer Berlin Heidelberg: 1289– 95. Ettinger, B, D M Black, L Palermo, M C Nevitt, S Melnikoff, and S R Cummings. 1994. “Kyphosis in Older Women and Its Relation to Back Pain, Disability and Osteopenia: The Study of Osteoporotic Fractures.” Osteoporosis International .4 (1): 55–60. Damasceno, Gerson Moreira, Arthur Sá Ferreira, Leandro Alberto Calazans Nogueira, Felipe José Jandre Reis, Igor Caio Santana Andrade, and Ney Meziat-Filho. 2018. “Text Neck and Neck Pain in 18–21-Year-Old Young Adults.” European Spine Journal 27 (6). Campos, Tarcisio F de, Chris G Maher, Daniel Steffens, Joel T Fuller, and Mark J Hancock. 2018. “Exercise Programs May Be Effective in Preventing a New Episode of Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Journal of Physiotherapy 64 (3). Netherlands: 159–65. Chaléat-Valayer, Emmanuelle, Jean-Marc Mac-Thiong, Jérôme Paquet, Eric Berthonnaud, Fabienne Siani, and Pierre Roussouly. 2011. “Sagittal Spino-Pelvic Alignment in Chronic Low Back Pain.” European Spine Journal 20 (S5): 634–40. Smith, Anne, Peter OʼSullivan, and Leon Straker. 2008. “Classification of Sagittal Thoraco-Lumbo-Pelvic Alignment of the Adolescent Spine in Standing and Its Relationship to Low Back Pain.” Spine 33 (19): 2101–7. Christensen, Sanne Toftgaard, and Jan Hartvigsen. 2008. “Spinal Curves and Health: A Systematic Critical Review of the Epidemiological Literature Dealing With Associations Between Sagittal Spinal Curves and Health.” Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 31 (9): 690–714. Théroux, Jean, Sylvie Le May, Carole Fortin, and Hubert Labelle. 2015. “Prevalence and Management of Back Pain in Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients: A Retrospective Study.” Pain Research & Management : The Journal of the Canadian Pain Society 20 (3). Pulsus Group Inc: 153–57. Hartvigsen, Jan, Charlotte Leboeuf-Yde, Svend Lings, and Elisabeth H Corder. 2002. “[Does Sitting at Work Cause Low Back Pain?].” Ugeskrift for Laeger 164 (6): 759–61. Wai, Eugene K., Darren M. Roffey, Paul Bishop, Brian K. Kwon, and Simon Dagenais. 2010. “Causal Assessment of Occupational Lifting and Low Back Pain: Results of a Systematic Review.” The Spine Journal 10 (6): 554–66. Kwon, B. K., D. M. Roffey, P. B. Bishop, S. Dagenais, and E. K. Wai. 2011. “Systematic Review: Occupational Physical Activity and Low Back Pain.” Occupational Medicine 61 (8): 541–48. Waddell, G., Burton, A.K., Mar 2001. Occupational health guide- lines for the management of low back pain at work: evidence review. Occup. Med. (Lond) 51 (2), 124e135 (Review). Shiri, Rahman, Jaro Karppinen, Päivi Leino-Arjas, Svetlana Solovieva, and Eira Viikari-Juntura. 2010. “The Association between Smoking and Low Back Pain: A Meta- Analysis.” The American Journal of Medicine 123 (1): 87.e7-87.e35. Hoogendoorn, W E, M N van Poppel, P M Bongers, B W Koes, and L M Bouter. 2000. “Systematic Review of Psychosocial Factors at Work and Private Life as Risk Factors for Back Pain.” Spine 25 (16): 2114–25. Hodges, Paul W., G. Lorimer Moseley, Anna Gabrielsson, and Simon C. Gandevia. 2003. “Experimental Muscle Pain Changes Feedforward Postural Responses of the Trunk Muscles.” Experimental Brain Research 151 (2): 262–71. Saragiotto, Bruno T, Christopher G Maher, Tie P Yamato, Leonardo O P Costa, Luciola C Menezes Costa, Raymond W J G Ostelo, and Luciana G Macedo. 2016. “Motor Control Exercise for Chronic Non-Specific Low-Back Pain.” The Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 1 (January). England: CD012004. Riley, S. P., Swanson, B. T., & Dyer, E. (2018). Are movement-based classification systems more effective than therapeutic exercise or guideline based care in improving outcomes for patients with chronic low back pain? A systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 1–10. Azevedo, Daniel Camara, Paulo Henrique Ferreira, Henrique de Oliveira Santos, Daniel Ribeiro Oliveira, Joao Victor Leite de Souza, and Leonardo Oliveira Pena Costa. 2018. “Movement System Impairment-Based Classification Treatment Versus General Exercises for Chronic Low Back Pain: Randomized Controlled Trial.” Physical Therapy 98 (1). United States: 28–39. Dillen, L., et al. 2017. Efficacy of classification-specific treatment and adherence on outcomes in people with chronic low back pain. A one-year follow-up, prospective, randomized, controlled clinical trial. Man Ther. 2016 August ; 24: 52–64 Timmons, Mark K, Chuck A Thigpen, Amee L Seitz, Andrew R Karduna, Brent L Arnold, and Lori A Michener. 2012. “Scapular Kinematics and Subacromial-Impingement Syndrome: A Meta-Analysis.” Journal of Sport Rehabilitation 21 (4). United States: 354–70. Ratcliffe, Elizabeth, Sharon Pickering, Sionnadh McLean, and Jeremy Lewis. 2014. “Is There a Relationship between Subacromial Impingement Syndrome and Scapular Orientation? A Systematic Review.” British Journal of Sports Medicine 48 (16): 1251–56. Struyf, F., J. Nijs, S. Mollekens, I. Jeurissen, S. Truijen, S. Mottram, and R. Meeusen. 2013. “Scapular-Focused Treatment in Patients with Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial.” Clinical Rheumatology 32 (1). Springer-Verlag: 73–85. Camargo, Paula R, Francisco Alburquerque-Sendin, Mariana A Avila, Melina N Haik, Amilton Vieira, and Tania F Salvini. 2015. “Effects of Stretching and Strengthening Exercises, With and Without Manual Therapy, on Scapular Kinematics, Function, and Pain in Individuals With Shoulder Impingement: A Randomized Controlled Trial.” The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 45 (12). United States: 984–97. McClure, Philip W, Jason Bialker, Nancy Neff, Gerald Williams, and Andrew Karduna. 2004. “Shoulder Function and 3-Dimensional Kinematics in People with Shoulder Impingement Syndrome before and after a 6-Week Exercise Program.” Physical Therapy 84 (9). United States: 832–48. Willy, R. W., & Meira, E. P. (2016). Current Concepts in Biomechanical Interventions for Patellofemoral Pain. International Journal of Sports Physical Therapy, 11(6), 877. Rabelo, N. D. D. A., & Lucareli, P. R. G. (2018). Do hip muscle weakness and dynamic knee valgus matter for the clinical evaluation and decision-making process in patients with patellofemoral pain? Brazilian Journal of Physical Therapy, 22(2), 105–109. Kim, Ji-Won, Oh-Yun Kwon, Tae-Ho Kim, Duk-Hyun An, and Jae-Seop Oh. 2014. “Effects of External Pelvic Compression on Trunk and Hip Muscle EMG Activity during Prone Hip Extension in Females with Chronic Low Back Pain.” Manual Therapy 19 (5). Scotland: 467–71. Lehman, Gregory J. 2006. “Trunk and Hip Muscle Recruitment Patterns during the Prone Leg Extension Following a Lateral Ankle Sprain: A Prospective Case Study Pre and Post Injury.” Chiropractic & Osteopathy 14 (February). England: 4. Suehiro, Tadanobu, Masatoshi Mizutani, Hiroshi Ishida, Kenichi Kobara, Hiroshi Osaka, and Susumu Watanabe. 2015. “Individuals with Chronic Low Back Pain Demonstrate Delayed Onset of the Back Muscle Activity during Prone Hip Extension.” Journal of Electromyography and Kinesiology : Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology 25 (4). England: 675–80. Dwyer, Maureen K, Kelly Stafford, Carl G Mattacola, Timothy L Uhl, and Mauro Giordani. 2013. “Comparison of Gluteus Medius Muscle Activity during Functional Tasks in Individuals with and without Osteoarthritis of the Hip Joint.” Clinical Biomechanics (Bristol, Avon) 28 (7). England: 757–61. Tumminello, N., Silvernail, J., & Cormack, B. (2017). The corrective exercise trap. Personal Training Quarterly, 4(1), 6–15.
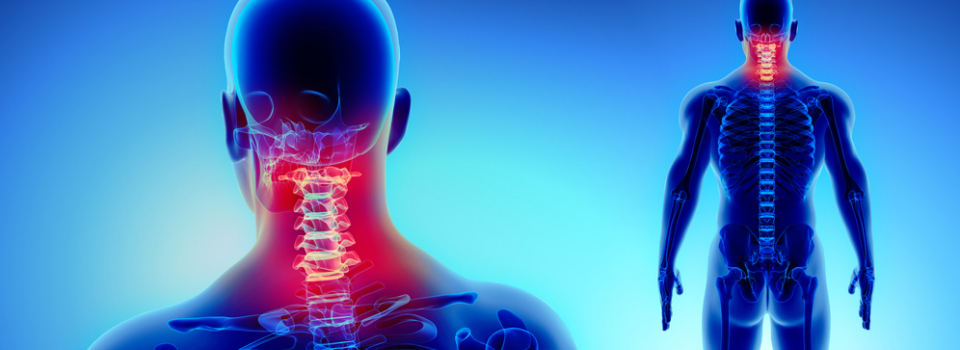
痛みの科学と身体力学についての本当の真実:批判への対応 パート1/2
パーソナルトレーナーであるジョエル・シードマンによって最近、『The Truth about Pain Science and Biomechanics:痛みの科学と身体力学についての真実』という記事が書かれました。この記事には、 “痛みの科学の専門家”と言われる人たちに対しての批判が延々と綴られています。シードマンは、こう訴えています。彼らは、運動と痛みの関係についての誤った危険な情報、たとえば、痛みはすべて頭の中にある、怪我や組織の損傷は痛みと関係がない、正しい動き方や間違った動き方は存在しない、アスリートや高重量ウェイトリフターなど高負荷がかかるような場合でもけが防止のためにわざわざ適切なテクニックで動くことを気にしないでもいいなどという情報を広めていると主張しています。 このブログの定期的な読者や痛みの科学界に詳しい人は、このような主張が明らかに正しくないことに直ぐ気がつくでしょう。しかし、この題材にあまり触れたことのない人にとって、この記事は、説得力があるのかもしれません。下記に、ロリマー・モーズリーやデビッド・バトラー、エイドリアン・ルイ、ペーター・オサリバン、グレッグ・リーマン、ベン・コーマックなど痛みの科学の教育者たちの業績をあまり目にすることのない人たちを対象に、詳細な対応をしていきます。その対象となる人たちにとって、この投稿は、ソーシャルメディアでの討論において引用したり参照したりするのに便利かもしれません。 要約 シードマンの投稿は、かなりの長文ですが、要約すると主張していることをいくつかに絞れます。こそれに対して、私はこのセクションでは簡潔に、そしてその後詳細に説明します。 主張 1 痛みの科学の専門家と言われる人たちが、痛みは “すべて頭の中”にあるもので、組織の損傷や怪我、動きのテクニックを心配する必要はないと教えているとシードマンは主張しています。これらは、藁人形論法であり、シードマンが特定の個人や引用を全く明確にしていないことを意味しています。本当のところ痛みの科学者たちはこのようなことは言っておらず、たいてい否定しています。その多くの例を下記に示します。 主張 2 痛みの科学者たちは、痛みのない人たちにも高い確率で椎間板ヘルニアや回旋腱板断裂、関節の退行変性など顕著な組織損傷が見られるというようにMRI研究を誤って解釈している、とシードマンは主張しています。シードマンは、このような人たちはいずれ将来的に確実に痛みに見舞われるだろうと主張します。しかし、いくつかの研究では、無症状の人たちに行われたMRIの結果、5年または10年先の将来的な痛みを予知することはほとんど、または全くできなかったことが判っています。 主張 3 痛み、姿勢、運動パターンの“機能不全”との相関関係は乏しいと示している研究を痛みの科学者たちが誤って解釈していると、シードマンは主張します。シードマンが引用する研究は、都合の良いものだけを選び出したに過ぎず、研究のより徹底的な調査によって得られる証拠の重要性に対抗しています。姿勢や習慣的な運動パターンは痛みと無関係ではありませんが、一般的に臨床で過剰に強調され過ぎているということなのです。 主張 4 シードマンは、痛みの科学者たちが痛みを伴う炎症の役割、つまり本来ならば異常な動きと痛みを関連付けるものを誤って把握していると主張します。疼痛感受性を伴う炎症の役割こそが痛みの生理学における最も基本的側面ですから、これはおかしな主張です。慢性的な炎症が明らかに健康不良や機能低下に関係してはいるものの、これが悪い姿勢や悪い運動パターンが原因で起こるというエビデンスはありません。 主張 5 痛みの科学の教育は、痛みを軽減する効果は中等度しかないので、メカニズムにおいて効果的な方法は、痛みを患っている人にもっと動いてもらうことかもしれません。これは、正当な主張ではあり、痛みの教育者たちの見解と一致しないことではありません。慢性疼痛に効く特効薬はなく、解決困難な問題であるかもしれないというのが痛みの教育者たちの一様な見解です。 上記の論議をさらに詳しく、広範囲の信頼性の高い引用で裏付けさせながら見ていきましょう。 1. 痛みの科学者達は、痛みがすべて頭の中の出来事であるとは指導していません。 シードマンの記事は、“痛みの科学者達”を批判していますが、それが誰なのか、またどの文献なのかを特定していません。しかし、どうやら基本的な痛みの生理学を理学療法士やカイロプラクター、ボディーワーカーやパーソナルトレーナーの人たちに教えている教育者たちを指しているようです。この教育の目的は、臨床家が治療を向上させたり、クライアントになぜ痛いのかを説明したりすることで、彼ら自身が回復に積極的に関われるようにすることです。 痛みの科学についての最も有名な情報源は、ロリマー・モーズリー(痛みの科学者であり理学療法士でもある)とデビッド・バトラー(理学療法士であり教育に関わるスペシャリスト)による『Explain Pain: 痛みの説明』という本とその関連コースです。その他にも有名な教育者でグレッグ・リーマン(理学療法士でもありカイロプラクターでもある。スチュワード・マックギルの元で学んだ元生体力学研究者)がいます。リーマンは、“Reconciling Pain Science and Biomechanics(痛みの科学と生体力学の和解)”というコースを教えています。私は、これらすべてのコースに参加しました。そして、私も時折同じようなコースを教えたり、痛みの科学のカンファレンスで講演したりします。そして、同じような題材を扱った『A Guide to Better Movement(より良い動きのための手引)』という本の著者でもあります。そのようなことから、痛みの教育者たちが発信しようとしているメッセージに直接触れる機会があるのです。そこで私たちが考える皆さんにご理解いただきたい重要なポイントを下記に示したいと思います: 痛みは、多因子性で“生物心理社会的”です。それは、組織の損傷や怪我、炎症(これが生物の側面)だけではなく、認知、思考、感情、社会的ストレス(これは心理社会の側面)など末梢の要因に起因します。複雑でもあります。つまり、これらの異なる因子は、たいてい個体差があり、状況依存性があり、予測不可能でありながら相互に関係し合っています(O’Sullivan 2018)。 痛みは、アラームのように働く、非常に洗練された防御システムのアウトプットです。身体への潜在的な恐怖は、末梢で感知され、それから脳へ伝達されます。脳は、その情報の意味を解釈し、防御すべきであると認識すれば、痛みを発信します。このシステムの感度は、怪我や炎症、感情、ストレス、記憶、健康全般など多くの様々な要因によって変化することがあります(Melzack 2010)。 痛みは知覚によるものであるため、組織の損傷が必ずしも痛みを出すわけではなく、組織の損傷の存在なしに痛みを感じることもあります。たとえば、痛みのない人のMRIに顕著な損傷が観察されることがよくあり、また、腰痛も特定の病理にまったく結びつけられないことが多くあります(Brinjikji 2015)。 姿勢と不完全な運動パターンと痛みとの結び付きは、過度に強調されてきました。研究において、これらの要因の相関性は低い、または無関係と示されています(Lederman 2011)。さらに、特定の“機能不全”との相互関係に焦点を当てた痛みの治療が、一般的なエクササイズより優れているということはほとんどありません。 (Foster 2018; O’Sullivan 2016; Riley 2018; Smith 2014; Ferreira 2007を参照)。 一方、心理社会的要因は、十分強調されないできました。たとえば、楽天的で自己効力感があれば怪我からの回復は見込まれますが、逆に、動くことへの不安や破滅化、恐怖は、慢性疼痛のリスクを高めます(Marcuzzi 2016)。患者に教育を提供することの一つの目的は、これらの変数を好ましい方向に変えていくことです(Louw 2016)。 痛みの教育者たちが、痛みはあなたの頭の中で起きている、組織の損傷は痛みとは関係ない、動きは怪我とは関係ない、と教えてはいないと私は断言できます。実際、多くの場合において全く正反対のことを私はよく述べてきました。ここに数年前に掲載された、痛みと姿勢との関連性は乏しいということに関するブログからいくつかの例をご紹介しましょう。 生体力学と正しいフォームはまったく重要ではない、という姿勢に関する研究を誤解しないようにしてください。活発なエクササイズは、単に座っていたり立っていたりすることとは異なり、より正しいアライメントに注意する必要があります・・・ですから、高重量デッドリフトでの姿勢やアライメントは重要です。ジャンプの着地やスプリント、ウェイトリフティングなど大きな力学的負荷がかかるような活動を行うとき、それらは重要になります。このような場合、生体力学や脊柱のアライメントが負荷を分散するのに適切かどうか、怪我のリスクを低減したりパフォーマンスを向上させたりするのに最適かどうかを指導したり意識的に努力することは賢明です。 ここに、痛みを作り出す脳の役割を論じた“A Guide to Better Movement(より良い動きのための手引)”という私の本から引用します。 明確にしておきたい重要ポイント:これらいずれも、痛みは実存しなく、すべて頭の中のことであると示唆しているのではありません。痛みは実在するものです。痛みは現実的な感覚ですが、しかし、その感覚が身体に実際に存在する損傷を反映しているとは限らないのです。さらに、痛みは、存続のために脳の活動に依存していますが、それは痛みを簡単に追い払うことができるとか、痛みはあなたのせいだという意味ではありません。残念ながら、痛みを発生させるプロセスは、ほとんど無意識で、自分で制御できるものでもありません。痛みについて意識的に考えることでそれを変えられるとしても、多くの症例ではその効果は小さいとされています。 痛みの科学の混乱についてのブログから: 痛みは、身体の状態に関連していることは言うまでもありません。ただ、それらの状態によってのみ決定するものではないのです。痛みは脳活動を要求するとしても、多くの場合において、組織の損傷がほぼ確実にその脳活動を起こすことは依然として事実です。ですから、組織の損傷は多いより少ない方が良いのです。 グレッグ・リーマンでも同じ論点が指摘されています: すべて頭の中のことではありません!医療専門家でさえもこの点で混乱しています。感情や心理的要因、脳について話し始めた途端に、痛みは単に頭の中で起きていることのように私たちが言っているという方向に話がすり替えられてしまいます。心理的要因や脳が関与しているということだけで、身体が重要でないとか痛みはイマージネーションであるとかを意味しているのではありません。 2. MRI研究では、痛みを伴わない組織損傷はよく見られることで、しかもそれは正常であると明示しています。 さらなる研究では、20歳を超えた人の身体のどの部位(たとえ痛みがない部位でも)のMRIを撮っても、顕著な損傷が観察される確率が非常に高いと示しています。下記にヨーゲン・イエブネがエビデンスをまとめた素晴らしいインフォグラフィックがあります。  この研究は、損傷を痛みと関連付けられないということを意味してはいません。非常に大きな損傷は当然大きな痛みと関連していますが、私たちが考える以上にはるかに関連性が少ないとうのは依然として興味深い見解です(Brinjikji 2015)。グレッグ・リーマンが有用な比喩表現を提供してくれています;脊椎や他の関節への損傷というものは、何らかの要因によって発火するかしないか分からない火種を抱えているようなものです。 これらの研究に協力した人たちは、今現在痛みを感じていないだけで将来的には当然痛みを伴うだろう、とシードマンは論じています。しかし、この懸念に対していくつかの研究がすでに取り組んでいます。7年間の追跡研究では、当初撮られたMRI画像と将来的な痛みとの間には相関性がないということが分かっています(Borenstein 2001)。その他の研究では、椎間板の退行変性や脊椎すべり症、椎間板膨隆などの所見にまで範囲を広げ、10年間の追跡調査を行いました。結論として:“私たちのデータは、MRI所見を基準に将来的に発症するかも知れない腰痛を予測することはできない、ということを示唆している。” (Tonosu 2017)。また、オーバーヘッド動作を伴うスポーツをする痛みのないアスリートの肩を対象にした研究では、40パーセントに回旋腱板の断裂が見つかりました。そして、研究が終わった後5年間においても、痛みを発症したアスリートはいませんでした(Conor 2003)。シードマンは、自分の主張を裏付けするひとつの研究を引用しました。その研究は、狭窄症の証拠を写したMRI画像が将来患うかもしれない腰痛を予想したと示していました。しかし、同じ研究で、その他多くのMRIによる陽性所見は将来の痛みを予測しなかったとしています。そして、“MRI所見とその結果を予測することにおいて一貫した関連性はないと確認された”と結論付けています(Hill 2018)。 参照 O’Sullivan, P. B., Caneiro, J. P., O’Keeffe, M., Smith, A., Dankaerts, W., Fersum, K., & O’Sullivan, K. (2018). Cognitive Functional Therapy: An Integrated Behavioral Approach for the Targeted Management of Disabling Low Back Pain. Physical Therapy, 98(5), 408–423. Melzack, R. (2010). Pain and the neuromatrix in the brain. Journal of Dental Education, 65(12), 1378–1382. Brinjikji, W., F. E. Diehn, J. G. Jarvik, C. M. Carr, D. F. Kallmes, M. H. Murad, and P. H. Luetmer. 2015. “MRI Findings of Disc Degeneration Are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis.” American Journal of Neuroradiology 36 (12). Lederman, E. (2011). The fall of the postural-structural-biomechanical model in manual and physical therapies: Exemplified by lower back pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(2), 131–138. Foster, N. E., Anema, J. R., Cherkin, D., Chou, R., Cohen, S. P., Gross, D. P., … Woolf, A. (2018). Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. The Lancet, 391(10137), 2368–2383; Riley, S. P., Swanson, B. T., & Dyer, E. (2018). Are movement-based classification systems more effective than therapeutic exercise or guideline based care in improving outcomes for patients with chronic low back pain? A systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 1–10. O’ Sullivan, P., & Caneiro, J. P. (2016). Unraveling the Complexity of Low Back Pain. J Orthop Sports Phys Ther 2016;46(11):932-937. Smith, B. E., Littlewood, C., & May, S. (2014). An update of stabilisation exercises for low back pain: A systematic review with meta-analysis. BMC Musculoskeletal Disorders, 15(1); Ferreira, M. L., Ferreira, P. H., Latimer, J., Herbert, R. D., Hodges, P. W., Jennings, M. D., … Refshauge, K. M. (2007). Comparison of general exercise, motor control exercise and spinal manipulative therapy for chronic low back pain: A randomized trial. Pain, 131(1–2), 31–37. Marcuzzi, A., Wrigley, P. J., Dean, C. M., Graham, P. L., & Hush, J. M. (2018). From acute to persistent low back pain: a longitudinal investigation of somatosensory changes using quantitative sensory testing — an exploratory study. Pain reports, 3, 1–10. Louw, A., Zimney, K., Puentedura, E. J., & Diener, I. (2016). The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. Physiotherapy Theory and Practice, 3985(September). Borenstein, D G, J W O’Mara, S D Boden, W C Lauerman, A Jacobson, C Platenberg, D Schellinger, and S W Wiesel. 2001. “The Value of Magnetic Resonance Imaging of the Lumbar Spine to Predict Low-Back Pain in Asymptomatic Subjects : A Seven-Year Follow-up Study.” The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume 83–A (9): 1306–11. Connor, Banks et al. (2003) Magnetic Resonance Imaging of the Asymptomatic Shoulder of Overhead Athletes. A 5-Year Follow-up Study. Am J Sports Med September 2003, Vol. 31, No. 5, 724–727. Hill, A. L., Aboud, D., Elliott, J., Magnussen, J., Steffens, D., & Hancock, M. (2018). Recover Injury Research Centre and Centre of Research Excellence in Recovery Following Surgical Outcomes Research Centre ( SOuRCe ), Royal Prince Alfred Hospital , Sydney. The Spine Journal. Tonosu, Juichi, Hiroyuki Oka, Akiro Higashikawa, Hiroshi Okazaki, Sakae Tanaka, and Ko Matsudaira. 2017. “The Associations between Magnetic Resonance Imaging Findings and Low Back Pain: A 10-Year Longitudinal Analysis,” 1–10. Grundy, P F, and C J Roberts. 1984. “Does Unequal Leg Length Cause Back Pain? A Case-Control Study.” Lancet (London, England) 2 (8397): 256–58. Pope, M H, T Bevins, D G Wilder, and J W Frymoyer. 1985. “The Relationship between Anthropometric, Postural, Muscular, and Mobility Characteristics of Males Ages 18-55.” Spine 10 (7): 644–48. Grob, D., H. Frauenfelder, and A. F. Mannion. 2007. “The Association between Cervical Spine Curvature and Neck Pain.” European Spine Journal 16 (5): 669–78. Nourbakhsh, M R, and A M Arab. 2002. “Relationship between Mechanical Factors and Incidence of Low Back Pain.” The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 32 (9): 447–60. Dieck, G S, J L Kelsey, V K Goel, M M Panjabi, S D Walter, and M H Laprade. 1985. “An Epidemiologic Study of the Relationship between Postural Asymmetry in the Teen Years and Subsequent Back and Neck Pain.” Spine 10 (10): 872–77. Franklin, Mary E., and Teresa Conner-Kerr. 1998. “An Analysis of Posture and Back Pain in the First and Third Trimesters of Pregnancy.” Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 28 (3): 133–38. Barrett, Eva, Mary O’Keeffe, Kieran O’Sullivan, Jeremy Lewis, and Karen McCreesh. 2016. “Is Thoracic Spine Posture Associated with Shoulder Pain, Range of Motion and Function? A Systematic Review.” Manual Therapy 26 (December): 38–46. Richards, K. V., D. J. Beales, A. J. Smith, P. B. O’Sullivan, and L. M. Straker. 2016. “Neck Posture Clusters and Their Association With Biopsychosocial Factors and Neck Pain in Australian Adolescents.” Physical Therapy 96 (10). Oxford University Press: 1576–87. Andrade, Nicholas S., Carol M. Ashton, Nelda P. Wray, Curtis Brown, and Viktor Bartanusz. 2015. “Systematic Review of Observational Studies Reveals No Association between Low Back Pain and Lumbar Spondylolysis with or without Isthmic Spondylolisthesis.” European Spine Journal 24 (6). Springer Berlin Heidelberg: 1289– 95. Ettinger, B, D M Black, L Palermo, M C Nevitt, S Melnikoff, and S R Cummings. 1994. “Kyphosis in Older Women and Its Relation to Back Pain, Disability and Osteopenia: The Study of Osteoporotic Fractures.” Osteoporosis International .4 (1): 55–60. Damasceno, Gerson Moreira, Arthur Sá Ferreira, Leandro Alberto Calazans Nogueira, Felipe José Jandre Reis, Igor Caio Santana Andrade, and Ney Meziat-Filho. 2018. “Text Neck and Neck Pain in 18–21-Year-Old Young Adults.” European Spine Journal 27 (6). Campos, Tarcisio F de, Chris G Maher, Daniel Steffens, Joel T Fuller, and Mark J Hancock. 2018. “Exercise Programs May Be Effective in Preventing a New Episode of Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Journal of Physiotherapy 64 (3). Netherlands: 159–65. Chaléat-Valayer, Emmanuelle, Jean-Marc Mac-Thiong, Jérôme Paquet, Eric Berthonnaud, Fabienne Siani, and Pierre Roussouly. 2011. “Sagittal Spino-Pelvic Alignment in Chronic Low Back Pain.” European Spine Journal 20 (S5): 634–40. Smith, Anne, Peter OʼSullivan, and Leon Straker. 2008. “Classification of Sagittal Thoraco-Lumbo-Pelvic Alignment of the Adolescent Spine in Standing and Its Relationship to Low Back Pain.” Spine 33 (19): 2101–7. Christensen, Sanne Toftgaard, and Jan Hartvigsen. 2008. “Spinal Curves and Health: A Systematic Critical Review of the Epidemiological Literature Dealing With Associations Between Sagittal Spinal Curves and Health.” Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 31 (9): 690–714. Théroux, Jean, Sylvie Le May, Carole Fortin, and Hubert Labelle. 2015. “Prevalence and Management of Back Pain in Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients: A Retrospective Study.” Pain Research & Management : The Journal of the Canadian Pain Society 20 (3). Pulsus Group Inc: 153–57. Hartvigsen, Jan, Charlotte Leboeuf-Yde, Svend Lings, and Elisabeth H Corder. 2002. “[Does Sitting at Work Cause Low Back Pain?].” Ugeskrift for Laeger 164 (6): 759–61. Wai, Eugene K., Darren M. Roffey, Paul Bishop, Brian K. Kwon, and Simon Dagenais. 2010. “Causal Assessment of Occupational Lifting and Low Back Pain: Results of a Systematic Review.” The Spine Journal 10 (6): 554–66. Kwon, B. K., D. M. Roffey, P. B. Bishop, S. Dagenais, and E. K. Wai. 2011. “Systematic Review: Occupational Physical Activity and Low Back Pain.” Occupational Medicine 61 (8): 541–48. Waddell, G., Burton, A.K., Mar 2001. Occupational health guide- lines for the management of low back pain at work: evidence review. Occup. Med. (Lond) 51 (2), 124e135 (Review). Shiri, Rahman, Jaro Karppinen, Päivi Leino-Arjas, Svetlana Solovieva, and Eira Viikari-Juntura. 2010. “The Association between Smoking and Low Back Pain: A Meta- Analysis.” The American Journal of Medicine 123 (1): 87.e7-87.e35. Hoogendoorn, W E, M N van Poppel, P M Bongers, B W Koes, and L M Bouter. 2000. “Systematic Review of Psychosocial Factors at Work and Private Life as Risk Factors for Back Pain.” Spine 25 (16): 2114–25. Hodges, Paul W., G. Lorimer Moseley, Anna Gabrielsson, and Simon C. Gandevia. 2003. “Experimental Muscle Pain Changes Feedforward Postural Responses of the Trunk Muscles.” Experimental Brain Research 151 (2): 262–71. Saragiotto, Bruno T, Christopher G Maher, Tie P Yamato, Leonardo O P Costa, Luciola C Menezes Costa, Raymond W J G Ostelo, and Luciana G Macedo. 2016. “Motor Control Exercise for Chronic Non-Specific Low-Back Pain.” The Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 1 (January). England: CD012004. Riley, S. P., Swanson, B. T., & Dyer, E. (2018). Are movement-based classification systems more effective than therapeutic exercise or guideline based care in improving outcomes for patients with chronic low back pain? A systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 1–10. Azevedo, Daniel Camara, Paulo Henrique Ferreira, Henrique de Oliveira Santos, Daniel Ribeiro Oliveira, Joao Victor Leite de Souza, and Leonardo Oliveira Pena Costa. 2018. “Movement System Impairment-Based Classification Treatment Versus General Exercises for Chronic Low Back Pain: Randomized Controlled Trial.” Physical Therapy 98 (1). United States: 28–39. Dillen, L., et al. 2017. Efficacy of classification-specific treatment and adherence on outcomes in people with chronic low back pain. A one-year follow-up, prospective, randomized, controlled clinical trial. Man Ther. 2016 August ; 24: 52–64 Timmons, Mark K, Chuck A Thigpen, Amee L Seitz, Andrew R Karduna, Brent L Arnold, and Lori A Michener. 2012. “Scapular Kinematics and Subacromial-Impingement Syndrome: A Meta-Analysis.” Journal of Sport Rehabilitation 21 (4). United States: 354–70. Ratcliffe, Elizabeth, Sharon Pickering, Sionnadh McLean, and Jeremy Lewis. 2014. “Is There a Relationship between Subacromial Impingement Syndrome and Scapular Orientation? A Systematic Review.” British Journal of Sports Medicine 48 (16): 1251–56. Struyf, F., J. Nijs, S. Mollekens, I. Jeurissen, S. Truijen, S. Mottram, and R. Meeusen. 2013. “Scapular-Focused Treatment in Patients with Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial.” Clinical Rheumatology 32 (1). Springer-Verlag: 73–85. Camargo, Paula R, Francisco Alburquerque-Sendin, Mariana A Avila, Melina N Haik, Amilton Vieira, and Tania F Salvini. 2015. “Effects of Stretching and Strengthening Exercises, With and Without Manual Therapy, on Scapular Kinematics, Function, and Pain in Individuals With Shoulder Impingement: A Randomized Controlled Trial.” The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 45 (12). United States: 984–97. McClure, Philip W, Jason Bialker, Nancy Neff, Gerald Williams, and Andrew Karduna. 2004. “Shoulder Function and 3-Dimensional Kinematics in People with Shoulder Impingement Syndrome before and after a 6-Week Exercise Program.” Physical Therapy 84 (9). United States: 832–48. Willy, R. W., & Meira, E. P. (2016). Current Concepts in Biomechanical Interventions for Patellofemoral Pain. International Journal of Sports Physical Therapy, 11(6), 877. Rabelo, N. D. D. A., & Lucareli, P. R. G. (2018). Do hip muscle weakness and dynamic knee valgus matter for the clinical evaluation and decision-making process in patients with patellofemoral pain? Brazilian Journal of Physical Therapy, 22(2), 105–109. Kim, Ji-Won, Oh-Yun Kwon, Tae-Ho Kim, Duk-Hyun An, and Jae-Seop Oh. 2014. “Effects of External Pelvic Compression on Trunk and Hip Muscle EMG Activity during Prone Hip Extension in Females with Chronic Low Back Pain.” Manual Therapy 19 (5). Scotland: 467–71. Lehman, Gregory J. 2006. “Trunk and Hip Muscle Recruitment Patterns during the Prone Leg Extension Following a Lateral Ankle Sprain: A Prospective Case Study Pre and Post Injury.” Chiropractic & Osteopathy 14 (February). England: 4. Suehiro, Tadanobu, Masatoshi Mizutani, Hiroshi Ishida, Kenichi Kobara, Hiroshi Osaka, and Susumu Watanabe. 2015. “Individuals with Chronic Low Back Pain Demonstrate Delayed Onset of the Back Muscle Activity during Prone Hip Extension.” Journal of Electromyography and Kinesiology : Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology 25 (4). England: 675–80. Dwyer, Maureen K, Kelly Stafford, Carl G Mattacola, Timothy L Uhl, and Mauro Giordani. 2013. “Comparison of Gluteus Medius Muscle Activity during Functional Tasks in Individuals with and without Osteoarthritis of the Hip Joint.” Clinical Biomechanics (Bristol, Avon) 28 (7). England: 757–61. Tumminello, N., Silvernail, J., & Cormack, B. (2017). The corrective exercise trap. Personal Training Quarterly, 4(1), 6–15.

どんなエクササイズが最も健康的か? パート2/2
狩猟採集民族の身体活動水準 どのように動くかと言う疑問に取り組むための他の方法は自然の環境下で生活をしている人間の身体活動水準を考えてみることです。これは、他のあらゆる動物の健康面の需要を分析するために応用する論理と同じです。もし、ペットのチータを飼っていて、健康を保つために走りまわるべき量を知るには、自然界でチータがどれだけ走るかについて知ろうとするでしょう。もし、ペットのチンパンジーがいれば、プールではなく、クライミングジムに連れていくことでしょう。 狩猟採集民族の文化を観察する人類学者は、彼らは一般的に素晴らしい健康とフィットネスを謳歌し、非活動的なライフスタイルに関連した慢性疾患の発生率がゼロあるいは限りなくゼロに近いことを発見しました(9)。彼らは高い水準の身体活動に励みますが、間違いなくそれをエクササイズや薬だと考えることはないでしょう(10)。動作は、彼らの生活におけるほぼ全ての重要な出来事から単に切り離すことが出来ないのです。それぞれの狩猟採集民族の文化が異なるライフスタイルを持っていたとしても、有益な一般的なパターンや標準的な事柄があるのです。 男性は通常、1日を狩猟に費やし、これは多くのウォーキングや時折のジョギング、そして稀にスプリントを必要とします。時には木に登ったり、塊茎を見つけるために地面を掘ったり、キャンプ地に食べ物(これらは屠殺しなければなりません)を運び帰ったりします。女性は一般的に植物を集めたりして日々を過ごし、抱き抱えなければならないことも多い幼い子供たちの世話もします。キャンプ地に戻ると、男性と女性は道具作りに取り組み、食事の用意をします。休んでいる時間は、下半身のモビリティを刺激するスクワットのようなポジションで地面にしゃがんで過ごします。 彼らは一日中動いてはいますが、そのペースは疲労困憊になるようなものではありません。タンザニアのハヅァ族に関する近年の研究は、彼らが1日に約135分の中程度から激しい身体活動を行うとしています(11)。これは週に約900分の身体活動であり、これは、近年の研究がエクササイズを追加することで死亡率減少に対する著しい追加の健康への効果が頭打ちになる点を少しだけ超過しています。 ある日は重労働を伴いますが、そのような日の後は大抵楽な日が続きます。おそらく、数日はスプリントや重い物を運ぶといった最大強度の努力を伴うでしょう。興味深いことに、身体活動の水準は年齢と共に大きく低下しません。65歳の高齢者は若い成人に苦もなくついていきます。総仕事量の大きな割合は日に5~10マイル歩くことです。歩数として考えるのであれば、これは約1~2万歩になります。 このような有機的で、全て天然のフィットネスのプログラムはどのように標準的な政府の推奨事項と比較できるでしょうか?そこにはいくつかの明らかな類似点があります。活動の大部分は早歩きのような中程度の持続的な動作です。激しい身体活動は全体の小さな割合で、筋力(クライミング、穴掘り、物を運ぶ、屠殺)やパワー(スプリント)にチャレンジするような活動を含みます。身体活動の多くは、不均等な地形を歩く、よじ登ったり這い回ったり、穴を掘る、変わった形の物体を持ち上げて運ぶ、投げる、そして地面に座るといったモビリティやコーディネーション、そしてバランスを必要とします。一つの大きな違いは、狩猟採集民族は低強度の身体活動を、現代の非常に活発な人と比べてもより多くのボリュームで行います。より多くのベンチプレスはしませんが、より多くの歩数を歩いているのです。 興味深いことに、ウォーキングはまさに現代の人が好んでより多く行たい身体活動の種類であるしょう、もし時間が有れば。Paddy Ekkekakishはエクササイズをする動機について研究しており、高強度のエクササイズは健康効果をすぐにもたらすのに効果的ではあるにもかかわらず、多くの人はそれをやろうとしないことに気づきました、なぜなら…(ショックを受けないように気をつけてください)…好きではないからです。しかし、人々はウォーキングを楽しむ傾向にあります。友人と一緒に良い環境で、など適切な環境のもとでは、それをエクササイズではなく、即座にご褒美となる楽しく元気の出る経験と考えるでしょう。 ウォーキングの特筆すべき他の特性は、最小限のけがのリスクで健康効果を得られることです。より強度の高いエクササイズ(例:バーベルスクワットのセット)はやりすぎと不十分間の範囲があまり広くありません。良いトレーニングとけがの境界線は数回の余剰なレップやバーベルにのせるプレートの枚数だけです。しかし、ウォーキングにおけるエラーの許容範囲はかなり大きいのです。健全な量のウォーキングの後、ほとんどの人はそれを二倍にしても簡単に回復できるでしょう。 ウォーキングは労力に見合う価値が最も高いことは理にかなっており、なぜならこれは私達が最も適応している運動だからです。他の動物と同様に、私たちの主な身体機能は移動運動であり、歩行はその目的を達成するために最もエネルギー効率の良い方法です。もし他に何もせずウォーキングだけを沢山行えば、ほとんどのアメリカ人よりもより健康になるでしょう。 簡単なまとめ もし、一般的な健康を向上する方法として、フィットネスを用いて「試して」みたいのであれば、覚えておきたい「ゲームのルール」を紹介します。これらの基本的制約を守りながらできる限り楽しみましょう: ほぼ毎日、最低30分から最大2時間までの身体活動を目指しましょう。 運動は、ボリュームや強度、種類の観点から様々なものになるべきです。ほとんどの身体活動はかなり軽くても良いでしょう。ウォーキングが人間にとって最も自然で効果的な動作です。 数日ごとに、あなたの筋力やパワー、または短い時間に高いエネルギー出力を維持する能力へ著しくチャレンジする強度の高い運動を取り入れましょう。クライミングやランニング、そしてレジスタンストレーニングが論理的な選択肢でしょう。 コーディネーションやバランス、可動域にチャレンジ運動を含めましょう。 あるいは、これらをより簡単な言葉で置き換えてみると: ゆっくりとした楽なペースでたくさん動き回りましょう。 頻繁に素早い動作を行なったり重い物を持ち上げましょう。 時折、あなたの命がかかっているかのように動きましょう。 そして楽しみましょう!身体活動は薬を飲むこととは違うんですよ。 参照 The Academy of Medical Royal Colleges (2015). Exercise: The Miracle Cure and The Role of The Doctor in Promoting It. Report from the Academy of Medical Royal Colleges, February. O’Donovan et al. (2017). Association of ‘Weekend Warrior’ and Other Leisure Time Physical Activity Patterns with Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality. JAMA Internal Medicine, 175(6), 959–67. Pedersen et al. (2015). Exercise as Medicine - Evidence for Prescribing Exercise as Therapy in 26 Different Chronic Diseases. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25, 1–72 Booth et al. (2012). Lack of Exercise Is a Major Cause of Chronic Diseases. Comprehensive Physiology, 2(2), 1143–1211. Piercy et al. (2018). The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA, 320(19), 2020 World Health Organisation. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva, 2010. Lear et al. (2017). The Effect of Physical Activity on Mortality and Cardiovascular Disease in 130,000 People From 17 High-Income, Middle-Income, and Low-Income Countries: The PURE Study. The Lancet, 390(10113), 2643–2654. Stamatakis, et al. (2017). Does Strength Promoting Exercise Confer Unique Health Benefits? A Pooled Analysis of Eleven Population Cohorts with All-Cause, Cancer, and Cardiovascular Mortality Endpoints. American Journal of Epidemiology, 187 (5), 1102-1112. O’Keefe, et al. (2011). Exercise Like a Hunter-Gatherer: A Prescription for Organic Physical Fitness. Progress in Cardiovascular Diseases. 53(6), 471 Lieberman (2015). Is Exercise Really Medicine? An Evolutionary Perspective. Current Sports Medicine Reports, 14(4), 313–319. Pontzer et al. (2018). Hunter-Gatherers as Models in Public Health. Obesity Reviews, 19(December), 24–35; Raichlen et al. (2017). Physical Activity Patterns and Biomarkers of Cardiovascular Disease Risk in Hunter-Gatherers. American Journal of Human Biology, 29(2), 1–13.

どんなエクササイズが最も健康的か? パート1/2
身体活動は今、健康に大きな影響を与えるライフスタイルの要因のビッグ4の一つと考えられています(他に喫煙、栄養、そして薬物乱用)。2015年に、メディカルロイヤルカレッジアカデミーがエクササイズの効果をまとめた報告を打ち出し、エクササイズを「妙薬」そして「特効薬」と称しました(1)。この報告は、定期的なエクササイズは認知症や2型糖尿病、ある種の癌、鬱、心臓疾患や他の一般的な重大な病気を予防できることを認めています−それぞれのリスクを少なくとも30%低下させるのです。これは多くの他の薬よりも優れています。 60,000件以上の回答からのデータの近年の分析によって、週に1、2回エクササイズを行なっている人は、エクササイズをしない人よりもあらゆる原因による死亡率が30%低いことがわかりました。週に3-5回エクササイズを行なっている人では35%低減しています(2)。同様の研究では、非活動的な生活は36もの疾患の主な原因であり、そしてエクササイズはそれらを予防するための有効的な処置であると結論づけました(3、4)。多くの専門家は、もしエクササイズが錠剤のようであれば、それは今までに開発された中で、最も効果的で広く処方される薬になるであろうと認めています。 エクササイズの健康への効果を支持するエビデンスは否定できませんが、私は、エクササイズを「薬」と比喩することをあまり魅力的に感じません。まず、薬は多くの人にとって、あまり取りたくないものであり、したがって、そのマーケティング方法はあまり良いものではないのです。次に、薬という言葉は、ある特定の疾患の治癒を示唆するものであり、これは誤解を招くものです。光や水、土が植物を育てるように、身体活動はあなたの健康を多くの様々な面から向上させることができます。しかし、特定の問題を「治す」という対象を絞った介入ではありません。 私が思う身体活動の効果のより良い比喩はKaty BowmanとNick Tuminelloによって推奨されたものです:運動は食べ物のようである。この喩えを用いた説明は、多くの様々な場面で意味を成します。まず、食物の栄養素は多すぎず少なすぎず、適度な量を摂取した場合に効果的です。例えば、貧血にならないために、鉄は最小摂取量が必要とされますが、多すぎると有毒になります。身体へ取り込む物の多くがこれと同様であり、水ですらそうなのです。身体活動をとってみると、最低限の量は必要不可欠ですが、多すぎれば有害であり、そして幅広い範囲の適度な量が存在します。 動作を食べ物に喩えた別の説明として、多くの様々な栄養素(それぞれに最適な摂取量が存在する)からなるバランスの取れた食事が必要であるということです。もし、ビタミンAが不足しているならば、ビタミンBの量を倍にしても効果はないでしょう。同じことが身体活動にも言えます。ベンチプレスは良いエクササイズですが、もしそれだけしかしてこなかったのであれば、身体機能の他の部分が不足してしまうでしょう。 もし、運動が食べ物のようであれば、どのようにしてバランスの取れた食事をとりますか?答えのひとつは…場合による、です。20歳のアスリートは、膝痛のある65歳の人と異な運動の処方が必要でしょう。実際に、膝痛のある65歳の人が2人いれば、完全に異なるプログラムから効果が得られるかもしれません。ある人にとって何が最も効果があるかを見つけるには、様々なオプションからなる広い範囲を探求する必要があるでしょう。良いニュースは、その範囲のある部分は他の部分よりも探求する価値があるということです。それがどこにあるかという大まかな認識を得るためには、2種類のデータの情報源を参考にすることができます:(1)政府の保険局からの公式な推奨事項、及び(2)自然環境に住む狩猟採集民族の身体活動を分析した研究。私は、これらのガイドラインを、運動に関する重要な行動指針であると考えます。幸いにも、これらは両方とも基本的に同じ方向を指し示しています。 保険局からの推奨事項 世界保健機関(WHO)や米国保険局、英国の国民保険サービスを含む多数の政府機関は身体活動のガイドラインを発行しています(5、6)。これらは、専門家による身体活動やフィットネス、そして健康を対象とした莫大な量の研究の分析をもとにしています。以下にそれらからのアドバイスの簡単な要約を紹介します(どの情報源においてもほぼ同様です)。 身体活動の量 ガイドラインは、少なくとも週に150分の「中程度」の身体活動か、その半分の時間の「激しい」活動を推奨しています。しかし、これらは最低限でしかなく、より良い目標は、週に300分の中程度の活動をすることです。さらにエクササイズを追加することは、週に750分までは死亡率を減少させ続け、この点を過ぎると身体活動の健康への効果は頭打ちになるようです(7)。 「中程度」の活動の定義 中程度の活動とは通常は軽い有酸素エクササイズ−持続的な周期性の動作を楽なペースで行なうことです。例として: 早歩き ハイキング ガーデニングまたは庭仕事 楽なペースでのジョギング、サイクリングまたは水泳 中程度の身体活動は運動をしているように感じますが、続けるのが不快であったり困難であったりという程ではありません。心拍数は最大の約60~80%で、呼吸数は歌うのは難しいが、話すのは容易であるところまで上がります。軽く汗をかくかもしれませんが、著しく身体が熱くなり過ぎることはありません。中程度の身体活動のセッションが終わった後、もし必要であればおそらくもう一セッション行うことができるでしょう。 「激しい」身体活動の定義 激しい身体活動はより高い強度の運動で、持続的または間欠的なものとなります。例として: ウェイト、マシーン、バンドまたは自体重を用いたレジスタンストレーニング スプリントやバイク、ロウイングマシーンでの高強度のインターバルトレーニング 持続的なランニング、サイクリング、スイミングまたはロウイングを挑戦的なペースで行う 重労働 ランニングやサイクリングといった持続的で激しい身体活動では、20分かそれ以上の時間維持できる最も速いペースに近づきます。呼吸数は会話ができないほど多くなります。ウェイトリフティングやスポーツ、スプリントなどの間欠的な活動は、インターバルでのみ行うことができ、持続的には行えません。激しい身体活動はキツく感じ、続けるには意志の力が必要です。やり終えた時、同じようなきついトレーニングを行う前に少なくとも1日は休みたいと思うでしょう。 筋力にチャレンジする運動 ほとんどのガイドラインでは、全ての主要な筋群の筋力を維持または向上させるセッションを最低でも2回、上記の週の総数に含むべきであると推奨しています。大多数の身体活動に関する研究が有酸素エクササイズに関するものであるにもかかわらず、ストレングストレーニングによる同様に素晴らしい健康効果を示した研究は多くあり、そしてその数は増え続けています。これらの効果の一部、特に筋量を維持することは有酸素エクササイズでは得ることができず、これは年齢と共に低下し、多くの場合において身体機能が著しく損なわれるまで低下します(8)。 モビリティと基本的なコーディネーションにチャレンジする運動 全てではありませんが、一部のポピュラーなガイドラインでは、機能的な可動域とスクワットや片脚バランスといった基本的な動作のスキルを維持する動作を含めることを推奨しています。これは、ストレッチやコレクティブエクササイズといった、この目的のためにとりわけ専念したエクササイズが必要であるという意味ではありません。ダンスや水泳、武術、体操、クライミング、自重運動や、プッシュアップやプルアップ、ロウ、プレス、スクワット、ランジといった昔からある複合的な筋力エクササイズを含む多くの一般的な身体活動はモビリティと機能的な運動スキルにチャレンジします。一方で、もしあなたはバイクやランニングだけしかしないのであれば、あなたのモビリティやコーディネーションはあまりチャレンジされていないでしょう。 参照 The Academy of Medical Royal Colleges (2015). Exercise: The Miracle Cure and The Role of The Doctor in Promoting It. Report from the Academy of Medical Royal Colleges, February. O’Donovan et al. (2017). Association of ‘Weekend Warrior’ and Other Leisure Time Physical Activity Patterns with Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality. JAMA Internal Medicine, 175(6), 959–67. Pedersen et al. (2015). Exercise as Medicine - Evidence for Prescribing Exercise as Therapy in 26 Different Chronic Diseases. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25, 1–72 Booth et al. (2012). Lack of Exercise Is a Major Cause of Chronic Diseases. Comprehensive Physiology, 2(2), 1143–1211. Piercy et al. (2018). The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA, 320(19), 2020 World Health Organisation. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva, 2010. Lear et al. (2017). The Effect of Physical Activity on Mortality and Cardiovascular Disease in 130,000 People From 17 High-Income, Middle-Income, and Low-Income Countries: The PURE Study. The Lancet, 390(10113), 2643–2654. Stamatakis, et al. (2017). Does Strength Promoting Exercise Confer Unique Health Benefits? A Pooled Analysis of Eleven Population Cohorts with All-Cause, Cancer, and Cardiovascular Mortality Endpoints. American Journal of Epidemiology, 187 (5), 1102-1112. O’Keefe, et al. (2011). Exercise Like a Hunter-Gatherer: A Prescription for Organic Physical Fitness. Progress in Cardiovascular Diseases. 53(6), 471 Lieberman (2015). Is Exercise Really Medicine? An Evolutionary Perspective. Current Sports Medicine Reports, 14(4), 313–319. Pontzer et al. (2018). Hunter-Gatherers as Models in Public Health. Obesity Reviews, 19(December), 24–35; Raichlen et al. (2017). Physical Activity Patterns and Biomarkers of Cardiovascular Disease Risk in Hunter-Gatherers. American Journal of Human Biology, 29(2), 1–13.

痛みから脱するための7つの道のり パート2/2
3.モビリティトレーニング 快適で機能的な可動域を広げるためにトレーニングをすることは、どのような療法でも伝統的に治療の基本となっています。静的ストレッチのような単純な介入は、即時にリラックス感を得ることができ、筋緊張を低下させ、疼痛感受性を低下させることができます。さらに、ストレッチは、様々な筋骨格系の痛みの治療に有用であることがわかっています。 モビリティトレーニングが特に有用であるのは次の場合であると思います:(1)痛みのある領域の近くの関節可動域が明らかに制限されている場合:(2)痛みのある領域の近くに不快なこわばり感がある場合; (3)こわばり感は関節ではなく筋にある場合;(4)現在、全可動域を使う必要があるエクササイズプログラムを行なっていない場合。 もし、私のクライアントにこれらの条件がいくつかあらば、モビリティを改善するための継続的な取り組みに彼らの痛みがどのように反応を示すか、非常に興味があると伝えるでしょう。取り組みには次のようなさまざまな方法があります: ヨガ ピラテス ダンス スポーツやトレーニングのウォームアップルーティーン ダイナミック関節モビリティドリル PNF コレクティブエクササイズ 魅力を感じる方法を選び、痛みを悪化させるほど頑張りすぎないようにし、痛みが改善するか確認してみます。モビリティトレーニングに効果がない場合には、次のチェックボックスを確認し、別の方法に切り替えます。 注意事項 柔軟性はあればあるだけ良いとは限りません。 関節ではなく筋の伸長を感じることを確認します。 組織を長くしたり、癒着を剥がしたり、筋膜を変形させることが目的ではありません。ストレッチはおそらく、構造を変えるのではなく、神経系の耐性を高めることで関節可動域を広げる働きをします。 4.運動制御/協調 理学療法では、しばしば“機能不全”の運動パターンを修正しようとします。他の投稿でもリビューしたように、このモデルにはいくつかの問題点があります。注目すべき研究によると、運動制御を変更する取り組みで痛みを軽減することができますが、多くの場合、一般的なエクササイズの効果と変わりはなく、運動制御が改善されなくても効果があると示されています。さらに、どの動きが機能不全であるかについての考えのほとんどは、私たちの推測であり、人間の動きの複雑さと個体差を無視しています。身体的タスクを実行するための方法には数多くの異なるものがあり、教科書に示されているようなひとつの“完璧”な方法ではなく、多種多様なやり方でそれらを実行できる方がおそらく優れていると言えるでしょう。そうは言っても、教科書に紹介されているフォームで動作してみようとすることは(たとえば、スクワットやダンベルローイングをしているとき)、多くの人々にとって魅力的で興味深い課題であり、それを達成するために取り組むことで、協調を改善し、痛みを軽減するのかもしれません。 このような理由から、特に痛みが運動に関連している場合、痛みを治療する方法として、さまざまな運動制御の方法を試す価値があると思います。ここに、少しですがいくつかを列挙します。 フェルデンクライスメソッド ヨガ ピラテス コレクティブエクササイズ 適切なフォームでのレジスタンスエクササイズ ランニングドリル プライマルパターン (例:クローイング、ローリング、クライミング、グラウンドフロー) 武道 注意事項 “誤った”やり方で動くことが危険であるという考えに固執しないでください。そうではなく、これらの介入を運動の語彙を改善する方法と捉えましょう。 5. マインド/ボディ 痛みは、単なる“組織の問題”だけではありません。それは、神経系と脳の無意識の部分が体で起こっていることをどのように知覚するかによります。これは、痛みが慢性的であったり、その他の知覚混乱と関連したりしている時は特に当てはまります。また、構造的な問題よりも心理社会的なものによって引き起こされることの方が多いようです。マインドフルアウェアネスやフォーカスアテンションなどを通して体への認識を改善しようとする数多くの異なるマインド/ボディの訓練があります。そのいくつかは痛みを軽減することが示されています。 マインド/ボディの訓練に興味があれば、慢性疼痛の治療と対処方法として、次のいずれかを検討してください。 瞑想 マインドフルネスストレス低減法 ヨガ ダンス フェルデンクライスメソッド 武道(特に太極拳と気功) 注意事項 痛みがすべて頭の中で起きている、体は関係ない、痛みがあるのは自分のせいである、または正しいマインドセットがあれば痛みを紛らせることができる、などとは決して考えないでください。 マインド/ボディのメソッドが、痛みを癒すということはほとんどありません。多くの場合、それらは痛みのマネージメントにおいて貴重なツールとはなります。 6.健康全般を改善 健康全般を改善するためにできることはすべて、筋骨格系の痛みに効果がある可能性があります。特に痛みが慢性的で、肥満、うつ病、不安症、過敏性腸症候群、自己免疫疾患などの他の慢性で複雑な症状を合併している場合、その可能性があります。 この場合、健康全般を改善するための努力が、痛みの最良の治療になるかもしれません。つまり、食事に取り組み、体組成を最適化し、有酸素運動をし、外に出て、友人や家族と有意義な時間を過ごし、感情的なストレスを最小限に抑え、睡眠の質を上げることです。 注意事項 健康的な生活への関心が、不健康な信念(毒素はどこにでもありそれらを回避することが毎日の仕事のようになってしまう)に変わらないように気をつけてください。 7.徒手療法 マッサージやカイロプラクティック矯正などの徒手療法が筋骨格系の痛みに効果があることを示すエビデンスがあります。しかし、いくつかの条件をつけてそれらを試してみることを、私は提案します。 まず、徒手療法はおそらく、ずれた椎骨や筋膜の癒着、筋の不均衡、悪いエネルギーなどの組織の問題を“修正”するというよりかは、神経系の痛みに対する感受性を調整することによって機能するということを認識しておいてください。 徒手療法で調子が良くなっても、生理学的メカニズムは、有酸素運動や筋力トレーニング、またはヨガで調子が良くなるのと大きくは変わらないかもしれません。このように受動的な療法の効果を身体運動(いつでもどこでも無料で行うことができ、他にも健康上の利点がある)で得ることができれば、おそらく受動的よりも能動的な方が良いでしょう。一方、巧みで共感的な人間のタッチが、他では得られない効果を提供してくれることも間違いありません。もしあなたが、ダイアン・ジェイコブスが言う“霊長類の社会的な身づくろい”に良い反応をする人であれば、徒手療法を受けてみてください。しかし、整備士が車を修理するのと同じように、身体の問題を“修理”する必要があるという思考の罠に陥らないでください。これは力を弱めることにつながることがあります。 まとめ 私は上記に挙げた取り組みを、多くの種類の筋骨格の痛みに対して、何をすべきかを明確に方向つける特定の方法はひとつもないという事実をより明らかにするための“道のり”と呼びます。何が最適な方法なのかを探る必要があります。複合科学では、問題解決は地図を持たずに変化に富んだ土地を旅するようなものです。方向を定めて目的地を見つけるには、行動を起こす必要があり、問題を解決するために必要なほとんどの情報は、行動するまでは見えてきません。テリトリー(領域)を知っているガイドは役に立ちますが、あなたもある程度自分でできるはずです。あなたが追求する道のりのいくつかは行き止まりかもしれませんが、他の道のりには多くの分岐点や小道もあるでしょう。それぞれに、いくつかの予期しない落とし穴、訪れて楽しい場所、そして時には宝があるかもしれません。続けていくためにも、好奇心やモチベーション、勇気が必要です。目的地にたどり着くことではなく、旅の道のりに価値があることもあります。幸運を祈ります。 参照 Malliaras P, Barton CJ, Reeves ND, Langberg H. Achilles and patellar tendinopathy loading programmes : a systematic review comparing clinical outcomes and identifying potential mechanisms for effectiveness. Sports Med. 2013;43(4):267-286. doi:10.1007/s40279-013-0019-z; Key factors to consider in Achilles tendinopathy rehab (Malliaris 2016). For information on resistance training for tendons generally, see: Cook et al. (2016). Revisiting the Continuum Model of Tendon Pathology: What Is Its Merit In Clinical Practice And Research? British Journal of Sports Medicine. 50(19), 1187–1191; Rio et al. (2014). The Pain of Tendinopathy: Physiological or Pathophysiological? Sports Medicine. 44(1), 9–23; Rio et al. (2016). Tendon Neuroplastic Training: Changing the Way We Think About Tendon Rehabilitation: A Narrative Review. British Journal of Sports Medicine. 50(4), 209–215. Willy et al. (2016). Current Concepts in Biomechanical Interventions for Patellofemoral Pain. International Journal of Sports Physical Therapy. 11(6), 877; Rabelo et al. (2018). Do Hip Muscle Weakness and Dynamic Knee Valgus Matter for The Clinical Evaluation and Decision-Making Process In Patients With Patellofemoral Pain? Brazilian Journal of Physical Therapy. 22(2), 105–109. Prevention and Treatment of Low Back Pain: Evidence, Challenges, and Promising Directions. The Lancet, 391 (10137), 2368–2383. Gross et al. (2015) Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD004250. See, e.g. Timmons et al. (2012). Scapular Kinematics and Subacromial-Impingement Syndrome: A Meta-Analysis. Journal of Sport Rehabilitation. 21(4), 354–70; Struyf et al. (2013). Scapular-Focused Treatment in Patients with Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Clinical Rheumatology. 32(1), 73–85; Camargo et al. (2015). Effects of Stretching and Strengthening Exercises, With and Without Manual Therapy, on Scapular Kinematics, Function, and Pain in Individuals with Shoulder Impingement: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 45(12), 984–97; McClure et al. (2004). Shoulder Function and 3-Dimensional Kinematics in People with Shoulder Impingement Syndrome before and after a 6-Week Exercise Program. Physical Therapy. 84(9), 832–48; McQuade et al. (2016). Critical and Theoretical Perspective on Scapular Stabilization: What Does It Really Mean, and Are We on the Right Track? Physical Therapy. 96(8), 1162–69.