マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

腸脛靭帯を助ける
走ったり坂道を下ったりした後で、膝の外側に鋭く執拗な痛みを感じたりすると、とりあえず腸脛靭帯のストレッチをしたり、フォームローラーやバイブレーションツールでリラックスさせようとしますよね?その時に不快感が減少したとしても、要因を見つけて取り組むことがなければ又同じ問題が繰り返し起こってくることになってしまいます。

プッシュアップパワーのためのベストなクロール
四つ這いのポジションで、両膝を床から持ち上げる瞬間に、あるいは持ち上げるその一瞬前に、コアの筋群が反射的に収縮するのを感じたことはありますか?いや、ないです。という方、今この場で両手両膝を床について試してみてください。この反射的な収縮を感じながら床の上を移動してみませんか?

骨盤のバランスが良い姿勢の鍵である理由
姿勢に回旋のパターンが見られる時、感じられる時、私達はまず脊柱の回旋に目を向けます。では脊柱に回旋パターンがある時、骨盤はどうなっているのでしょうか?骨盤の姿勢の重要さと、マインドフルなエクササイズで骨盤周辺の組織のバランスを取り戻す方法をカリン・ガートナーがシェアします。

目的を伴う減速:側方減速バンドローディング
側方への動きの減速をより効果的に安全に行うための、ゴムバンドを使ったドリルの実行方法と注意点をリー・タフトが紹介します。ゴムのバンドというシンプルなツールを使ってモメンタムのコントロール方法を学びます。

ピラー5:統合
FTIファンクショナルトレーニングシリーズの最後は、ピラー5となる動きの統合です。コーチ・タレクが、全身の動きを統合してダイナミックに持久力やスピードやパワーの向上に働きかける、バトルロープの段階的指導のアイデアをシェアしてくれます。

正座の基本ポジションへの沢山の入力
日本の家屋内で正座をする際に、シューズを履いているってことはまずないよねぇ、というツッコミは聞こえてきそうではありますが、このビデオでは、マイケルが正座のポジションのメリットと、そのポジションからの様々な応用による神経系への入力の変化について興味深い解説をしてくれています。
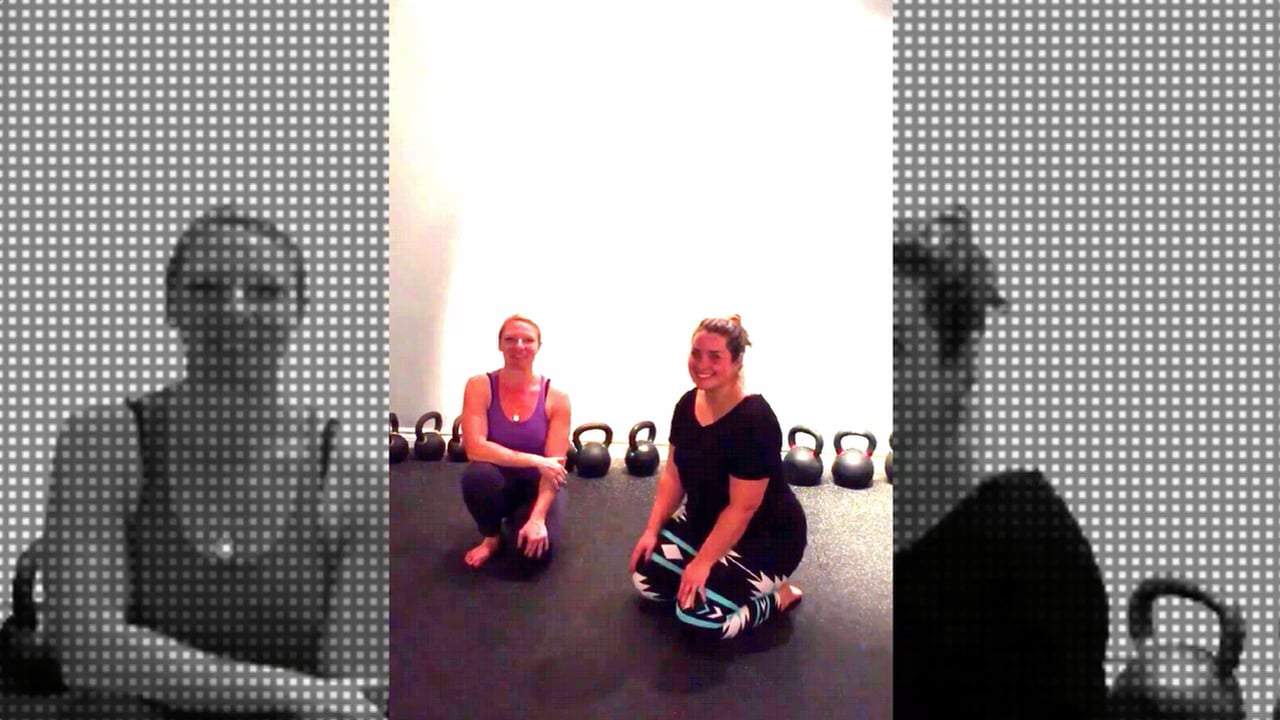
四つ這いでのチンタック
頭部前突して、顎を突き出した姿勢になってしまいやすい現代の私達にとって、顎を引いて首の後ろを長く維持しつつ脊椎のニュートラルを維持するのは、なかなか大変なこと。四つ這いの姿勢で、顎を引く練習をするシンプルだけれどハードなドリルをご紹介します。

チェーンリアクションバイオメカニクス・相対的な動きと実際の動き:距骨下関節
距骨下関節は、運動のチェーンリアクションの成功にとってとても重要です。距骨下関節の位置は、足部の可動性に直接的に影響を与えます。距骨下関節の動きは、膝、股関節、脊柱と身体上部に向かう運動連鎖を引き起こします。距骨下関節の複雑さを学ぶことは重要ですが、機能的運動における関節の実践的単純さを理解することもまた不可欠です。 これは実は、動きを解説するために使用された用語によって引き起こされた混乱であるために、この複雑さはある意味偽の複雑さであるとも言えます。距骨下関節の動きを解説するために、最もよく使われる用語は、回内と回外でしょう。一軸としてラベルづけされていますが、実は三軸の動きです。一軸とは、単一の軸に対して垂直に、一つの運動のみが起きているということを表します。ここでの動きは、三面の動きです。なぜなら、軸の方向性は、三面全てにおける(主に前額面と水平面)動きが起こる結果をもたらすからです。 回内、回外は、相対的な関節の動きに言及するものです。これらの相対的な関節の動きは、どのような骨の動きによって引き起こされるのでしょうか?下から上に向かって見てみましょう。もし踵骨が前額面において、中心線から離れる方向に動くとすれば、この骨の実際の動きは踵骨の外反と呼ばれるものになります。もし踵骨が外反すると、ほぼ全ての場合において(荷重時でも非荷重時でも)、この外反は、関節における回内を起こします。距骨下関節は三面的な関節であるために、前額面において外反をすれば、常にそこには水平面での動きも起こることになります。この動きに対しての用語は、外転、あるいは外旋となります。ですから、関節で回内が起きる時、踵骨は前額面で外反し、水平面で外旋し、矢状面でやや背屈するのです。 足に体重がかかっている時には、踵骨の実際の骨の動きは、その上側にある距骨の実際の動きを伴って起こります。軸の傾斜角度のために、距骨下関節はトルク変換器として働きます。踵骨の前額面での動きは、その上にある脚の水平面での動きに変換されるのです。踵骨の外反は、(相対的な)距骨下関節の回内の一部として、距骨の内旋/内転という実際の骨の動きを起こします。距骨は足関節において、水平面での動きは僅かしかないために、距骨の内旋は、下腿部の内旋を引き起こすことになります。多くの状況において、大腿骨の実際の骨の動きが股関節の相対的な動きという結果を生み出し、チェーンリアクションは、継続していくことになります。この素晴らしいチェーンリアクションのシークエンスは、トップダウン(身体上部から下部へ)でもボトムアップ(身体下部から上部へ)でも起こります。起き上がった状態での機能においては、大腿骨が内旋をすれば、下腿部もまた内旋をし、距骨もまた内旋します。距骨の動きが相対的な関節の動きである回内を起こし、踵骨が外反をすることになります。 上記で解説されたボトムアップとトップダウンという生体力学は、共に相対的な距骨下関節の回外において反転して発生します。距骨下関節の動きの能力と、荷重時(身体の他の部分との統合)のその動きの範囲の評価ができることは、全ての運動に関わるプラクティショナー達にとって必要とされる不可欠な“ツール”です。3DMAPSは、ボトムアップ(ランジ)ドライバーとトップダウン(腕のスイング)ドライバーを用いて、距骨下関節の回内と回外を、全体的な機能的動作の一部として生み出します。身体全体に対しての距骨下関節の影響と、距骨下関節に対しての身体全体の影響を分析する能力は、3DMAPSのパワーと言えるでしょう。

スクワットデッドリフトの違いは何か?
スクワットのパターンとデッドリフトに代表されるヒンジのパターンの相違を、はっきりと区別して見極めるポイントとなる主な関節の動きを、4つにまとめてストレングスコーチのマイク・ロバートソンがシェアします。

パワーと安定性のためのより良いケトルベルトレーニング
ハーフニーリングのポジションからケトルベルクリーンを行おうとする際、危険性を抑えてより安全に効果的に実行するには、どのようなことが必要となるのか?軽めのベルで試してみてください。かなりチャレンジし甲斐があります。

呼吸と肩のモビリティ
頚椎の固定手術を経験しているジョシュ・ヘンキンをモデルに、妻であり理学療法士であるジェシカ・ベントが、肩関節の外旋の動きを例にとって、関節可動域の問題を改善するためのアプローチに、より統合された方法を取り入れることの重要さを解説します。

足首のモビリゼーション
足や足首周辺の結合組織のモビリティを高めるためのアプローチも、運動の3面性を理解した上で全ての運動面において行うのがより効果的。軟部組織のエキスパートであるレニー・パラチーノがシンプルに実行できる方法をシェアします。