マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

USBでのデッドバグ・プログレッション
デッドバグのエクササイズを、段階的に漸進させていくにあたり、反射的に広背筋と臀筋とコアのコネクションを引き出していくことができるバリエーションとキューイングのポイントを理学療法士のジェシカ・ベントがシェアします。
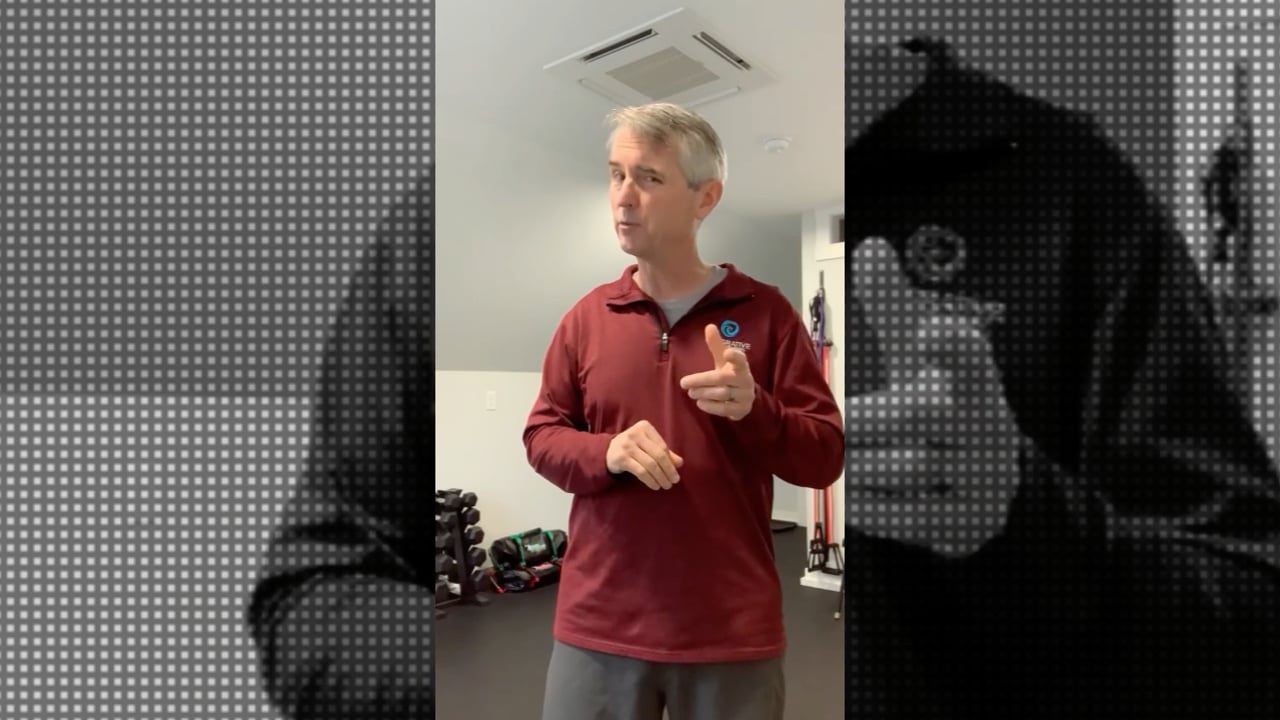
横隔膜が身体を人質にとる「姿勢筋」になる
呼吸の主導筋であるはずの横隔膜が、身体構造のポジションの変化による影響を受けて、本来の仕事ではなく姿勢を支える筋肉として働き始めてしまう時、身体にはどのようなことが起こるのか?マイケル・ムリンがクライアントに説明をする解説のビデオは私達の理解を深めることも助けてくれます。

ピラー1:関節ローリング
FTI(ファンクショナル・トレーニング・インスティチュート)のコーチ・タレクが、プログラムのピラー1と呼ぶセクションで行うことのできる、関節モビリゼーションテクニック、関節ローリングの実践方法をデモと共に紹介してくれます。

脳の発達に欠けているリンク
クローリングをしながら、さらに脳に対して真新しくて楽しいチャレンジを提供する方法を試してみませんか?楽しく遊ぶように動くことが、私達の動きを、そして身体をより動きやすく楽にしてくれることを実感できると思います。
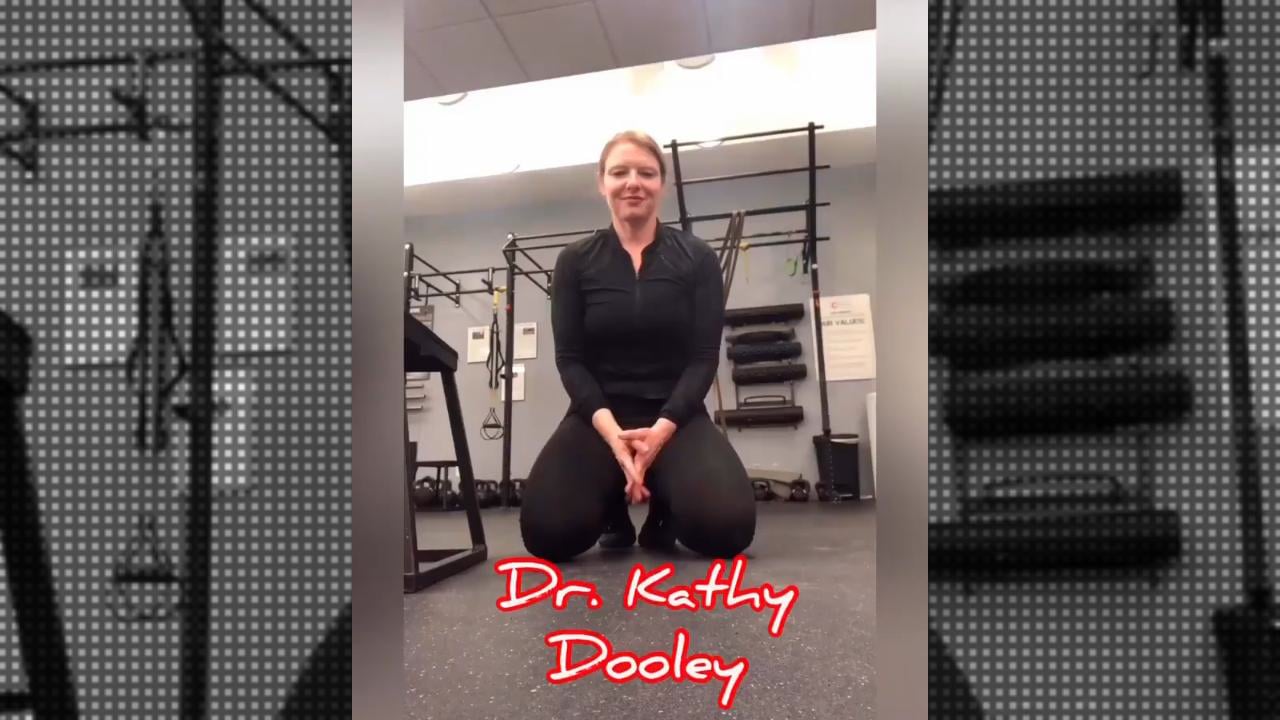
股関節の固さ解決の答えはストレッチではない
股関節周辺の固さに悩まされて、延々とストレッチを繰り返してもその効果感が長続きしなかったという経験を持つ人は多いのではないでしょうか?ストレッチではなく、何か他の要素が必要なのだとしたら?試してみたいですよね。

Kaori’s Update #97 - オリジナルストレングス
オリジナルストレングスというのは、動きの修復を目指すムーブメントシステムの名称ですが、この名称が意味するのは「元来の強さ/元々持っている強さ」です。生まれてから死ぬまで、強くあるように、そして自らを治癒することができるようにデザインされた人間の素晴らしい強さを、さまざまな動きの可能性を探求することで再確認してみませんか?

機能のために重要なエビデンス:関節鏡下半月板部分切除後の機能的パフォーマンス
Ganderup T, Jensen C, Holsgaard-Larsen A, Thorlund JB. Recovery of lower extremity muscle strength and functional performance in middle-aged patients undergoing arthroscopic partial menisectomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2017, 25:347-354. この論文は、部分的な半月板切除術の前後の中年患者の筋力と機能的パフォーマンスの回復について記録してます。2年間にわたり、関節鏡下半月板切除術を受けた23人の患者を、手術の2週間前、そして術後3ヶ月および12ヶ月で検査しました。アイソメトリック筋力データは、膝屈筋群、膝伸筋群群、および股関節外転筋群から得られたものです。最大力生成にかかる時間を使用して、力の発達速度を計算しました。さらに、30秒間の片脚スクワットと最大前方ホップ距離という2つの機能テストも測定されました。 結果は、膝伸筋群の力および発達速度における術前の欠損を示しました。片脚スクワットとホップ距離テストでは、負傷した脚と負傷していない脚の間にも統計的な差がありました。4つの尺度の不足率は12%から19%の範囲でした。術後3ヵ月では、左右の欠損が残り、股関節外転筋群と膝屈筋群も統計的差異を示しました。12ヶ月で、データのすべての相違は解決されました。これらの結果は、手術後12ヶ月から48ヶ月後に解決する術後のかなりの欠損を示す以前の研究を支持しています。 なぜこの研究が機能にとって重要なのでしょうか?理由の1つは、一部の人が「良性」と考え、術後トレーニングを必要としない手術後の機能障害を示していることです。もう1つの理由は、著者が力の発達を計算したことです。発達するのに長い時間がかかる筋力は、ほとんどの活動にとって実行可能なリソースではない可能性があるために、この計測は機能的な結果をもたらします。3つめに、従属変数には30秒間の片脚スクワットとホップ距離という2つの機能テストが含まれていたことです。他のテストの方がより適切であると主張することもできるでしょうが、筋力のリソースがどのように利用されるかのいくつかの尺度を見ることは、運動の指導者にとって重要なものです。 運動業界の私たち全員が、患者/クライアントが怪我の原因となったスポーツ/活動にいつ復帰できるかを判断することを挑戦してされています。怪我/手術からの時間は、個人差を考慮しないため、効果的な基準ではありません。膝の怪我からの復帰は、股関節、足、およびキネティックチェーンの他の領域からの影響のために測定するのが特に困難です。足や股関節の単独のテストでは、必要な情報を得ることもできません。身体全体を関与させ、膝への本物のストレスを再現するように設計されて機能的テストが行われる時にのみ、クライアントが復帰する準備ができているという確信を持つことができるのです。 グレイ・インスティテュート®において、アプライド・ファンクショナル・サイエンス®のプラクティショナーは、「36-360」テストと呼ばれる動きのシークエンスを活用するように教えられています。このテストは、36回のジャンプまたはホップを90度の回旋と組み合わせて、両方向に360度の身体の回旋(および膝のストレス)を生成します。ホップテストが片脚で36回連続して行われる時、片脚ともう片方の脚を比較するために使用できます(この研究調査で行われたように)。「36-360」は、回旋シークエンスを完了するまでの時間を記録すると共に、カバーされた水平距離の合計を測定するために使用できます。両側の損失の割合を計算して、残存損失または復帰の準備を文書化することができます。 「36-360」は、動的機能活動で見られる膝への3次元的ストレスを作り出します。これは、身体の神経筋骨格リソースに高い要求を課すため、患者/クライアントが全方向に片脚でホップする能力を示した場合にのみ、プレイ再開テストとして使用されます。しかし、患者/クライアントが「36-360」の構成要素の動きのプログレッションを進行している場合には、それが患者/クライアントと運動プラクティショナーに機能の客観的な尺度を提供する運動チャレンジを提供してくれます。

アスリートのための簡単な股関節伸展アセスメント
エクササイズはテストである、という捉え方をすれば、様々な動きのドリルを実践するところを観察することでその動きのパターンが成功して実施されているか否かを見極めることができます。股関節伸展の動作を確認するためのドリルを段階的に後退させるシークエンスをリー・タフトがシェアします。

ハイプル&キャッチ
ケトルベルでのパワーのエクササイズといえば、誰もがスイングから始めるように思いがちですが、スイングってかなり難しいのですよねぇ。確実にヒップヒンジのパワーを発揮する方法を学習して、エキセントリックのコントロールを学習するためにジョシュは他の選択肢を推奨しています。

ロールダウンのタクタイルキューイング:エピソード3
ロールダウンの動きにありがちなエラーを優しく修正したり、後頭骨と仙骨の間のスペースをよりオープンにしたりする感覚を、軽く優しい手の感覚で伝えることを目指したタクタイルキューイングのポイントをカリン・ガートナーがシェアします。

運動と変形性膝関節症に関する専門家の偏見との奮闘
私たちは、膝の変形性関節症(OA)の管理のための新しい臨床ケア基準を持っています(リンクはこちら)。これは、私が実践する方法と私が教えることと完全に一致しています。 これ以上の偏見を確認することはできず、私は幸せであるべきです。しかし、私は心地悪いのです。 それは私が愛するものを支持します: 良い教育 適切な画像化 人間を中心としたケア その人全体に対応する 関節のレジリアンシーに関する楽観主義 「磨耗や損傷」に関する信条の再構築 栄養 減量 痛みと機能のための運動 すべて良いことのように見えるでしょう?そう、しかし、私は同様の臨床結果を持つ他の保存的アプローチを提唱することなく、痛みと機能のための運動を提唱することに気まずさを感じているのです。私たちは一貫して、他のあらゆる介入と同様なエビデンスに基づく実践の厳格な基準を、エクササイズに対しては保持していません。そして、この一貫性の欠如が私を心地悪くさせるのです。私にとって、ここで強い意見を持つことは学術的に真実性に欠けるのです。運動に関する研究基盤を簡単に批評し、私たちの偏見が患者のケアにどのように悪影響を与える可能性があるかを説明させてください。 運動は他の介入と比較して非常に低い基準に保たれています。 研究者と臨床医は、研究が行われる前に、運動と身体活動が膝の変形性関節症の主要な治療法であるべきであるという決定を下したことを私は主張します。 私達が介入を評価する時のゴールドスタンダードは、ランダム化比較試験(RCT)の宝庫であることを願っています。これらのRCTでは、対照群が必要とされます。介入の非特異的な影響を制御する必要があるのです。これは、運動と変形性膝関節症の世界では決して起こらないか、まれにしか起こらず、それを誰も気にしていないようです。 この例は、GLADのエクササイズと教育の試験(リンクはこちら)でしょう。これらは、エクササイズと教育が効果的かどうかをテストするために設計されたものではない、実用的な研究です。対照群がないため、その結論を出すことができません。 要約を読むだけで、著者がGLAD介入が痛みの軽減と薬物使用の減少につながったと述べているのがわかります。しかし、それを言うことはできないのです。対照群がなければ、その結論を出すことはできません。私たちは、鍼治療や電気療法などの他の介入に対して、このような種類の試験を受け入れはしないでしょう。実際、多くの臨床診療ガイドラインでは、対照群が存在しないため、受動的治療法に関する文献を明示的に除外しています。 運動と他の介入との間で直接比較を行うと、運動はそれほどうまくいかないことがわかります。たとえば、Messier 2021の論文(リンクはこちら)では、高重量の抵抗トレーニングは非常に低負荷の運動プログラムを上回らず、注意対照群を上回りませんでした。GLADプログラムを生理食塩水注射と比較したときにも同じことが見られ、グループ間で違いは見られませんでした(リンクはこちら) なぜ私はおどおどしているのでしょうか? 私は、運動と変形性膝関節症の最大の応援団員になりたいのです。この基準があらゆる種類の運動を提唱し、身体活動のための多くの選択肢を提供するという点で、非常に患者中心であることを嬉しく思います。 これは、「適切なアライメント」と「神経筋コントロール」の運動を提唱していた元のGLADプログラムからの大きな改善です。(当時の人々は、そのタイプの運動の必要性の証拠として、すべての非対照GLAD試験を引用しました…彼らは決してそうすべきではありませんでしたが、やってしまったのです。)幸いなことに、私たちはそこから前に進みました。 しかし…もし私が文献をよく知っているのだとすれば、いかにして学術的に厳密で正直であることができるのでしょうか? どれだけ不十分にテストされているかを知っているのに、いかにして運動を支持することができるのでしょうか? 私たちは他の一般的な介入をはるかに高い基準に保っているがゆえに、それらの介入を省略する基準を、いかにして支持できるのでしょうか? または、運動に関する研究が多く行われているので、臨床診療ガイドライン(CPG)に含めるべきであると言いますが、そのような推論は循環的で自己充足的です。私たちはこの説得力のない運動研究を続けており、それがCPGで繰り返され続けています。そして、CPGでこれらの介入を最小限に抑え続ければ、当然それらを研究する試験が少なくなるために、その他の介入(手技療法、受動的療法、鍼治療など)に関する研究は限られていると言われることになるでしょう。単に自己充足的になるのです。運動は厳密さなしに受け入れられ、他の形態のケアは研究がないために却下されます。 私たちは本当に人間を中心に考えているのでしょうか? 人間を中心としたケアの基盤は、選択肢の提供です。そして、人々が持っているオプションと、それらのオプションを支える研究について、私たちは正直でなければなりません。このような臨床ケア基準とCPGは、文献の非常に偏った解釈に基づいてオプションを単に選別しているのです。これは基準からの引用です: 「治療用超音波や電気療法などの受動的な手技療法は、変形性膝関節症の治療において重要な役割を果たしていない」。 これもまた、これらの受動的な様式に関する研究の解釈に基づいています。 実際に痛みと機能を調査する論文を見ると、受動的様式グループが痛みと機能に同等の減少を有することがわかります。しかし、これらの論文の多くには対照群が存在しません。そこで、CPG委員会はそれらの論文を無視してしまうのです。 他の論文では、偽の比較グループがあります。そして、何が見つかるでしょうか?両方のグループが痛みの軽減と機能の改善を示します。しかし、違いがないため、私たちは結果が現実的ではないと言います。 しかし、繰り返しますが、私たちは何をしたのでしょうか?私たちはこれらの介入を、運動とは異なる基準に保っているのです。 徒手療法や鍼治療でも同じことが見られます。エクササイズを徒手療法に対して直接比較してみると、痛みの軽減や機能の違いは見られません。しかし、運動に関する研究が非常に多いため(弱いものですが)、ガイドラインはより支持されているものとして運動を提唱します。それがより良いということを意味しているわけではないのです。ただ、研究がより多いというだけです。これは私が先に述べたように、CPGによる自己充足的な予言です。 もし私たちが患者に対して本当に正直であるならば、彼らには痛みと機能を助けるための多くの選択肢があると言うのは公平だと思います。私たちは、少なくとも私は、正直に言って、エクササイズが優れていることが「証明されている」とは言えません。そして、私たちがそれを言うことができないのであれば、これらのガイドラインはどのようにそれを言っているのでしょうか?なぜ彼らは人々から選択肢を奪うのでしょうか?この人間中心のケアはどうですか?私には門番をしているように見えます。 運動やその他の選択肢についての、より正直な見方は何なのでしょうか? 臨床医と患者の会話は、次のようになるとイメージします: 「運動は膝の痛みを和らげるのに役立つかもしれない選択肢の一つだよ。運動を続けて活動的でありたいのであれば、絶対にできますよ。運動は完全に安全で、あなたにとって有害ではありません。変形性関節症を悪化させることはありません。エクササイズプログラムを開始したいのなら、いくつかのオプションとガイダンスを提供できます。エクササイズには、転倒防止、健康的な老化、すべての原因による死亡率の低下など、健康上のメリットもたくさんあります。」 「しかし、運動をしたくない、何か他のことを試したい場合には、痛みや機能の改善を報告している人々がいるという研究や多くの事例がいくつもあります。鍼治療、理学療法、手技療法、装具、さらには歩行の再トレーニングなどが役立つかもしれません。しかし、これらの問題は、誰かがあなたに対して行う介入であるということです。非常に受動的です。クリニックに来なければならず、費用がかかる傾向があり、運動のような健康効果は得られません。」

膝の痛みなくスクワットの仕方を指導する
膝に痛みを抱える人に対してスクワットを指導しようとする際に、どのような方法で指導をすることがより効果的なのでしょうか?ツールを選択する際に、そのツールを使う目的は何か?そしてその先に何を目指しているのか?理解した上で選択していきたいですね。