マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。
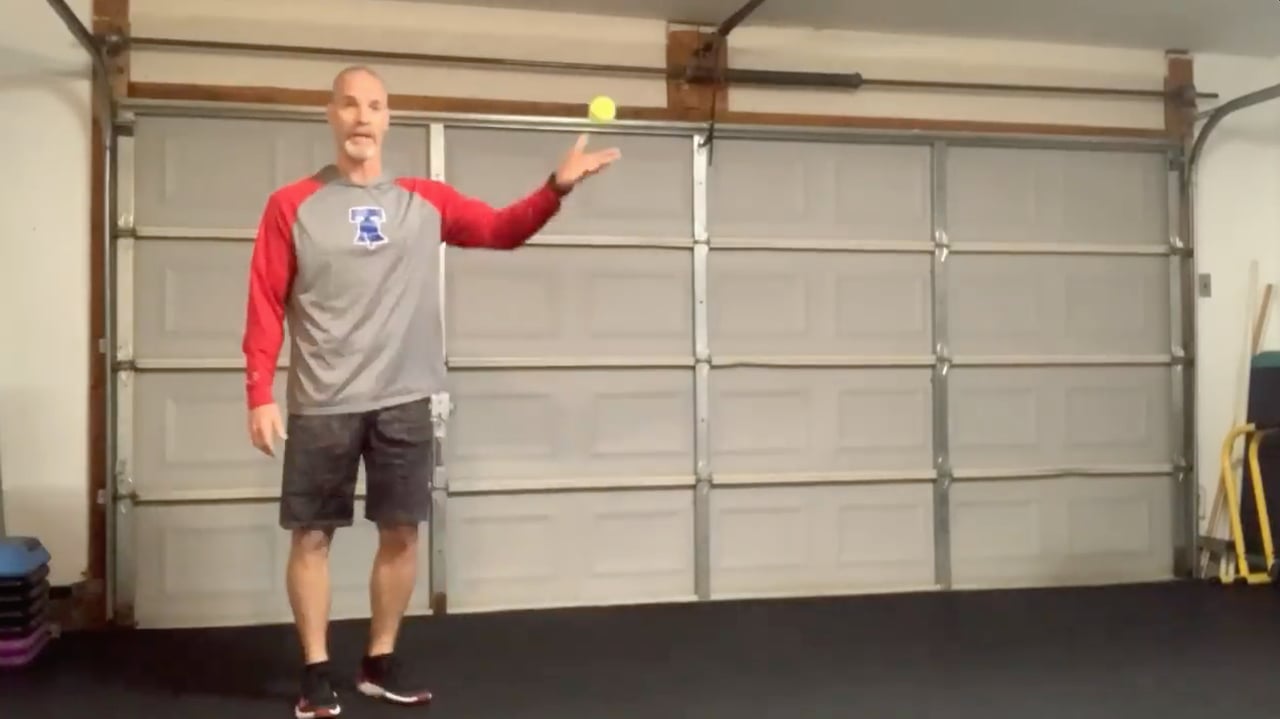
ダイナミックな動きと手と目のコーディネーション
SAQスペシャリストであるリー・タフトが、一般成人に向けて、特に年齢を重ねていく大人達に向けて発信している動きのアイデアのシリーズから、楽しくボールをトスしたりキャッチしたりすることで身体機能をトレーニングできる方法をシェアします。すぐにでも試せますね。

ケトルベルスイングの科学とテクニック:前十字靭帯損傷予防との関わり
ケトルベルスイングの科学的背景と、それに関わるテクニックをカバーするシリーズのパート3では、ハムストリングスの動員に関してのEMGのデータをその他のエクササイズと比較しながら、特に内側ハムズとリングスの動員率が高い理由を解説します。ACL障害予防との関わりとは?

オフセット・スプリンター・デッドリフト
ケトルベルを使ったデッドリフトのプログレッションとして、両足平行から突然片足にジャンプしたりするケースもよく見かけますが、側屈や回旋の力により安全に確実に抵抗する方法を学ぶためには、その間のステップを飛ばしてしまわないことも重要です。どのような方法があり得るのでしょうか?

60代そしてその先に向かってリフトする最良の方法
68歳の現在も大会でリフトするストレングスコーチのダン・ジョンが、リスナーからの質問に答えて、年齢を重ねながらリフティングを継続していくために、可動性や強さを維持し続けるために可能な最善の方法と考え方についてシェアします。

ハーフニーリングのコーチングとキューイング
ハーフニーリングのポジションをしっかりと設定して維持するだけでも、様々な身体構造と機能が活性化されます。このハーフニーリングのポジションを使うことのメリットについて、そして実際にジムで行うことができるエクササイズのキューイングについてマイク・ロバートソンがシェアします。
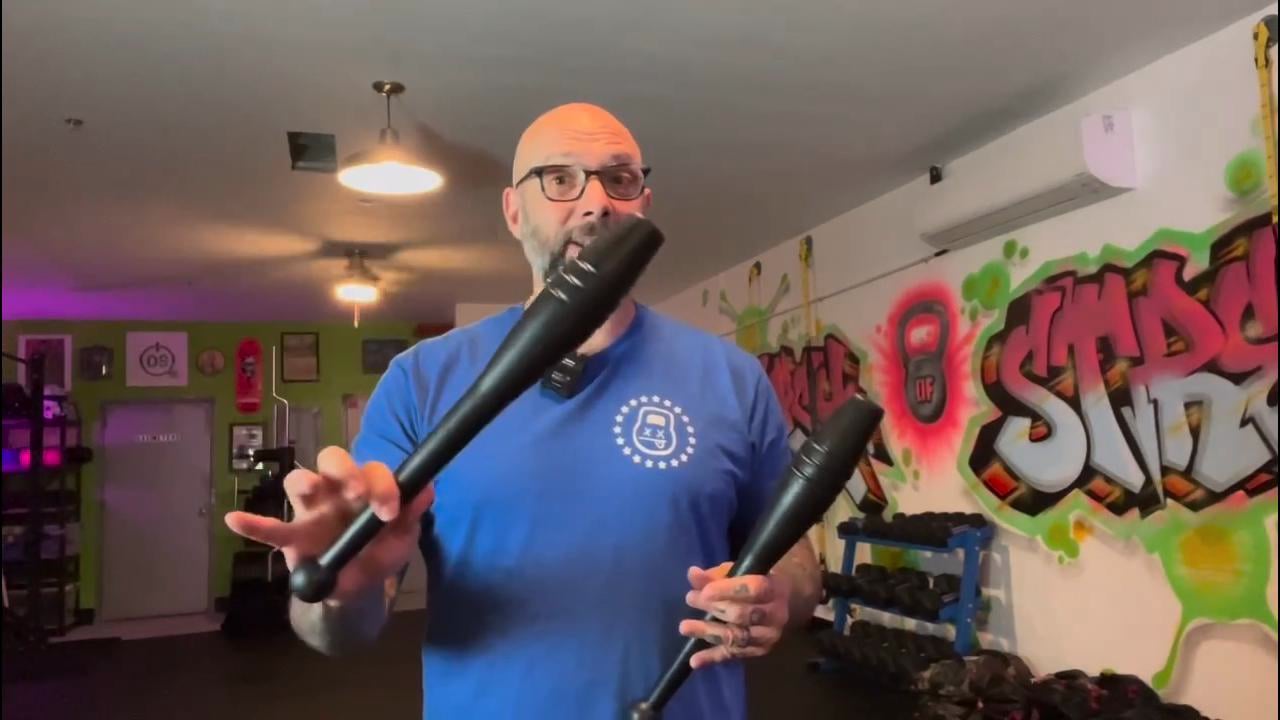
インディアンクラブスイングへの簡単なイントロ
自分自身の肩の手術からの回復にもインディアンクラブを活用しているコーチ・フューリーが、インディアンクラブを見たこともない人にもわかる簡単なイントロを提供してくれています。私も1ポンド程度の軽いクラブを使いますが、螺旋の動きが組織を牽引する感覚がなんとも言えず大好きです。試してみたくなりますよ。

ケトルベルのボトムアップの動きを探索する
必ずしもケトルベルである必要はないけれど、自分自身にとってちょうど適切な負荷の量や、ちょうど適切な時間の量を見つけてみること、自分がやりたいと思っていることを試してみること、探ってみること、そして自分自身について発見をすることがいかにワクワクするかをティムがシェアします。

機能のために重要なエビデンス:タスク特化&状況依存
Windhorst U. Muscle proprioceptive feedback and spinal networks. Brain Research Bulletin 2007, 73: 155-202. この論文は、感覚機械受容器からの求心情報の特定の側面の驚くべきレビューを提供し、グレイ・インスティテュート®の固有受容器シリーズのビデオで議論されたものです。この論文は、主に動物の実験を網羅していますが、人間の動きについてのいくつかの研究も含んでいます。タイトルにもかかわらず、ゴルジ腱器官(GTO)が提供する情報に関する多くの研究をカバーしています。この記事で焦点を当てるのは、この論文のその側面です。 特にGTOからの信号が脊髄のインターニューロンに与える影響について、Windhorstは「...これらの効果は状態に依存する、つまり、状況と運動行為のタスクに依存する」と述べています。初期の研究からのGTOからの情報の単純な見方は、GTOからの放電が脊髄ニューロンに情報を送り、その脊髄ニューロンがその腱に接続された筋肉を抑制するというものでした。これは、四肢が受動的に伸ばされた場合に当てはまるものです。これは自律性抑制と呼ばれます。この筋肉収縮の抑制は保護機構であると仮定されました。 より最近の研究では、GTOからの放電と筋肉への影響はそれほど単純ではないと判断されています。ここで状況とタスクが重要になるのです。動物が体重を支える位置にある場合、GTO放電は、抑制ではなく、スタンスを維持するための力の生成を高める促進効果を生み出します。したがって、体重を支える四肢に関する他の固有受容覚の入力が、GTOからの信号に対する反応を変化/調節するようです! なぜ動物のGTOに関するこの知識が「機能にとって重要」なのでしょうか?神経放電を観察する人体に関する限られた実験から、動物実験から学んだことと多くの一致があるのです。脊髄のインターニューロンが人間でも同じように反応する場合、この情報を運動制御と動的システム理論からの知識と組み合わせると、私たちのテストとトレーニングの動きが活動に忠実であることがいかに重要であるかを示唆しています。 長年にわたって、グレイ・インスティテュート®は、機能はタスク特化であり、状況に依存するという「声明」を出してきました。あらゆるの活動のチェーンリアクション®バイオメカニクスを理解したうえで、患者/クライアントに挑戦するために選択した動きは、その活動そのものにできるだけ似ているものでなければなりません。特定の出力(運動反応)が必要な場合、その動きは特定の感覚入力を提供しなければなりません。 単語を書くというタスクは、この点についての洞察を提供する例として使用できるかもしれません。特定の単語を書くためには、その単語を構成する各文字を書く能力が必要です。文字C、A、およびTの書き方を知っていても、DOGを書く助けにはなりません。これはタスク特化です。これは、関節運動と筋力のリソースを持つことに似ています。D、O、Gを書くための筋肉の動きと関節の動きをすべて学習すると、タスクは完了しますが、その後状況依存性が重要になる可能性があります。ペンで紙に単語を書くことは、黒板にチョークで同じ単語を書くこととは非常に異なる状況になります。必要とされる関節運動と筋肉の動きは非常に異なります。 同様に、椅子に座って膝を曲げることは、抵抗に対して膝を曲げることとは非常に異なり、立って体重を支える姿勢で膝を曲げることとは全く異なります。タスクと状況は、あらゆる動きを成し遂げるための重要な要素なのです。患者/クライアントを評価し、トレーニングするための動きは、患者/クライアントが望む機能を(可能な限り)再現しなければなりません。固有受容器は、望ましい運動出力を生成するために適切な感覚入力を提供します。しかし、感覚入力を提供する関節の動きは、本物のグローバルな動きの一部でなければなりません。動きにより大きな本質性を与えるものは、グレイインスティチュートのファンクショナル・ムーブメント・スペクトラムを見ることで推測することができます。アプライド・ファンクショナル・サイエンス®の原理原則に基づいて、ファンクショナル・ムーブメント・スペクトラムは、私たちの動きの「機能性」のためのリトマステストとしての役割を果たすだけでなく、動きをより機能的にする方法について無限の「提案」を提供します。

マコーネル膝蓋テーピングに効果がある理由
膝蓋大腿痛の最も一般的でありながら、理解が進んでいない治療法の1つは、膝蓋骨テーピング、またはマコーネルテーピングとも呼ばれる方法です。1984年にオーストラリアの理学療法士ジェニー・マコーネルによって初めて紹介された膝蓋テーピングは、ますます人気が高まっています。膝蓋テーピングを行う元々の意図は、膝蓋骨の傾きと位置を変更することで、最も一般的には、横方向に変位した膝蓋骨をより内側に移動させて、膝蓋大腿「トラッキング」の問題を修正することでした。 現在までに、膝蓋大腿テーピングの有効性について多くの研究が行われており、それらの結果は矛盾しています。変化した膝蓋運動学、向上したEMGと筋肉機能、改善された動的アライメント、そして膝蓋大腿関節反力の減少を示す全ての研究に対して、まった反対の結果を示す別の研究があるようです。しかし、1つだけ確かなのは、ほとんどの研究が、膝蓋骨テーピングが膝蓋大腿痛症候群患者(PFPS)の痛みを軽減することに同意している傾向があるということです。ここでの質問は、なぜなのか? 膝蓋テーピング - なぜ効果があるのか、その理由として考えられるものは何か? 2010年に発表された研究は、膝蓋テーピングが働くメカニズムを説明していると思います。実際、この研究の著者は論文でこのメカニズムについて全く触れておらず、彼らが研究したのは実際それではなかったのですが、この論文を読んだ後、私は「なるほど」という瞬間を経験したのです!後で説明しますが、まずはこの論文について話し合いましょう。 マコーネルテーピングとダイナミックMRI Journal of Physical Therapyに掲載されたDerasariらの研究では、ダイナミックMRIを用いたマコーネルテーピング後の膝蓋大腿痛患者の膝蓋運動を調べることを試みました。これは、能動的な膝の伸展中に6自由度で膝蓋大腿運動を評価する最初の研究です。 1年以上PFPSを患っていた14人の被験者がこの研究に含まれ、膝蓋テーピングの有無にかかわらず、能動的な膝伸展中にダイナミックMRIを受けました。この写真のように、膝蓋骨を内側にグライドさせるために、標準的なマコーネルテーピングを外側から内側に向かって適用しました。 この研究の結果、膝蓋テーピングは、膝蓋骨を内側ではなく、下方向に有意に移動させたことが示されました。実際、この研究では、すべてのPFPS患者が膝蓋骨の外側への変位をもっていたわけではなく、内側に変位した人もいたことが示されました。しかし、(ここで私の電球が消えたのですが)、内側に変位した膝蓋骨を持つ人は、テープが標準的な外側から内側に向かって貼付されたにも関わらず、実際に膝蓋骨の位置の外側方向へのシフトが見られました。膝蓋骨はテープの方向に反して動いたのです!おそらくこれが、文献に矛盾する研究が数多くある理由でもあるでしょう。 なぜ膝蓋テーピングが本当に効果があるのか この研究は私にとって大きな「なるほど」の瞬間であり、膝蓋大腿テーピングがなぜ効果があるかを説明するための有望な理由を見つけたのかもしれないと思います。考えてみてください。外側から内側への膝蓋骨テーピングは、外側に変位した人の膝蓋骨の内側へのシフトを引き起こしましたが、内側に変位した人では、膝蓋骨が実際にテーピングの方向と反対方向に動いたのです。なぜでしょうか? この研究を読んだ後、テーピングは膝蓋骨を一方向に動かすのではなく、膝蓋大腿関節を圧迫するのだと考えます。下の図を見てください。左側の図は、膝蓋骨が外側に変位した膝蓋大腿関節を示しており、膝蓋骨は膝蓋溝の中心に位置していません。右側の図は、同じ膝ですが、膝蓋骨テープ(オレンジ色の線)を貼付した状態です。ご覧の通り、膝蓋骨を溝内中央に配置し圧迫し、膝蓋骨は滑車の突起部に対してグライドします: 内側に変位した膝蓋骨についても同じことが言え、外側から内側に向かってテープを貼付しても、関係なく、この場合、膝蓋骨は膝蓋溝に沿ってグライドするため、実際には外側にシフトします。 これは本質的に、膝蓋溝内で膝蓋大腿関節を圧迫することによって、膝蓋大腿関節の「センタリング効果」を引き起こします。その後、この「センタリング効果」は膝蓋大腿の接触面積を増加させ、これが痛みに大きな影響を与える可能性があります。 変位した膝蓋骨は、膝蓋大腿接触面積を減少させ、同じ量の力をより局所的な領域に加えることはよく知られています。膝蓋骨を滑車の中央に配置することにより、この力はより大きな表面積に分散され、軟骨へのストレスが減少します。以下の図でご覧いただけるように、同じ量の力がより大きな接触面に加えられると、力は軟骨全体に均等に分散されます: 明らかに、さらに研究を行う必要がありますが、この仮説はいくつかの潜在的な妥当性を有するようであり、なぜ膝蓋テーピングが機能するのか、なぜ文献に非常に多くの矛盾があるのかを説明することができるかもしれません。

テニスにおけるメンタルタフネス
ロジャー・フェデラーは、歴史上最高のテニスプレイヤーの一人です。彼自身が最近の卒業式のスピーチで提供した、彼のキャリアに関する興味深い統計をご紹介します。 彼はプレしたポイントの54%のみで勝っています。 半分より少し良いだけなのです!明らかに、テニスでは勝ちと負けの間にはわずかな違いしかありません。ここで、フェデラーが勝ち続けることを可能にした精神状態について話しています。 「平均して2回目のポイントごとに負けるとき、すべてのショットにこだわらないようになります。自分自身にこう考えるようにします:『ダブルフォールトだったけど...ただのポイントだ。』『オーケー、ネットに来て、またパスされた...ただのポイントだ。』素晴らしいショットでさえ、ESPNのトップ10プレイリストに入るオーバーヘッドバックハンドスマッシュでさえ、それもただのポイントに過ぎません。これをお話ししている理由はここにあります。ポイントをプレイしているとき、それが世界で最も重要なことでなければなりません。そして、その通りなのです。しかし、それが過ぎ去った時、それは過ぎ去ったことなのです。この考え方が重要であり、なぜなら、これにより、次のポイントに集中し、明確に、そしてフォーカスできるようになるからです。」 元競技テニス選手、スカッシュ選手として、私はここ数週間このことについてかなり考えていました。以下は、テニスにおけるメンタルゲームについてのいくつかの考えです。 (画像はウィキメディアコモンズ提供) 興奮と恐怖のバランス テニスでうまく競うためには、結果を心から気にかけることが求められます。勝利への強い欲求がなければ、エネルギーと注意力という資源を完全に動員することはできません。生理学的に言えば、ストレスホルモンを放出して最高レベルで戦い、集中する準備をするためには、緊急事態を認識する必要があります。 しかし、ここにトレードオフがあります:勝利への強い欲求は負けることへの恐れを生み、この恐れは不安を生み出し、それは最悪の気分なのです。胃のざわつき、胸の締め付け、あるいは観衆の前での屈辱を鮮明に想像することなどがあります。この最悪さを単に我慢し、戦い続けることが、テニスにおける「メンタルタフネス」の意味することの大きな部分です。 恐怖によって生み出されるもう一つの大きな問題は、テクニックの低下です。恐怖は手の震え、または全身に抑制感や躊躇感を引き起こす可能性があります。これにより、動きの範囲が制限され、流れるような力強い動きに必要なスムーズな自然さが失われます。その結果、短くて硬いスイングになることがよくあります。私たちはこれをボールを「プッシュする」と表現していました。受け入れられた解決法は、「打ち出す」ことで、これは自分のストロークを信頼して、それを飛ばすことを意味します。ポケットビリヤードにも同様の概念があり、ストレスを感じるとストロークが短くて不格好になる傾向があるのですが、その対処法は「ストロークを出す」ことです。流れを妨げる厳格なコントロールを手放す必要があります。しかし、悪い結果を恐れているとき、それは難しいことです。 リラックスしようとすることは役に立ちますが、強さを失うほどリラックスしすぎてはいけません。負けることへの恐れに対する非常に自然な反応は、感情的に戦いから離れることです。これは本当の戦いではないので、いつでも試合を真剣に考えるのをやめるのはかなり簡単にできることです。頭の中で「ただのゲームだ」や「それほど大したことない」といった声が聞こえ始めるかもしれません。これらのポイントは本当かもしれませんが、それは叡智から来ているのか、恐怖から来ているのか? 遊び場でゲームを競い合う子どもたちについて、私が気づいたことを思い出しました。かけっこのような単純な競技を避ける子どもたちがいて、その理由を尋ねると、誰が勝つかなんて気にしないと答えることがあります。これは場合によっては本当かもしれませんが、逆の場合もあり、問題は誰が勝つか気にしないということではなく、誰が勝つか気にしすぎているということです。彼らは負けの痛みに耐えることができず、これが彼らが競争を避ける理由なのです。 テニスコートでは、このようなことについて自分自身に嘘をつくのは簡単です。勝つことを気にしていないと自分に言い聞かせるかもしれませんが、現実には、負ける可能性のある痛みを軽減するためだけに言っているのです。本気で挑戦しなければ負けは許容できるかもしれず、そうすれば、もっと一生懸命戦っていれば勝てたかもしれないという幻想を維持することができます。しかし、全力を尽くして負けた場合、自分が思っているほど自分が優れていないという現実を受け入れなければなりません。それは苦痛であり、テニスにおけるメンタルタフネスの一部は、その脆弱な立場に自分自身を置くことです。 競技のストレスから抜け出すもう一つの方法は、言い訳をすること:「先週病気だったから、この試合は数に入らない」、「練習していない」、「相手は運が良かった」といった言い訳を。もう一つの落とし穴は、より優れたプレイヤーに対して良いパフォーマンスをしたなど、勝利以下の何かに満足することです。これは試合が終わる前にリラックスする許可の一種として使えます。私の頭の中には、緊張した試合の最中、ほぼ毎分このような考えが浮かんできます。私は、勝利のために戦うことをやめさせないように、精神的/感情的な努力をする必要があります。 要約すると、ベストを尽くすためには、恐怖と不安を最小限に抑えながら、興奮と強さを最大限に引き出すことを必要とするのです。このバランスを維持するには、常に内なる考えを処理し、セルフトークを通じてそれらを管理する必要があります。このバランスを見つけるための哲学的なアプローチがいくつかあります。これには、「今この瞬間にとどまる」(上記でフェデラーが述べた)ことや、結果ではなくプロセスに強く執着することが含まれるかもしれません。これらの哲学にはある種の知恵があることは確かですが、実際にそれらを適用することは単に言うことよりもはるかに困難であり、実際に自分に合うものを見つけることは非常に困難です。 テニスに固有の精神的な課題の1つは、各ポイント間のアクションの中断です。プレーが連続しているバスケットボールやサッカーのようなスポーツとは異なり、テニスではポイントの間に考える時間が十分にあり、考えすぎることもあります。過去にこだわったり、将来を心配したりする機会です。これはあなたを今この瞬間から連れ出し、息が詰まるための完璧な環境を作り出します。 競技中に、ある種の禅の状態やフロー状態に入り、最大限の覚醒と集中力を持ち、最小限の不安と落ち着きを感じる、稀な時があるでしょう。どういうわけか、将来や過去を心配することなく、完全に現在に集中したままなのです。このような状態は本物だと思いますし(私自身も時折感じたことがあります)、正しいマインドセットとセルフトークをすれば、もっと頻繁にこの状態に到達できるのです。しかし、試合では必ず最悪の状況に陥ることがあり、その状況に耐えて、前に進むために最善を尽くすことができるだけです。 (画像はウィキメディアコモンズ提供) 戦略:リスクと報酬のバランス テニスの戦略的側面はいくらか過大評価されていると思いますし、ショットの選択にはそれほど多くの考えが関係していないと主張したいと思います。サッカーのように、コーチが何百もの異なるプレーから選ぶことができるのとは異なり、テニスプレイヤーは通常、クロスコートか直線という狭い選択肢の中から選ぶことになります。 テニスにおける優れた意思決定は、ショットの選択ではなく、どれだけアグレッシブにショットを実行するかについてです。各ストロークで、プレイヤーはボールをどれだけ速く、ネットのどれだけ高く、どれだけ奥に、どれだけサイドラインに近づけるかについて何らかの意図を持たなければなりません。より攻撃的なショットは、勝つチャンスを増やしますが、エラーのリスクも高くなります。賢明なテニスとは、これらのリスクと報酬の確率を何度も何度も正確に調整することを意味します。試合を通してわずかに優れた判断を下すプレイヤーは、最終的に圧倒的な優位性を持つことになります。 この側面で良い選択をすることは、上記で説明した興奮と落ち着きのバランスと並行した感情的なスキルです。恐れる心は守りに入り、興奮すると攻撃的になりすぎる傾向があります。プレイヤーは、適切なレベルの攻撃性と忍耐力を維持するために、常にセルフトークを行う必要があります。 このプロセスの繰り返す性質は、飽きやすい人や創造性を発揮したい人にとっては課題になる可能性があります。サッカーやバスケットボールのようなスポーツでは、ゲームの複雑さは常に新しい問題を提示し、新しい解決策を生み出すことを意味します。アメリカンフットボールでは、1回の大きなプレーで試合が大きく変わる可能性があります。テニスでは…それほどではありません。何度も同じことが繰り返され、すべてのポイントは1ポイントしかありません。勝利は、賢明で高い確率を持つことを繰り返すことで得られます。1ポイントで試合に勝つことは決してありません。したがって、創造的な天才よりも、職人のような努力家を好む傾向があります。 このような精神的、感情的な努力はすべて消耗するものです。テレビでスポーツイベントを観戦するとき、結果が気になってしまうと、どれほど観戦が大変になるかに気づいたことがありますか?サスペンス、逃したチャンスに対する不満、浮き沈みの激しさは、数時間で疲弊してしまうことがあるものです。選手にとって、これがどれだけ大変か想像してみてください!そして、彼らは毎日このようなことをしているということを考えてみてください。 私の個人的な経験では、テニス(とスカッシュ)をプレイすると、2、3試合は良いプレイができましたが、それ以上の長期間、そのレベルの強さを維持するのは難しいと感じました。そして、5セットの試合などしたこともありません!フェデラーやジョコビッチのような選手達が、毎日、毎週、毎年、飢えた若者からの挑戦を打ち負かして、トップの座を守る姿を見るのは、とても驚嘆に値することだと思います。彼らの精神的/感情的なスキルは、彼らの身体的能力と同様に稀である可能性があると思います。

荷重回外と回内の解剖学と全身の出来事の解説
足部の回内、回外の動きは、単に足の後ろ側の部分で起こる動きのように捉えがちですが、これらの動きは全身に影響し、また全身の動きがこれらの動きに影響もします。Dr.キャシーが、実際に動きながら、歩行周期におけるこれらの動きを解説します。
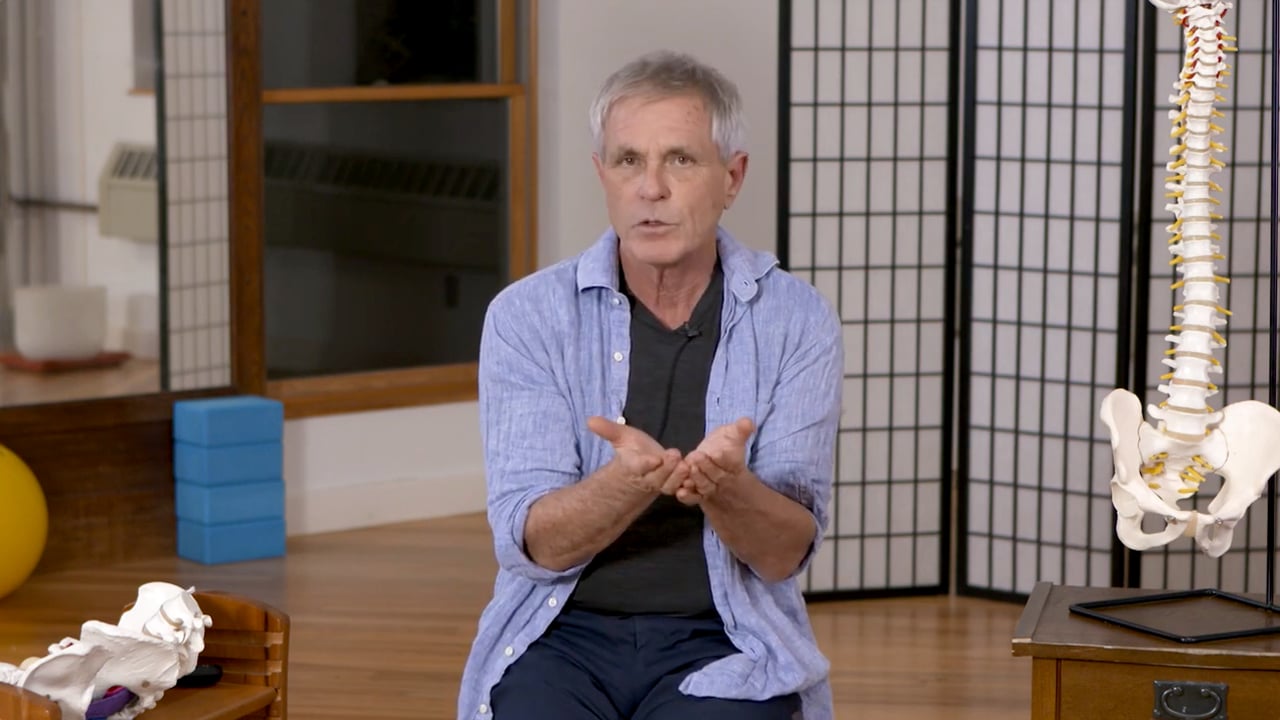
女性の骨盤のより深く効果的な修復とバイタリティ
尿漏れなどの骨盤底機能障害を経験すると「骨盤底の強化」が必要!ということで、骨盤底に注目をしたケーゲルエクササイズなどを処方されることも少なくないのでは?本当に必要なのは、骨盤底の筋力強化なのでしょうか?腹部骨盤全体のバランスについてトム・マイヤーズが提案をします。