マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。
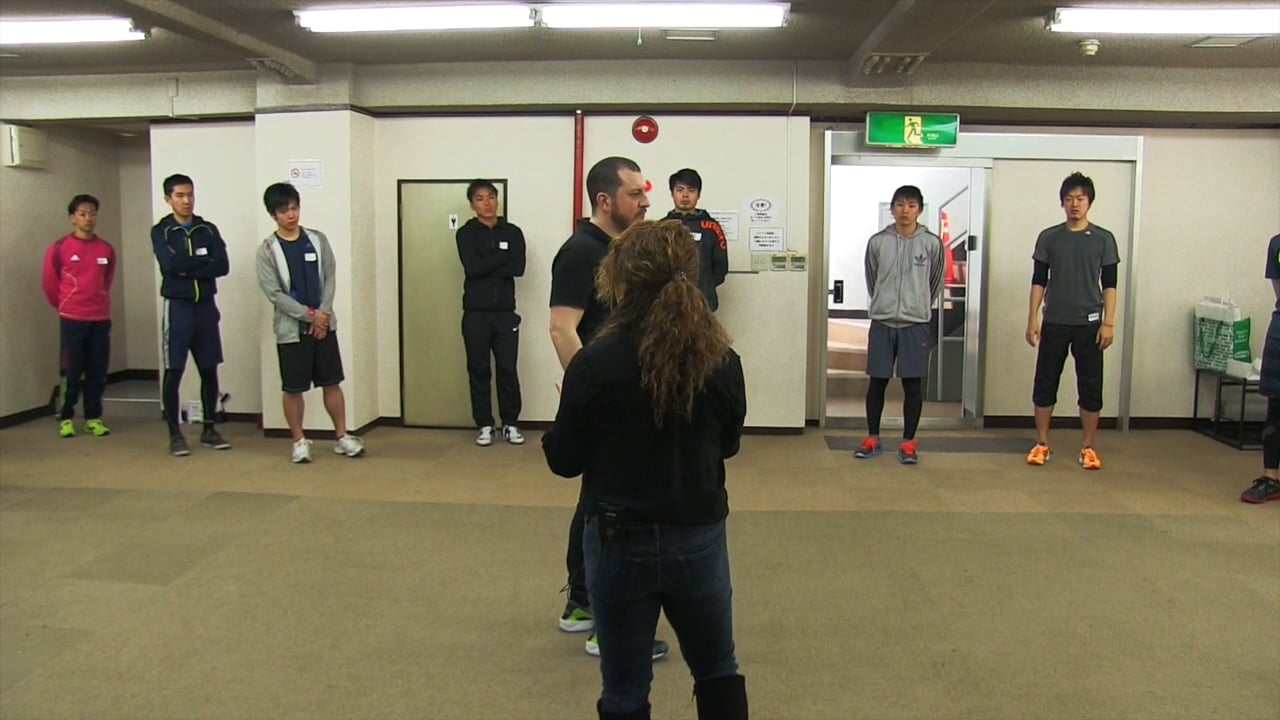
動作に対するリアクション(ビデオ)
爪先をタッチする動きから、片脚立ちでバランスをとる必要のある動きに変化した時、その状況に対して身体はどのように反応するのでしょうか?矢状面、前額面、横断面全てにおいて、左右の動きを比較したり、身体の硬さを比較したりすることで神経系の反応を確認します。
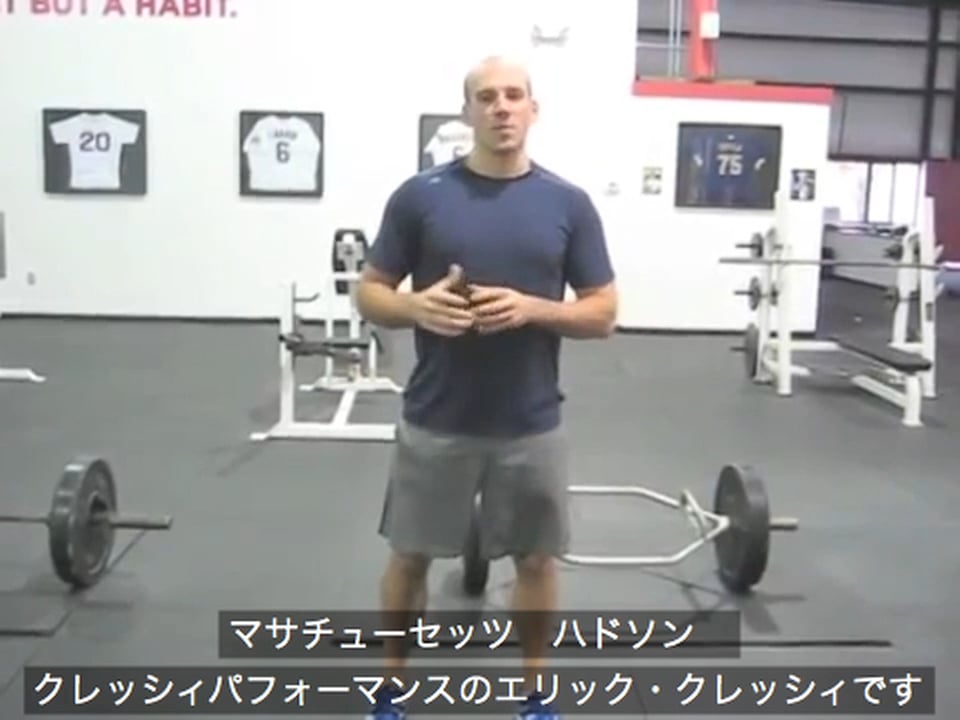
足は狭く 膝を外へ(ビデオ)
スクワットを指導する時に、良く耳にする”膝を外へ”というキューイング。どのようなケースにも当てはまるものなのでしょうか?このキューイングをより効果的に使うためのポイントを、エリック・クレッシィがシェアします。
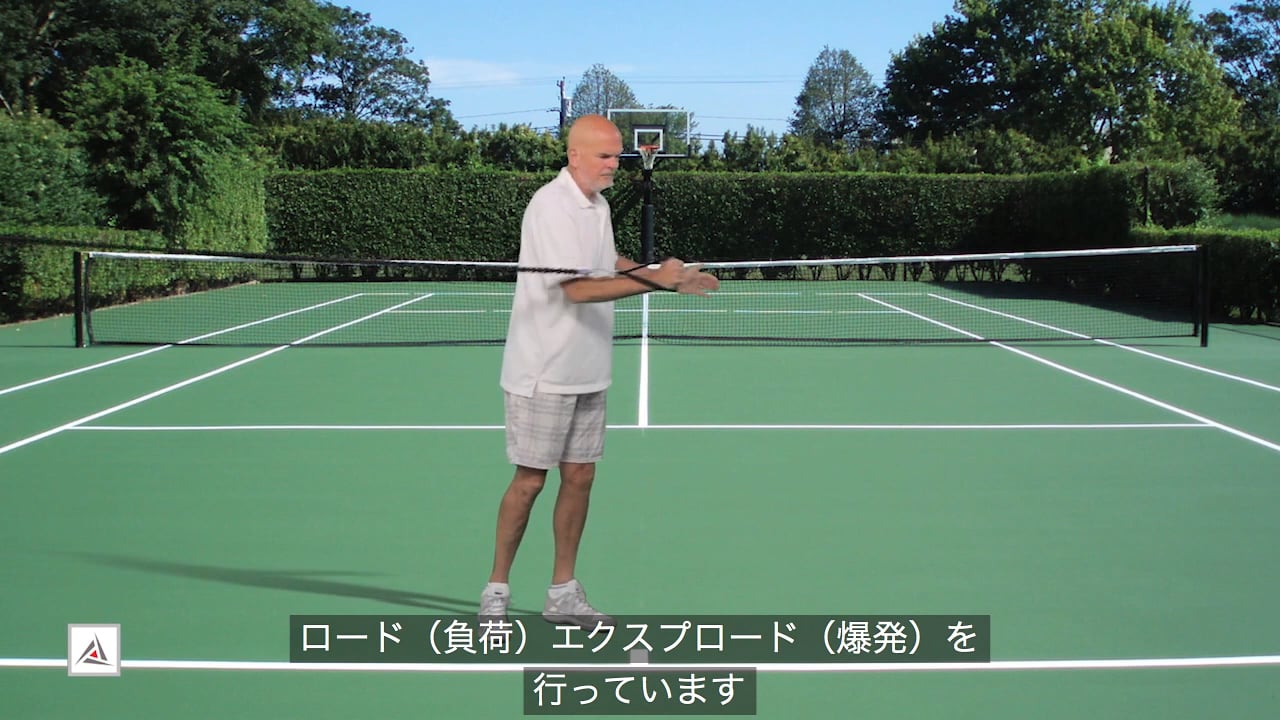
テニス肘 パート2A(ビデオ)
(パート2Bはこちらへ) テニス肘として知られる外側上顆の炎症は、腕、前腕、手首周辺の筋肉群のオーバーユースやストレスの結果として起こる慢性的な怪我のひとつです。予防のため、パフォーマンス向上のため、リハビリのためのエクササイズの考え方を、ギャリー・グレイがご紹介します。

テニス肘 パート2B(ビデオ)
(パート2Aはこちらへ) (パート2Cはこちらへ) テニス肘として知られる外側上顆の炎症は、腕、前腕、手首周辺の筋肉群のオーバーユースやストレスの結果として起こる慢性的な怪我のひとつです。予防のため、パフォーマンス向上のため、リハビリのためのエクササイズの考え方を、ギャリー・グレイがご紹介します

テニス肘 パート2C(ビデオ)
(パート2Bはこちらへ) (パート2Dはこちらへ) テニス肘として知られる外側上顆の炎症は、腕、前腕、手首周辺の筋肉群のオーバーユースやストレスの結果として起こる慢性的な怪我のひとつです。予防のため、パフォーマンス向上のため、リハビリのためのエクササイズの考え方を、ギャリー・グレイがご紹介します。
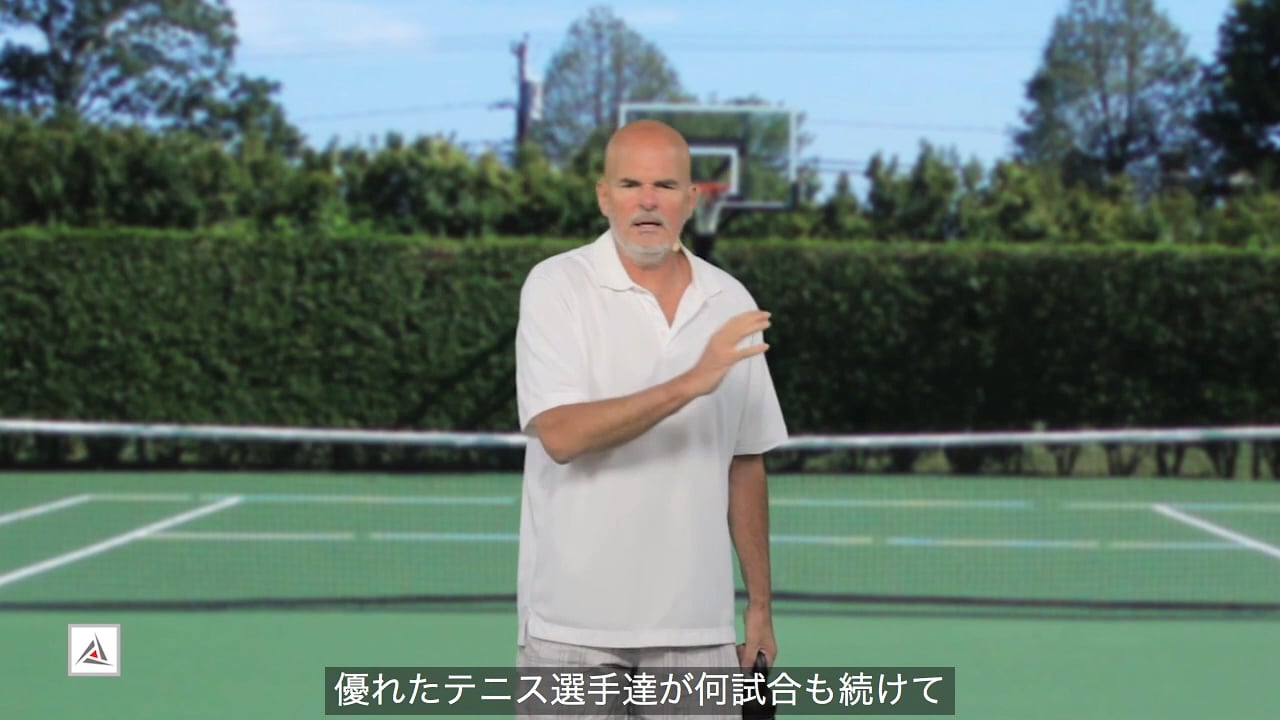
テニス肘 パート2D(ビデオ)
(パート2Cはこちらへ) テニス肘として知られる外側上顆の炎症は、腕、前腕、手首周辺の筋肉群のオーバーユースやストレスの結果として起こる慢性的な怪我のひとつです。予防のため、パフォーマンス向上のため、リハビリのためのエクササイズの考え方を、ギャリー・グレイがご紹介します。
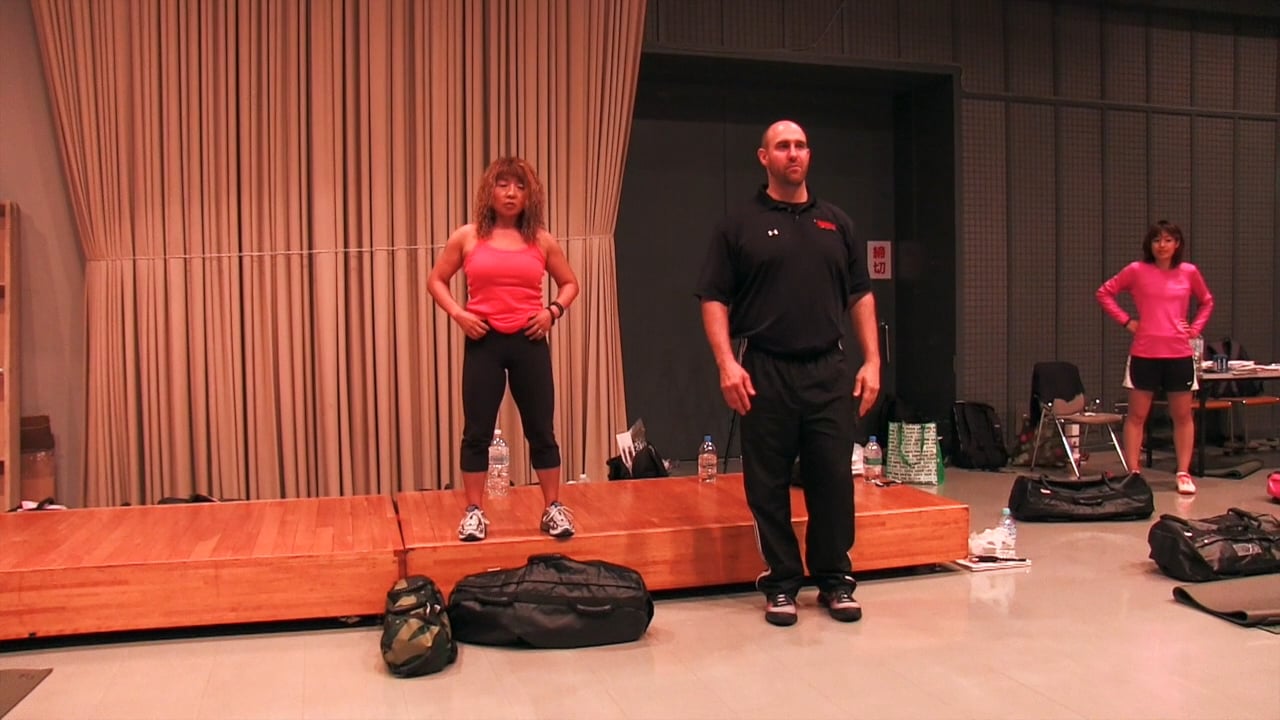
DVRT アドバンス グッドモーニングマトリックス
アルティメイトサンドバッグをフロントホールドのポジションで持ち、ヒップヒンジを行えば、これはグッドモーニングのエクササイズになります。このグッドモーニングに前額面の要素を加えたり、横断面の要素を加えたり、片脚立ちのバランスの要素を加えたりするアドバンス編をお試し下さい。

スクワットは脛を垂直にして行うべきか?
レクリエーションとしてのリフターのほとんど、そしてアスリートの多くは、スクワットを行う際、膝が前方へ移動しすぎてしまうのを回避するために意識的な努力を行っている。これに対する根拠は、膝関節角度の増加は膝関節におけるより大きな剪断力、そして、より大きな損傷につながるかもしれないと考えられているということである。しかしながら、スクワットにおいてリフターが前方への膝の動きを防ごうと試みる際に何が起こるのかについて、研究ではどのような見解を示しているのだろうか?この論説ではクリス・ベアスリー(@SandCResearch)が、危険性およびトレーニングの観点の両方からの興味深い洞察が含まれている研究論文の再考察を行う。 研究論文: 制限された、および無制限のスクワットにおける膝関節と股関節の関節角度、またそれに伴うモーメントの比較、ロレンツェッティ、グレイ、ストゥープ、リスト、ゲルバー、シェレンベルク、ストゥース、ストレングス&コンディショニングリサーチジャーナル、2012年 背景 全米ストレングス&コンディショニング協会を含む多くの機関は、膝はつま先よりも前へ出るべきではなく、スクワットは脛を垂直、もしくは出来る限り垂直に近い状態にして行われるべきであると推奨している。これは、膝がつま先よりも前方へ出た場合、膝関節における剪断力は増加し、内部構造の損傷へとつながる可能性がある、という考えに基づいている。 しかしながら、ロレンツェッティおよびその他は、膝が前方へ移動しても良いとされているスクワットの際に起こる関節角度とモーメントが、リフターがさらに後ろへ座るようにすることにより、意識的に膝をつま先よりも手前に保持しておこうとする場合のそれらと比較されていないということを指摘している。この研究において研究者たちは、膝の前方への動きを抑えるためのこのような意識的な試みを、身体的な制限はないにもかかわらず、“制限された“と表現していた。これから述べるが、制限は単にリフターにより使われたフォームからきていた。 研究者たちは何を行ったのか? 研究者たちは、無制限及び制限されたスクワットパフォーマンスの際の、スクワットの全可動域における、膝関節と股関節の屈曲角度及びモーメントを比較したいと考えた。そこで彼らは、レジスタンストレーニングの経験は持つが、特定のスポーツに対するトレーニングを行った経歴の無い20名(男性10名、女性10名)の被験者を集めた。そして研究者たちは被験者に、制限された及び無制限のスクワットを無負荷、そして体重の25%と50%のバーベルを使用し行うよう求めた。 制限されたスクワットの際、研究者たちは被験者の膝が垂直面、つまり彼らのつま先を超えることを許容しなかった。研究者たちは、被験者の動きを身体的に制限し、無必要な追加反力を生み出すのではなく、被験者を横から撮影し彼らの前の壁にその映像を映し出すようにした。この方法により、被験者は彼らの膝がつま先よりも後ろになっていることを確認する事が可能であった。 被験者が異なる負荷でスクワットを行っている間、研究者たちは12台のカメラによる3次元モーションキャプチャーシステムを使用し、関節の動きを記録した。さらに彼らは、床反力を測定するために2台のフォースプレートを使用した。研究者たちはこれらのデータから関節モーメントを計算するために逆動力学を使った。 何が起こったのか? 関節角度 研究者たちは、制限されたスクワットにおける最大膝関節屈曲角度は85 ± 11度であり、無制限のスクワットにおいては106 ± 10度であったと観察している。つまり、制限されたスクワットはより小さな膝関節角度につながっていた。 関節モーメント 研究者たちは、下記のグラフにおいて見られるように、制限されたスクワットの際の最大膝関節モーメントは、無制限のスクワットにおける最大膝関節モーメントに比べより小さかったということを観察した。また予想通り、膝関節モーメントは負荷の増加に伴い増加している。 研究者たちは、下記のグラフにおいて見られるように、制限されたスクワットの際の最大股関節モーメントは、無制限のスクワットにおけるものよりもより大きかったと観察した。股関節モーメントもまた予想通り、負荷の増加と共に増加している。 この同一の情報の興味深い提示方法は、膝関節及び股関節モーメントの負荷に伴う増加の割合に目を向けることである。以前に考察した研究(スクワットの深さの影響)と同じようにこの研究は、負荷の増加に伴い股関節伸展モーメントは膝関節伸展モーメントに比べはるかに速く増加するということを示している。 研究者たちはどのような結論に達したのか? 研究者たちは、膝関節モーメントは無制限のスクワットにおいてより大きく、股関節モーメントは制限されたスクワットにおいてより大きかったという結論に至った。この影響は下記の通りである: 無制限のスクワットは、膝関節伸筋群のより大きな貢献につながり、またそれゆえ大腿四頭筋のより大きな活性化につながるようである。しかしそれらはまた、膝関節におけるより大きな剪断力を引き起こす。そして 制限されたスクワットは股関節伸筋群のより大きな貢献につながり、またそれゆえ大臀筋及びハムストリングスのより大きな活性化へとつながるようである。しかしそれらはまた、腰へのより大きな力を引き起こし得る。 研究者たちは、脊柱へのストレスは、おそらく膝関節へのストレスと比較し、最小限に抑えることがより重要であるだろう、と示唆している。ゆえに彼らは無制限のスクワットが推奨されるべきであると示唆している。しかしながら、腰には問題がないが、膝関節に既往歴を持つ人に対しては、逆の方法が有益であるかもしれない。 制限要素 この研究は、低負荷が使用されたということが制限であり、高負荷においては異なる結果、もしくはより大きな差違が観察されたかもしれない。さらに、前方への膝の動きを最小限に抑えるために被験者が正確にはどのような戦略を使ったのかは知られていない。 被験者は、要求された膝関節角度を達成するために足幅を変化させた、もしくは同じままであった可能性がある。他の研究は、前方への膝関節の動きは、必ずしも腰への力を増大させることなく、足幅を広げることにより最小限に抑えることが可能であると示唆している。残念ながら、膝関節角度が変化するに従い胴体角度が変化するのかどうかを評価するための胴体角度は測定されていなかった。 実践的な意義は何か? 無制限のスクワットは膝関節伸筋群のより大きな貢献につながり、ゆえに大腿四頭筋のより大きな活性化につながるようである。もし膝関節に痛みが無く、制限の無い方法でスクワットを行うことができる恩恵を受けており、かつ大腿四頭筋の発達を望むのであれば、無制限のスクワットは良い方法であるかもしれない。 しかしながら上記のように、無制限のスクワットは膝関節におけるより大きな剪断力につながる。ゆえに膝の問題や痛みの既往歴を持つ個人は、それらを避けたいと考えるかもしれない。 制限のあるスクワットは、股関節伸筋のより大きな貢献につながり、ゆえに大臀筋及びハムストリングスのより大きな活性化につながるようである。従って、もし後ろへ座るようなスクワットを心地良く行うことができ、またハムストリングスと臀筋を発達させたいと考えているのならば、制限のあるスクワットが使用できるかもしれない(おそらくスクワットパターンよりも、より良い選択肢があるだろうが)。 しかしながら、制限されたスクワットもまた、前方への膝関節の動きを最小限に抑えるために使われる戦略により、より大きな腰への力を引き起こす可能性がある。腰の不快感の既往歴を持つ個人は制限されたスクワットは避けたいと考えるかもしれない。

パフォーマンス向上のためのコアスタビリティトレーニング : 裏付けるエビデンスは本当に存在するのか?(パート1/2)
“良い” コアの安定性は、特に腰痛治療に必要であるといった概念が、悪性の風邪が蔓延するがごとく過去15年以上流行しています。 なかなか治らずいつまでも長引くうっとうしい風邪と同じようなものです。この仮説やトレーニング神話を裏付ける画期的または際立ったエビデンスは今日まで得られていません。 トップレベルのスポーツクラブから近所のジムまで、パフォーマンス向上のための‘コアスタビリティ’トレーニングを実施しています。ランニング雑誌やトレーニング雑誌を手に取れば、やはり‘コアスタビリティ’を取り上げていますし、ネット上では‘コアスタビリティ’に関する情報量があふれています。たいていその内容は、月並みな仮説とその適用であり、確固たるエビデンスという点では、ほとんど何の情報提供もしていません。 多くのトレーニングやセラピーの概念が事実として盛り上げられてしまうように、エビデンスがないにもかかわらず、この見解はまだ多くの人たちや専門家、‘研究所’の基本的な概念を形成しています。 このブログでは、コアスタビリティトレーニングに時間と労力をかける価値が本当にあるのか、またそれが実際有益なのかどうかを、パフォーマンスの観点からとらえていきます。いつもの通り、たくさんの意見の寄せ集めではなく、有用なエビデンスをレビューしていきます。これを美的観点からのコアトレーニングと混同しないようにしたいと思います。もし、腹筋がどのように機能するか、またはどのようにパフォーマンスの向上につながるのかを気にすることなく、だた外観的にかっこいい腹筋を手に入れたいということであれば、ここでの議論はあまり意味を持たなくなります。 “コアスタビリティトレーニング:スポーツのコンディショニングプログラムへの適用”(ここをクリック)でウィラードソンは、次のように述べています: “コアスタビリティエクササイズをスポーツコンディショニングのために推奨する人もいますが、この主張を裏付けする科学的根拠はほとんどありません。” これに対する反対意見の参考文献もチェックしてみてください!(9, 12, 18, 38, 42) ここで一つ念頭に置いておかなくてはならないことは、そもそもしっかりしたコア“スタビリティ(安定性)”が備わっているかどうかを究明するのは現実的には難しいということです。つまり、正確に測定できない事柄と関連づけることは困難だということです。 この論文(ここをクリック)では、コアスタビリティに関する6つの臨床試験は、異なる評価者同士でも(評価者間)、また同一評価者による2度に及ぶ試験(同一評価者内)でも信頼性がないということを示しています。スポーツ環境においても、より信頼度が高いと証明されてはないと思います。 このトピックを研究するためのいくつかの制約があります。 コアスタビリティを測定する信頼性の高い基準がない。 コアスタビリティは、他のエクササイズと併用される。 アスレチックパフォーマンスは主観的なので、そのかわりにアスレチックパフォーマンス測定が用いられる。 エビデンス このことに留意して、まず、“アスレチックパフォーマンス測定における単独および複合での「コアスタビリティ」トレーニングの効果”(ここをクリック)をみてみましょう。 この体系的レビューは、コアスタビリティ、パフォーマンス測定、アスレチックパフォーマンスの関連を検討しています。彼らは、179の特定された記事中24の記事を含みました。 これらの研究者らが発見したのは、効果を上げるための主な目的として、特にコアに焦点を当てた研究論文では、一貫した結果が得られなかったことでした。彼らは、コアスタビリティトレーニングは、限界利益しかもたらさないと結論づけました。限界利益しかもたらさないものにどれだけの時間を費やすか、私たちは考慮しなくてはなりません。 次は、シャーロックらの論文 “コアスタビリティとアスレチックパフォーマンスの試験的研究:これらに関連性はあるのか?”(ここをクリック)です。 この論文は、関連性があると考えられるという結論づけをしましたが、そう確信を持っていない私には少し疑問が残ります。特に、文頭でこうした結論を示しながらも、それを十分に裏付けできるエビデンスを提示しないのですからなおさらです。 “この仮説の中で、コアスタビリティとアスレチックパフォーマンスは相互に関連することを認めたわけですが、最近の文献はこの関係性を支持していません。” この記述は、他のすべてのコアスタビリティに関する仮説をうまく総括しています。口ばかりで行動が伴っておらず、多くの主張と複雑な仮説ばかりで証拠に欠けています。 コアスタビリティを測定するにあたってダブルレッグローワリングテストを採用し、40ヤード(36.5メートル)ダッシュ、メディスンボール投げ、Tテストや垂直跳びといったパフォーマンスのテストと関連付けました。 コアスタビリティ測定と顕著な相互関係があるとされたのは、メディスンボール投げのみであったことが分かりました。他のすべてのテストとの相関性は低く、顕著なものではなく、もちろん明確に支持する結果ではありませんでした。ここでは見るべきものは何もないので、次に行きましょう。 良いコアスタビリティとはそもそもなんであるのか、それを測るための、信頼できる測定方法がないということは主な制約として先述しました。 著者らは警告しています: “コアスタビリティを測定することは、基準となるテストや測定法がない限り難しい作業となる。ダブルレッグローワリングは、コアストレングスの測定方法として有効で信頼性があるとする文献がある。” 個人的には、コアスタビリティとコアストレングスとの間に関連性を見いだすことは難しいと感じています。前者は筋活性のタイミングに基づいており、後者は力を産生する能力なのです。 この論文(ここをクリック)は、FMS、コアスタビリティ、パフォーマンステストとの間にみられる相関性に注目しました。ここで分かったことは、コアスタビリティテストとパフォーマンステストの間には低~中程度の関連性しかなかったことでした。また、コアスタビリティとFMSスコアーとの間にも顕著な相互関係は見つからなかったのです。FMSでは、コアスタビリティに重点を置いているようでしたが、コアスタビリティはFMSのスクリーニングには無関係であり、これらのスクリーニングのタスクを実施するために要求されるレベルのコアスタビリティのレベルは非常に低いことをこの論文は明らかにしています。 彼らの結論 “フィットネスのプロフェッショナルが、パフォーマンスを向上するためにファンクショナルムーブメント(機能的動作)とコアトレーニングに重点を置いてきたにも関わらず、私たちの研究結果は、それとは逆を示唆している” 同意します!またもや失敗。 また彼らは、FMSとコアトレーニングは、ケガの予防に活用されるべきだと結論づけています(あまりしっくりときませんが)。しかし、この論文の記述、参考文献のどこを探してみても、この結論に対する正確なエビデンスは見当たりませんでした! 事実、シシックの論文では、パフォーマンスやケガの予防、腰痛のためのコアトレーニングに関しての科学界における主張や大衆文化に対して、彼は明確な見方をしています。(ここをクリック) “これらの主張にも関わらず、この文献はコアトレーニングのメリットについてとても決定的とは言えません。” ウィラードソンの論文に戻りましょう。“コアスタビリティトレーニング:スポーツのコンディショニングプログラムへの適用”と題する論文の中で、次のように引用しています: “裏付ける科学的根拠がほとんどないまま、コアスタビリティエクササイズをスポーツコンディショニングのために推奨する人達がいる。”(9, 12, 18, 38, 42) つまり、この主張のエビデンスがないにも関わらず、それでも彼はコアスタビリティトレーニングを支持しているようです。 “コアスタビリティの向上は、すべてのスポーツコンディショニングプログラムでの優先事項であるべき。” 彼は律儀に理論を展開し、EMG測定値の上昇やコアスタビリティ測定の向上で、どのエクササイズがコアにより大きな影響を及ぼすかというエビデンスを提供しています。しかし彼には、スポーツのコンディショニングプログラムにおいてコアスタビリティトレ―ニングの妥当性を証明するために、コアスタビリティトレーニングによって実際に、アイスホッケーの滑走スピードやランニングまたは水泳に改善がみられたなどの具体的な意味を持つエビデンスを提示するということができていませんでした。公平な精神に則れば、彼は具体性の必要性について議論はしているのですが。

パフォーマンス向上のためのコアスタビリティトレーニング : 裏付けるエビデンスは本当に存在するのか?(パート2/2)
エビデンス(続き) この論文(ここをクリック)では、コアスタビリティパフォーマンスとショルダープレスを検証しています。ここでもグループ間での有意な差はみられませんでした。彼らが出した結論は、コアスタビリティは“比較的高いレベルの課題特異性を示す。”そして、“動的な多関節運動に比べ、静的な単関節エクササイズとの関連性は高くない”としていますが、こんなことは既に分かっていたことですよね? ネッセルら(ここをクリック)は、3つのストレングス変数と4つのパフォーマンス変数において“フットボールのディビジョン1の選手のパフォーマンスとコアスタビリティの関連性”を検証しました。ここでも、中程度の関連性しかみられず、結局、著者らは、トレーニングでコアスタビリティに焦点を当てる十分な根拠はないと結論付けました。 “下肢のパワー測定に与えるコアストレングスの影響”(ここをクリック)におけるコアストレングスについて、私たちはやや異なる捉え方をしています。 メディスンボール投げが、単にコアストレングスを測るひとつの手段であるという考えはしっくりきませんが、ここでは実際、統計学的に有意な相関性が見て取れます。コアが力の総和の主な発生元であるとするなら、動きの中のパワー増大はより強いコアにかかっていると結論づけられるのでしょうか? パワー測定は、メディスンボールが飛んだ距離で行われましたが、これは他の要因にも左右されたかもしれませんし、6回のメディスンボール投げテストのうち、回旋に関与したものはひとつもありませんでした。 この最後の記述に私は同意します。しかし: “最近プランクエクササイズが、アスリートがコアストレングスとコアスタビリティを向上するための適切なコアトレーニング方法と考えられています。これは問題です。プランクエクササイズは、アスリートを、実際のスポーツ活動で要求される動きを再現することがほとんどない、機能的ではない静的なポジションにおくのです。コアは、身体のほとんどの運動連鎖の中心ですから、そのようにトレーニングされるべきなのです。” ランナーのトレーニングプログラムの一貫としてコアスタビリティはよく推奨されますが、ここでも本当のエビデンスはないのです。この論文(ここをクリック)で、スイスボールトレーニングはコアスタビリティ測定に顕著な影響を与えたが、ランニングパフォーマンス測定には何の効果もなかったとされました。またも特異性の呪いにやられました! よって、多くの仮説、システム、専門家に示唆されているコアスタビリティは確たる影響をパフォーマンスに与えるという考え方は、研究にはあまり反映されていません。せいぜい弱い相関性がみつかる程度です。このようなエビデンスをもとに、スポーツ強化の正当な理由として私たちは最近のコアトレーニングの流行と実施を心から支持できるのでしょうか? この結論が、都合の悪い証拠は無視して、支持する証拠だけ選び出したものではなく、入手できる証拠の総体に基づいているものであることを望みます。 いくつかの意見 何をしてもコアはトレーニングされていることを忘れてはなりません。コアは骨盤、胸郭、脊椎、さまざまな部位に付着していますから、これらが動けばコアの筋群も動くのです。頭上に手を伸ばしたり、屈んで靴ひもを締めたりする動作は、どちらもコアエクササイズです。骨盤と脊椎を逆方向に回旋させるランニングも、素晴らしいコアトレーニングのひとつです。 おそらく、コアのパワーとは、それがどれだけ変化に対応できるかという能力かもしれません。コアを発火させることについてよく議論されますが、時には筋が発火し過ぎて動きを制限していることもあります。動作に準じて柔軟性レベルを変化させる能力の欠如は、腰痛を患っている人に見ることがあります。卵が先か鶏が先か?と同じようにこれは結果なのでしょうか、それとも原因なのでしょうか? これに答えがあるのか、また両方の可能性があるのかは分かりません。痛みはここでの焦点ではないのですが、腰痛で苦しんでいるのであれば、このエリアのトレーニングへのアプローチのにおいyて考慮に入れなくてはなりません。 急性腰痛を患っている人の脊椎は、筋活動により実際、安定性を増しているということがあります(ここをクリック)。さらに、人々の筋活動パターンに2つとして同じものはありませんでした。これは、ある研究(ここをクリック)によって裏付けされています。この研究では、制御された運動(フリーダイナミックリフティング)をする腰痛を患っている患者のグループは、無症状(痛みなし)のグループに比べ、圧迫負荷が26%大きく、剪断負荷が75%大きかったと示しています。体幹の筋活動の分析では、体幹の筋に同時活性の増加が見られたとが分かりました。 ファリャらは、次の論文(ここをクリック)の腰痛グループは、健康なグループと比べ、リフティング動作時に筋内活性の多様性が減少していることを発見しました。 次に、多くの人は、運転や座りっぱなし、同じ姿勢で長時間メールを打ったりと、多様性のある動きをあまりしなくて済む生活をしています。ちょっとプランクエクササイズのようですね! 体幹の多様性のある動きを練習しなければ、上手く行うことができないかもしれません。孤立化された安定性のために、特別に、かなり不自然にデザインされたエクササイズではなく、コアは運動連鎖の中心として力を減速したり総計したりしなければなりません。 たとえば、頭上に手を伸ばすには、伸展をするために体幹の硬さを緩めるか、そのエリアの柔軟性レベルを上げる必要があります。コアにおける大変多くの動きが考案されています。解剖学を見てみればわかるように、進化はコアのエリアにかなり沢山の動きを与えたのであれば、なぜ静止させておきたいと思うのでしょうか? 動きの向上させるためのスタビリティという考え方、特にプランクのようなエクササイズには、少し違和感を覚えます。 次に、スポーツで特異的な反応を得たいのであれば、特異的な機能に留意して、コアトレーニングをした方が良いでしょう。これは前述の“下肢のパワー測定に与えるコアストレングスの影響”の研究とコアスタビリティパフォーマンスとショルダープレスを論じた研究の結論でもありました。 機能に関連した動作に関わる運動連鎖の一部として、特定の動きに関与する筋の相互作用、連鎖、タイミングは、特異的なモーターパターンの一部と言えます。シンプルに、もしテニスの試合で、コアをもう少し上手く働かせたいのであれば、コアがテニスの試合でいったいどのような働きをするのかを考える必要があります。コアスタビリティトレーニングの問題点は、トレーニングそのものがスポーツと化していることです。次のステップは、さらなる研究において、ある機能に対する特定のコアトレーニングが、その機能のパフォーマンスを向上するのかどうかを見ていくことです。 このブログのトピックではありませんが、トレーニングの特異性は、多くの研究で示されています。

6ポイントロック&ノッド
オリジナルムーブメントの動きの中から、手と膝と足を床についた6ポイントのポジションで行うシンプルなエクササイズをダン・ジョンがご紹介します。モビリティー向上のみでなく、動作の向上のために役立つシンプルでありながら利用価値の高いエクササイズです。

6ポイントゼニス
足と膝と手を床についた6ポイントのポジションで行う6ポイントゼウスと言うシンプルなエクササイズで、胸椎の可動性を高める方法をダン・ジョンがご紹介します。