マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

ウエイトはすべて同じでしょうか?
フィットネス業界すべての人にとって、それはもっとも厄介な言い回しであるかもしません。とても聡明で、かつ最も成功しているストレングスコーチのなかにも、その犠牲になっている人がいると聞いたことさえあります。 “ウエイトはただのウエイトにすぎないのであって、身体にはその違いなど分からない” 一見すると、かなり理にかなっています!“1000ポンドの羽と1000ポンドの岩はどちらが重いですか?” という古いジョークを思い出させます。では、科学や現実世界は何か違うことを教えてくれるのでしょうか? 私は、初めてタイヤをひっくり返した時のこと、アトラスストーンを持ち上げた時のこと、ストロングマンログを持ち上げた時のことを覚えています。なんてことでしょう!私は10年間ダンベルトレーニングをしてきていて、結構重いウエイトもリフトしてきましたが、すべては完全に無意味でした。私は強かったし、そんなわけはない、と思ったものです。しかし、現実には、別のウエイトを行ったときに、私たちは皆似たような経験をしていて、皆さんの多くも初めてケトルベルを用いた時に、この感覚に気づいたでしょう。 ケトルベルの突き出たハンドルのおかげで、ダンベルやバーベルを持ち上げたときとはまったく違う感覚になります。48kg(106ポンド)のケトルベルでクリーンできる人よりも、90kg ( 200ポンド )以上のバーベルでクリーンできる人のほうがより多くいます。 なぜでしょう? すべての道具は、異なっているのです。てこの作用やサイズはすべて、ウエイトの感じ方の違いに影響しますし、より重要なのは、まったく新しいストレスを身体に与えることです。道具による差を理解することで、よりよいエクササイズ、プログレッション、プログラムを作ることができます。 全て聞こえは良いのですが、それらの経験をどのように感じるのか以外に、これらの主張を後押しする実際の科学的根拠はあるのでしょうか? 去年、ウィズコンシン-ミルウォーキー大学の研究チームと一緒に仕事をさせていただくという光栄があり、我々のDVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングに関するテスト行いました。DVRTアルティメイトサンドバッグについて言及していたことが正しいのか否か判明することになるわけで、とても不安でした。この研究が、多くの優れた“理論”の打ち止めになるかもしれなかったのです。 研究者達のテストは、比較的シンプルなものです。18名の大学生のエネルギー消費が評価されました。ダンベルとアルティメイトサンドバッグを持ってランジをしてもらい、その二つのエネルギー消費に有位な違いがあるかどうかを見ることが目標でした。 18名の大学生は、ダンベル、アルティメイトサンドバッグを持ち、60秒間のランジトライアルを無作為に指示され、それぞれを完了しました。それぞれのトライアルでは、1分間に60回のリズムでトータル30回のランジをしなければなりませんでした。 被験者は自重の25%の重量のダンベル、または、アルティメイトサンドバッグを使用しました。テストの一貫性を保つため、ダンベルは肩の幅でニュートラルなグリップとし、アルティメイトサンドバッグはほぼ同じ姿位で、拳の上に乗せるように持ってもらいました。 研究において、学生達は同じ仕事量を同じ重量で、基本的に同じポジションで行いました。 ここで、仮に“ウエイトはただのウエイトにすぎない”と信じているなら、ダンベルとアルティメイトサンドバッグの間に違いはまったくないはずであると考えるでしょう。 研究者はなにを発見したのでしょうか? エネルギー消費の概算では、ダンベル使用時よりもアルティメイトサンドバッグ使用時のほうが有位に高くなりました。なんだって?そんなことがあるのだろうか? 残念ながら、この最初の研究の目的は、その理由を見つけることではありませんでしたが、正直なところ、この2つのトライアルの差異が非常に大きかったことに、とても衝撃をうけました。1分間心拍数に8拍以上もの違いがあったのです。紙面上、そのトライアルではすべてが同じであったことを考慮すると、その差は非常に大きいのです。1分間に8拍というのは、心拍の割合を考慮した場合、強度においてむしろ大きな変化であると言えます。 私たちは、ダンベルとアルティメイトサンドバッグの間でそのような大きな違いが生まれた理由について、確かな理由は分かりませんが、経験に基づき、いくつかの推測ができます。 アルティメイトサンドバッグは不安定であり、その不安定さがその違いを生んだのではないかと言う人もいます。しかし、ここではそうではありません。その研究の施行において、アルティメイトサンドバッグのホールディングポジションで、用具自体にいっさい不安定性のある動きがでていないことを確証しています。違いは身体にかかる圧迫力によるものではないかと思われます。その力により、上半身から体幹にいたるより多くの筋肉に刺激が加わり、その結果、アルティメイトサンドバッグを使用しランジを行った際、より多くのエネルギーが使われた可能性があります。 これは、我々が使用する道具がすべて同じではないということを検証する、初めての試みでありました。私たちがアルティメイトサンドバッグを使用する理由は、それが単に違うから、あるいは、違う種類の刺激が欲しいからではありません。そうではなく、道具のトレーニングにもたらす独特の効果を認識することができれば、私たちの使う道具はかなり違った結果をもたらすことができます。それらの特性を理解することができれば、自分のフィットネスにも、クライアントのトレーニングにおいても本当に有利になるのです。 よりよいフィットネスのプロであるというとは、また、道具の持つ力を認識しているということでもあるのです!

ACLパート5:ホップ(ビデオ)
(パート4はこちらへ) (パート6はこちらへ) 東京での来日セミナーも近づいてきたベン・コーマックのACLシリーズの5番目は、ホップの動きのプログレッションです。決まりきった方向や角度のみでなく、様々な方向や角度のホップを段階的に経験することで、身体はそれらの動きのコントロールを学ぶことができるのです。

Q&A:ファズスピーチについて
ファズスピーチ(結合組織間の産毛のような繊維発生に関するギル・ヘッドリー博士のビデオ)に対する最近の考え方はどのようなものでしょうか?これが動くということについては、さまざまな説が出ていて、どれも完璧な説得力がありますが、これらには、生体ではなく検体におけるデータが使用されています。数年前のウェビナーで、あなたが次のようにおっしゃっていたことを思い出します。生体におけるファズは、それほど速く厚みを増すことはなく、改善するのも比較的簡単であると。今もそのようにお考えですか?動きとファズについて、クライアントに伝える時、最新のリサーチをもとに、より正確でありたいと思っています。 トムの返答: 今年末に取り上げる予定の大きなテーマではありますが、とりあえず簡単にお答えしましょう: すべては互いに“ファズ (産毛のようなもの)”によってつなげられています。“ファズ”とは、グリコアミノグリカン(糖タンパク質、粘液)とコラーゲン線維が結びついている疎性組織であり、脂肪細胞もよく含まれています。 おっしゃる通り、防腐処理を施した検体でみることができる“ファズ”は、何も処理されていない組織でみられるものよりも、より乾燥し、固定されています。そして、処理されていない組織のファズは、人工的に作られた動画の組織よりも動きが少ないでしょう 。これは、多くの生体に触れることによる感覚や未処理の検体を解剖してきた経験に基づいています。間違いなく、通常、書籍に記載されているいるものよりも、もっと、全ては筋膜でつながっているのです。 なにも処理が施されていない検体の“ファズ”です。上が上腕二頭筋で下が上腕筋です。解剖では通常切り離すことになっているため、解剖学の本に登場することはほとんどありません。ファズは、筋と筋の間の動きを可能にはしますが、と同時に、動きを制限し、筋間の力が側方へ伝達されることも明らかです。たとえば、上の筋が左方向へ収縮または伸長したとしましょう。そうすれば、下の筋の筋膜に力が分散することになります。 私達は、筋は相互に“スライドする”と言いますが、私が行ってきた解剖では、僧帽筋は菱形筋に産毛のようなものでからみつき、広背筋は前鋸筋に同様にからみついています 。必ずそうであり例外はありません。教科書通りの個々の筋の起始・停止の様子を得るためには、このけばだったファズを指でなぞり“壊し”たり“溶かし”たりしなければなりません。 実際の生体内で隣接する組織の面と面の間に動きがあるということは、ファズの2つの要素によって決定されます。それは、組織の流動性と線維の長さです。 A) 組織内の水分が多ければ多いほど、グリコアミノグリカンは水分を吸収し、セラピストの手により、または身体を動かすことで生じるストレッチにより動き易くなります。 B) 線維が短ければ短いほど、隣接する面間では、一方の面が動いてからもう一方の面がそれにつられて動き始めるまでの動きは少なくなります。ガタガタな古ぼけたはしごで例えると、両サイドの支柱が筋膜の面で、横木がファズだとします;横木が長ければ長いほど、支柱と支柱はお互いにシフトしやすくなります。 よって、より緩くて水和されたファズは、十分な動きを可能にするでしょう。一方、固く乾燥したファズであれば、ひとつの筋からファズで繋がっている筋や骨、血管、膜構造へと効率的に力を伝達するでしょう。線維が乾燥して短いほど、より高い安定性を生み出します(もちろん、これは時には好ましく、安定性が必要な部位ではファズが動きを制限してくれていると推定します)。緩すぎる組織(過可動)は、可動性が低下した組織と同様に問題になることがあります。ここで疑問となるのは“どこで?”そして“だれにとって?”なのです。 たとえば、前腕を例にとると、筋群の近位端である肘の付近では、ファズがしっかりと筋をつなげ、まとめています。これらの筋群が、最良のコンディションであっても互いにスライドし合うとは考えにくいでしょう。それぞれの筋間で多少のスライドはあるにしても、私がこれまでに解剖してきた前腕では、これらの筋群はすべてしっかりと束ねられ、完全につながって力を側方へ互いに伝達できる仕組みになっています (私はそのように考えますし、フイジン氏の見解とも一致しています)。これは、効率の良い力の分散機構です。筋間の壁(筋間中隔)も互いを固く結びつけており、グレープフルーツの薄皮の仕切りに少し似ています。むいて離すことはできますが収穫前のグレープフルーツでは、ファズでしっかり結びついています。 手首に近い遠位端では、腱は周辺組織に対して明らかにスライドします。少し近位の筋腹より遥かに多くスライドします。ガンベルト医師は、腱組織と周囲組織は“筋膜の泡のようなもの”(多数のマクロ液胞スライドと緩衝機構)でできているフラクタクルな構造でつながっており、腱はこの複合体の中をスライドするということを発表しました。 興味深い部位は、筋の半分ぐらいの位置にあります。どのぐらい遠位になるとつながっているべきで、どこでスライドが始まるべきのか?それは、その人の遺伝的性質や身体が受けている負荷によります。そして、“筋の約半分ぐらいの位置”は通常、動きを制限している“ファズ”を分解するのに最も施術効果が高い部位です。言うまでもなく、ここは筋紡錘やゴルジ腱受容器、その他の伸張受容器などの筋膜のセンサーが豊富な部位で、つまりこの部位での施術は、筋膜的にも神経的にも意義深いものになります。 たとえば、ハムストリングは、坐骨結節までの全域を3つの筋に、かなり容易に分けることができますが、臨床では、たいてい大腿後面の中部から膝上5センチまでかなり厚い“ファズ”で筋膜同士がつながっています。これらを離して下肢にもっと“自由”を与えるべきでしょうか? ダンサーやヨガを実施する人には“イエス”ですが、ランナーやフットボール選手にとっては“ノー”でしょう。

足底腱膜へのアプローチ
2014年10月8日&9日、東京で開催されたグレイインスティチュートFSTT 機能的軟部組織の変容 下肢コースより。何層にも重なった厚みのある結合組織である足底腱膜への手技によるアプローチをご紹介します。

足部、足首複合体へのコンプレッションバンドの適用
2014年10月8日&9日、東京で開催されたグレイインスティチュートFSTT 機能的軟部組織の変容 下肢コースより。足底腱膜への手技によるアプローチを実施した後に、コンプレッションバンドを使用して、足部、足首複合体に、更なる水和作用を促すテクニックをご紹介します。

プログレッションを評価する
(テクニックに関するビデオはこちらへ) 漸進的に提供したアプローチに効果があったか否か、その結果は教科書が決定するのではなく、各個人の機能が決定すること。反応を確認するために常に評価を繰り返すことの重要性を、レニーが語ります。

より良い呼吸 より良い動き パート1/2(ビデオ)
より良い呼吸ができれば、姿勢も向上します。より良い姿勢は、より楽な呼吸を助けます。トレーニングを行う前のウォームアップに取り入れることができる呼吸と姿勢の向上のためのエクササイズを、エリック・クレッシィがご紹介します。パート1

より良い呼吸 より良い動き パート2/2(ビデオ)
より良い呼吸ができれば、姿勢も向上します。より良い姿勢は、より楽な呼吸を助けます。トレーニングを行う前のウォームアップに取り入れることができる呼吸と姿勢の向上のためのエクササイズを、エリック・クレッシィがご紹介します。パート2
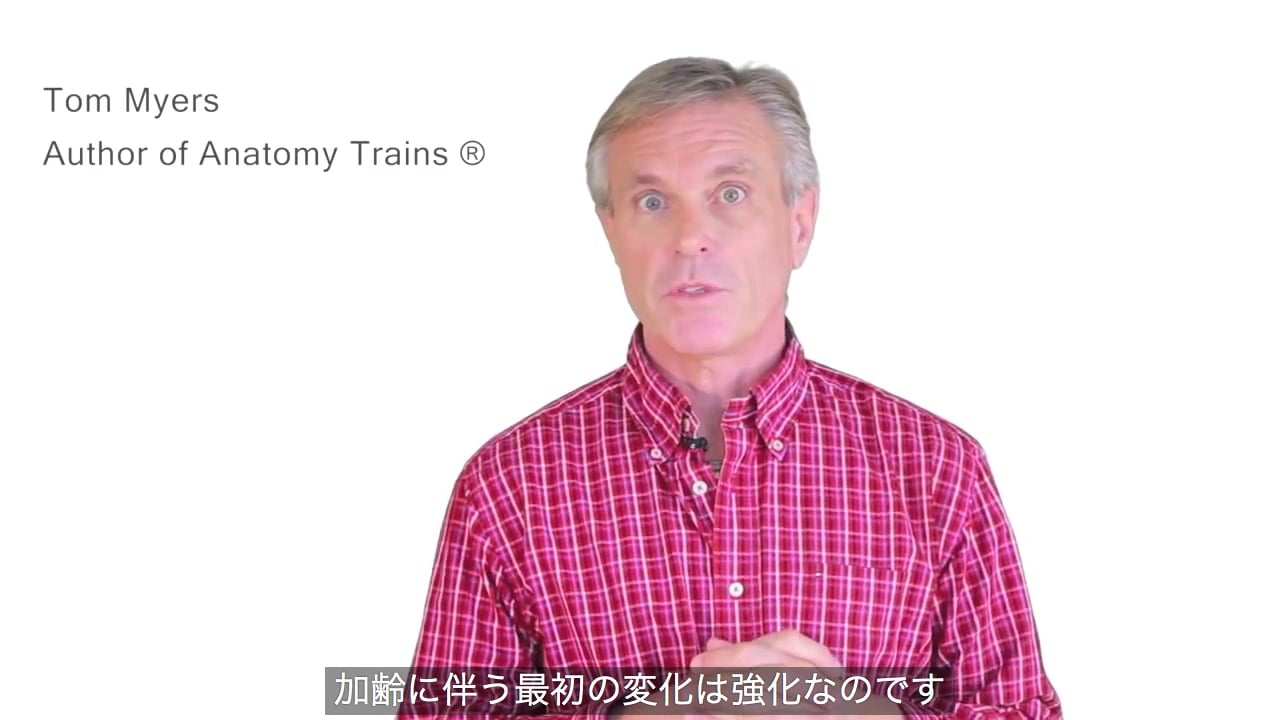
健康な筋膜を保つには
4月に来日するアナトミートレインの著者、トーマス・マイヤースが、筋膜の加齢に伴う変化と筋膜の健康維持に関して、わかり易く解説をします。組織への水分供給には動きが不可欠!

ACLパート6:カット&ラン(ビデオ)
(パート5はこちらへ) ACLシリーズの最後のビデオは、よりスポーツの動きに近い、カット&ランの動きを使ったリハビリのアイデアのご紹介です。減速して加速する。方向転換をする。スポーツの動きの中で、様々な場面で見られる動きへの適合力を高めます。
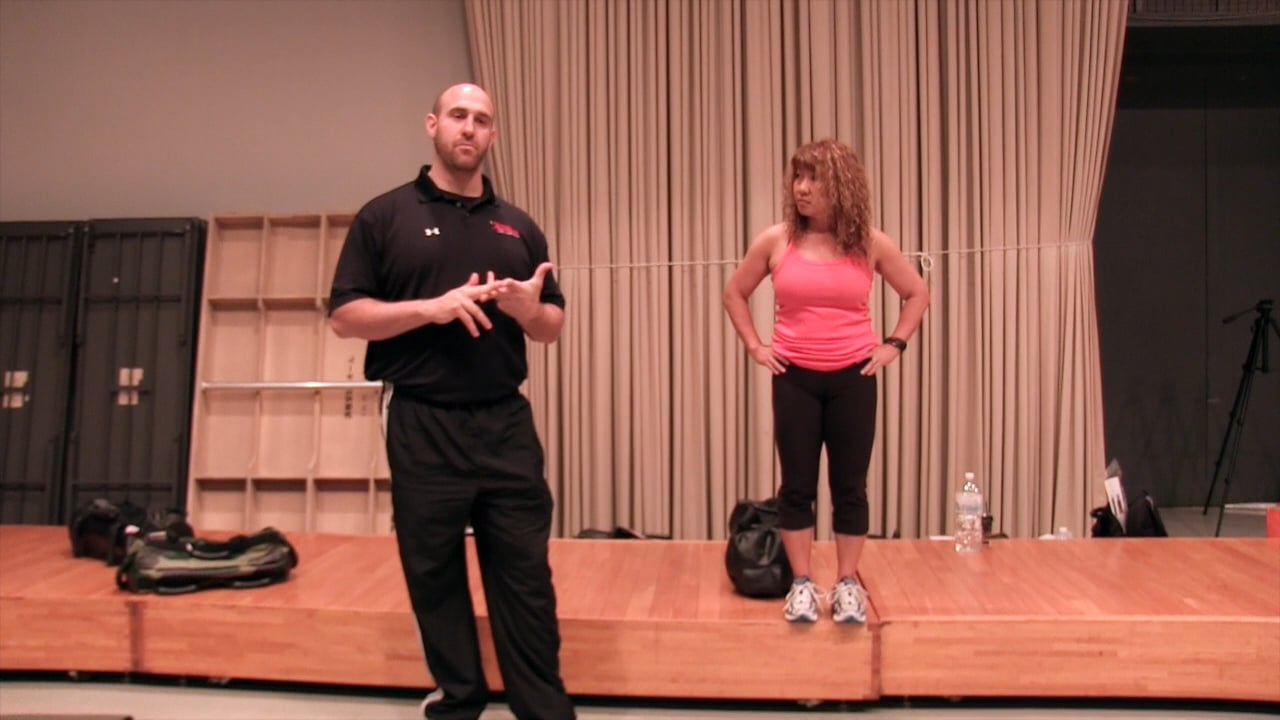
DVRTデッドリフトマトリックス
2014年7月4日に開催されたDVRTレベル2認定コースより。グレイインスティチュートの校長である理学療法博士のギャリー・グレイの3Dアプローチであるマトリックスの考え方をDVRTに活かした3Dのデッドリフトマトリックス。矢状面と前額面のバリエーションをご紹介します。
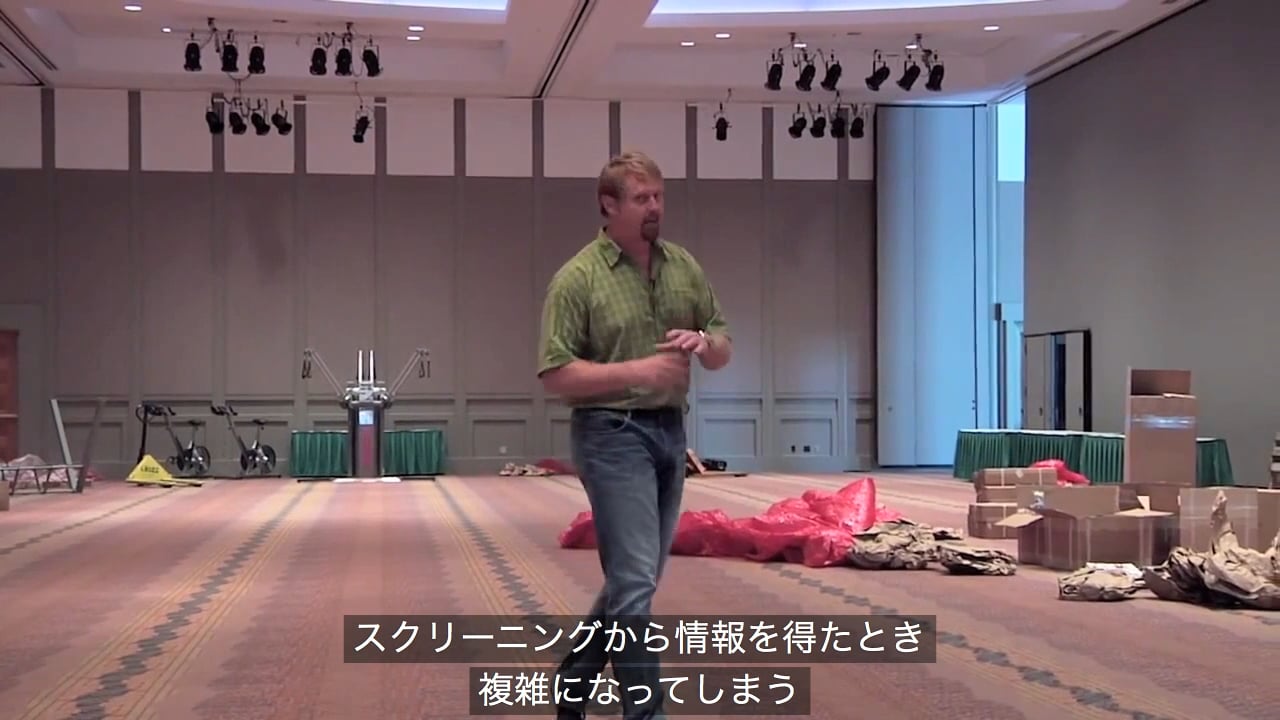
FMSモデルを実生活例に応用する~イントロ(ビデオ)
パフォームベターのプレカンファレンスとして提供されたFMSのグレイ・クックとブレット・ジョーンズの指導したセミナーからの抜粋。ファンクショナルムーブメントスクリーンとは?現在翻訳準備中のセミナーからそのイントロ部分をご紹介します。