マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。
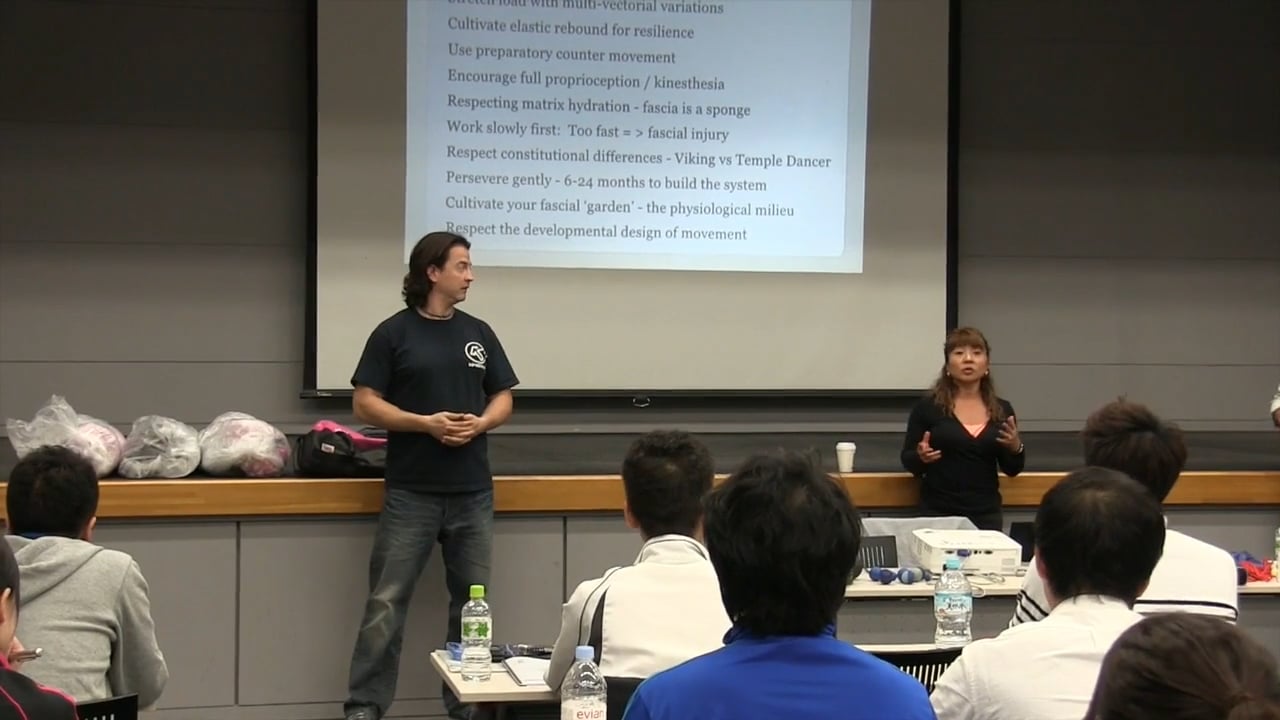
肩の部位的可動域の評価と改善 パート1/2
トーマス・マイヤースの筋膜ネットワークのトレーニングのセミナーから、トラビスがダイナミックな動作を可能にする為に不可欠な部位的な可動域の評価方法をご紹介します。オーダーヘッドのプレス、スイング、プルアップが無理なく行えるか否かも、このような部位的な可動域が関与します。
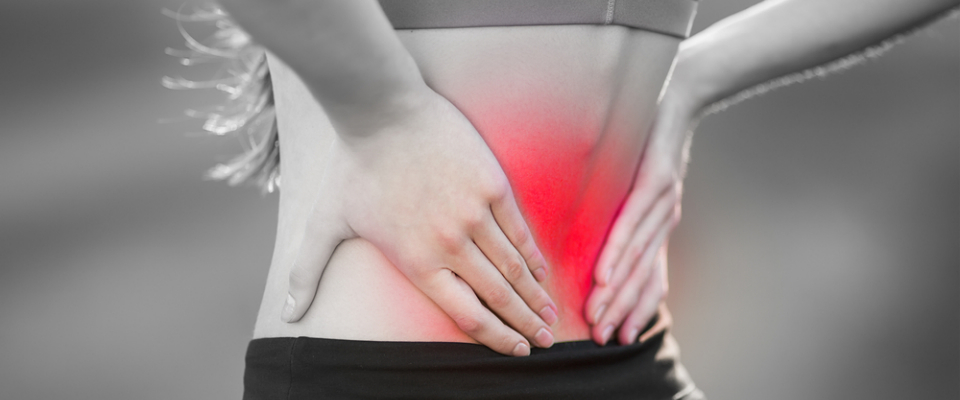
腰痛のためのエクササイズは意外な効果が!
腰痛のためのエクササイズは、総じてヘルスケア全般にわたって、かなり問題のある事柄において、ある程度有益のように見えます。メタ分析を含む最近の系統的レビューは、ほぼ全ての種類のエクササイズにおいて、有益な効果を発見しました*ここをクリックしてください*。ピラティスのようないくつかの種類のエクササイズは、より秀でているともてはやされていますが、最近のコクランのレビューによれば、これは当てはまらないようです*ここをクリックしてください*。 私は、一般的な腰痛と治療的エクササイズに焦点を合わせる方法に関して、考えさせてくれた腰痛に関する二つの研究に注目したいと思います。両方ともあまり目立たなように見えますが、私見では、私達の治療的エクササイズの捉え方に対して、深遠な意味を持っていると思います。 最初に、2012年の系統的レビューを見てみましょう。 “非特異性慢性腰痛における運動療法後の有益な臨床転帰は、目標とするパフォーマンスにおける同様の向上を条件とするのか?系統的レビュー” この研究論文は、慢性腰痛における運動療法試験に着目しました。彼らは初期検索の1217報の論文から、試験対象患者基準を満たす13報の無作為化比較試験と5報の非無作為化比較試験に絞り込みました。 レビューの目的は、これらの試験に含まれている科学的根拠が、運動療法後の目標とした身体機能面で、患者の痛みの変化を立証しているかどうかを発見することでした。身体機能面は、可動性、体幹伸展と体幹屈曲の強さ、背筋の持久力に関するものでした。 研究者視点からのポイントは、その結果が目標とされた運動プログラム面と実際に結びついているか否かではなく、慢性腰痛における運動の介入が、痛み、あるいは身体障害のような、肝心な結果変数に影響を与えたかどうかという研究報告でした。 10報の研究では、痛みの変化と矢状面(屈曲と伸展)での可動性における関連性を調査しました。7報の研究は、相関関係だけではなく立証するデータがでず、3報の研究では、データとの相関関係すら見つけられませんでした。著者は、このデータのメタ分析を行い、可動性の変化と痛みの変化の間の全相関が、極めて低いことを発見しました。 9報の研究と5報の研究は、それぞれ体幹伸展と体幹屈曲の強さを調査しました。利用可能なデータでのメタ分析は、痛みの変化と強さの変化の間には、有意な相関関係がないことを示しました。 筋持久力に関しては7報の研究の中で行われ、相関関係だけでなく、特定の相関係数もありませんでした。 身体障害、強さ、可動性に関する相関関係もあまり興味深いものではありませんでした。 著者達は下記のように述べています: “私達は、入手可能な文献は、慢性腰痛における運動療法後の臨床転帰の変化と身体機能の変化の間に、納得できる関連性を立証していないようであると結論付ける“ “結果は、慢性腰痛における運動療法の治療効果が、筋骨格系の変化に直接的に起因するという考えを立証していません。慢性腰痛における運動療法の有効性の増大を目的とする今後の研究は、症状改善に影響している偶発性の要素を詳しく調査するべきです” 人々はエクササイズで改善するでしょう。私達は、運動が効果的であることを知っていますが、弱さや柔軟性の低さが腰痛の原因である、あるいはその解決に取り組むことが腰痛の問題に対する治療法であるということを意味していないのかもしれません。これらの著者達は、エクササイズの効果は、心理的、認知的、あるいは神経生理学的適応のように、‘局所的’変化というより、より‘中枢的’であるかもしれないと感じています。 これらは、運動パターンと感覚入力の変化、皮質再現、あるいは身体図式における変化、そして、療法士/患者のポジティブな相互関係を含めたのでしょう。恐怖回避や破局的行動の減少を伴ったのかもしれません。 血流量の向上や、単純により多く動くことによる人々の全体的な健康の増進、または人々の‘ホメオスタシスの領域’の細胞レベル、あるいはより中枢神経系に基づいた活動の増大といった、運動に関連する基本的な生理学的プロセスを軽視することができるとは考えていません。 もう一つの潜在的な問題は、人々に‘強くなる’必要があると言うことが、どのように彼等の能力への認識に影響を与えるのかということです。多くの人達にとって、それは彼等弱いところからスタートするという意味を含み、よって、真実かもしれないし、真実でないかもしれないリスク増大はしばしば、仮定される代わりに定量化されてしまいます。 以前に私が議論してきたように、多くの治療的エクササイズは、ほとんど筋力強化にはなりませんが、より多くの運動を伴うのです! この文献は、なぜエクササイズが有益であるのかという理由の背後にある潜在的なメカニズムをどのように見ているのかを問いかけていると思います。 次は、目標設定に関する短い文献です。 “慢性腰痛における目標設定を指導された患者−どんな目標が患者には重要で、その目標は私達が評価するものに沿っているのか?” この文献は、対象者20名のうち27名の特有な目標のうち、身体活動に関連する目標が最もよく見られる(49.2%)ものであったことを確認しています。2番目に多かった目標は、14.29%を占める職場に関連するものでした。この文献に、これらの目標が何であるかという幾つかの例を含めることで有意に裏付けされ、人々が重要だと思う機能的活動が分かったであろうと強く感じます。私はそれらが、彼等が靴ひもを結んだり、子供を迎えに行くことのような物事と関連しているのではないかと思います。これらは、強さや関節可動域(ROM)のような、より臨床的変数に関連して調査されていないかもしれないけれど、重要で、関連性があり、有意義な目標です。それらはしばしば関連性なく、単にこれらの構成要素を分離させて、単独で考えていては解決されない身体的なパフォーマンスの側面を含んでいるかもしれません。 この研究結果は、患者の目標が、理学療法士によって使用される一般的な評価基準に全く沿っていないということを発見しました。従来の評価基準は、痛み、筋力、関節可動域(ROM)でした。ここでの議論は、これらの従来の評価基準が、患者が彼らの目標を達成することを可能にする助けとなるであろうということですが、ただ、これは仮定にしか過ぎません。もしあなたが、誰かがあなたの思い通りの評価基準を達成したと感じたとしても、それは、彼等の評価基準には、あまり関連性が無いのかもしれません。 著者達は次のように述べています: “臨床転帰の評価基準は、患者にとって有意義な治療の成功についての正確な情報を提供していないかもしれない。患者の選択によって動かされる治療介入を決定するために、臨床医は慢性腰痛患者との共同アプローチを考察するべきである” 誰かが痛みをあまり経験しないように助けることは、単純かもしれません。一例として、もし彼等が前屈をすることによって腰痛があるのであれば、彼等にその動作を避けるように告げることです。成功に関するひとつの観点は、前屈において痛みが無いこと−目標達成です。もう一つの観点は、再び靴ひもを結ぶためにしゃがむことが可能になること−目標は達成できていません。痛みの評価基準の削減は、当事者から見た成功を意味するわけではないのです。人々は、痛みの無い身体障害の感覚を味わうより、より良い機能性を伴うかなりの不快感に耐えようとするのかもしれません。 これら二つの文献は、治療的エクササイズと前向きな結果の背景にあるメカニズムにおける従来の考え方に挑んでいるのだと、私は考えます。私達がメカニズムに関して、理解すればするほど、エクササイズのパラメーターをよりうまくデザインすることができるでしょう。強さ、あるいは関節可動域に関する評価基準の使用は、人々の目標に沿うものではなく、これらの評価基準の変化によって回復が左右されるわけでもありません。 恐らく、成功は従来の評価基準によって常に定量化されるわけではなく、結局のところ、結果の成功は、これらの評価基準にかかっているのではなく、治療的エクササイズが適用される人たちの認識にかかっているのです。非難されるかもしれませんが、これらの結果は私達の身体の他の部分にも適用することができるのではないかと提案しますs! 私見では、量、関連性(考えられている場合でも)、喜びは、慢性腰痛患者における運動の鍵となる要素ではないかと考えます。これらの変数がさらに調査されるのを、是非みてみたいと思っています。

スプリントのためのレジスタンストレーニング
目的 この記事は、趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングを行う成人アスリートのいずれかにおいて、従来のレジスタンストレーニングは、スプリントスピードを向上するためにどの程度効果的であるかということを堤示している。 背景 序論 レジスタンストレーニングは、スポーツパフォーマンスを向上するための、極めて伝統的な方法のひとつである。それは筋力および筋サイズを増加し、アスリートの力生成能力を向上する。レジスタンストレーニングの幅広い導入以前、多くのコーチたちは、ウェイトリフティングは(エクササイズが競技に特化していないため)無効であり、アスリートを大きく、強く、そして筋骨隆々とするため、彼らを減速するであろうと信じていたが、後にこの批評は不当であるということが発見されている。興味深いことに、30-40年前にレジスタンストレーニングの反対者により行われた議論と、現在、高負荷レジステッドスプリントトレーニングの使用に反対するコーチたちによる議論には、多くの共通項が見られる。レジステッドスプリントトレーニングと同様に、レジスタンストレーニングの際の実際の負荷は、(スクワットやデッドリフトのような軸方向エクササイズを使用する)垂直方向、もしくは(プルスルー、ヒップスラスト、グルートブリッジ、もしくは水平バックエクステンションのような、前後方向のエクササイズを使用する)水平方向のどちらも有りえる。 動作のメカニズム レジスタンストレーニングが、スプリント速度を向上するためのトレーニングプログラムに一般的に含まれるようになったのは、過去数十年ほどのことである。レジスタンストレーニングは、その低速における力生成を向上する能力により効果的であり、また、本来筋肉に備わっている力対速度の関係により、より高速における力生成能力を向上する。 メタ分析 趣味としてトレーニングを行うアスリート レジスタンストレーニングは、スプリント速度を向上するために広く調査されているため、様々な研究のメタ分析が可能である。ルンプおよびその他(2014年)は、趣味としてのアスリートにおける、スプリントパフォーマンス向上のための異なるトレーニング方法の影響に関し、メタ分析を行った。最初に彼らは、トレーニング方法を特異(スプリントもしくはレジステッドスプリント)、および非特異(プライオメトリック、レジスタンストレーニング、及びバリスティックトレーニング)へと分類した。彼らは、趣味としてのアスリートにおいて、スプリント速度を向上するために、特異および(レジスタンストレーニングのような)非特異両方のトレーニングは同様に効果的であったと記述している。実際に数人の研究者たちは、一般的なレジスタンストレーニングおよび特にスクワットエクササイズは、スプリント能力を向上するために効果的であるということを確認している。クローニンおよびその他(2007年)は、研究論文を再考察し、長期のレジスタンストレーニングプログラムから得られる最大スクワット強度の増加は、スプリントタイムの減少と関係があるということを報告している。しかし彼らはまた、趣味としてトレーニングを行うアスリートにおいて、有意義なスプリントタイム減少のためには、スクワット強度の大幅な増加が必要であると記述している。具体的に彼らは、約2%のスプリントタイムの減少のためには、約23%のスクワット強度の増加が必要であると観察している。より最近にはサイツおよびその他(2014年)が、(バックスクワットの1RMによる測定において) 下半身の筋力の増加と、40m以下の距離におけるスプリントパフォーマンスの間の長期的な関係を調査している。彼らは、スクワット効果量およびスプリント効果量の間において、統計的に有意である比較的大きな(R-squared = 0.60)相関関係を報告している。これは、1RMバックスクワットおよび短距離スプリント能力の間における密接な関係を発見した過去の筋断面解析(例、ヴィスロフおよびその他、2004年)を支持している。ゆえに一般的なレジスタンストレーニング、特にバックスクワットエクササイズは、スプリントパフォーマンスを向上することが可能であるということは比較的明白である。しかし両方の研究は、非常に限られたトレーニング経験しかない人を含む、広範な被験者を含んでいたという点で制限があった。上記の分析から、十分にトレーニングされた個人がより少なく除外されていた場合、そのような強い関係が存在していたかどうかは明確ではない。 高度にトレーニングされたアスリート 上記のようにメタ分析は、レジスタンストレーニングはスプリント能力を向上することが可能であり、また、彼らの比較的浅いトレーニング経験にもかかわらず、趣味としてトレーニングを行うアスリートにおいて、最大スクワット強度の増加はスプリントタイムの減少と関連があるということを報告している。このような発見は、高度にトレーニングされたアスリートに対しても、少なくともある程度は適用されるようである。実際にヴィスロフおよびその他(2004年)は、国際的レベルの男性サッカー選手において、最大スクワット強度および短距離スプリントパフォーマンス間の強い断面的相関関係を報告している。ルンプおよびその他(2014年)は、高度にトレーニングされたアスリートにおける、スプリントパフォーマンスに対する様々なトレーニングタイプの影響に関し、メタ分析を行った。最初に彼らはトレーニング方法を、特異(スプリントもしくはレジステッドスプリント)および非特異(プライオメトリックス、レジスタンストレーニング、そしてバリスティックトレーニング)に分類した。彼らは、特異および非特異な両方のトレーニング方法は効果的ではあると発見している。しかしながら彼らは、高度にトレーニングされたアスリートに対しては、レジスタンストレーニングのような非特異な方法は効果が低いということを記述している。彼らは、アスリートが既に筋力、パワー共に発達した基板を持ち、これは、追加のレジスタンストレーニングにより更に向上しなかったことに起因している可能性があると示唆している。高度にトレーニングされたアスリートは、相当量の最大スクワット(もしくは他のエクササイズ)強度を発達させることは不可能であるようであるという事実と併せ、これは、高度にトレーニングされたアスリートは、非特異な方法を使用する時間を減らし、より多くの時間を特異な方法に費やすべきであるということを示唆している可能性がある。 アスリートにおけるレジスタンストレーニングのスプリント速度への影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – レジスタンストレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:フライ(1991年)、ホフマン(1991年)、ウィルソン(1993年)、ウィルソン(1996年)、マーフィ(1997年)、ハリス(2000年)、ブレイゼビッチ(2002年)、アスクリング(2003年)、ホフマン(2004年)、コチャマンディス(2005年)、ドッド(2007年)、レネスタッド(2008年)、ムジカ(2009年)、シェリー(2009年)、ヘルガード(2011年)、ヘルマシー(2011年)、レネスタッド(2011年)、ロッキー(2012年)、コンフォート(2012年)、サンダー(2013年)、ロツゥーコ(2013年)、クードラスキー(2014年)、ブリット(2014年)、トーマス(2014年)。これらの研究のほとんどは、レジスタンストレーニングは、アスリートにおけるスプリントパフォーマンスを向上するということを発見している。バックスクワットが使用されていなくとも向上が観察されたといういくつかの例(例:アスクリングおよびその他、2003年)は存在するが、含まれている研究の多くはバックスクワットを使用していた。 スプリント速度に対する、レジスタンストレーニングの際の負荷の影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – 2つ以上の異なる負荷(つまりバー速度)におけるレジスタンストレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール、および異なる負荷におけるレジスタンストレーニング 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:ハリス(2000年)、ブレイゼビッチ(2002年)。両方の研究は、低速および高速でのレジスタンストレーニングの間における差違を発見しなかった。これは、トレーニングされたアスリートにおいて、より低負荷およびより速いバー速度を使用することは、レジスタンストレーニングからのスプリントへの適応を最大化するために重要ではないかもしれないということを示唆している。 レジスタンストレーニングの際の、スプリント速度に対するエクササイズの影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – 2つ以上の異なるエクササイズにおけるレジスタンストレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール、および異なる負荷におけるレジスタンストレーニング 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:スピアーズ(2015年)。この研究は、両脚スクワットおよび後ろ足を挙上したスプリットスクワットトレーニングの間において、チームスポーツを行うアスリートにおけるスプリント能力の向上に差違はないということを確認している。これは、トレーニングされたアスリートにおいて、下半身の筋肉を発達させるために、ここで使用されたタイプのエクササイズは、レジスタンストレーニングからのスプリントへの適応を最大化するために重要ではないかもしれないということを示唆している。 スプリントに関する結論 様々なエクササイズを使用したレジスタンストレーニングは、アスリートにおけるスプリントパフォーマンスを向上させるために効果的なようである。低負荷およびより速いバー速度を使用することは、高負荷および遅いバー速度の使用に比べ、よりよい結果を生み出すわけではないようである。現在のところ、エクササイズ選択の影響は明確ではない。 高度にトレーニングされたアスリートは、レジスタンストレーニングのような非特異な方法からはより少ない恩恵しか受けない可能性があるが、趣味としてトレーニングを行うアスリートは、特異および非特異両方の方法から同様に恩恵を受ける可能性がある。

肩と腰部を改善するひとつのエクササイズ(ビデオ付き)
ひとつのドリルで肩と腰部を改善する クリニックで一番良く見る問題を2つだけ選択しなければならないとしたら、肩と腰部と言えるでしょう。考えてみれば驚くことでもありません。私達の現代のライフスタイル、バランスの悪いトレーニング、不良姿勢など様々なことが、肩や股関節の可動性の不足を生み出します。 激しい痛みを伴う問題も、これらのエリアがあまり上手く動かないことからスタートするのです。腰部ではなく股関節の動きと言いましたよね。股関節も肩関節も共にとても類似したタイプの関節です。解剖学的に深くカバーはしませんが、これらはボールとソケットの球関節と考えることができます。これにはプラス面もマイナス面もあります。というのも、球関節は豊富な動作を可能にしますが、この可動性の為に摩耗しやすいからです。 更に厄介なことに、これらの関節は一旦自由に稼動できる能力を失ってしまうと、ダメージを受けたり大きな代償動作を生み出したりする可能性をかなり持っているのです。良く分かっているはずです。私自身、水泳競技の経験の中で、両肩の回旋腱板損傷と5箇所の椎間板ヘルニアを経験しているのですから。私はただセラピストとしてのみお話をしているのではなく、これらの問題を沢山経験したひとりの人間としてお話しています。 これらの古傷を持っていた為に、プルアップ、プッシュアップ、クリーンやスクワットをはじめとした沢山のエクササイズができるようになるとは全く考えていませんでした。しかし、DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングを自分自身が経験して、ただ体脂肪が減少するということのみではなく、身体の治癒ということが特に衝撃的でした。 もちろん、誰かをより良くしていくということには、スローダウンするというチャレンジもあります。DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングで良く言われることですが、ただウエイトを持ち上げるのではなく、いかに身体を動かすのかを理解することが重要です。DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングにおいては、いかに自分自身の身体を動かすのかを指導することが重要なのです。 ファンクショナルトレーニングとは、身体がより優雅さと強さを持って動くことを指導することを意味します。 実際、多くの人達が驚くのは、動作に欠けているのが筋力ではなく、身体統合性の効率性の理解であり、失った可動性を取り戻すことが必要であるということです。 ですから、ここで、ただ汗をかいて呼吸が激しくなり沢山のカロリーを燃焼するだけではない、DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングのドリルをご紹介したかったのです。これらのドリルを、ただ筋力を培うのみでなく、より効率よく強さを培い、失った可動性を取り戻すための方法として捉えることができます。効率性の良さを得ることができれば、より健康で長生きをすることにも繋がります。 こんな風にシンプルに見えるドリルが、今まで考えてこともなかったようなパワフルさを持ちえることがお分かりになりますね。

トラクションを伴う股関節包のモビリゼーション
股関節の関節包にある制限を自由にする為に、ベルトやタオル、そして手を利用して関節のスペースを広げるようにトラクションをかけつつ、股関節を3Dに動かすことで、関節包及び周囲軟部組織の可動性を高めるテクニックをレニー・パラチーノがご紹介します。

肩甲骨プッシュアップが好きではない理由
肩甲骨の後退と前突の動きを学ぶエクササイズとして人気のあるスキャププッシュアップ/肩甲骨プッシュアップを、かつては頻繁に使用していたエリック・クレッシィが、このエクササイズを使わなくなった理由とは?

痛みにおける姿勢の評価・非難する理由の背景にある科学はデタラメである
もしソーシャルメディアで姿勢、あるいは痛みの問題について言及する全ての人にお金が支払われて、それを私が受け取っていたら…、私は今頃、裕福になっているでしょう。 痛みの無い人達と腰痛、肩痛、頸部痛を患っている人達の姿勢を比較する数多くの研究があり、実際の差異は発見されていないにも関わらず、この情報は通常無視され、腰痛、肩痛、頸部痛について口にするとき、姿勢は文字通り人々の思考に深く染み込んでいます。 決して科学的知識に良いお話の邪魔をさせてはいけません!特にインターネット上では尚更です! 実際、私は以前に何度か姿勢に関して記述しています:) とはいえ、科学的知識で始めましょう。2016年に発表されたこの研究論文*ここをクリックしてください*では、腰痛患者と腰痛を持たない人達の間の腰椎前彎(脊柱彎曲)において、有意差は発見されませんでした。 これは非常に重要です。いかにして、痛みの無い人達に見られる何かを痛みの原因として非難することができるのでしょうか? 十分に理解しましょう…。 私達は何を測定しているのか? このブログで私達は、どのように姿勢を評価するのか、そして、それは科学的に有効なのかどうかということに関連しているいくつかの疑問を調査します。まず始めるにあたって、優れた測定方法を持っていなければ、問題に関する何かを非難するのは非常に困難ですから。 実際の科学的根拠に関する最初の情報は(姿勢に関する議論でしばしば欠けていますが)、立位での腰椎彎曲の測定に着目すること(しばしば脊椎彎曲は腰痛の原因として非難される)。この評価は、世界中の治療室やジムにおいて行われているものです。 腰椎彎曲は腰痛における大きな要因ではないようではありますが(上記の科学参照)、腰椎彎曲の増大(時折減少)は腰痛を増悪させるという考えは、骨盤の傾きが腰椎彎曲の大きさに影響を与えているという考えとしばしば組み合わさっています。 かなり昔、1990年に、この考えはHeinoおよびその他によって研究され*ここをクリックしてください*、骨盤傾斜角と腰椎彎曲は単純に相関関係が無いということを発見しています!骨盤のポジションに着目することが、測定がより困難である腰椎で何が起きているのかに関して伝えてくれることはほとんどありません。これよりも以前の1987年に発表された非常に類似した研究*ここをクリックしてください*もまた、同様の結果を輩出しましたが、このデタラメは、今日いまだに教えられています。 ともかく、立位の測定に関する研究論文*ここをクリックしてください*に戻りましょう。著者は、400名(無痛者332名、腰痛罹患者83名)の立位姿勢における変動性に関して調査し、立位の際は毎回やや異なる方法で立っていることを発見しました。 著者は彼等の言葉で“立位は非常に個性的で、再現性に乏しい”と述べています。 では、これがなぜ重要なのでしょうか? 簡単に言えば、あなたが姿勢の評価をする際、実際にどの姿勢を測定しているのかということです。ある姿勢は大きな彎曲を、またある姿勢は小さな彎曲を示すかもしれません。 この情報を踏まえて、姿勢評価の解釈の仕方に関していくつかの疑問があります。 これらの姿勢のうちのどれが問題に関連しているのか? 何回測定して、何回平均値を求めるのか? 彎曲が過剰、あるいは彎曲が不十分かどうかを決定するために、何に対して比較するのか? 著者は、立位姿勢における一貫性の欠如は、実際に“間違った診断と場合によっては不必要な治療”に通じるかもしれないという点を強調しています。 もしあなたが問題ではないことを重要視すれば、それが効果を表していない、あるいは一時的にしか効果を表していないという事実(潜在的になぜかなりひどい腰痛が持続するのか)がわからなくなるかもしれない、何か他のことに注目しなくなるでしょう。 人々が日常生活で用いているものもまた、クリニック、あるいはジムで測定されるものとは異なるかもしれません。クリニックやジムで測定するものは、‘スナップ写真’として表現されるかもしれません。そして、この研究*ここをクリックしてください*は、この‘スナップ写真’を研究の被験者によって日常的に実際に用いられているものと比較しました。 著者は立位時の平均値が姿勢評価時の腰椎前彎は最大で33.3度であったのに対し、24時間通しての平均値はたったの8度であることを発見しました!。とても大きな差異です! ‘スナップ写真’的な姿勢評価は、どの程度の前弯が実際に用いられているのかに関して、私達に十分に情報を与えてくれないでしょう。そして、実在しない問題の及ぶ範囲を多く見積もり過ぎてしまうかもしれません。 また、これらは放射線測定であり、臨床における‘最高基準’であることを忘れてはいけません。しばしば腰椎前彎は、骨盤傾斜を示している骨盤上の目印の関連性に着目するといった、より初歩的な方法で測定されますが、これと腰椎彎曲とのはっきりとした関連性は無いことを私達はすでに議論しています!これ自体、2008年にPreeceの研究*ここをクリックしてください*によって、問題として立証され、骨盤の形態学もまた変動的であり、誤った測定に通じるとされています。 “これらの結果は、骨盤の形態学におけるバリエーションは、骨盤傾斜と左右非対称な寛骨の回旋の測定に有意に影響を及ぼすかもしれないということを示唆している” ここにASIS(上前腸骨棘)−PSIS(上後腸骨棘)の左右差における関連性(骨盤傾斜を測定するために使用された)の配分があります。右側に偏っていることが見て取れ、骨レベルでより前傾していることを意味しています。 つまり、私達がそれほど問題ではないことを測定することが本当に苦手であるということかもしれません。なんてことでしょう! あなたは先入観にとらわれている? 姿勢を測定する人達にとってもう一つの重要な疑問は…、痛みが存在することを知っている際に、更に姿勢の‘異常な点’を見ようとする傾向があるのかということです。 この研究論文*ここをクリックしてください*は、そのように示唆するでしょう。ここで著者は、しばしば肩痛の原因として提案される、肩甲骨の運動障害、あるいは肩甲骨の異常な位置と動作に着目しています。 彼等は、肩に痛みを持つ人67名と無痛の人68名を比較し、二つのグループの間において、肩の位置、あるいは動作には差異が無かったことを最初に発見しました。 興味深いことに、評価者が有痛者を評価していることをわかっていた際、彼等は 姿勢、あるいは動作の問題に対して高い罹患率を報告していました。有痛者における‘異常な点’が無痛者と同等の場合であっても、有痛の場合ににおいては、非難すべき‘異常な点’を発見することに対して先入観があることを示しています。 著者はまた、肩甲骨の運動障害は実際のところ、個体間における正常な変動性を表していると示唆しています!恐らく、もし彼等が何度も肩甲骨の運動障害を評価すれば、異なった測定値を出すのではないでしょうか?まず始めに、逸脱に対する基準として用いられる有意に定義された‘良い姿勢’など無い、ということを覚えておくことが重要です。 健常者はどのように座るのか? もう一つの疑問は、腰痛を患っていない人達が実際にどのように振る舞うのかということです。彼等は日常的に素晴らしい姿勢をしているに違いないということですよね?しかし、実際はそんなことはありません。 この研究論文*ここをクリックしてください*は、前かがみの姿勢で座る無症状の50名の状態を示しています。10分間の座位で、立位姿勢と比較して、脊椎角度は腰椎で24度屈曲、胸腰部で12度を示しましたが、この前かがみの姿勢での座位は、彼らに問題を起こす原因になっているようには見えませんでした。 下記のグラフからも見て取れるように、脊椎彎曲の変化は、痛みにはそれほど関連していないように見えます。 もし姿勢と痛みが相関関係になければ、痛みは何と相関関係があるか? この研究論文*ここをクリックしてください*は、頸椎のアライメントの変化が実際に年齢と相関関係にあることを示しています。この研究は被験者を年齢に応じて4つのグループに分けました。そして、4つのグループ全てにおいて、年齢の増加に伴い、頸部の角度の値が全て相関関係にあるということを発見しました。 ここでの覚えておくべき重要なポイントは、120名の被験者全員が痛みを患っていないということです。実際に、ここでの除外基準はかなり厳格で、著者は実際に、現在痛みを抱えている、あるいは痛みの既往がある64名(標本の3分の1にあたる)を除外しました。 簡潔に言えば、私達は年を重ねるにつれ、姿勢は‘より悪く’なり、あるいは、恐らくもっと正確にいれば、姿勢は(角度を)増大させる…。しかし、これは重大なしかしですが、これが更なる痛みの原因のようではありません。 要約すると、あなたが読んだり、バー、ジム、治療室で言われたりするような、‘悪い’ 姿勢=痛みというほど単純なものではないようです。 覚えておいてほしいこと 痛みを抱えている人達と痛みの無い人達とでは、姿勢に差異は無い。 姿勢は動作と同様に変動性を示している。 これは、行なっている評価があなたが思っていることを示さないかもしれないということを意味している。 あなたの評価は、姿勢の‘問題’を見つけ出そうとする先入観を持っているかもしれない。 1日を通して用いられている姿勢は、恐らく評価される姿勢とは異なるであろう。 私達は歳を重ねるごとに姿勢は変化し、これは痛みの無い人にも起こることである。

肩甲骨前突:ボックスドロウドリル
肩甲骨周辺の筋群が本来の働きを十分に発揮できるように、肩甲骨の挙上と下制、前突と後退を正しく行うことを学習するためのドリルをぜひお試しください。簡単なように見えて、実はとてもチャレンジ度の高いドリルです。

バンドプルアパートの微調整
上半身の姿勢を整え、ローテーターカフの筋強化にも効果的なバンドを使ったエクササイズを、より正しく行うための注意点をエリック・クレッシィがご紹介します。

クローリングはデッドリフトに勝る
負荷をかけたクローリングはデッドリフトより優れている、と公言した時、ストレングストレーニング業界の人々は私が正気を無くしたのではないかと思うことでしょう。元パワーリフターの立場として、頭がおかしくなったように聞こえるのはわかります。マジで!長年、強くなりたければバーに重りをつけて持ち上げてきたわけです。私たちは、デッドリフトの全身的効果は、すべての筋力を向上させると教えられてきました。ですが、もしも他に優れたものがあったとしたらどうでしょう?そしてより簡単だとしたら? 4月の話ですが、私の良き友人、アレックス・サルキンが、私のトレーニング施設であるリゾルトパーソナルトレーニングで、自重のストレングストレーニングワークショップを指導していました。彼は最後の1時間を、クローリングと様々なクローリングのバリエーションに費やしました。ティム・アンダーソンとオリジナルストレングスムーブメントが過去1年勢いをつけてきていることは周知のことですが、アレックスの気味が悪いくらいのクローリングに対する情熱が私を動かしたのです。抵抗できるわけないじゃないですか?彼は 2~3ヶ月のクローリングでストレングスと持久力の両方において劇的な成果をだした人たちの話をしてくれました。彼は私に、30日間のクローリングチャレンジを与えました。その後様々なテストで、数値が上がっているかを確認するよう提案してきたのです。正直に言います;その時私の主なゴールは、ただ痛みの軽減のみでした。下背部に痛みがあり、硬い股関節、頚椎の椎間板の問題に加えて右腕に痛みもありました。かなり程度の強い脊柱側湾症のために、デッドリフトやオーバーヘッドプレスはなかなかで出来なかったので、クローリングはなかなか魅力的でした。もし痛みが消えてストレングスが回復するのであれば、やってみようじゃないですか! 正直に言うと、クローリングは私にとってはそこまで目新しいものではありませんでした;1年前にプライマル・ムーブの資格認定を受講以来、クローリングを自分のセッションにも活用していたからです。しかしながら、より一貫した実践というアイデアは、私にとって新しいものでした。最初は疑わしい気持ちで体重計に乗り、計測し、そして体脂肪を計測しました。どうせやるのなら、最終的にアレックスの主張が正しいかどうかを証明するつもりでした。私のプログラムは以下のような形でした:月曜、水曜、そして金曜は様々なセットのクローリングで終わる自重ストレングストレーニング日。火曜と木曜はコンディショニングの日で、シンプルにクローリングを10~15分繰り返して必要に応じてレストをとります…が、レストはできるだけ短く抑えるようにしました。土曜日はスレッドに負荷をつけて5セットの負荷付きクローリングとヒップブリッジの組み合わせでした - これは20ヤード前進に続いて20ヤードの後退でした。アレックスは私に、たった25ポンドの負荷のスレッドからスタートし、毎週徐々に負荷を上げるように指示しました。6週目になる頃には100ポンドの負荷で行っていました。 私は何を学んだのでしょうか?まず初めに、抱えていた腰痛と股関節の制限、そして首の問題は一週間と少しで完全に消え去りました。痛みがなくなるとともに、私はある意味クローリングに取り憑かれるようになりました。調子の良さを感じる為に必要な何かがクローリングになっていたのです。 次に、持久力が劇的に向上したのです!火曜と木曜のクローリングセッションは沢山の学びをもたらしてくれました。呼吸と上昇した心拍数のコントロール方法を学びました。苦しい時もある意味リラックスできる方法を学び、動き続けることができたのです。加えて、 下を向いて、ほんの少し床から浮いている膝を床に下ろしてしまわないように我慢できるよう、肉体的に自分を追い込む方法も学びました。負荷なしのクローリングは、まるで負荷なしのピストルスクワットのようです;負荷なしで、うまく動けるようになれば、負荷ありでの動きは向上します。火曜日と木曜日のセッションはクロスパターンの動作、広背筋の活性化、股関節のスタビリティと脚や腕からの駆動に注目させてくれました。 3つめに、私の筋力も毎週向上していきました。毎週ピストルスクワット、片手でのプッシュアップ、そしてプルアップが楽になりました。6週目が終わる頃、自分の測定をして使用前、使用後を比べる直前に災難に見舞われました:自転車から転倒し右の三頭筋を断裂したのです。プッシュアップもプルアップも、クローリングですらテストできなくなってしまいました。数え切れないほど効果を実感していたのに何もテストできなかったのです!手術の直前に体脂肪の測定を行いました。クローリングやトレーニングを約10日間できなかったので期待していなかった私は、筋肉が6パウンド増量し、体脂肪3%減という結果に衝撃を受けました!食事もトレーニングも何も変えていません。ただクローリングという運動負荷を加えただけなのです。アレックスの言うとおりでした… クローリングはすごいんです! アレックスに、私の電話番号をそえたFacebookメッセージを送り、クローリングはデッドリフトに勝ると思うと伝えました。指導という観点から見ると;誰もがどんな形にせよクローリングをすることができますし、ほぼ毎日取り組むこともでき、自体重さえあれば可能です。そしてそれは身体機能の向上だけでなく、コンディショニングやストレングスも同様に向上させることができます。 デッドリフトと比べた場合、指導曲線はクライアント次第でとても長くなります。毎日行うのはお勧めできず、道具が必要となります。デッドリフトを指導すべきではないと言っているわけではありません;ただ時に、最もシンプルな動作が大きな成果を生み出すことがあるのです。考えてみてください。身体は対角パターンで機能し、もしも私たちがその自然な動きを神経的、そして身体的観点で鍛えれば身体はより効率的に機能します。そしてグレイ・クックが指導するように、もしもより効果的に動ければ、ストレングスと持久力はついてきます。私は皆さんに自分が経験したことをチャレンジします。自身で体感してみてください。クローリングはあなたを強くしてくれるのです!さあやってみましょう!
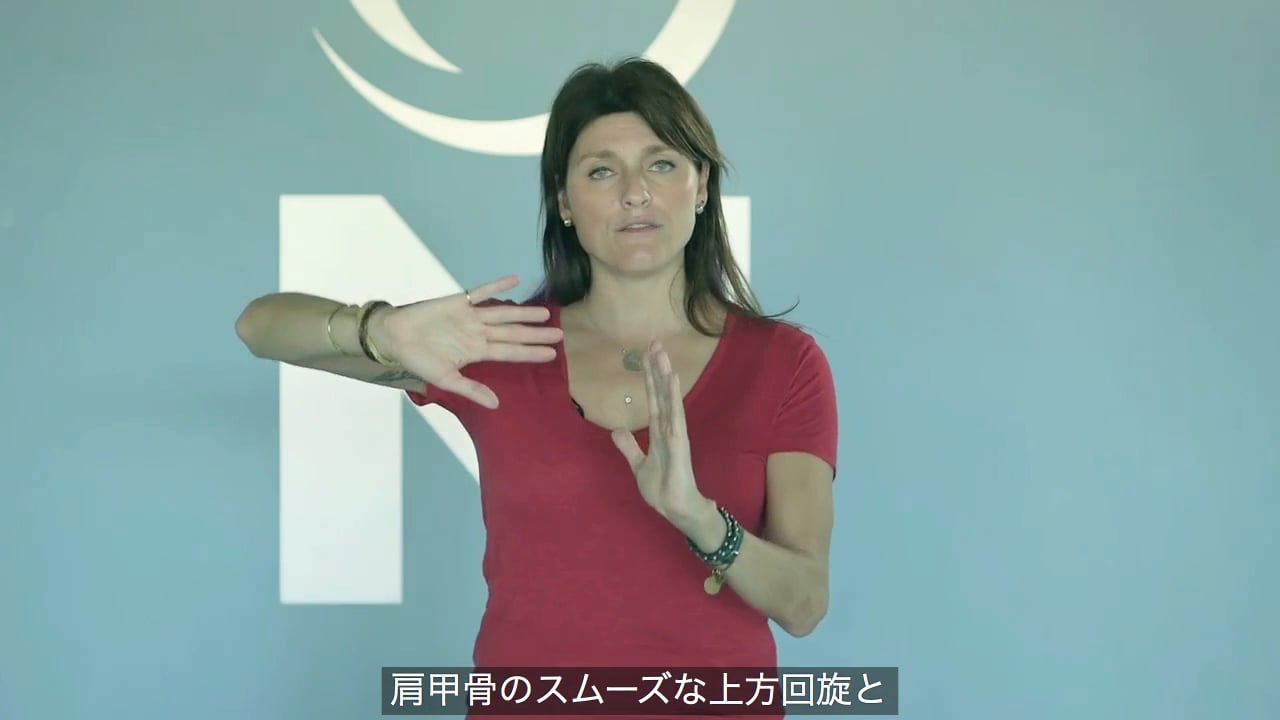
肩甲骨の上方回旋と下方回旋
スー・ファルソニの、肩複合体に関するDVDシリーズから、オーバーヘッドアスリートに、よく見られる腕の挙上に伴う代償動作のパターンを改善する為のエクササイズのアイデアをお届けいます。
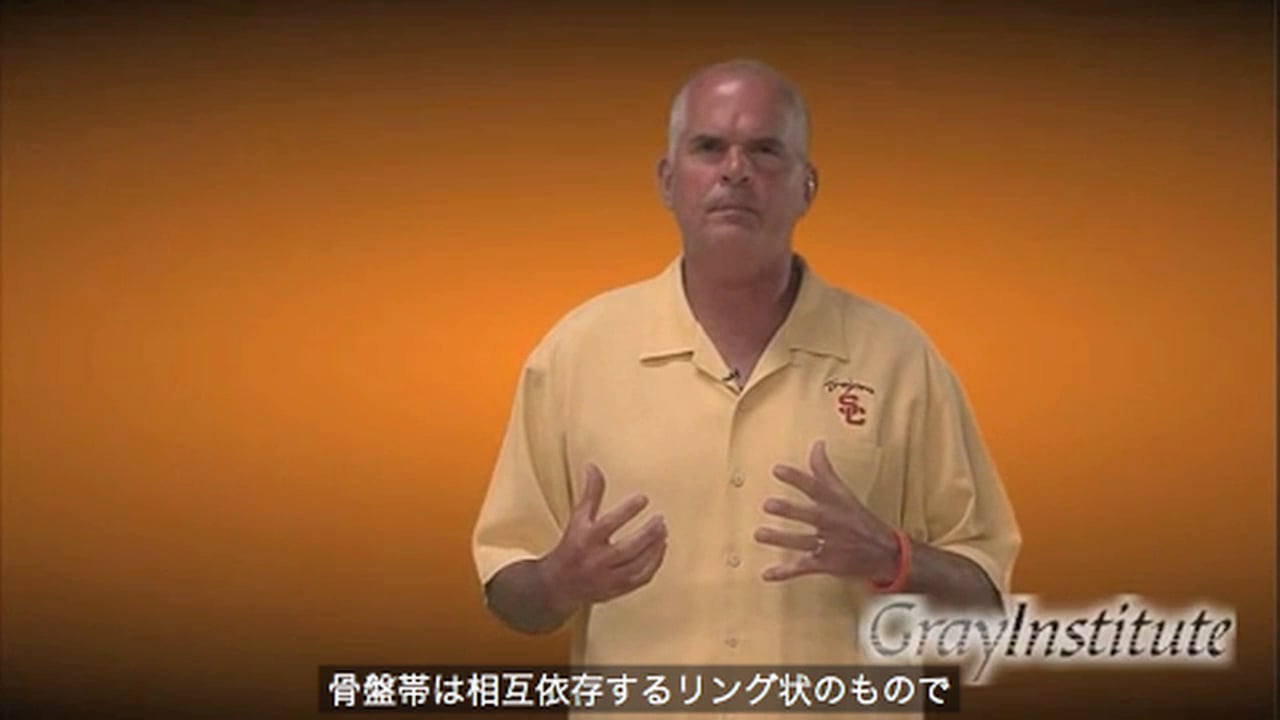
股関節を理解する
右の股関節に機能不全がある時、その問題の原因は右股関節にあるのでしょうか?身体構造全体の相互依存とチェーンリアクションを理解して分析し、治療、トレーニングを提供する為の、全体像を捉える考え方をギャリー・グレイが提案します。