マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

股関節外旋のモビリゼーション
グローバルの機能を補助するためにローカルの許容量を向上させる必要があることもよくあります。何をするかではなく、いかに行うかが重要であり、ディティールを聞き取ることができるか否かも重要。レニーは、教科書や解剖実習を通しての解剖学の学習からのみでなく、ファンクショナルアナトミーセミナーを通しても学びを得てきました。彼自身の学びから得た重要なポイントをレニーがシェアします。
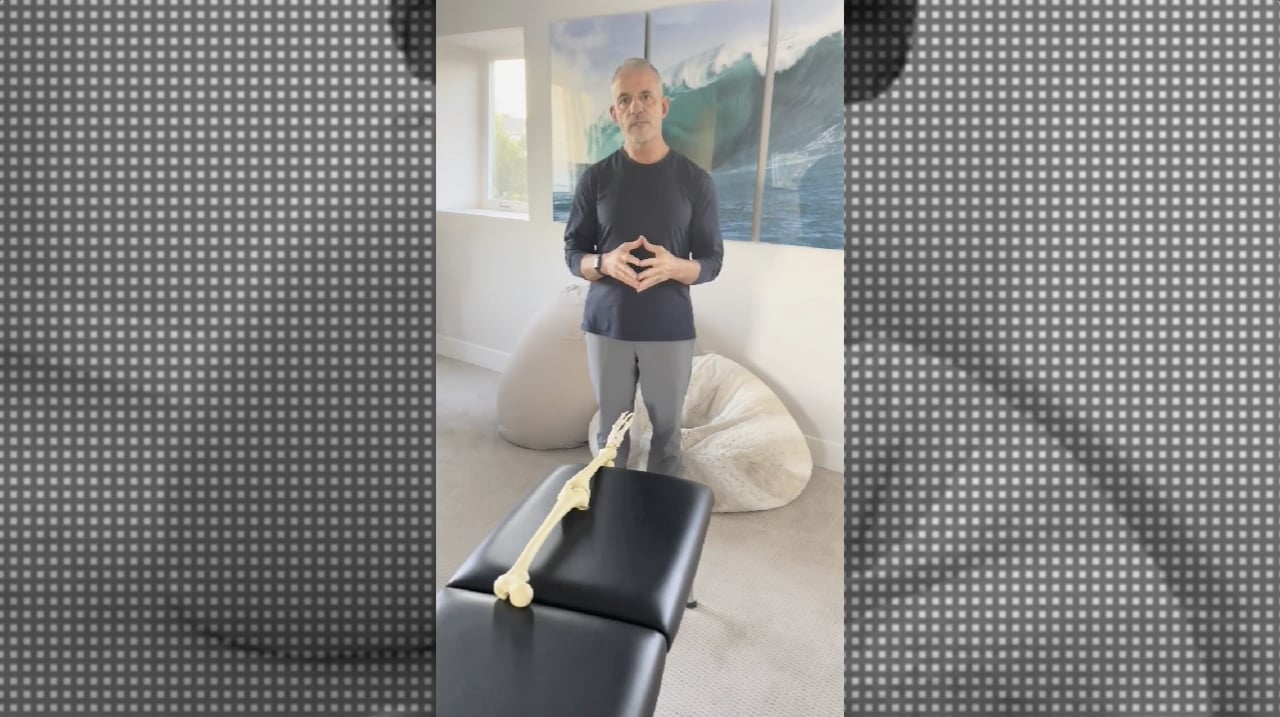
距骨のモビリティの評価とトリートメント
足部の機能にとって重要な役割を担う距骨の動きがどの程度スムーズに起きているか、距骨を動かすことで評価とトリートメントの両方のメリットを得ることができるシンプルなアプローチをレニー・パラシーノがご紹介します。

手首から肘への軟部組織モビリゼーション
手首から肘にかけての関節を動かす際に、関節の可動する全ての方向に向かって、トラクションをかけたり圧迫したりしながら、動きの可能性と質を確認する具体的な方法を軟部組織スペシャリストであるレニーがご紹介します。
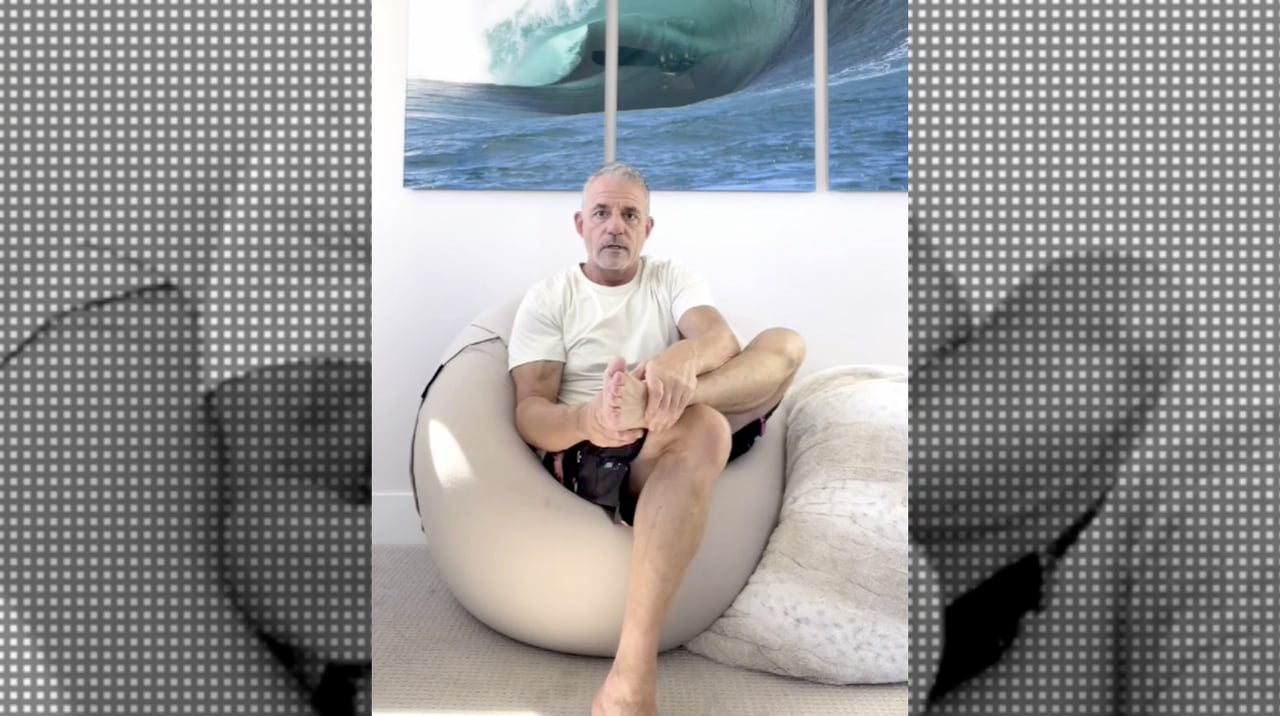
セルフフットケア
皆さん自身の足のケア、あるいはクライアントの方々の足のケアは日頃どのようなことを行なっていますか?足部の関節が本来の動きを維持することができるように、自分自身で簡単に行える毎日のモビリゼーションをレニーがご紹介します。
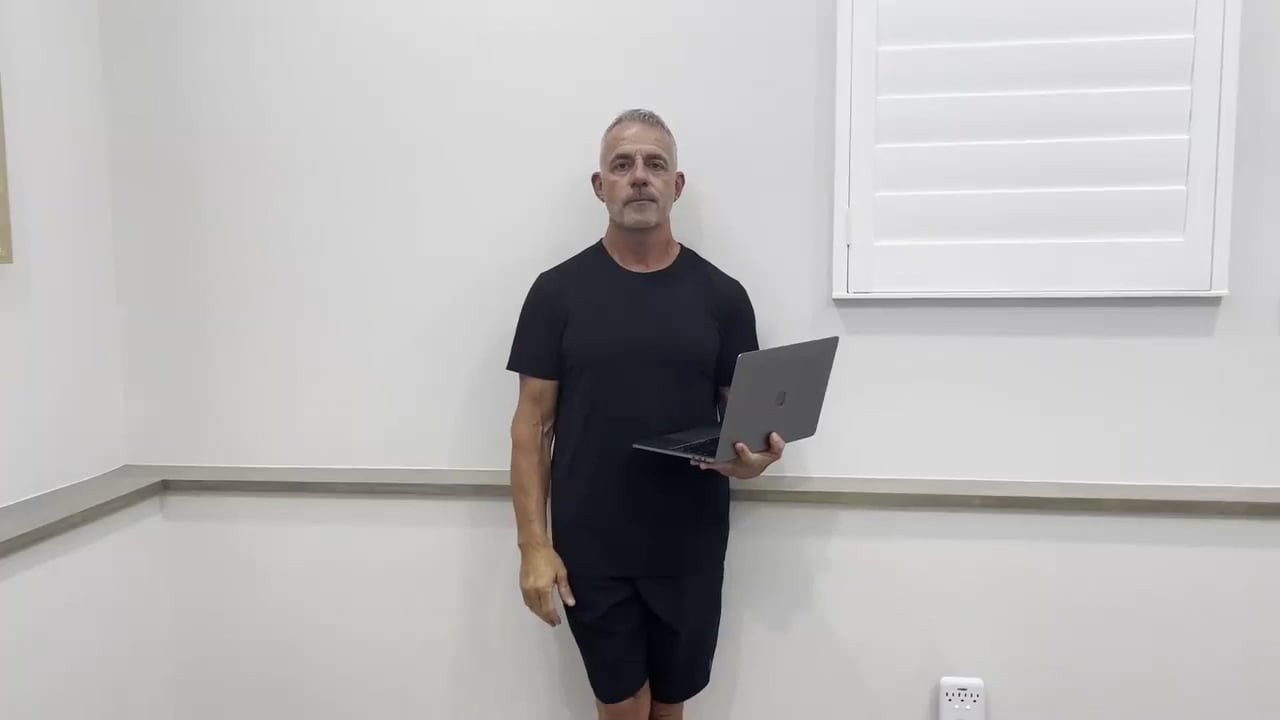
ランジマトリックス
ランジをする時、スクワットをする時、膝が第二足趾と同一線上にならなければならない、というまるで規則のような表現を聞いたこと、あるいは教えられたことのある方は多いのではないでしょうか?長年使われているこの表現に関してのレニーの考えをシェアします。

腰椎の牽引
運動を始める前や終了後に、アクティブなアプローチと組み合わせて行う受動的なアプローチは、なかなか気持ちの良いものですよね。誰にでもできるシンプルな腰椎の牽引の方法を軟部組織スペシャリストであるレニーがご紹介します。

モーションはローションである
NBLのL.A.クリッパーズの選手たちの軟部組織ケアを担当してもいるレニーが、膝蓋骨周辺エリアを例にとって3Dに組織を動かしながら状態を評価していくプロセスと、その評価をもとにバイブレーションガンなどを用いたアプローチを原理原則にもとぢぃて紹介します。

脊椎の牽引モビリゼーション
デスクに向かって長時間座位で過ごす生活を送っていると脊椎は圧縮された状態で固まってしまいがちです。自宅でもオフィスでも簡単に実行できる、脊椎のセルフ牽引モビリゼーションの方法をレニー・パラシーノがご紹介します。

足首のモビリゼーション
壁を使ったポジションと、両膝をついた四つん這いのポジションで行う足首の3Dモビリゼーションをご紹介します。テンションを強く感じるエリアを見つけたら、段階的にアイソメトリック収縮を行います。組織の強化を行いつつ可動性を高めるユニークな方法を是非お試し下さい。

床の上でのファンクション
子どもの動きを見ていると、常に拡張して収縮する、まさに有機体的な自由で自然な動きをしていることに気づきませんか?有機体としての私達の身体は、常に動き続けるように作られているのです。床の上で、様々な動きを多面的に行うドリルで、子どものような自由な動きを取り戻せるかもしれません。