マイクロラーニング
隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。
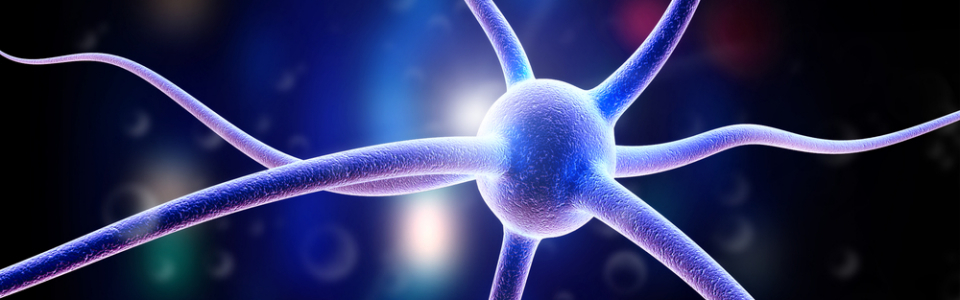
筋紡錘とゴルジ腱受容器:ガンマシステムについて
質問: 筋紡錘ガンマシステム(紡錘の両端にある筋線維)に関するトム・マイヤー氏の解説に少々混乱してします。そこでは、ガンマシステムとは、紡錘からの求心性神経をごまかし、あたかも筋線維の伸張が増加したかのように伝えられるということでした。彼は以前、筋の長さの増加が感知されると、紡錘の求心性神経は、筋の緊張/収縮の増加をももたらすと説明していました。 紡錘の両端にある筋線維が、紡錘の中央部ではなく、紡錘の両端を引き伸ばすということは、それによって、他の筋線維よりも少ない伸張を、紡錘の中央にある求心性神経が感知させるということですね? 彼は、この影響はガンマシステムによるものだとしています。ガンマシステムは、筋の収縮/緊張を伸ばし(減少)および減速し、そして無理に伸張した後には、自然な静止長を取り戻します(これは、神経の影響というよりは、筋膜の可塑性によるものかもしれません)。 ここで言う筋収縮を伸ばすということが、動きをより簡単かつ効果的にするということ以外に、学習をした動きを自動化する(それによって、同時に起こっている別の動きの学習に注意を注ぐことができる)のに、どのように役立つのか、まだ良く理解できないでいます。ただ、私の現在の学習段階では、このトピックは必須というよりは好奇心といった方がいいでしょう。 私が今まであまり理解できなかった筋紡錘/ゴルジ腱受容器についての、明確な説明に感謝しています。微視的構造を知ることは楽しく、今後必要になるかもしれない即興で行うような治療に役立つかもしれません。 ビルより回答: ビル、あなたはご自分の手技の領域を正確にしっかり把握していますね。 神経筋筋膜システムが実際どのように機能するか、まだ初歩的なことしか分からない研究段階ではありますが、あなたの疑問を解消することができるか、試みてみたいと思います。理解が深まると同時にそのまま適用できると思います。 私たち臨床家に理解され始めた、ひとつの重要なことがあります。これまで長年にわたり教えかつ思い込んできたのとは異なり、脳/身体は、筋肉によって動きを統制しているのではなく、筋肉内にある10~100本の筋線維に(繊細の運動制御を必要とする目や舌の筋肉にはより少なく、それぞれの神経が数百の筋繊維に対して指令を与える臀筋では、より多い)存在する神経運動単位を介して動きを調整します。 円滑な加速は、筋肉の筋動員によって起こるのではなく、局所に存在する多くの条件によって協調された各神経筋単位の動員によって起こるのです。しかし、主として脳を介します。その脳は、以前に経験したような運動(加重)の一連の記憶のシグナルを統合する働きをしますが、分かりにくい文章になってしまいましたので、かみ砕いて説明しましょう。 それぞれの神経運動単位は、筋内で機能しています。それは、末端の腱または、その神経筋単位が関与するあらゆる筋膜(筋肉を包むサランラップのような筋外膜も、筋間の疎性組織や中隔組織も含む)と協調しながら、特定の筋を引っ張ります。すべて特異性があり、知覚と予測のつく推測が混ざり合った記憶を通してプログラミングされています。人間の優れた努力の証です。 各神経運動単位には、特定の筋線維があり、その筋線維は特定の腱線維に連結して、ゴルジ腱受容器にシグナルを送り、それからその神経運動単位の筋紡錘が伝達する同じ領域にシグナルを送ります。筋のみにとらわれるのはやめて、神経運動単位を考えるようにしましょう。 では、神経運動単位についてですが、特にガンマシステムについてお話ししましょう。円滑な加速を起こすにあたり、神経系は2つのちょっとしたシンプルな装置を採用しています。それは、筋長と筋長変化率を検出する筋紡錘と、それと筋への張力を感受する筋線維の末端にあるゴルジ腱受容器です。 この絵で筋紡錘が確認できるでしょう。そして、筋の伸張によってどのようにシグナルが増加し、また収縮によってどのようにシグナルが減少するのかがお分かりになるでしょう。 筋が伸張すると紡錘も伸張し、そして、筋内での他動的伸張は神経によって記録されます。よく知られている膝蓋腱反射のような、紡錘を興奮させる短く急な伸張(バリスティック)では、静止長に戻るように働きます。つまり、紡錘を伸張すると、その紡錘を支配している神経運動単位の反射収縮が得られるのです。 「ごまかす」に関して:筋のほんの一部のタスクの遂行による力伝達の円滑な加速と、、筋全体から合成された安定性を得るため、神経筋筋膜ウェブにはうまい具合の仕組みが備わっているのです。つまり、紡錘の各両端に、ひとつのとても小さな運動神経(これをガンマと呼びましょう)を追加することにより、紡錘内のエラスチン線維を引っ張ることができるのです。この小さな運動シグナルは、紡錘の端の細い線維を収縮させます。よって、紡錘を「ごまかし」、あたかも周りの筋組織が伸張しているかのように感受させるのです。筋紡錘が紡錘内の伸張に反応すると、脊髄にシグナルを送り、脊髄は通常のルートで単位全体を収縮するように反応します。 ここで、ガンマ線維が紡錘をどのように引っ張るかが分かります。脊髄を「ごまかし」、遠心性のアルファ神経を興奮させ、神経運動単位を収縮していることがお分かりでしょう。 遠回りであると感じるかもしれません:紡錘の両端を刺激するだけの“それっぽっち”のシグナルを、わざわざ脳からガンマ神経に発信し、それから紡錘が脊髄にシグナルを送り返し、さらに脊髄が下肢に筋収縮を起こすために、またシグナルを送る。アルファ運動神経に直接シグナルを送った方がよっぽど速いのではないでしょうか? もちろん、その通りですが、そうなるとスピードは速いが、協調性を失います。この「ごまかし」システム、つまりガンマシステムは、筋へのシグナル、脊髄へのシグナル、そしてまた筋へのシグナルといった混沌に対して、私達の身体が次に何が起きるか推測できるとき、過去の経験を基にしてマクロ秒の余裕をもって計画ができるときに初めて使われるのです。 子どもが初めて釘を打つ時のシグナルは、直接アルファ運動神経に伝えられます――大人がいっぺんに上手に釘が打てるのは、ガンマシステムが働いているからです。ハンマーの使い方の記憶プログラムを、アルファ神経を動員して、微調整しているのです。一つの部屋から隣の部屋に踏込んだとき、思っていたよりも床が数センチ低かった、というような不意なことに直面した時、ガンマシステムが次に何が起きるか準備し、正確に微調整してくれるのです。 神経科学は私の理解を超えていますが、さまざまなレベルのプログラミングは、「高度な安定化プログラム」(私は、セントラルパターンジェネレーターという用語を使用します)に影響します。しかし、感覚受容器である紡錘やゴルジ腱受容器の発火パターン、および成功のもと完了した動きの記憶の累積を保存する主な部位は、小脳と考えられています。 靴の紐を結ぶことを学習している子どもは、すべてアルファ運動パターンを利用しています。なぜなら、その子どもには、ガンマパターンを使うほど十分な記憶がバックアップされていないからです。一方、大人は、おしゃべりをしながらでもできます。すでに経験したことのある、靴紐を結ぶという指先の感覚が、予測可能パターンとして形成され、なじみのあるプログラムとして表面下で稼動しているからです。 ここで疑問に思うことは、では、私たちはどのようにして、負担が少ない新しい運動パターンをアルファプログラミングの大脳皮質から、ガンマ‐小脳‐大脳基底核‐脳幹 - 応答システムの一部へと深化させていくのでしょうか。それに応えて、もちろん自律神経‐迷走神経‐神経内分泌‐海馬 - 神経系のアラームの部分の影響を受けますが、これに関しては、ここではなく次の機会の別のトピックでお話ししましょう。 ご質問の答えになっていればよいのですが。

膝蓋大腿関節痛:機能的アプローチ
膝痛は、非常に一般的です。膝部の滑液包、腱、靭帯に影響を及ぼす多くのタイプの痛みがありますが、最も一般的なものの一つが膝蓋大腿関節痛です。 このブログで、ささいなことまで深く掘り下げるよりも、良好な膝蓋大腿関節のメカニズムのために必要とされていることについての、概念的な理解をもつことの方が、はるかに良いのではないかと思います。 膝蓋骨は、膝蓋靭帯を経由して、大腿骨と脛骨に付着しています。実際、膝蓋骨は膝窩溝、もしくは大腿骨と脛骨の両方の骨にある、内側顆と外側顆の間に位置しています。これは、膝蓋骨の良好な動作のために、これらの膝窩溝は、近接した状態を保つ必要があるということを意味しています。それを言い表している素晴らしい表現は、“順序通りに”でしょう。そうでなければ、膝蓋骨は膝窩溝に激突し、痛みを発生させることでしょう。 これら二つの骨に付着する重要な身体の部位が、二ヶ所あります。つまり、大腿骨が関節接合している股関節と脛骨が関節接合している足です。それは、膝窩溝の配列が、股関節側、もしくは足側のどちらかの末端においての、過度な動作、もしくは動作の制限の影響を受けるかもしれないことを意味しています。 一般的なアプローチは、股関節と足の動作を、矢状面において膝の動作を追跡することによって、制限しようと試みることで、動作のばらつきを減らす効果があります。球関節の素晴らしい特質は、それが私達にもたらす動作の多大な自由度と多様性です。実際、この自由度と多様性は、“三次元”と言い表されるかもしれません。矢状面における動作縮小の試みは、明らかな三次元の特質を提示している股関節筋群への負荷を減らすことになるでしょう。臀筋群とその斜めに走る線維方向に目を向けてください。大腿骨の前額面と横断面での動作なしには、効果的に働きません。実際、臀筋群は内転と内旋への動作を制御するでしょう。機能的な体重負荷動作においてしばしば発生する、膝の外反(大腿骨内転)と大腿部の内旋のような矢状面からの逸脱は、臀筋群と股関節筋群の遠心性収縮の活動によって、減速させる必要があります。これが、健康的な膝蓋大腿関節機構のために、大腿骨と脛骨の間の最適な順序を保持しているのです。 同様に、足の働きが脛骨の配列に影響を及ぼすでしょう。これもまた、膝窩溝における膝蓋骨の動作の乱れを引き起こすでしょう。一例として歩行(万人に共通する機能)を用いてみると、後足部、もしくは前足部内反は、足の回内後の脛骨への促進作用を有しており、脛骨内旋と外転の増大を作り出しています。回内の順序もまた、膝蓋大腿関節機構の配列に影響を及ぼすでしょう。後足部回内の遅延が、脛骨外旋を減少させ、と共に大腿骨外旋が膝窩溝の密接な順序を保持しています。実際、大腿骨と脛骨の反対方向への回旋が起こるかもしれません。私の友人であるゲイリー・グレイが、“真ん中に挟まってしまって、逃げ場がない状態”と言及するように、膝蓋骨は大腿骨と脛骨の両方に付着しています。 足関節背屈のような矢状面での動作の欠如もまた、膝に影響を及ぼす回内を増大するかもしれません。これが、人々が階段を使う際に、更なる膝の違和感を訴えるかもしれない理由なのです。足関節背屈の増大は、階段の昇降時において、必須とされています。足関節背屈が距腿関節において得られないのであれば、身体は足関節背屈を作り出すために、距骨下関節と横足根関節において、回内を増大するかもしれません。これは脛骨、ひいては膝蓋骨において、前額面力と横断面力を増大させています。よって、膝蓋大腿関節機構を得ようとする従来のエクササイズが行うように、矢状面の要求を増大させることは、実際、痛みを発生させる運動の増大を引き起こすかもしれないのです!足関節背屈が制限されているかもしれない理由を理解することは、ただ矢状面における膝の運動を強いようとするよりも、より成功したアプローチではないでしょうか。 一般的な万能エクササイズではなく、何が膝痛を引き起こしている可能性があるのかを理解するためには、股関節と足関節の両方における機能的三次元評価が求められています。一般人口の中に存在する数多くの構造的な足の機能不全の問題は、機能的な運動力学と構造の理解なしに、効果的に治療することができません。三次元の動作は主に体重負荷がかかっている状態で起こるために、治療用ベッドの上はなく、体重が掛かっている状態で、膝がどのように作動するのかという知識が不可欠なのです。 常に私を困惑させるものは、足の回内と膝の動作間の分離です。回内は動作として、足関節背屈、外転、外反と分類され、十分に解説されています。これは距骨に続いて、脛骨内旋を作り出すでしょう。この大腿骨と接続されている脛骨の動作は、膝の内旋を作り出すでしょう。体重の掛かった状態で、膝はどのようにして矢状面のみの動作をし、単純な蝶番関節として作用することができるのでしょうか??? 同様に、脛骨遠位端が外転することによって、近位端が身体の正中線に向かって傾き、膝の外反をもたらします。この場合も先と同様に、どのようにしたら膝を蝶番関節として、単純に見ることができるのでしょうか? 機能的な成功のために、三平面すべてにおいて大腿骨と脛骨の間の密接な関連が起こることは非常に重要です。つまり足と足関節が、体重の掛かっている状態で動的位置にある際に、評価することは重要なことなのです。

実践的なトレーニングの助言 パート1/2
パーシャルスクワットとフルスクワットを使い分ける最善の方法とは? 研究によると: ストレングスとパワーを向上させる為には高負荷でのパーシャルスクワットが最善であり、スピードを発達させるためには低負荷での深いスクワットが最適である。助言: 高負荷でのパーシャルスクワットと低負荷でのパラレルスクワットの組み合わせは、スピードに重きを置けば、アスリートのスピードとストレングスの質を発達させるための良い組み合わせとなり得る。研究によると: 何セットにも及ぶ高負荷でのより深いスクワットは、大量の作業を行うためには最適である。助言: 筋肥大を必要とする身体組性のプログラムに対しては、作業出力(筋肥大へとつながる機械的張力)は高負荷でのより深いスクワットを行うことで最大化することが可能である。 *** スクワットは高負荷であるべきか、深くあるべきか? 研究によると: 膝伸筋へ要求される力に対しては、負荷よりもスクワットの深さの方がより重要な要素である。助言: 垂直跳びの高さを向上させるために膝関節主導のジャンプ戦略をとっている場合は、大腿四頭筋への刺激を最大化するためにより深いスクワットを行うべきである。同様に大腿四頭筋のサイズを向上させたいのであれば、負荷を軽減し、安全に行える範囲で、できるだけ深いスクワットを行う。 *** スクワットの際、椅子に深く座るような形になるべきか? 研究によると: オリンピックスタイル(椅子に深く腰掛ける形にならない)のスクワットは膝伸筋を最も発達させるようであり、それゆえ大腿四頭筋をより活性化するが、膝には大きな剪断力がかかる。助言: もしオリンピックスタイルのスクワットを、膝の痛み無く行うことができ、かつ大腿四頭筋群を発達させたいのであれば、オリンピックスタイルのスクワットが最適な手段である。少しでも膝に痛みがある場合は行うべきではない。研究によると: 椅子に深く腰掛ける形になるスクワットは股関節の伸筋群をより使うようであり、よって大臀筋(と多少ハムストリングスも)のより大きな活性化につながるようである。助言: もし臀筋やハムストリングスを鍛えたく、椅子に深く腰掛けるような形でのスクワットが問題なく行えるのであれば、制限されたスクワットが有効であろう。(もちろんハムストリングスを発達させるのには、スクワットパターンよりもよりよい選択肢があるが) *** フォワードランジは大腿四頭筋とハムストリングスのどちらに効果的なエクササイズか? 研究によると: フォワードランジの際の外部負荷の増加は、足関節、膝関節、股関節のモーメントを同等に増加させるのではなく、むしろ股関節モーメントを足関節や膝関節のモーメント以上に増加させる。助言: ランジの際、安全に、かつ膝の痛みを回避しながら、臀筋やハムストリングによって行われた仕事量を比例的に増加するためには、高負荷で各セットのレップ数を少なく行うと良い。研究によると: フォワードランジの際、膝関節ではコンセントリックの仕事量よりもエキセントリックの仕事量の方が多い。これは、身体を下に下ろしてゆくにつれて、膝伸筋(大腿四頭筋)が、増加してゆく膝の屈曲を減速することにより関わっているということを示唆している。エキセントリック収縮は辛い筋肉痛を引き起こすため、多くの人がランジは大腿四頭筋がとても痛くなると感じている理由はこれなのかもしれない。助言: 大腿四頭筋により効果的なフォワードランジを行うためには、低負荷で多くのレップ数を行うべきである。(ロニー・コールマンの駐車場ランジのような) *** 広背筋を発達させるためにはプルダウンよりもローイングの方が良いか? 研究によると: シーテッドローはどのようなタイプのプルダウンよりも広背筋と中部僧帽筋/菱形筋の大きな活動を生み出す。背中のエクササイズを「背中の広さ」と「背中の厚み」に分けるという考えは研究者から支持されていない。助言: ボディビルダーや主に身体的発達を考慮する人は、ラットプルダウンよりもローイングを中心に背中の強化パターンを組む方が理にかなっている。そして背中のプログラムを「背中の広さ」と「背中の厚み」で分けるのではなく、背中のトレーニングを2度行うようにすれば十分であろう。研究によると: シーテッドローは肩甲骨の後退を組み合わせた際、広背筋と中部僧帽筋/菱形筋に、より大きな活動を生み出す傾向にある。助言: シーテッドローを行う際は、筋活動を向上させるために、各レップの最後に必ず肩甲骨の後退を行うべきである。可動域を向上させることは肩の健康のためにも好ましいことである。研究によると: プルダウンの際、腕が回内しているか回外しているか(チンニングとプルアップ)の違いは、広背筋と上腕二頭筋の相対的な活動における多少の相違にすぎない。ゆえにこれらの相違は、初心者や中級者に対して大きな違いを生み出すわけではないようである。助言: チンニングやプルアップのどちらを使ってもさほど相違はないため、おそらく好みに応じて選択するか、もしくは飽きることを避けるためにそれらを混合して行うべきである。もし、どうしても選択しなくてはいけないのであれば、より大きな負荷を使えるためチンニングの方が多少優位であろう。 ***

実践的なトレーニングの助言 パート2/2
どのローイングエクササイズが最善か? 研究によると: 広背筋と上背を鍛えるには、ベントオーバーローよりもインバーティッドローの方が良い。ベントオーバーローは全体的な(上部、下部共に)背中の筋活動を生み出し、脊椎の安定性に最も働きかける。助言: 高齢期まで元気にトレーニングを行うためには、ベントオーバーローや片手でのケーブルローよりも、負荷付きのインバーティッドローを中心としたプログラムで上背と広背筋を鍛えるべきである。 *** 筋肥大のためには、相撲デッドリフトは通常のデッドリフトよりも良いのか? 研究によると: 相撲デッドリフトで使われる主な筋肉は大臀筋、ハムストリングス、大腿四頭筋、前脛骨筋である。通常のデッドリフトで使われる下肢の筋肉は、ハムストリングス、大臀筋、腓腹筋、ヒラメ筋である。助言: 両方のデッドリフトのバリエーションを向上させるためのトレーニングにはもちろん、大量の大臀筋とハムストリングスの強化が含まれているべきである。しかし、通常のデッドリフトは大腿四頭筋とふくらはぎの筋力をより強調するのに対し、相撲デッドリフトでは大腿四頭筋と前脛骨筋の筋力に重きが置かれている。研究によると: 通常のデッドリフトよりも相撲デッドリフトの方が、加速段階にいる時間が非常に長い。これは、相撲デッドリフトがよりよい筋肉の適応をもたらすということを示しているのかもしれない。助言: 特に相撲デッドリフトは腰への負担が少ないが、同様の股関節の伸展モーメントを含む可能性が高いため、筋肉のサイズを大きくするためのトレーニングとしては、通常のデッドリフトよりも相撲デッドリフトの方が優れているかもしれない。 *** ストレートバーとヘックスバーはどのように違うか? 研究によると: 膝関節に対する股関節の伸展モーメントの比率はストレートバーデッドリフトでは負荷の増加に伴い上昇するが、ヘックスバーデッドリフトでは変化がなかった。これは、ストレートバーデッドリフトは負荷が上がるにつれてより股関節主導になってゆくが、ヘックスバーデッドリフトでは同様ではないということを意味している。助言: ストレートバーデッドリフトでは、股関節の伸展トルクの重要性が負荷の増加につれて上がるということを考慮に入れると、弱点が股関節の伸展トルクの場合(多くの場合その可能性が高いが)、ストレートバーデッドリフトを向上させるためにヘックスバーデッドリフトを使ってトレーニングすることは、最適な持ち越し効果を生み出さない可能性がある。股関節の伸展トルクを発達させるようなエクササイズの方が、より良い選択かもしれない。研究によると: デッドリフトは両バリエーション共に、オリンピックリフトやそのバリエーションと同様、最大下負荷において多大な力を生み出す。助言: スポーツのために最大力をトレーニングしているが、オリンピックリフトを快適に行うことができない人は、オリンピックリフトを安全に行うために何年も費やしてそのスキルを養う必要なはい。ストレートバーやヘックスバーを使う最大下デットリフトは両方とも同等の出力を生み出す(ストレートバーでは1RMの30%、ヘックスバーでは40%、スクワットでは50−60%を使う) *** フォームローラーは可動性を向上させるか? 研究によると: 被験者がワークアウト前にフォームローラーを使用した場合、使用後彼らはより広い可動域で膝関節を動かすことができた。静的ストレッチとは違い、フォームローリングは被験者に実施直後の筋力低下をもたらさない。助言: ディープスクワット、スプリットスクワット、デフィシットデッドリフトなど、大きな可動域内で関節を動かすようなエクササイズを含むワークアウト前には、筋肉を伸長するためにフォームローラーを使用しよう。 *** 柔軟性を増すためにストレッチを毎日行う必要はあるのか? 研究によると: ハムストリングスのストレッチ実験では、研究者たちは数分のストレッチを毎日行うことと、数分のストレッチを週に3−4回行うことでは同様に可動域が拡大されると発見している。(18.1 ± 6.3度)助言: もしストレッチが優先であるならば、毎日行うことはより早い改善につながる。しかし、時間がないのであれば、数分のストレッチを週に3−4回行うことは同様に良い成果を与えてくれる。毎日数時間もストレッチする必要はないのである。 *** バーの速度は筋力の増加に影響を与えるのか? 研究によると: 自己選択したバースピードよりも、より速いバースピードはより大きな筋力の増加につながる。助言: ワークアウトの際のバースピードをコントロールする習慣がないのであれば、ある一定期期間より速いバースピードを試してみると良いだろう。より大きな向上が見られるかもしれない。 *** レジスタンストレーニングと持久系トレーニングを組み合せて行うことは可能か? 研究によると: レジスタンストレーニングと持久系トレーニングを組み合わせて同時に行うことは(同時訓練という)筋力の増強を妨げはしないが、おそらく力開発速度の低下による結果としてパワーの向上を低下させる。助言: スポーツのためのパワーを最大化することに生計がかかっているのであれば、持久系トレーニングは必要最小限にとどめておくのがよいだろう。 *** ストレングストレーニングと持久系トレーニングを組み合せて行うことはより良い筋肉量の増加につながるか? 研究によると: 多くの人が考えていることに反するが、同時訓練を行うことは実際の筋肉の増加程度を上げる。助言: 体格のためにレジスタンストレーニングを行っているのであれば、ある程度の持久系トレーニングは、実質的にはレジスタンストレーニングの効果を助長する可能性がる。 ***

回旋腱板修復手術後の成功を高める方法
回旋腱板断裂は、すべての年齢の人々にとてもよく見られる傷害です。読む論文にもよりますが、50歳以上で13%の人が、80歳以上で50%の人が回旋腱板断裂を患っているだろうと報告されています。自然の成り行きとして、回旋腱板修復手術も同様によく見られるようになってきています。過去数十年で、我々は、回旋腱板修復手術技術を大きく進歩させ、直視下手術から、より低侵襲な“開口部の小さい”手術、そして、完全関節鏡視下手術へと発展させてきました。 最新の関節鏡視下回旋腱板手術では、疼痛が緩和される傾向があり、患者により早く活動させることができるようになります。しかし、私たちがあまり耳にすることの少ない事実として、回旋腱板手術の失敗率は、依然として高すぎるということがあります。 術後、腱板が元の健全な状態に戻っていないことを手術失敗と定義する場合、過去の研究では、回旋腱板修復術を受けた人のうち75%が、技術的に“失敗”であるだろうと示されています。JOSPTに公表された最近のシステマティックレヴューでは、10以上の様々な研究報告によると、18-40%程度の失敗率が報告されています。 これらの失敗率に関わらず、術後の患者の満足度は依然としてとても高いことが、大部分の研究で示されています。このことは、実際の手術よりも、リハビリテーションの過程のほうがかなり重要であるということを示唆しています。これはとても素晴らしいニュースです。たとえ、回旋腱板が術後完全に修復されていないことが判明しても、痛み、動き、強度、機能、そして、満足度すべてにおいて、大いに改善することが可能になります。 そうであるとしても、私達は、回旋腱板修復術後、腱板が完全に回復できるよう、私たちができるすべてのことを実践していくべきです。 JOSPTに投稿された最新の系統的な文献論評では、関節鏡視下腱板修復術後の良好な回復に関わる予後要因の決定を試みています。この論文によると、術後の経過を最良にするいくつかの要因を特定することができるのです。これらの要因すべてが容易に対処できると簡単には言えませんが、多くはそうであり、患者が最良に回復できるよう促していくことを、常時目指しています。 腱板修復術後の良好な回復に関連する要因 その論評では、著者の厳密なガイドラインに合致する10個の論文に焦点を当てていました。これら10の論文に基づき、回旋腱板修復術後の良好な回復と関連がある12の要因を特定することができました。これら12の要因は、4つのカテゴリーに分類されます:人口統計学的要因、臨床学的要因、回旋腱板の整合性に関連する要因、そして、手術方法に関連する要因。 回旋腱板手術後の予後を最善にするために我々ができうること(できないこともあるが)に関連している、最初の3つの要因について論じていきます。手術要因に関しては、上腕二頭筋、または、肩鎖関節に追加の処置をした場合、結果はあまりよくないという報告が、ある研究で示されていました。我々が、手術方法を選択することはできませんが、恐らく、この情報は手術医に有益となるでしょう。 人口統計学的要因 一般統計学に関するもっとも重要な発見は、手術を受ける際の患者の年齢と関連があるということでした。年齢の高さは回復に対して、マイナスの影響を持っていたのです。 この研究では、年齢を重ねれば重ねるほど、腱の治癒のチャンスが低くなると報告されていました。55歳以下の人々では、腱の治癒が88-95%の確率で見られ、予後も最良でした。反対に、60歳以上の人々では腱の治癒が43-65%しか見られませんでした。 回旋腱板に問題が起こる時期を操作することはできませんが、これらの結果から、症状を無視するべきではなく、肩と回旋腱板を徐々に退行させていくべきであるということが示唆されています。問題に対し早期に取り組むことで、これらの結果を改善するべきです。我々は、多くの人が何年もの間、肩の痛みに目を向けることなく、不快を感じながらもなんとかしようとしている場面を多く見てきています。機能的な問題がかなり大きくならない限り、普通我々は助けを求めたりはしません。 臨床要因 驚くことではありませんが、骨のミネラル密度や糖尿病のどちらも組織治癒に悪影響を及ぼします。肥満も結果に悪影響を及ぼします。肥満傾向の人は予後良好になる割合が12%減少するとされています。 興味深い発見だと私が思ったことは、手術前の活動レベルに関連することです。身体活動をほとんど行っていない人は、中強度、高強度のスポーツ、例えば、ゴルフ、スイミング、サイクリング、ランニング、テニスをしている人に比べて、予後があまりよくありませんでした。 筋力や動きに関して、最終的な強度を予測できる最たる因子は、最初の強度であることが分かりました。手術前の肩の剛性も回復時間にマイナスの影響を与え、復帰を遅らせることになります。 骨のミネラル密度や糖尿病のように、これらの要因のうちのいくつかは、避けることができないかもしれませんが、手術前に医学的治療を受け調整されていることを確実にすることができます。しかし、肥満、活動レベル、筋力や可動性といった要因は、すべて十分に関連性があり、手術前に注意を払うことができます。このことは、手術前に理学療法を行うことの重要性を強調しています。私が常々伝えていることですが、手術を受けるまでがよい状態であればあるほど、術後はよりよい状態になります。 回旋腱板の整合性の要因 予後不良と関連する回旋腱板の整合性に関する要因が4つあります:断裂の大きさ、関与している回旋腱板筋の数、腱の退縮の量、脂肪浸潤の量。これらの要因はすべて、組織の退行と関連があり、おそらく、年齢とも関連があります。 基本的には、組織が退行していればいるほど、予後不良になります。時間がたてば、腱板断裂の大きさは拡大し、骨から剥がれ(退縮)始め、弱化していきます。 これらの要因は、上記の年齢に関する私のコメントとより関わりがあります。おそらく、腱板の断裂が顕著になる前、そして組織がより退行してくる前に、早い段階で決断をして、肩のケアをするべきなのです。考慮することとして、小さな回旋腱板断裂であれば、手術により96.7%の確立で治癒することができます。一方で、断裂が大きくなってしまった場合、治癒する確立は58.8%になります。 回旋腱板修復術後の成功を高めるためにはなにができるのか。 この研究は、回旋腱板修復術の予後を良好にするためにできるいくつかのことに光明を投じていると感じます: 手術時の年齢が高いほど、手術の成功率は低くなるので、不必要に手術を延期するべきではありません。 上記のことに関して、手術を延期することで、腱板の退行が進むことも考慮してください。断裂が大きければ大きいほど、組織の退行が進めば進むほど、結果は不良になります。 身体的に活動的であること、体重が減少していることは、良好な予後と関連があります。重い腰を上げてください。 手術前に理学療法を始める。手術時に肩が強ければ強いほど、可動性がよければ良いほど、予後は良好になります。より強く、そして早く活動に復帰できます。それに加えて、いくつかの研究では、理学療法は回旋腱板手術の回避に効果があると示されています。 骨のミネラル密度や糖尿病などの健康状態は手術前に治療を受けてコントロールされていることを確実にしておいてください。 この記事を読んでいる臨床家のために、私たちは回旋腱板修復術後のリハビリテーションをどのように漸進させていくのかを決定するために、この情報を利用することもできます。患者が予後不良となるような要因を有していればいるほど、より保守的に進めていく必要があるかもしれません。 身体活動を活発に行っていて、回旋腱板の断裂も小さく、健康上なにも問題ない52歳の患者と、断裂が大きく、虚弱で糖尿病を患っている74歳の患者を同じペースで漸進させますか?もちろん、そうはしません。私たちは、やみくもにプロトコールに従ってはなりません。プロトコールは有益であり、必要なものですが、より保守的になるべき要因がある場合は、調整できる要素を含んでいます。 回旋腱修復術の術後を良好にする方法はありますし、それらの多くは調整することができます。皆さん自身、あるいは皆さんの患者さんの予後を最良にするために、これらを利用してください。

登板と登板の間の新しいトレーニングモデル:パートA (1/3)
(パートA2/3はこちらへ) 登板と次の登板の間における投手のマネージメントは、野球トレーニング界でも最も意見が分かれるトピックです。登板と登板の間に、複数回の投球セッションを好むピッチングコーチもいれば、ブルペンは1回で十分と主張するコーチもいます。また、アスレチックトレーナーの間では、投球セッション後にアイシングをすべきか否かで議論されます。私の専門領域に特定すると、投球の合間に投手がどのようなランニングプログラムを行うのが適切か、異なる見解があります。 自慢するわけではありませんが、私はたいへんな読書家です。しかし、そんな私でも、特に投手のためのランニングプログラムについて、論理的に主張または批判したものを読んだことがありません。そういうこともあって、この論考を書くことにしたのです。 その点を考慮して率直に言えば、投手に長距離ランニングをさせることは、私の好みではありません(さらに言えば、投手以外の圧倒的多数の選手も同様です)。おそらく多くの投手コーチは、この記事を読んで、常識の逆を言う私のことを罵っているのではないでしょうか。みなさん、是非この話を最後まで読んで欲しいと思います。なぜ長距離ランニングが、活動方針として望ましくないのかを、9つの項目にまとめ下記で説明します。そして、次回の投稿では、私たちが実施し、プロ、大学、高校レベルで大きな成功を収めている投球と投球の間に行う新しいトレーニングモデルを概説します。 理由その1:免疫への配慮 ストレングス&コンディショニングコーチとして、私にとって最も優先順位の高いのは、選手の健康を維持すること。これは、筋骨格系の健康のみならず、身体の健康全般を指します。2006年に発表された優れたレビューの中で、グリーソン氏は次のように述べています。「運動後の免疫機能低下は、運動が継続(および)持続された時に最も顕著であった」。興味深いことに、このレビューでは、「これら症状の多くは、感染発症が原因ではなく、上気道の炎症に起因する(1)。」と記されています。つまり、登板と登板の合間に長距離ランニングをすることは、選手控室で病気を引き起こし蔓延させることになるのです。 1ストライク。 理由その2:内分泌への考慮 オフシーズン中に、私がトレーニングしたマイナーリーグの選手からのメールの一部をご紹介しましょう: 昨日は、これまでの選手生活で最もハードな一日でした。日曜日の試合が終わり、11:30pmに部屋に戻ったあと、少なくとも12:30amまで眠れませんでした。それから、3:30amにモーニングコールがあり、6:15am発の飛行機に間に合うように空港行きのバスに乗り込みました。1時間半の乗継時間のあと、11:00amに次の町に到着しました。スリープインというホテルまで車を走らせ、臭い部屋に到着し、少しだけ睡眠をとったものの4:00pmには球場に集合しなければなりませんでした。 これは、多くのプロ投手(特にマイナーリーグ)にとってごく普通の出来事です:夜遅く寝て、朝早く起き、深夜便で移動し、長距離バスに乗り、その結果、完全に睡眠パターンが狂ってしまうのです。容易に想像できると思いますが、このような移動をしていると食事も理想的ではなくなります。とりわけ、選手控室の食事が、グルメでも健康的でもない場合には。大学レベルとプロレベルの球技選手の多くは、アルコールを過剰摂取しています。これは、睡眠と組織の質に直接影響するということも言っておきましょう。 つまり基本的に、彼らの睡眠時間はでたらめで、食生活もひどく、アルコールを過剰に摂取しているということです。そして、スポーツの中でもシーズンが最も長いのです。事実上、テスタステロンと成長ホルモンの分泌を低下させ、ホルモン環境を乱す、あらゆる原因を作り上げていることになるのです。率直に言えば、自転車のサドルにまたがりながら「ゴールデン・ガールズ」(アメリカのホームコメディー)の再放送を見て、エストロゲンの錠剤を飲み下しても、同じようなホルモン反応が表れるでしょう。この状況ならば、足底筋膜炎を発症させずにすむはずなのです。 その結果、代わりに何が行われるかおわかりですか? 長距離ランニングです! そうです、持久力の必要な選手の低テスタステロン値と高コルチゾール値を生み出す、長距離ランニングです。これは、四角い車輪の車に最新型のエンジンを搭載するのとおなじこと:誤ったテストのために勉強するようなものです。 ランニングプログラムのマイナス効果に反作用する運動能力向上薬を使用して、何になるのだろうと疑問に思わされますね! 2ストライクです。 理由その3:モビリティへの配慮 以前のニュースレターでも書きましたが、長距離ランニングの問題のひとつに、本当の意味で股関節屈筋群を活性化するのに十分な股関節の屈曲が得られないということがあります。特に大腿直筋は、十分に動員されますが、股関節が90度以上屈曲するときに主に活動する大腰筋の活性化はほとんどありません。同様に、股関節の伸展もほとんど行われないのです。 概して、ジョギングのような反復性運動を長時間行うことで、投手の股関節は動きを失っていくのです。それはまさに、ストライドと、ひいては速度を生み出すのに選手が必要としている動きなのです。 率直に言えば、私が指導しているなかで、ジョギングのストライドでの関節可動域の不足のために、最も顕著な下肢の機能障害が見られるのが、ランナーなのです。そして、彼らは実際誤った運動パターンで距離を重ねていくわけです。人間の身体は、ジョギングではなくスプリントをするためにできていると私は固く信じています。 3ストライク、バッターアウト! 参考文献 Gleeson, M. Immune systems adaptation in elite athletes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006 Nov;9(6):659-65. Komi, P.V. Stretch-shortening cycle. In: Strength and Power in Sport (2nd Ed.) P.V. Komi, ed. Oxford: Blackwell, 2003. pp. 184-202. Hennessy L, Kilty J. Relationship of the stretch-shortening cycle to sprint performance in trained female athletes. J Strength Cond Res. 2001 Aug;15(3):326-31. McCarthy JP, Agre JC, Graf BK, Pozniak MA, Vailas AC. Compatibility of adaptive responses with combining strength and endurance training. Med Sci Sports Exerc. 1995 Mar;27(3):429-36. Ouelette, H, Labis J, Bredella M, Palmer WE, Sheah K, Torriani M. Spectrum of shoulder injuries in the baseball pitcher. Skeletal Radiol. 2007 Oct 3. Fleisig, GS. The Biomechanics of Baseball Pitching. Spring 2008 Southeast ACSM Conference.

登板と登板の間の新しいトレーニングモデル:パートA (2/3)
(パートA1/3はこちらへ) (パートA3/3はこちらへ) なぜ長距離ランニングが、活動方針として望ましくないのか? 理由その4:伸張-短縮サイクルのマイナス効果 伸張-短縮サイクル(SSC)を説明するために、ここで私は少しオタクっぽくならざるをえません。最も簡単な例えを使うとすれば、仮にゴムバンドを誰かに向けて飛ばそうとしたとき、あなたは、ゴムを撃つ前にゴムを伸張しておきますね。筋も同じように作用します;筋が短縮(求心性作用)する前に、伸張(遠心性作用)することによって弾性エネルギーを蓄えます。そうすることによって、筋はより多くの力を発生します。逸話風ですが、投球速度の25-30%は、弾性エネルギーによるものだと推定されると聞いたことがあります。つまり、いかに有効に伸張-短縮サイクルを利用するかということです。 私達の筋肉がゴムバンドと違う点は、その弾性を実際トレーニングでき、腱が弾性エネルギーをより効率よく吸収し、一時的に貯蔵、放出できるようにすることで、より速く走ったり、より高くジャンプしたり、より強く投げたりできるようになるのです。それが、プライオメトリックスやスプリント、メディスンボールを投げたりするトレーニングが驚くほど効果的であることの理由なのです。 コミ氏(2)によると、伸張-短縮サイクルには、次の3つの要素が必要です: 1.遠心性局面の前の、タイミングを計った筋の予備活性化 2.短く速い遠心性要素 3.伸張(遠心性)局面と短縮(求心性)局面の素早い切り替え(最低限の遅延)。償却局面として知られる期間が短ければ短いほど、(熱としての)弾性エネルギーの散逸は少なくて済む。 率直に言えば、#1はうまくいきます。しかし、#2と#3においては、運動時間が長くなるにつれて、SSCの重要性が急速に減少し、まさに長距離ランニングとは逆の動きをしていることになります。事実、垂直飛びでは、最大300mまでのスプリント能力しか予測できません(3)。 言い換えれば、エクササイズが長引けば長引くほど、弛緩させるというより力づくになってしまうのです。ホームベースに向かって、力づくで投球する選手について我々は何を知っているのでしょうか?実は、彼らは投球特有の動きを損なうので、強くは投げられず、腕のむち運動も完全には行えません。 私は、高度の最大酸素摂取量(VO2max)を示す選手より、垂直飛びのうまい選手の方を評価します。長距離ランニングは、バウンスよりも足を引きずる状態にしてしまいます。そしてこれは、慢性的なオーバーユース状態という意味でも深く影響しています。 1ストライク。 理由その5:ストレングスとパワーの減少 投球運動がどんなに身体にストレスをかけるかの一例として、投球の加速期に上腕骨が7,500°/秒内旋するということがあります。これだけの速度を出すのに、かなりのストレングスとパワーを使いますが、同様に重要なのは、直ちに減速するためにも、多くのストレングスとパワーを費やすということです。この加速を可動最終域で抵抗し制御するのに十分なストレングスとパワーを作り出すだけでなく、素早く力(パワー)を生み出す必要があるのです。そのために、投手のコンディショニングは、長距離ランニングをまったくしないストレングスとパワー系の選手のコンディショニングと似ていると思われるかもしれません。 ところが、ほとんどの投手は週に数回ランニングをしています。マラソンランナーが時速153kmの球を投げるのを見たことはありましたっけ?。 さらに、コーチ達は、ウェイトトレーニング器具を使用する機会がなかったラテンアメリカの選手を担当することがよくあります。これは、知られざる潜在的な可能性の扉を大きく開くものです。彼らは強化を図るため、より多くの時間を費やすことができたはずだったにもかかわらず、長距離ランニングに時間を使ってしまったということは、より速く走るようになるのではなく、より長い距離が走れるようにしか調整していないために、選手の成長を大きく阻害しているのです。ただオイル交換をするだけではなく、必要なのはエンジンにもっと馬力を注入することなのです。 若手選手に初めてウェイトトレーニングを導入すると、8-10週間後には運動能力が向上するという大きな変化が見られます。初期段階で上級投手に優れたトレーニングを導入すると、その有効性の大きさにも驚くことでしょう。その理由は、多くの投手は野手とは違って、(言葉は悪いですが)一芸に秀でたポニーのようなものなのです。投手は、いやらしいカットボールや強烈なドロップカーブ、奇妙なアームスロットでのスライダーの投げ方を知っています。ですから、投球以外ではそれほど運動能力に優れていなくてもOKだったわけです。アウトをとるかもしれませんが、ケガのリスクが増大するので、チームとしては長期にわたって一か八かのギャンブルをしているようなものなのです;脆弱であまり動けない身体は、まるで長距離ランナーのように、最も早く故障します。さらに、素早く(かつ力強く)筋を動員することは、足首の捻挫やACL断裂のような急性損傷の予防のため、また関節複合体を素早く硬くし安定させるために、きわめて重要です。ストレングスとパワー系の選手は、この点に関して持久力競技の選手より上手くできています。 2ストライク。 理由その6:不適切な強度 少なくとも私にとって、とても画期的な研究(マッカーシーら、1995)は、最近のストレングストレーニングと持久力トレーニングの「両立性」につて注目していました。伝統的に、持久力エクササイズがストレングストレーニングのプログラムに追加されると、ストレングスとパワーの増加傾向が減退していくことが、大きな問題になってきました。私が、他の記事で記述したように、研究者らは、ストレングスとパワー喪失は、持久力エクササイズの強度が、予備心拍数(HRR)の75%を超えるとき初めて問題になってくるということを発見しています。長距離ランニングをする投手達の大多数は75%以上のHRRで走っていることは、保証してもいいでしょう。 この記事の結論でも私のおすすめを述べますが、どのようなスタイルのランニングを実施するにも、ずっと上(つまり、ほぼ最強度のスプリント)または下(安全のため予備心拍数の70%)をキープすることが秘訣であると、私は強く感じます。ゆっくりでもなく速くもない中間を避けることが肝心なのです。この中間が、選手を本当の意味での「ゆっくり」にさせてしまうのです! そして理想的には、低強度エクササイズが、可動性の向上に利する方法となり得るのです。 3ストライク、バッターアウト! 参考文献 Gleeson, M. Immune systems adaptation in elite athletes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006 Nov;9(6):659-65. Komi, P.V. Stretch-shortening cycle. In: Strength and Power in Sport (2nd Ed.) P.V. Komi, ed. Oxford: Blackwell, 2003. pp. 184-202. Hennessy L, Kilty J. Relationship of the stretch-shortening cycle to sprint performance in trained female athletes. J Strength Cond Res. 2001 Aug;15(3):326-31. McCarthy JP, Agre JC, Graf BK, Pozniak MA, Vailas AC. Compatibility of adaptive responses with combining strength and endurance training. Med Sci Sports Exerc. 1995 Mar;27(3):429-36. Ouelette, H, Labis J, Bredella M, Palmer WE, Sheah K, Torriani M. Spectrum of shoulder injuries in the baseball pitcher. Skeletal Radiol. 2007 Oct 3. Fleisig, GS. The Biomechanics of Baseball Pitching. Spring 2008 Southeast ACSM Conference.

登板と登板の間の新しいトレーニングモデル:パートA (3/3)
(パートA2/3はこちらへ) なぜ長距離ランニングが、活動方針として望ましくないのか? 理由その7:子守りをするのはだれも好きではない 端的に言えば、ランニングは子守りをするようなものです。捕手は実際、野球で最も持久力を要求されるポジションですが、捕手に、追加で走らせたりはしませんよね?その理由として、ブルペンでボールを受け、バッティング練習をする他にも、投手の扱いやフィールドではコーチ代わりとしての責任もすべて負っているのです。 約10年前、私のビジネスパートナーは、1部リーグの投手でした。そこで、私がこの議論を持ちかけた時、彼は微笑み、うなずき、そして、「私が投手だった頃、私たちが練習したことといったら、フライを捕球する練習とポールダッシュのみだったよ」と言いました。そんな中で、57%の投手は試合シーズン中に肩のケガに苦しんでいました(5)。この数値には、肘や腰、下肢のケガは含まれていないのです! メジャーリーグでは、全選手に占める投手の割合は49%ですが、その投手だけで、リーグ全体の故障者リストの68%を占めています(6)。ランニングでは、このような問題を予防することはできず、かえって悪化させてしまいます。 1ストライク。 理由その8:長距離ランニングは既存するバランス異常を無視する いくつかの理由から、野球はリスクのあるスポーツと言えます。シーズンがかなり長く、オーバーヘッドスローをし、片側優位性が最も顕著である競技です。スイッチヒッターや右打ち左投げ(または左右その逆)であれば、少しは対称である傾向にはありますが、打つのも投げるのも同側であれば、最も顕著な問題が起こり得ます。数多くの賢い人達のなかでも、最も注目すべきグレイ・クックは、こうした非対称性こそが、ケガにつながりうる最も大きな要因であることを述べています。長いシーズンを終えた投手を担当する場合、最初の目標は、下記の可動域不全の問題に取り組むことです: 1.前脚の股関節伸展(股関節屈筋群の緊張) 2.前脚の股関節内旋(股関節外旋筋群の緊張) 3.前脚の膝屈曲(大腿四頭筋の緊張) 4.投球側の肩内旋(ローテーターカフと関節包の後面の緊張) 5.肩甲骨の後方傾斜(小胸筋と肩甲挙筋の緊張) 6.投球側の肘伸展(肘屈筋群の緊張) カフェインをガブ飲みしても、水で顔を洗っても、また、どんなによく考えても、長距離ランニングでこれらの問題にどう向き合えるのか、私には理論的根拠を見つけられません。結局のところ根拠はどこにも見つかりませんでした。それよりも、ジョギングはほとんどの選手にとってマイナス効果であると実感しました。長距離ランニングやジョギングに割く時間があるならば、投手はフライを捕球する練習をした方が賢明です。とりあえず、フライを追いかける時には横への動きが加わりますから。 2ストライク。 理由その9:とにかくつまらない! 私は、選手の関心を引きつけるコーチが最良のコーチだと確信しています。現役選手だった私の経験の中でのベストコーチは、毎回のトレーニングセッションを楽しみにさせてくれた人でした。そんな訳で、もうお分かりかもしれませんが、長距離ランニングを心待ちにしている選手は、長距離ランナーしかいないんですよ! 皆さんが指導している球技選手達の多くは、ランニングを何か悪いことをしたら課せられるひとつの罰と捉えているでしょう。彼らも私が感じているぐらい嫌いだと思います(そこまでではないかもしれませんが)。実を言うと、もしそれが選手としての成長を妨げるものだと気がついたら、もっと嫌いになるでしょう。 3ストライク バッターアウト イニング終了 結論 現状維持を非難するにも関わらず解決方法を自ら提案しない人のことを、私はどうも好きになれません。この点を考慮して、次回の投稿では、引き続き登板と次の登板の間にどのように取り組むかについて、私の個人的な見解をまとめる予定です。 参考文献 Gleeson, M. Immune systems adaptation in elite athletes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006 Nov;9(6):659-65. Komi, P.V. Stretch-shortening cycle. In: Strength and Power in Sport (2nd Ed.) P.V. Komi, ed. Oxford: Blackwell, 2003. pp. 184-202. Hennessy L, Kilty J. Relationship of the stretch-shortening cycle to sprint performance in trained female athletes. J Strength Cond Res. 2001 Aug;15(3):326-31. McCarthy JP, Agre JC, Graf BK, Pozniak MA, Vailas AC. Compatibility of adaptive responses with combining strength and endurance training. Med Sci Sports Exerc. 1995 Mar;27(3):429-36. Ouelette, H, Labis J, Bredella M, Palmer WE, Sheah K, Torriani M. Spectrum of shoulder injuries in the baseball pitcher. Skeletal Radiol. 2007 Oct 3. Fleisig, GS. The Biomechanics of Baseball Pitching. Spring 2008 Southeast ACSM Conference.

エネルギーシステムトレーニングにおける10の助言と秘訣 パート1/2
エネルギーシステムトレーニング(以下EST)はフィットネスと運動競技育成業界で常に注目を集めるトピックですが、 残念ながら、ESTに関して、非常に多くのことが誤解されていると思います。 余分な脂肪を落としたい人、”ひきしめたい”人、単純に見た目にも気分的にもセクシーになりたい人は、解糖系/無酸素トレーニングこそが本当に必要なすべてであると思い込むのは当然でしょう。 白黒はっきりした発言が最高のキャッチフレーズを作り出す背景も相まって、誤った情報のレシピが出来上がってしまうのです。 下に述べることは、よりESTを有効に行う為の、10のとっておきの助言と秘訣です。楽しんでください! 1 自分の身体が、人類史上最も効率的で効果的な機械であると考える。 身体に大きくなれと言えば、身体は大きくなります。強くなれと言えば、身体は強くなります。 同様のことがエネルギーシステムトレーニングにもあてはまります。 もしあなたが有酸素機能の向上を目的としたトレーニングをしているのであれば、身体は有酸素性エネルギー供給機構の効率を上げるために、できる限りの全てを行います。 より多くの有酸素系酵素 より大きな左心室 筋レベルの酸素活用能力の向上等です。 逆もまた然り。宗教的に無酸素性エネルギー供給機構のトレーニングに取り組めば、あなたの身体は無酸素的な面において効率が高まるでしょう。 これはかなり退屈に見えて、実は強力な主張です。いかなる形式のエクササイズも、身体に信号を送り、それが適応を引き起こすことを私達は覚えておかなければなりません。 2 有酸素性エネルギー供給機構と無酸素性エネルギー供給機構はお互いに直接競合している。 身体は非常に賢く、私たちが課したトレーニングに常に適応していることに同意することができれば、私達は一度にすべてのことはできないのだと気づき始めるでしょう。 仮にあなたがとても強度の低いエクササイズを、あるいは、より有酸素域でエクササイズを行ったとします。これにより、身体が有酸素性のエクササイズに対してより効率かつ効果的になるように、様々な適応が身体に現われるようになります。 しかしもしあなたが無酸素的にトレーニングを行った場合、身体は正反対の方向に進みます。 右の図でもわかる通り(エリートアスレチック育成セミナーで行ったプログラムデザインのレクチャーより抜粋)、同時に全ての身体要素をトレーニングする事があまり良いアイデアでないことがわかります。 単純に、我々が達成しようとしている適応はお互いに直接競合しているのです。 有酸素トレーニングは有酸素系酵素を発達させ、無酸素トレーニングは無酸素系酵素を発達させます。 有酸素トレーニングはミトコンドリアを作りだし、無酸素トレーニングはミトコンドリアを破壊します。 有酸素トレーニングは副交感神経を刺激し、無酸素トレーニングは交感神経を刺激します。 お互いの機能を同時に発達させるのではなく(初心者に対してのみ効果的)、ピラミッドの土台から築き上げることに集中しましょう 3 有酸素的土台の無い状態で、解糖系/無酸素的発達に集中してはいけない。 私が思う大きな問題の一つに、選手達が常に解糖系の高強度のエクササイズでエネルギーシステムを爆撃してしまうことが挙げられます。 エネルギーシステムの発達をピラミッドのように考えてください。一番下には低強度(有酸素性)エクササイズ、次に中強度のエクササイズ、そして一番上に高強度(解糖系/無酸素性)のエクササイズが続きます。 もしも頂上だけに特化するなら、土台を広げることはできません。これにより最終的には高強度の運動を持続して行う能力を制限してしまいます。 逆に、もしも”土台”作りにしっかりと時間を費やせば、高強度のトレーニングを行う際の基礎を身につけることができます。 これは、解糖系及び高強度の運動を通年行うことが得策ではない理由の一つにしか過ぎません。レスラーや総合格闘技選手のように、作業-休憩比が逆であっても、最初に基礎を固めることはプラスに働き、試合が近くなりにつれより高強度の勝負や練習に移行していくことができます。 4 ”8秒間無料でエネルギーが手に入る” チャーリーフランシス これはクレアチンリン酸系に言及していますが、簡単に言えば、ATP-CPの蓄えが全て使われるまで、8秒間は無料でエネルギーを手に入れることができるという意味です。それ以後は有酸素系/解糖系エネルギー供給機構がその役割を引き継ぎます。 ちなみに、チャーリーフランシスは非常に賢い人物でした。 5 全てのエネルギー供給機構は同時に動員される。 生理学を学んだ時、エネルギー供給機構は順番に動員されるものだという印象をおそらく受けたのではないでしょうか。皆さんの場合は違うかもしれませんが、私はそうでした。 はじめに、乳酸性及びATP-クレアチンリン酸機構が6-8秒間動員されます。 そこでエネルギーが枯渇したら、無酸素性/解糖系エネルギー供給機構が最長2分間動員されます。 その後、有酸素性エネルギー供給機構の動員が活発化します。 残念ながら、実際にはそのようになりません。 それどころか、すべてのエネルギー供給機構は同時に動員され、かつエクササイズの強度によって上方または下方制御されているのです。. つまり、あなたが必死に30秒または1分間動いている間、無酸素性/解糖系エネルギー供給機構は多くの作業をこなしているかもしれませんが、実は有酸素性機構もそれと同じくらい必死に働いているのです。

エネルギーシステムトレーニングにおける10の助言と秘訣 パート2/2
6. パワー/容量の連続体を重視する 最近、数多くの賢いコーチ(パトリック•ワード、ムラーデン•ヨバノビッチ等)が、パワー/容量の連続体について論じています。まだ馴染みがない方のために、ごく簡単な概要をここで説明します: 全てのスポーツ及びエクササイズは、パワー/容量の連続体のどこかに位置します。連続体の左側に属するのは、重量挙げやオリンピックリフティング、投てきといったパワー優勢型のスポーツです。 本質的には、一度にスピード/筋力/パワーを強力に発揮した後、しばらくの間休憩することになります。 連続体の反対側に属するのは、持続性があるが、スピード/筋力/パワーの出力が比較的低いスポーツ及びエクササイズです。トライアスロン、マラソン選手がこのケースに当てはまります。(写真はムラーデン•ヨバノビッチ提供) これらは明らかに連続体の両極端な例であり、大部分のチームスポーツはこれらの中間に属します。 右の図はジョー・ケンと私がEADSコースのために作製したものです。ここでは、私達は上の図の中心部分を抜粋し、それ自体を連続体にして表しました。 野球は長時間の休憩または回復をはさみ、かつ非常に爆発的であるため、最も"パワー"優位のチームスポーツであるといえます。 対極に位置するのはサッカーです。間違いなくパワー/スピード/筋力の要素も強いのですが、サッカー選手は同時に非常に多くの容量を必要とします。最終的には、開始15分間でどれだけよく見えても意味がなくー80分、85分、90分経過した際に走ることができなければ、大変なことになるのです! ひとたびパワー/容量の連続体を理解し、重視するようになれば、対象がどのような選手でも、ESTのプログラム作製は非常に容易になります。 7. 有酸素トレーニングは回復のために優れている。 有酸素トレーニングの最大の利点の一つは、回復を促進し、改善させることです。有酸素トレーニングはセットやエクササイズ間の効率を怪物並みにするだけでなく、ワークアウト間の回復も同様に促進する効果があります。 これをもう一歩前に進めてみましょう。私は回復を促すために、オフ日に行う有酸素/低強度のトレーニングが気に入っています。 それが心拍出量であれ、プールでのセッションであれ、もしくは高強度の連続性のトレーニングであれ、私、は積極的回復は受動的な手段よりも好ましいと固く信じています。 これは筋力パワー系のスポーツ選手には当てはまらないとお考えですか? よく考えてみてください。 ルイ•シモンズは、そり引き走と全身準備運動(GPP)をトレーニングプログラムに取り入れてから、彼の重量挙げ選手達のパフォーマンスの劇的な変化に気づきました。 それが積極的回復要素によるものであっても、心拍出量が向上した結果であっても、副交感神経、及び迷走神経の緊張度が改善した結果であっても、またはそれらすべて(と他の要素)によるものであっても、効果があるのは事実なのです。 8. 本当の解糖系及び無酸素性トレーニングは恐ろしい。. 人々がタバタプロトコールや高強度のトレーニングについて話していることを耳にするのは滑稽です、というのも大部分の方がそれに似ても似つかぬ運動をしているからです。 まず初めに、本当の意味でのタバタプロトコールトレーニングは、最大酸素摂取量の170%で行われます。これは途方も無く高強度であり、大部分の人が今まで(今後も決して)直面することがないものでしょう。 しかし、これをもう一歩前に進めてみたとして、極端な高強度で30、60、または90秒間行う運動はまさに、実に恐ろしいものです。このような種類のワークアウトを選手に書かなくてはならない時、私は一瞬沈黙してしまいます。なぜならその恐ろしさを本当に知っているからです。 もし私が信じられないのであれば、ジムに行き、ウォームアップをし、エアーダインバイクに乗って30秒真剣に、全力で漕いでみてください。 そしてその後の気分を私に教えてください! 9. あなたは心臓を変化させることができることをご存知でしたか? 筋肉を発達させることと同様、心臓も鍛えられる事をあなたはご存知でしたか? 筋肉が、漸進的により重い重量でトレーニングをしていくことで肥大するように、ESTを賢く行えば、特有の適応を心臓に引き起こすことが実現可能です。 まず、低強度のエクササイズは心臓の左心室のエキセントリック的な伸張/ストレッチを促進します。 長期間に渡って行うことで適応が起こり、一回の脈拍でより多くの血液を効果的に左心室に送り込めるようになります(1回拍出量の増大)。 そしてより多くの血液を一回の脈拍で動かすことで、心臓は脈拍数を抑えることができ、心拍数を減少させることができます。 簡単に言えば、より心臓を効率化することができるのです。 しかしもう一つ良い事があります。私達は、ミトコンドリアが我々の身体の細胞の発電所であることを知っています。高強度のエクササイズ(60秒以下)を最大心拍数で行った後、5分以下の休憩をとることで心臓内部にミトコンドリアを作り出す刺激を与えることができるのです! これは凄いことではないでしょうか? これだけは覚えておいてください。私達が行う全てのエクササイズが、何らかの適応を促進するのです。 10. ESTは楽しく続けることが重要 最後にはなりましたが、大切なこととして、EST トレーニングはかなり厳しいものにもなり得ます。 また、それは非常につまらないものにもなり得ます。 私が提供できる最大の助言の一つは、新鮮さを保ち続ける努力をするということ。 もちろんスポーツや動作に特化した作業が必要な時もありますが、質の高い適応を得るために、夢中になって楽しみながら、全体的に取り組むべき時も同様に必要なのです。 例えば、心拍出量向上のトレーニングをする際の手段をトレッドミル、バイク、クロストレーナーでのエクササイズだけに限定しないようにしてください。 メディスンボールを投げたり、プロウラーを押したり、またコレクティブやモビリティードリルを行うサーキットトレーニングを作ってみましょう。 簡単に言えば、より楽しく、夢中になればなるほど、長続きし、恩恵を受けられるようになるのです。

組織の方向
学生からの問い: 私が近位から遠位へのストロークという考えを提示すると、インストラクターはまるで私の頭がおかしいのではないかという視線を送り、その方向でのストロークは静脈に損傷を及ぼす危険があることを教えられていないのではないかと心配しました。そのインストラクターは、過去にヘラーワーカーから、近位から遠位への手法を受け、激しい痛みを覚えたことがありました。彼はそのボディワーカーの、安全の知識の欠けた施術に驚いたのです。 重ねますが、これは、あなたが言うように、血管がより効果的に機能するために空間を作ることではなく、素晴らしい恩恵をもたらす可能性のある、遠位へのストロークについてです。彼は、遠位からの働きかけをせずに筋膜を延ばすことはできるのかどうか問いかけてきました。この質問に対する私の意見と反応は、もちろんどちらの方向から働きかけても筋膜の長さに影響はある、というものでしたが、私はそこで、方向に対する神経学的反応がクライアントの固有受容性フィードバックを高め、身体を生理学的のみではなく、かつ神経学的に調整するという「考え」を提示しました。 この件に関しては、何の証拠も前提もありませんが、これは論理的な考え方だと思っています。私はインストラクターに、遠位からアプローチすることが静脈弁の解剖的構造、および生理的構造に変化をもたらす証拠を示した研究や資料はあるのかを聞きました。彼の返事は不確かなものでした。 筋膜のモビリゼーションを行う方向は、生理学的および神経学的にクライアントの成果に重要な要素なのでしょうか? ルー・ベンソンの返答: あなたの先生は不確かな返答をして適切でした。私の好きな文献の一つにトレーシー・ウォルトンによる「Medical Conditions and Massage Therapy」(LWW 2001)があります。学校にも一部あるのではないかと思いますが、ありますか? 私の理解では、健康な血管(と弁)は高い弾性を持っており、様々な力学的ストレスに耐えられるようにできているため、たとえ下手なマッサージ(強すぎ、深すぎ)が施されても、特に悪い影響が起こることはないはずです。つまりは、鋼鉄を壊すためには、十分な圧力をかける必要があるということです。痛みは、圧力が害をもたらす可能性がありえることの良い指標になります。 静脈の病理学的問題は、比較的小さな圧力によって、時には何の圧力も関係せず、不均衡な量の、強烈な、うずくような痛みとともに起こります。明らかな静脈瘤が見られることもあれば、静脈が深部にあって見えないこともあります。肌が変色したり、浮腫があったりもします。もちろん、圧痕性浮腫は、マッサージの禁忌であり、腫れ上がった「テカテカした皮膚の」浮腫、特に下腿に見られる場合は、手技をほどこすにあたって、明確な禁忌です(リンパドレナージュ手技の精通者であれば別かもしれません)。 筋膜が流動性を失った状態になり、脱水状態になり、繊維形成されて、その筋膜自体、そして周辺組織に癒着し、血管や神経管が、その空間媒体や通路を組織化するために筋膜の健全を必要とするのなら、筋膜に水分を取り戻し、健康な繊維の数、向き、分配が得られるよう助けることは、これらの管にとっても環境の改善になるのではないでしょうか? トムのコメント: これについては、2つの観点から分けて見てみましょう 深層部のボディワークによる静脈損傷 この弁の損傷の問題を解決するために、リンパの配置から静脈を見てみましょう。もしこれが真実であれば、プールから身体を引き上げてくる時に(この過程で身体に圧力が伝達する)静脈が損傷することになります。慎重に施されたストロークは、身体の静脈の軌道を「下がっていく」他の圧力と同様に、管と液体が、浅層の静脈とリンパ管の複雑なデルタ状のネットワークから抜け出すのに十分な時間を与えています。 損傷を生み出すものとして考えられる唯一のストロークは、ダビンチコードの飾り輪のように腕や脚を包みこんで、強いプレッシャーを与え、心臓から四肢への伝達がなくなるまでプレッシャーを維持する、止血帯のようなストロークです。もしあなたがこれを行って、しかも上手にできて、かなり多くの圧力をかけることができれば、いくつかの弁を壊せるかもしれません。これらの弁はどちらかというと海藻のような感じで、自身ですばやく修復して回復します(生体でよく起こりますが、鬱血がある場合には、静脈瘤ができます)。 以上の理由により、私はヘラーワーカーによる叫びは、静脈を損傷したことによって起きたわけではなく、神経学的組織に圧力を急に与えたか、圧力が強すぎたために起きたものだと考えます。 なぜ KMI(Kinesis Myofascial Integration)では組織を望む方向に動かすのでしょう? アイダ・ロルフの「前側を上に、後ろ側を下に、骨盤は水平に」という格言があります。私の考える骨盤の水平な位置が、アイダ・ロルフの理想よりも少し前傾しているとしても、これは良いアドバイスだと思います。 この論理は、伸長するという概念には適用しません。組織を伸長しているのならば、それは伸長しているのであって、方向はあまり関係ありません。人が立っているとき、長さは利用されることもありますし、利用されないこともあります。 運動感覚もまた、私達が支持するものの実行しないことの一つです。私たちは組織を望む方向に持っていき、それによって神経システムにゴーサインを出しています。この話は、受容器とそのメッセージに関係しており、ロバート・シュライプのウェブサイトや研究を通じて、最も明確に確かめることができます。これは良いことですし、私達はこのように話をしてきましたが、私達の言っていることは、私達が行っているボディワークのみではなく、運動感覚のセンサーに触れるいかなるボディワークにも適用されるものです。 ガンベルト医師の動画とユージン氏らの研究を組み合わせた新しい答えは、好む方向に、せん断力を与えることで、その方向に新しい「けばのような」結合のようなものを作り出すことになりますが(いわゆる織物の「もつれ」のようなもの)、私たちの見識では、これが起きてほしいことなのです。 直感的に、構造的ボディワークにおいて方向は大切ですが、この剪断力と力の伝達物質としてのけば」の話題が出てくるまでは、しっかりとした説明ができていませんでした。これは、私の講義では「トーガ(古代ローマの男性の外衣)」の考え方として扱っています。筋膜のトーガを骨格に対してゆったりと掛け直す必要があり、それには筋膜面がお互いに関係して動く必要があります。私はこのような考え方をする療法を他に知りません-誰か知っていますか?

より速いレップ速度は筋力の増加を助長するか? パート1/2
レップ速度の筋力に対する影響は、評価を行うことが困難である。速いバー速度を指示する人達と遅いバー速度を支持する人達が、それぞれに存在し、速いバー速度の支持者たちは、速いバー速度は閾値の高い筋繊維をより多く動員することを可能にすると示唆し、遅いバー速度を支持者たちは、より大きなタイムアンダーテンション(筋緊張下の時間)をアピールしている。研究者たちは他の変数を制御することの難しさに悩まされている。力-速度の関係性のために、最も問題となる要素は相対的負荷である。この総括は、相対的負荷を制御した等慣性筋力トレーニングを行う際、レップ速度がどのように筋力増加に影響を及ぼすかについて我々が現在知り得ていることを詳しく説いたものである。 背景 序論 様々な研究者たちやストレングス&コンディショニングコーチたちは、レップ速度が筋力に対して重要かもしれないと提議している。ウェイトトレーニングには次に挙げるような2つの基本的な方法がある:(1)最大速度にて、(2)制御された最大下速度にて。この2つめの方法においては、超低速から超高速(最高速度以下ではあるが)まで様々に異なるリフティングの速度を用いることができる。一部の研究者たちとストレングス&コンディショニングコーチたちは、レップ速度やバー速度に対するより適切な言葉は「レップ継続時間」であると提議している。これは「タイムアンダーテンション=筋緊張下の時間」の重要さをより強調した言葉である。しかしながら、このような専門用語に対する考察は、より深刻な問題である変数を隔離することや結果を測定することと比較するとそれほど重要なものではない。 変数の分離に関する問題 関連のある他の全てのトレーニング変数(相対的負荷、トレーニング量、筋限界、タイムアンダーテンションなど)から完全に分離して、レップ速度を変化させることは実際には不可能である。これは主として力-速度関係のためである。高負荷を動かすために大きな力が必要な場合、筋肉の収縮速度は遅くなくてはならない。これは、速いレップ速度と遅いレップ速度の比較は多くの場合、力産出が異なるため本質的には異なる相対的負荷を比較しているということを意味する。 この点における当然の結果、相対的負荷が統一され、全ての場合においてセットが筋限界までおこなわれた場合、異なるレップ速度の2つのワークアウトプロトコールが同等のトレーニング量(負荷xセット数xレップ数)となることはないであろう。実際には同等の相対的負荷の場合、速いレップ速度はより多くのレップ数を行うことにつながるというのが常である。ゆえにトレーニング量は多くの場合、コンディションにより異なってくる。同様に、トレーニング量が人為的に均一化された場合、1つのコンディションにおいてのみ筋限界まで行うことが必要となるようである。これは、研究者たちがどの変数が最も結果を混乱させがちであるかを選ぶ必要があることを意味しており、この研究を完了する前に最も重要なトレーニング変数を決定せねばいけないことを意味している。 全てのこの議論は、トレーニング変数としてレップスピードのみを孤立させることは難しいということを単に示しているだけである。レップ速度が変化すると、相対的負荷や量や筋限界への接近などの他のトレーニング変数は固定されている他のパラメーター次第で同時に変化するのである。 筋力測定に関する問題 異なるレップ速度によるトレーニングプログラムの効果を評価する際の、その他の主な問題点は、筋力を測定する方法である。概ね我々は、等尺性筋力、等運動性筋力、及び等慣性筋力(エクササイズに対する1RM )を測定することができる。これらのカテゴリーの中で、等尺性筋力は異なる関節角度において測定することができ、等運動性筋力は異なる速度において測定が可能である。 レップ速度については、テストされるトレーニングプログラムの多くが同じ速度でのトレーニングを含んでいることが多いため、異なる速度において等運動性筋力を測定する際に最も問題となる。それゆえ、トレーニングの特異性の問題が存在し、低速での等運動性トレーニングが低速での等運動性筋力につながり、高速での等運動性トレーニングが高速での等運動性筋力につながるということは、特に驚くべきことではないのである。しかし残念なことに、等運動性の測定方法を除外する以外にはこの問題を簡単に解決する方法はない。 選択基準 この総括に対して私は下記の選択基準を設けた。 レップ速度の筋力増加に対する意図的な(偶発的ではなく)効果を調査している介入 従来のレジスタンストレーニングの方法のみを用いた介入(等運動性及び等尺性以外) 動力学的/等慣性、等尺性、等運動性の方法による筋力測定 均一な相対的負荷での研究 これは理想的なアプローチ方法ではないが、これが現在のところ研究論文における限界のようであり、単にバーを可能な限り速く動かすよう試みるというよりはむしろ、特定のバー速度もしくはテンポでのトレーニングによる効果の違いを調査する1つの方法であると意図されている。研究論文を分析する方法が他にも存在する(おそらく同等に有効)ということは周知のことである。 洞察力の高い人は、私が均一の相対的負荷による研究についても述べていることから、等運動性もしくは等尺性トレーニングの介入が除外されたということを明記する必要はなかったことに気がつくだろう。異なる等運動性速度はそれが最大の努力により行われるため本質的には異なる相対的負荷が関わっており、ゆえに力-速度の関係は、より遅い等運動性速度はより速い等運動性速度よりも高い相対的負荷を伴うということを意味する。グループ間でトレーニング総量を明確に一致させた従来のレジスタンストレーニングに関する研究を見つけることは不可能であった。 ***